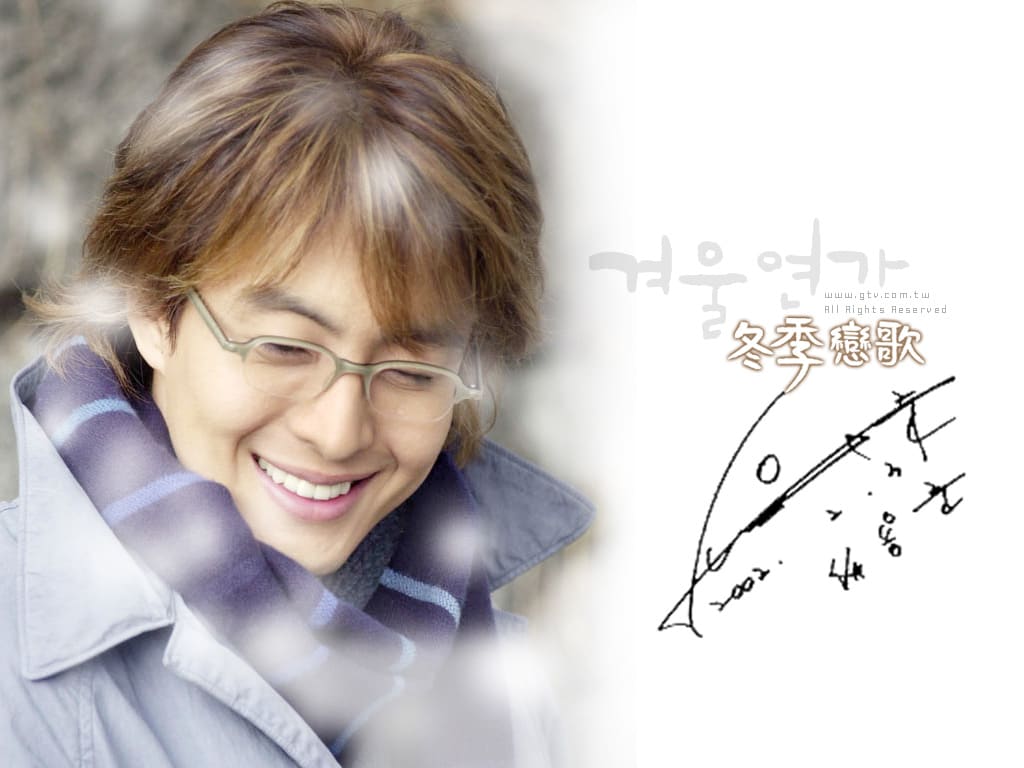現代英語圏の心の哲学の二大巨頭といえばダニエル・デネットとデイヴィッド・チャルマーズである。
デネットは1940年生まれの年長哲学者で、チャルマーズは1966年生まれの若き哲学教授である。
しかし年の差は哲学の本質とあまり関係がない。
問題はデネットとチャルマーズが「意識の神秘」に対してどういう態度をとっているか、である。
周知のように、チャルマーズは「意識のハード・プロブレム」というものを提起し、主観的現象性をもちクオリア(感覚質)に満ちた「意識」は、脳科学(神経科学+認知科学)の標準的な探究方法では決してその本質を捉えることはできない、と主張した。
「ハード・プロブレム」とは「困難で厄介な問題」という意味で、実験科学的に対象化できず客観的データに還元できない「意識の主観的特質」に関する問いかけである。
こうした問いを立てるチャルマーズの姿勢の背景には、言うまでもなく二元論的な存在論が控えている。
ただし、それは古いデカルト的実体二元論ではなく、現代風に洗練された性質二元論である。
とはいえ、物理主義と還元主義と唯物論に対する感情的とも言える反発は、はっきり言って問題である。
この点を辛辣かつ鋭利に批判したのがデネットなのである。
デネットは、デカルトの二元論的心観を根底から破壊したギルバート・ライルの弟子であり、実体的意識観を徹底的に排除する。
それは同時に性質二元論の批判にもつながる。
そこで、チャルマーズとデネットの間では「クオリア」に対する評価が全然違ったものとなる。
チャルマーズがクオリアを現象的意識の中核をなすものと考え、クオリアの存在こそ脳科学が意識の本質を解明できないことの証だ、と言い張る。
それに対して、デネットはクオリアは一種の幻であり、なんら意識の本質に関与するものではない、断言する。
デネットにとって大事なのは文化的遺伝子ミームの伝承において自然的ならびに社会的環境に関与する人間的意識の「機能特性」なのである。
ちなみに、デネットは「自己」というものを脳内の複合的情報処理の機能的因果連関の織り成す神経的物語の単なる「重心」のようなものと捉えている。
これは構造主義、行動主義、機能主義に共通する自我の脱実体化の姿勢を表している。
遡ればヒュームの主張「自我とは知覚の束である」に行きつくことは言うまでもない。
ところで、チャルマーズは意識が物理的過程に還元できないと熱弁しながら、人工知能の可能性を肯定したり、情報の二重側面理論などという形而上学的観点をとっているが、社会文化的環境の中における間主観的意識と人間的自我の問題にはほとんどタッチしていない。
チャルマーズの思想は非常に啓発的、刺激的だが、意外と大きな見落としがあるのだ。
しかし、それはあらゆる思想に見られるものであり、そこばかり突いていてもしょうがない。
対立する思想を弁証法的に統合して、より高次の見解へと創造的に進化することが要請されるのである。
デネットとチャルマーズの対立を含んだ現代意識哲学の諸派の評価と統一的見解の模索に関しては、2004年の拙著『意識の神経哲学』を参照されたい。