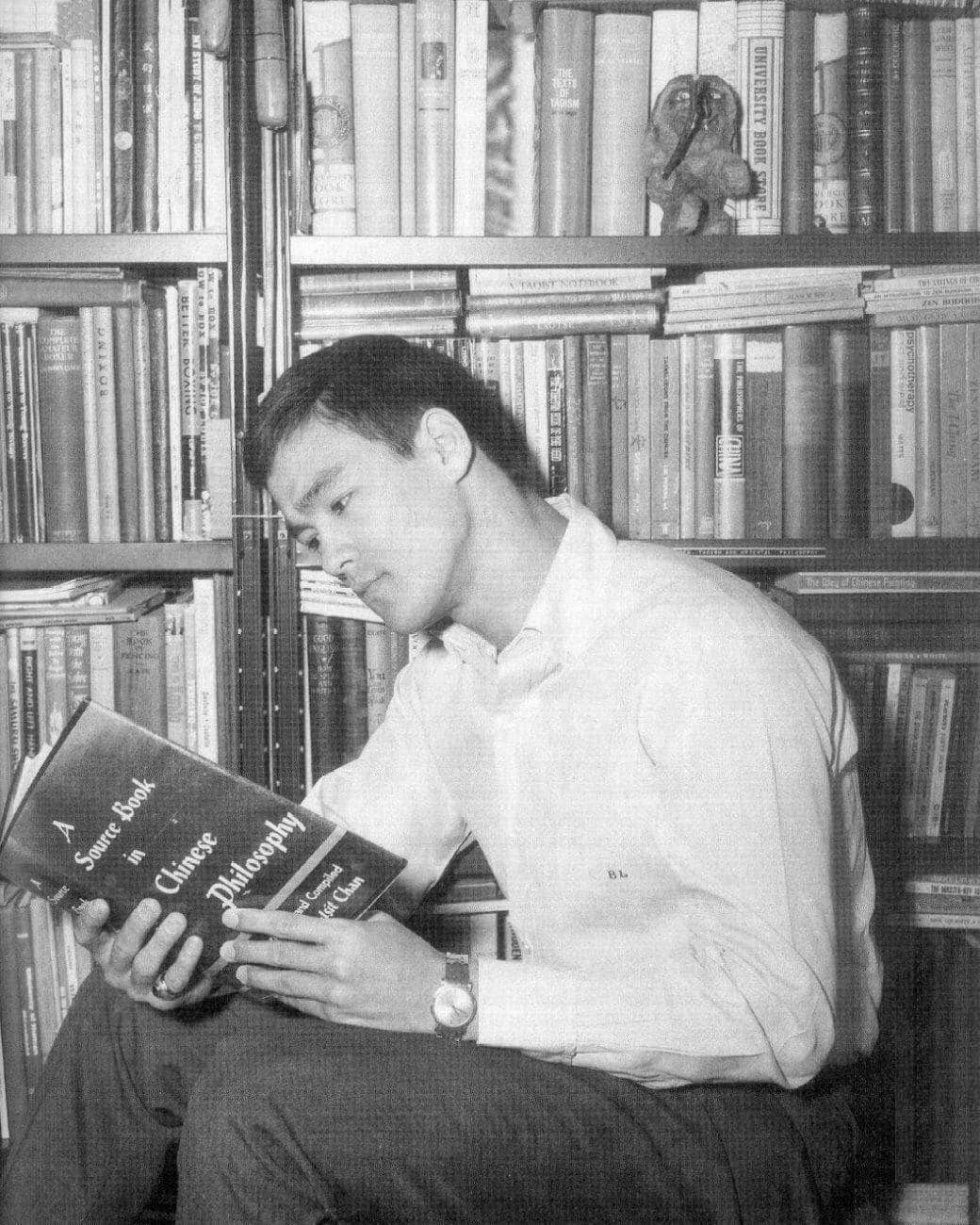今日はテキスト『心境小説的短編小説集』の中の五番目の作品「医学と哲学と人生」について文章で講義する。
この講義を読む者は、あらかじめ作品を読んでいなければならない。
必ず一度読んでから、この文章講義を読むこと。
もしテキストを読んでいなかったら、ブログから離れてテキストに向え!!
はい、みんな「医学と哲学と人生」を読んだね。
すごく短い作品だから、すぐ読み終えたはず。
それに簡単で読みやすい内容だから、すぐに読み終えたはずだよね。
それでは、解説に入ることにする。
この作品は他の典型的なものとは違い、最初からすぐ心境小説が展開し始める。
語り手の「私」のモデルはいちおう私自身だが、百パーセントそうなわけではない。
少し脚色している。
心境小説というものは私小説的性格が強く、だいたい自分の体験や心境を想起して書かれるものだが、少し脚色しているものもある。
また、この「医学と哲学と人生」は、これまでこの授業で扱ってきた短編小説群の中では最も専門用語や哲学議論が少なく、生活感に満ちているので、学生諸君も親しみやすいはずだ。
自分の体験や心境にも重ね合わせやすい。
それでは、内容に入ろう。
冒頭には私の小学生の頃の嗜癖が書かれている。
それは家庭医学書、あの分厚い家庭医学書を愛読書にしていたことである。
昭和の頃にはどの家庭にも必ず分厚い家庭医学書が一冊常備されていた。
私の家には二冊あり、他にも父親の勤める会社から付与された類書が三冊あった。
この計五冊を私はよく読んでいたのである。
母親に「心配性になるから止めなさい」と言われたが、止められない。
止められない止まらない、のである。
普通の少年、いや大人でも死に至る病の厳しい症状が多数記載された医学書は読みたくないものであるが、私はまるでホラー映画を楽しむしように、読みふけった。
読んだ後、恐ろしく不安になり、病気ってこんなに怖いんだ、死にたくない、自分は虚弱気味だから、多分30代で大病になり死ぬかもな、と戦慄、悪寒でがくがくブルブル状態。
だったら、読むの止めなよ、と言われそうだが、止められない止まらないカッパエビセンなのである。
あの頃からあのお菓子はあったのだろうか。
古い家庭医学書を読んでいると、医学と治療の進歩をつくづくと感じるが、昔と大して変わらないものもある。
それに最近増えている重病、難病もあるし。
例えば、日本においてかつて「がん」と言えば、まず「胃がん」であった。
それが近年、大腸がん、乳がん、肺がん、前立腺がんの方が優位に立ってきた。
また、昔はがん=死のイメージが強烈で、ほとんど死ぬという感じだったが、近年はかなり長生きするようになってきた。
たしかに、未だに手の打ちようのない悪性度の高いがんもあるが、典型的で症例の多いがんは治りやすくなってきたし、死なない。
治らない、死なない、というよりもがんと共生して何十年も生きられるようになったのである。
また、インターネット全盛のこの時代、ネットには闘病ブログがあふれ、書店には闘病記本がたくさん置かれている。
かつて家庭医学書オタクであった私は、今や闘病ブログ・闘病記オタクになっている。
続けて読んでいる闘病ブログが常に5~10あるが、読んでいるうちに死んでしまうものが多い。
今も、近いうちに死にそうな女医のブログを読み続けている。
これには禁断の楽しみがある。
禁断の楽しみと言うと、悪い嗜癖のように思われやすいが、そうでもない。
もし、知人がこういう状態になったら色々アドバイスできるし、自分の健康維持のためにもなる。
死に瀕したがん患者は、他人の役に少しでも役に立てばと思い、あえて無様な自分の状態をさらしているのだ。
それは必ずしも本人にとってマイナスの要素しかないものではない。
むしろストレス解消となるのだ。
やりきれない末期がんとの戦い、あるいは長期の闘病のストレスの愚痴として書くのだ。
応援のコメントも励みになるし、広告収入もある。
抗がん剤治療は高くつくからなー。
仕事も休み、収入は減るし。
テキストを要約してもしょうがないので、すかしたような文章で間接的に内容に触れているが、どうしても引用したい部分がある。
それは頚髄損傷を負った出版社の編集長の言葉である。
「闘病記なんてものは、健康な人が自分はこんな苦しい思いや不自由さを味合わなくて済むんだなー、とその有り難味を再認識するために読むものなんだよなー」。
これがその文章である。
頚髄損傷においては首から下の上半身・下半身が全麻痺になる。
それには程度の差があるが、基本一生寝たきりになる。
想像以上に厳しい。
治るタイプのがんよりも数十倍厳しい。
私は禁断の楽しみを指摘されたように感じ、いったん恐縮したが、すぐに、「そんなことないよ。それだけじゃないよ。医学、病理学、治療技術、死の意識、患者の心理
に興味が強く、それを自分の臨床哲学と小説執筆のために役立てているんだよ」と言いたくなった。
実際、それは自身の健康の維持、病気になった他人へのアドバイス、臨床哲学の研究に役立っている。
医学自体を趣味でずっと研究、勉強しているが、患者本人の心理、苦しみ、死の意識には並々ならぬ興味がある。
そして、ここから「医学と哲学と人生」という思考案件への思い入れとその心境小説化が実現したのだ。
この短編のなかで他に注目してほしい箇所が二つある。
それは「私」の友人の睡眠習慣と安倍元首相のことである。
安倍元首相というよりは、故・安倍元首相ということろが悲しいところだが。
私の友人が豪語していた「俺は五時に寝て七時に起きる」ということに着目されたい。
これは二時間睡眠ではなく、14時間睡眠である。
その後、彼は38歳で大腸がんで死んだ。
ここら辺の叙述を良く味わい、その意味を深く考えてほしい。
安倍首相に関しては暗殺のことはもとより、彼が抱えていた潰瘍性大腸炎という難病の克服、しかしその後の暗殺ということについて深く考えてほしい。
最後の方で「長期療養生活」について書かれている。
今では前述の頚髄損傷などがこれにあたるが、かつては「結核」がこの代表であった。
この長期療養生活についても深く考える必要がある。
これによって「医学と哲学と人生」という思考案件への視界がひらけてくるであろう。
以上、内容を体系的に解説することを避け、すかした解説にしたが、この方が君たちのために有益なんだ。
最後に、恒例の猫様に登場願う。
面白かったにゃ

ためになったにゃ

この魚のように旨いにゃ