◇ 北国街道・追分宿から高田宿へ向けて
江戸幕府道中奉行支配下の五街道(東海道・中山道・日光道中・甲州道中・奥州街道)を完全踏破
したのが2008年。その後水戸街道を2年かけて歩いたが、終点の水戸に到着したのが昨年の2月
のこと。健康維持のための散歩はともかく「歩き」はどこか目的があった方が歩き甲斐がある、という
相棒の言い分に同感して、懐かしい中山道・追分宿の分去れから新潟県高田宿までの北国街道を
歩いてみることを計画した。
北国街道には三つの顔がある。
一つは主として加賀藩の江戸参勤の道としての役割。この場合高田宿からは加賀街道が分岐する。
二つ目は佐渡で採られた金を運ぶ道。この場合佐渡から近い出雲崎までが北国街道とされる。
三つ目が庶民の信仰の道としての北国街道。信濃善光寺へ通ずる道で「善光寺道」とも呼ばれた。
この場合、中山道洗馬宿から善光寺に至る道を北国西街道と呼んだ。
また北国街道は塩の道とも言われる。通常塩の道といえば、いわゆる千国街道とも言われる越後の
糸魚川から信州大町を経て塩尻・中信方面に運ばれる塩の道を指すが、信州では日本海の塩は直
江津から北信へ、また倉賀野で陸揚げされた塩は中山道・北国街道で中信・佐久地方に運ばれた。
その意味では中山道・北国街道は塩の道とも呼ばれるのである。ただ江戸後期では瀬戸内海の塩
がコスト的に断然安く、輸送ルートも開発されて、ほぼ全国制覇を果たしたようである。
北国街道は中山道追分宿から分去れの地で分岐し、小諸宿、田中宿、海野宿、上田宿、坂木宿、
戸倉宿、矢代宿、丹波島宿、善光寺宿、新町宿、牟礼宿、柏原宿、野尻宿、関川宿、田切宿、関山宿、
二本木宿、新井宿、高田宿までの19宿である。なお矢代宿からのバイパスが松代道と呼ばれる。
松代経由の道は元々は本道であったが、善光寺道が本街道になってからは北国東脇街道となった。
松代宿、川田宿、福島宿、長沼宿、神代宿まで5宿がある。122町およそ146キロである。善光寺は
かつて5年を過ごした地であり、その周辺は詳しいので、今回は脇往還の松代道を選んだ。
◇追分宿から小諸宿まで
長野新幹線で軽井沢へ。そこで「しなの鉄道」に乗り換えて信濃追分駅に降り立ったのが9:38。
昔懐かしい駅舎は10年前と全く変わっていない。

本日の最高気温20度と異常に暖かい日の予報であったが、朝はさすがに空気は冷たく、12・3度
という感じであった。相棒は手袋を着用。
先ず目指すは中山道追分宿。別荘地を抜けて国道18号をまたいで街道みちに入る。
浅間山はうっすらと雪化粧。



10年前に中山道を歩いて時と随分印象が違う。道路があまりにきれいに舗装されていて驚いて地
元のおじいさんに聞いたら「去年に出来上がったばかりだよ」とのこと。
街づくりはいいが雰囲気がどうも旧街道らしさからどんどん遠ざかっていくようで寂いしい。
軽井沢が舞台の小説「風立ちぬ」の作者堀辰雄文学記念館の門は旧本陣の門を移設したもの。
かつて脇本陣でもあった旅籠「油屋」はいまではゲストハウス、アートギャラリーなど文化イベントの場
として活用されている。



宿場の高札場とまだ残る街道の屋並み。枡形の茶屋「つがるや」は分去れのシンボルとして有名。




追分宿の「分去れ」は、中山道と北国街道の分岐点で、左中山道、右北国街道の分去れの碑
(さらしなは右、みよし野は左にて 月と花とを追分の宿)がある。
街道の傍らに咲く桜(枝垂れ)はまだ見頃だった。
また桜と浅間山も見事に調和していた。
分去れの 碑も懐かしき 山桜






間瀬口の明治天皇小休所は塩野牧の入り口に当たる。
この辺りは高原キャベツやレタスの栽培が盛んである。
田起こしや 北国街道 細き道



上信越道長野線を越える。

ここからの浅間は角度が違うため黒斑山も幾分穏やかになる。
街道には大抵立派な火の見櫓がある。いまでは半鐘を鳴らすことはなく、むしろ有線で
地域連絡放送を主としているのかもしれない。しかし半鐘の鐘は象徴的に残されている。



はるか彼方に連なる山は北アルプス。春霞でおぼろだった。

唐松の一里塚跡。


小諸本町に入る。町屋はなべて立派な構えである。
有名な酢久(味噌)の店。屋根をかぶせた看板が有名。









関ヶ原の戦に駆けつける初陣の徳川秀忠。2万の大軍を率いながら僅か2千の
上田城の真田昌幸軍に惨敗し、足止めを食わされた。この折り徳川秀忠と真田
昌幸との休戦の仲立ちをしたのがここ「海応院」の住職であった。
この寺で発見された八重咲きの「コモロスミレ」はまだ咲いていなかった。



市内与良町に「高浜虚子記念館」がある。俳人虚子は戦時中ここに足掛け4年間
疎開し、句作を行った。




1682年(天和2年)創業の旅籠「つるや」は今は立派なホテル。「旅籠つるやホテル」
と言っている。
その並びには脇本陣と本陣が。この本町一帯は旧い街並みを保存再現している。
本陣の主屋は駅近くに移設した。








小諸城の大手門は四の門。小諸城のすぐ前に三の門がある。
小諸城址公園の桜はソメイヨシノは既に花が終わり、有名な「小諸八重紅枝垂れ」
は最後のあでやかさを誇っていた。






本日の歩行距離はほぼ15キロと軽かった。
今宵の宿は「小諸グランドキャッスルホテル」。小諸城址公園に隣接し、街道にも近い
上に食事(夕食飲み放題)、ホテルサービス(TW=24㎡)も十分で大いに満足した。
(以上この項終わり)
最新の画像[もっと見る]
-
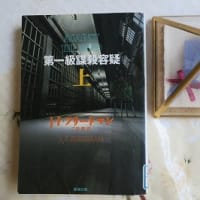 J・F・フリードマ ンの『第一級謀殺容疑』<上>
17時間前
J・F・フリードマ ンの『第一級謀殺容疑』<上>
17時間前
-
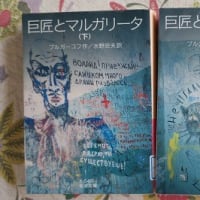 ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ(下)』
2週間前
ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ(下)』
2週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
令和6年のトマト栽培ー3ー
2週間前
-
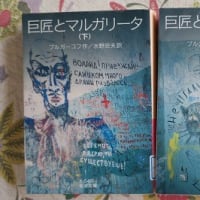 ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ(上)』
3週間前
ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ(上)』
3週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
令和6年のトマト栽培ー2ー
1ヶ月前
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます