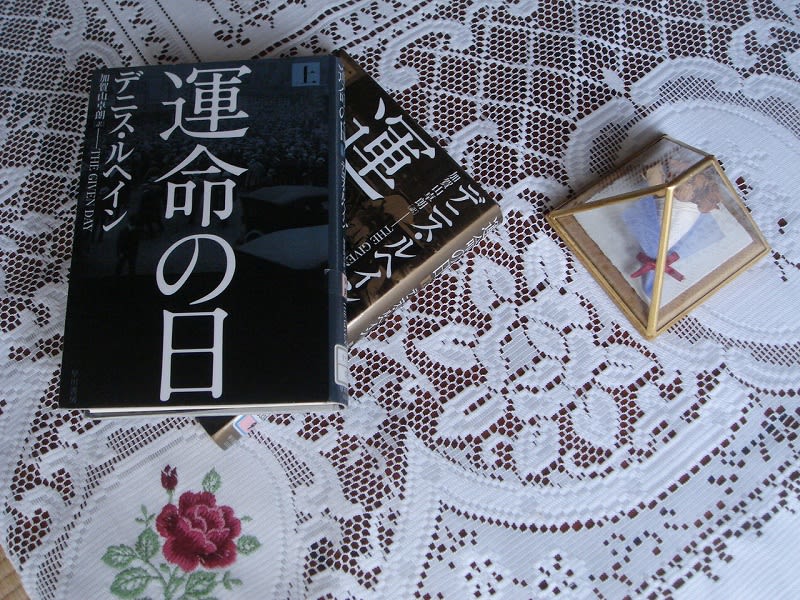◇水戸街道(松戸宿から柏宿まで)
前回は松戸のお祭りを見て、電車で自宅に帰った。
今回は時間があってお天気のいい日を狙っていたら、土曜・日曜が秋晴れ
との天気予報。最近は予報もあまり外れないので安心して行こうということな
った。
日曜日は勤労感謝の日。旗日で、翌月曜日は振り替え休日(雨模様)にな
っている。勤労感謝祭は昔は「新嘗祭」といって、天皇陛下が宮中の田圃に
お手植えした稲を刈り取り、新米を神様に供えるという儀式を前面に出して
いたので分かりやすかった。子供には学校で紅白の饅頭が貰えるというだ
けで、本来の祝日の意味などそっちのけで嬉しかったものだが、今は「勤労
感謝」なんて誰が誰に感謝するのかさっぱりわからない。勤労できることを素
直に天に感謝するのだと言われても、毎日が日曜日状態のリタイア組なんぞ
は身の置き所がない。では勤労している人達に感謝しようと言われても、どう
感謝しようと散々考えたが好い考えも浮かばない。仕様がないから余り働い
てる人たちの邪魔にならないように静かにしているのが一番だと思うことにし
た。しかし、明日は天気と言われると、働いてる人の行楽を邪魔することにな
るのを構わず出かけてしまう。まったく聞き分けのない年寄りだということに
なる。
まあそんな訳で今日は我孫子宿か、その手前の北柏辺りまで歩こうと出か
けたが、結局北拍で切り上げることになった。
風も無く、小春日和の快晴で、夕刻の空は見事な夕焼けだった。
<松戸宿>
まずは前回の終点、「松戸駅入口」信号からスタート。水戸街道とはいっても
この辺りは素っ気ないもの。

松戸市根本付近
製パン工場の手前(「竹ヶ花」)で左折し、住宅地の中を進む。やがて国道
6号に合流し、うるさい車の喧騒の中を北松戸、馬橋ヘと向かう。


松戸市新作付近 馬橋万願寺
「八ケ崎交差点」の先「蘇羽鷹神社」前の信号で右折する。少し街道筋らしく
なる。
武蔵野線のガードをくぐる。
松戸市場へ向かうケヤキ並木はきれいに色づいていた。また道筋の畑では
柿がたわわになっていた。



蘇羽鷹神社 水戸街道の案内柱 武蔵野線ガード


松戸市場への道 枝もたわわ
道はやがて国道6号を横断し、真直ぐ北小金駅方向に向かう。
「虚無僧寺『一月寺』跡」という標柱があった。今は日蓮正宗金龍山
一月寺となっている。
珍しく旅籠の旧家があった。「玉屋」といったらしい。



虚無僧寺跡標柱 一月寺 旅籠「玉屋」跡
不明にしてこれまで知らなかったが、ここに「東漸寺」という名刹がある。
東漸寺は、元々1キロほど離れた根木内に文明13年(1481)開創。その後
この地に移設。関東18檀林の一つといわれる。明治初頭に勅願所とな
った。境内には一時20以上の堂宇を擁したという。
枝垂桜が有名で時期になると多くの人を集める。
今日はたまたま万灯行列という行事のある日で、出発準備の檀徒さん
達の勇ましい姿に接することが出来た。



東漸寺参道 準備中の万灯 山門



万灯行列出発前の準備


紅葉もきれいでした 松戸市の汚水マンホールのデザインは「矢切の渡し」です。
やがて北小金駅前に着くと直角に道が右折することになりそこに
「水戸街道」の道標が立っている。

水戸街道道標
道を辿ることほぼ1キロ。国道6号を横断すると左手に「根木内城跡」の
「根木内歴史公園」があり、そこで持参のオニギリで昼食をとった。
流山電鉄大谷口にある小金城跡と同じようなつくりで、残っているのは土
塁と濠跡(空堀)、復原土橋などである。寛成年(1462)高城胤忠の築城で
ある。



城跡概念図 土塁 空堀
道をどんどん南柏の方向へ北上すると、香取神社の境内脇に「一里塚跡」
の碑があった。鳥居の右手に立派な榎があったが枝を落とされてみじめな
姿であった。下から子供が生えていたが、ちゃんとするまで何百年も掛か
る。


一里塚の碑 一里塚の榎
南柏駅入口の先に、昭和37年頃の松並木の写真が残っていた。今はもう
そんな風情は望むべくもない。


松並木の写真 八坂神社
更に進むこと1.6キロ。東武線のガードが見えてきた。柏宿である。
やはり柏宿は柏神社が中心。社格は村社で、1660年八坂神社と羽黒神社
の合祀とあるが、境内に樹齢300年近い銀杏の樹があったりし威容がある。
しばらく行くと明治天皇小休所記念碑が建っている。



東武野田線ガード 柏神社 明治天皇柏御小休所
道は800mほどで国道16号を横断すると一旦常磐線を高架で渡るが、
再度旧道の小道に入り、大堀川に近い道を再び常磐線のガード下を
くぐり国道6号に合流する。ややこしい道筋である。
今日は相棒の妻が少々脚が不調のようなのでここで打ち止め。
今日は結局18キロほどの歩行であった。


常磐線ガード手前 手賀沼に入る大堀川
(以上[その4]終わり)