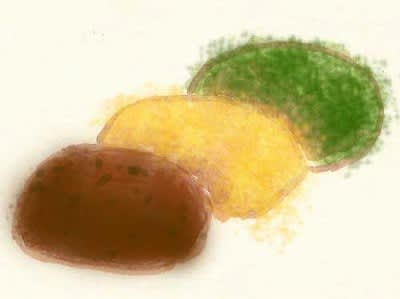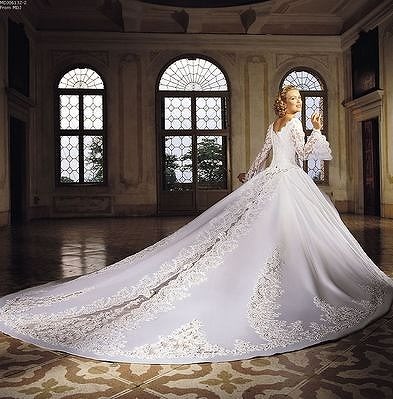大学の家政学部出身というのは、なかなかスゴイものがある。
「家政学」であって、「家事学」でない。
家政と、家事は、違う(はず)。
なにぶん、わたしは、家政学部出身ではないので、なんともかんとも、どうとも言えないが。
食物学科、児童学科なんてのもある。
発達心理学やら、児童心理学、家政学、なんて、学問もある。
これらを完全にマスターし、習得すると、スーパー主婦、ミラクル・ママ、
ひいては、モンスター・ママになって、学校に苦情の山を言いに、先生に、詰め寄り襲い掛かっていくのだろうか。
あるいは、賢すぎて、育児や教育を詳しく深く知りすぎて、完璧を目指して育児ノイローゼになるかも知れない。
(わたしは、いい加減すぎて、マズすぎたが・・・)
その、家政学を究め、学士サマになると、結婚の条件がワンランクもツーランクもアップするとか。
女子大は、高級花嫁専門学校か?
以前にいた会社で、ある総務の女の子が言っていた。
「短大は、化粧を習うところだからって、親が行かせてくれなかった」
その女子は、高卒で就職した。
で、その総務に4年制・国立大学(昔の国立一期校)卒の女性が、入ってきた。
ああ、よりによって総務に入るとは、なんと、お気の毒。
高卒の女の子が、うじゃうじゃ、しかも、お局さまも高卒(短大かも?よく知らない・・・)
国立卒でも、中途採用なので、新米。
まあ、よってたかって、女子が女子を、いじめたおしていた(ように見えた)。
だが、国立卒女性は、理屈に合わないことに関しては、相手にしてなかったように見えた。
背の高い、クールな女性だった。
20代後半に独立して税理士事務所を開いている、K税理士によると、
国立大学卒と、私立大学卒、専門学校卒、高校卒では、デキがまったく違うそうだ。
私立でも、大学ランクによって、ぜんぜん、アタマのランクが違うとのこと。
事務所スタッフ採用にあたって、いろんな人材に接してきたK氏は、
実感として、「○○卒」というのは、単なる、お飾りではない、と仰る。
なかには、冠にそぐわない不純ブツ・不デキ人も混じっているかも知れないが、
だいたいは、学歴に応じた実力を内に持っているそうだ。
わたしが、仮に彼の事務所に(なにかのマチガイで)紛れ込んで入ったら、
「その他大勢の、デキないクズ」として、ゴミ箱ファイルに、即、放り込まれそうだ。
え・・と・・・それは、そうとして・・・
話は、なんでしたっけ・・・??
家政学を究めた高級花嫁を妻にもつ、いくらお稼ぎになるのか知らないが、
仕事で、くたくたに疲れて帰ってきて、さらに家事をさせられる、しかも、嫁は、一日中、家にいるのに、と嘆く花婿さん。
この不平、不満、なんとなく、わかるような気がする。
妻も、ばりばりに能力があり、家で閉じこもっているような人材でないのに、嫌々渋々、今は、事情で家にいる。
もし、バトンタッチして自分が稼いだら、夫なんぞ、ヘのカッパ。
だが、キャリアがないなら、すでに妻は手足をもぎ取られている。
家政科を選び、結婚後も就職せずに、いた妻。
つまり、結婚を選択したというわけだ。
じゃあ、家事しないと、だめですね。
そもそも家政科を選んだあたり、結婚一直線が、見え見えではないか。
夫に家事・育児を手伝わせるのも、今の時流だけれど、
くたくたに疲れて帰ってきている夫に、「はい、これ、やって」と、
当たり前のような顔をして、家事を押し付けるのも、いかがなるものかと。
いっそ、家事は、100パーセント、いや300パーセント妻がやるとして、
そのかわり、夫の給料や福利厚生、待遇のことで、思いっきり意見・希望を夫に述べましょう。
隣の○○さんは、給料は、これこれらしい、△△さんは、海外旅行に家族で行ったらしい、
■■さんは、新車を買った、もっと広いマンションに移った・・・
あれこれ、一気に言いましょう。
家のことは、わたしが300パーセント全力を出し切って担当しているけれど、収入を得るのは、あなたの役目でしょ?
帰ってくる時間が遅いのは、あなたの仕事能率が悪いからよ。
上司が帰らないから、先に帰れない? そんな会社しか、あなたは居るところがないのよ。
そういうわけには、いかない、おまえは仕事のことなんか、なにもわかってないって?
はい、わかりません。
なんでもいから、もっと、給料、多く、とってこい。あんた。
お互い、自分の希望ばっかり押し付けあって、家庭は最悪の雲行きになる。
ここで、わたしの超個人的な意見ですが・・・
いまどき、専業主婦を飼える、いや、間違えた、抱えることのできる夫、って、どれぐらい、いる?
妻には働いてもらって、家計を助けてもらい、自分も家事を負担する。
家事を押し付けられた、疲れた夫は、妻が専業主婦であれば、言い分はあると思う。
もちろん、妻に家事をおしつけられない程度の堂々の稼ぎがあって、の場合だが。
稼ぎは悪いは、家では殿様だ、では、話にならない。
なにか、ひとつ良いことがあれば、ひとつ、良くないことがある。これは仕方ない。
ひとつも良いことがない、あるいは、悪いことばかり、よりは、ましだ。
稼ぎばかりをバロメーターにするもの、偏りがある。
労働に貴賎はないはずだし、金額ばかりにとらわれると、歪が生じる。
お互いの役割に対して、感謝とねぎらいの気持ちを持つということが基本。
厳しく辛い外で思いっきり働けるのは、銃後で家庭をしっかり守っている妻のおかげだ、ということを忘れずに。
生活の基盤となるお金を稼いできてくれる夫なくしては、生活は成り立たないということも肝に銘じて。