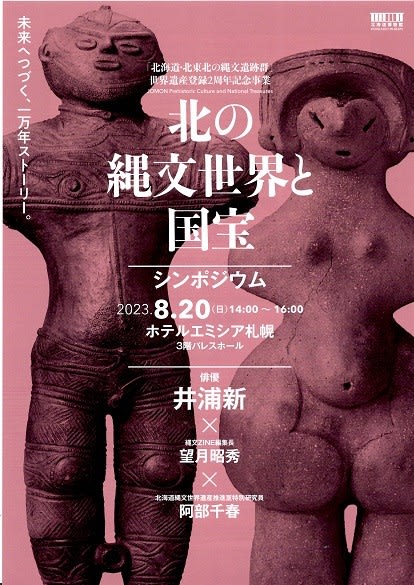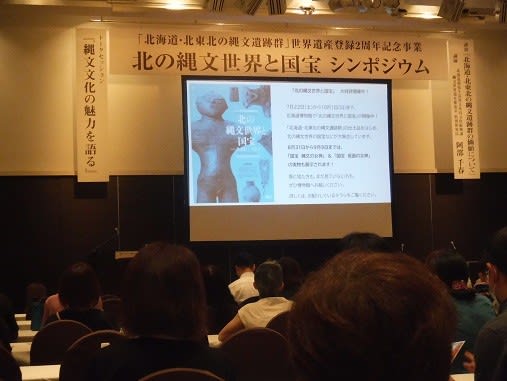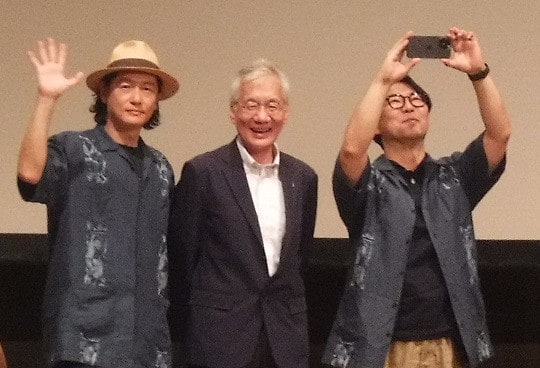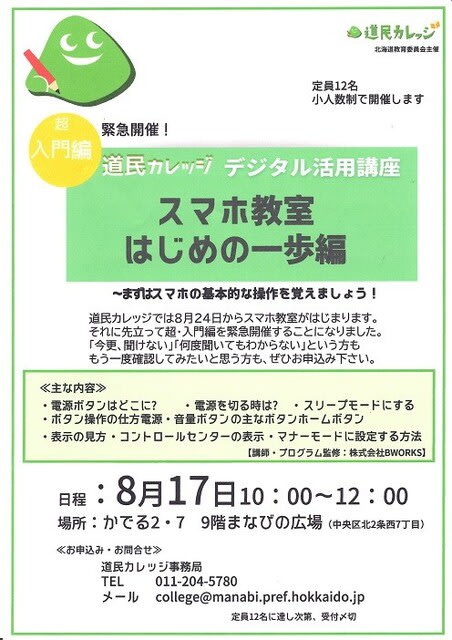花咲か爺さんならぬ、水遣り爺さんがこのところ大奮闘中である。このところの酷暑で花壇の花たちは悲鳴をあげている!?そこで爺さんは朝に、夕に花たちに懸命に水遣りを続けている。
何の因果か、私たち近美前の歩道の清掃ボランティアを続けるグループが何時の頃からかマンション周囲の街路枡花壇の維持管理を行うことになってしまった。思い返すとこちらもすでに少なくとも10年以上が経過している。
我がマンションの周囲には計4ヵ所の街路樹を利用した花壇がある。そこに花苗を植栽し、そして維持管理をすることが私たちに課せられているのである。(その経過はいろいろあるのだが、そのことを詳らかにするのが本投稿の趣旨ではないので割愛する)
当初は管理しやすい四季咲きベゴニアを主として植栽していた。ベゴニアは帯水性に優れていることもあり、あまり水遣りなどは気にしなくとも良かった。しかし、いつまでもベゴニアではなかろうと、昨年からインパチェンスという花に切り替えた。これが意外に乾燥には弱いことが判明した。少し雨が降らないと、たちまち花が萎んでしまうのだ。誰かにお願いするわけにはいかないので、自分がやるしかなかった…。
マンションの前で「私は水遣りをしていますよ~」などとこれ見よがしにするのは気が引けるが花たちは水を待っている。昨年は最低限の水遣りをして過ごした。
ところが今年の気象は異常である。連日の真夏日が続き、花壇の土は乾燥しきっている。私は気恥ずかしさも捨てて、朝に夕に気が付いたときにはできるだけ水遣りをするように心がけた。中にはかなり危うくなりかけた花壇もあったが、積極的に水遣りを続けたために、このところは花たちが元気いっぱいに花を咲かせてくれている。インパチェンスは花の色がいろいろあるが、その配色をどうするかなどといったセンスは皆無なので、アトランダムに配置した花壇の様子を私は気に入っている。
※ マンション東側に配されている3つの街路枡花壇の様子です。

※ 写真がボケているのは愛敬として、こちらはアイビーがあまり育っていません

※ こちらのス入りアイビーは私の好みなのですが、少し元気がありません。

※ こちらのアイビーが一番元気です。
水遣りは毎朝、毎夕というわけにはいかないので、一度に多量の水を撒くことを心掛けている。その水の量は、花壇の大きさが2㎡くらいなので、一度に20リットル前後を撒いている。一つの花壇だけは倍の4㎡くらいあるので、こちらは35リットル前後を撒いている。繰り返し水を撒くことでコツのようなものも見出した。それは、水を花や葉にかけるのではなく、できるだけ花の根元にかけることを心掛けている。

※ こちらが最も大きい北一条側の花壇です。ようやく見てもらえるかな?という花壇になりました。
こうして今、私たちが維持管理する4つの花壇はかなり理想に近い状態に花を咲かせている。インパチェンスの周りに配したアイビーがいま一つではあるのだが…。
酷暑の期間も間もなく終焉となるだろう。その時までせっせと “水遣り爺さん” に徹しようと覚悟を決めている今日この頃の私である。