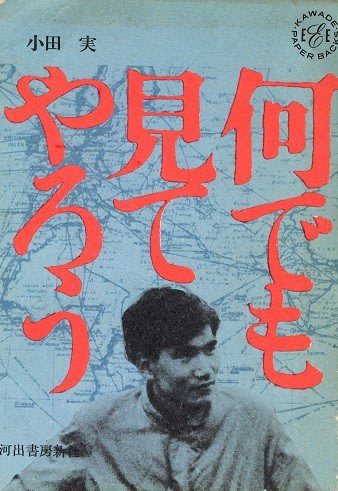年齢を問わず誰もが参加できる学びの場として、昨年度から道民カレッジが全道各地で開催している「学びカフェ」の指導のお手伝いとして昨年から参加させていただいていますが、今年も過日の夕張市に続き、本日室蘭市でお手伝いをしてきました。

道民カレッジでは、・気軽に立ち寄れる ・暮らしに役立つまなびがある ・それぞれのペースで学べる ・新しい出会いがあるかもしれない そんな、あたたかみのある居心地の良いカフェのようなまなびのスペースを参加される皆さんといっしょに創りたいと考えています。
という謳い文句で、今年は帯広市、夕張市、稚内市、室蘭市の4市で「道民カレッジ まなびカフェ」を、すでに開催したり、これから開催を予定しています。
私はそのうち、夕張市と室蘭市の指導のお手伝いを依頼されました。
そして過日8月5日(火)に夕張市の「拠点複合施設りすた」において、最初の授業を担当してきました。
教科は、昨年は「国語科」だったのですが、今年は「理科」を担当することを依頼されました。

※ 夕張市の会場「拠点複合施設りすた」です。
どのような内容を取り扱うか、事務局と相談して小学校3年生の「電気の通り道」という学習を実験学習を中心とした内容で組み立てました。
まずは私たちがふだん手にしているコインは「電気を通すだろうか?」という問いを発し、予想を立ててもらってから、実際に乾電池と豆電球を用意して確かめてもらいました。
コインは、1円がアルミニウム、5円が真鍮、10円が銅、50円、100円が白銅、500円がニッケル銅と、全てが金属製ですから、実験の結果は全て「電気を通す」という結果になり、参加した皆さんも納得でした。

※ このような教材を用意して学習に臨みました。
そこで中間のまとめとして「全てのコインは電気を通しました。これは、コインが全て金属だったからです。金属は電気を通すのですね」とまとめた後、次の問いを発しました。
「それでは私が用意した次のものは電気を通すでしょうか?」と問い、次のようにものを提示しました。
その用意したものとは?
◇ゼムクリップ、◇アルミカップ、◇鉛筆の芯、◇金色の折り紙、◇銀色の折り紙、◇仁丹、◇スチール缶、を用意しました。

※ 夕張会場で予想を立てている皆さんです。手元に飲み物を用意して気軽に学習に臨めるよう配慮しています。
さて、どのような結果になったでしょうか??
こちらも初めに予想を立てていただいてから、確かめの実験をしてもらいました。
その結果については、ここでは秘密にしておきましょう。
面白いのは、金色と銀色の折り紙では違う結果だったということです。さて、皆さまはお分かりですか?
不安に思われる方は、百均ショップに金色と銀色の折り紙が販売されていますから、お確かめください。
このような簡単(?)な学習を本日も「室蘭市生涯学習センターきらん」に集まっていただいた9名の皆さまと一緒に学習してきました。(夕張会場は14名でした)
さて、どのような結果になったでしょうか??
こちらも初めに予想を立てていただいてから、確かめの実験をしてもらいました。
その結果については、ここでは秘密にしておきましょう。
面白いのは、金色と銀色の折り紙では違う結果だったということです。さて、皆さまはお分かりですか?
不安に思われる方は、百均ショップに金色と銀色の折り紙が販売されていますから、お確かめください。
このような簡単(?)な学習を本日も「室蘭市生涯学習センターきらん」に集まっていただいた9名の皆さまと一緒に学習してきました。(夕張会場は14名でした)

※ 室蘭市の会場「室蘭市生涯学習センターきらん」の外観です。
両会場ともに立派な施設でした。
どちらの会場も参加していただいた方々が嬉々として取り組んでくれたことが私には嬉しいことでした。

※ 室蘭市会場でもう一つの教科の学習に取り組む皆さんです。
私はさらに10月にもう一度室蘭市でお手伝いすることになっています。さて、次はどのような教材で皆さまと一緒に学習しようか?と頭を悩ましてみたいと思っています。