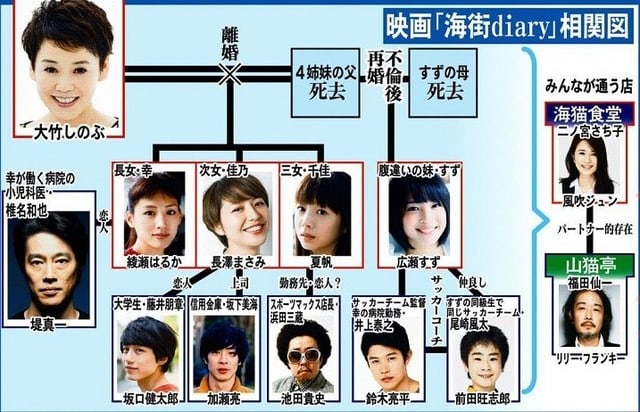ビルの谷間にひっそりと建つ古民家を再利用した珈琲館は、内部は和モダンといったつくりで落ち着ける空間だった。久しぶりの本格的なカフェ訪問だったが、オーダーしたカフェオレも、プレーンワッフルも満足の一品だった。

今日は風が冷たい一日だったが、空は晴れていたので一昨昨日に続いて春の兆しを探しに自宅周辺を中心に10キロほどあちこちと歩いてみた。しかし、まだ日当たりの良い戸建て住宅のどの庭先にも花らしきものを見かけることはなかった。
ガッカリしながら帰路についた時、「そうだ!」(とここで膝を打つ)「過日(3月9日)のぶらり散歩で見かけたカフェに寄ってみよう!」と思い立った。それはブログの上での知人である出ちゃっ太さんのたっての希望でもあったからだ。(あれっ?希望してたかな?)

というわけで北6条西20丁目のビルの間に建つ古民家を再利用した北円山店を午後1時過ぎに訪れた。内部は建築当時のつくりを極力そのまま活かしたというが、当時としてはかなりモダンな暮らしをしていたことが想像されるような感じだった。窓際のディスプレーや、テーブル・椅子なども凝ったつくりで和モダンを演出していることが感じられた。

店内は休日とあってグループやカップルの客が目立った。私は小腹が空いていたこともあって、ワッフルとカフェオレをオーダーした。するとそれらが出されるまでにけっこうな時間待たされた。店のホームページを見てみると、ワッフルは注文が出されたから焼くため「少々時間がかかる」と出ていた。納得である。


提供されたプレーンワッフルは予想していたよりボリュームがあったのでちょっと驚いたが、甘みをやや抑えた上品な味が好ましかった。また、最近はコクのあるコーヒーは苦手になりつつある私にはカフェオレも優しく感じられて良い味だった。

午後のひと時、オヤジが一人でカフェに佇む図はどうなのだろう?次の機会には出不精の妻と一緒に来てみようかな?
【サッポロ珈琲館 北円山店 データー】
北海道札幌市中央区北6条西20丁目1-5
電 話 011-615-7277
営業時間 9:00~21:30
定休日 月曜日(基本は月曜日だが、変更の場合有り)
駐車場 有(10台)
座 席 55席(カウンター席・個室あり)
入店日 ‘15/09/20
※ というわけで、5日ぶりに映画関連以外の投稿ができたが、アカデミー賞関連のDVDはまだ残っている。明日からまたしばらくは映画関連の投稿が続きそうである。