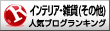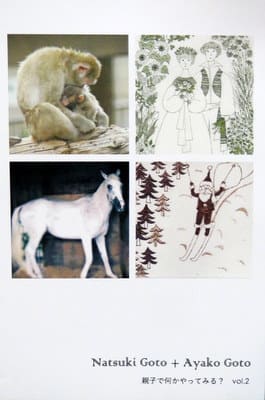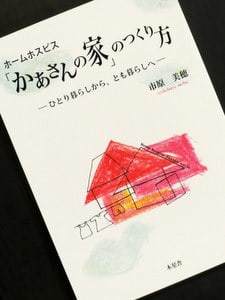いや~びっくりした
まさかこんな展開になろうとは
年末に落語に行こう、と誘われたのは11月のこと。
友人は柳家喬太郎さんという落語家のファンなのだという。
失礼ながら存じ上げないが、チケットはすぐに売り切れてしまうとか・・・。
この日は柳亭市馬と言う人の落語の会だけれど、ゲストとして出演するという。
誘われたら断らない、を信条としているので、もちろん行っちゃう。
会場は新宿文化センター。
東新宿という駅は初めてだ。
入り口でプログラムが配られる。
「あれ?」と友人が声を上げる。
歌?
彼女が様子がおかしいのでプログラムを見る。

彼女のお目当ての喬太郎さんは第一部の「落語競演」ではなく、「第二部 昭和歌謡大全集」のところにお名前が。
そもそも「昭和歌謡大全集」って?
どうやら彼女も事情が呑み込めてない様子。
そうこうしているうちに幕が上がり、今日の主役市馬さんの落語「厄払い」がはじまる。
仲入となり、ふたたび幕が上がると、ビミョーなオーケストラ(?)が座っている。
市馬氏の弟子という蝶ネクタイに銀色のスーツの人が、昔の歌謡番組のような司会を始める。
そして始まる「丘を越えて」
え?ホントに歌?
しかも、ほとんど知らない曲

喬太郎さんまで何やらわけのわからない下ネタソングを1曲歌っておしまい。
どこの忘年会だ
舞台の上では市馬さんが気持ちよさそうに歌い続ける。
確かにちょっと藤山一郎さんっぽいかも。
テレビ東京で年末にこんなのやってなかったっけ?なんて思いながら見ていたら、
段々可笑しくてたまらなくなってきた。
こんな面白い舞台に遭遇することなんて、きっと二度とない
喬太郎さんが歌い終わり、ああ、ホントに歌だけなんだ、と思ったころ、
バラバラと帰りだす人たちが。
私の隣にいたオジサマも、さっとバッグを持ち上げ席を立った・・・。
彼らも、きっと間違えたに違いない。
友人は「ごめんね 」と何度も謝るけれど、もともと喬太郎さんを知らない私はそれほどの落胆もない。
」と何度も謝るけれど、もともと喬太郎さんを知らない私はそれほどの落胆もない。
むしろ、こんなことがなければ、一生お目にかかれない貴重な経験だ。
しかも、大半の人は「歌」とわかっていて、ペンライトまで用意して振ったりしていた。
会場には1500人もいる、とご本人がおっしゃる。
まあ、気持ちよさそうに歌う歌う
人間、力があるとこんなこともできちゃうんだなあ、と妙に感心しちゃった不思議で楽しい夜でした。

まさかこんな展開になろうとは

年末に落語に行こう、と誘われたのは11月のこと。
友人は柳家喬太郎さんという落語家のファンなのだという。
失礼ながら存じ上げないが、チケットはすぐに売り切れてしまうとか・・・。
この日は柳亭市馬と言う人の落語の会だけれど、ゲストとして出演するという。
誘われたら断らない、を信条としているので、もちろん行っちゃう。
会場は新宿文化センター。
東新宿という駅は初めてだ。
入り口でプログラムが配られる。
「あれ?」と友人が声を上げる。
歌?
彼女が様子がおかしいのでプログラムを見る。

彼女のお目当ての喬太郎さんは第一部の「落語競演」ではなく、「第二部 昭和歌謡大全集」のところにお名前が。
そもそも「昭和歌謡大全集」って?
どうやら彼女も事情が呑み込めてない様子。
そうこうしているうちに幕が上がり、今日の主役市馬さんの落語「厄払い」がはじまる。
仲入となり、ふたたび幕が上がると、ビミョーなオーケストラ(?)が座っている。
市馬氏の弟子という蝶ネクタイに銀色のスーツの人が、昔の歌謡番組のような司会を始める。
そして始まる「丘を越えて」

え?ホントに歌?
しかも、ほとんど知らない曲


喬太郎さんまで何やらわけのわからない下ネタソングを1曲歌っておしまい。
どこの忘年会だ

舞台の上では市馬さんが気持ちよさそうに歌い続ける。
確かにちょっと藤山一郎さんっぽいかも。
テレビ東京で年末にこんなのやってなかったっけ?なんて思いながら見ていたら、
段々可笑しくてたまらなくなってきた。
こんな面白い舞台に遭遇することなんて、きっと二度とない

喬太郎さんが歌い終わり、ああ、ホントに歌だけなんだ、と思ったころ、
バラバラと帰りだす人たちが。
私の隣にいたオジサマも、さっとバッグを持ち上げ席を立った・・・。
彼らも、きっと間違えたに違いない。
友人は「ごめんね
 」と何度も謝るけれど、もともと喬太郎さんを知らない私はそれほどの落胆もない。
」と何度も謝るけれど、もともと喬太郎さんを知らない私はそれほどの落胆もない。むしろ、こんなことがなければ、一生お目にかかれない貴重な経験だ。
しかも、大半の人は「歌」とわかっていて、ペンライトまで用意して振ったりしていた。
会場には1500人もいる、とご本人がおっしゃる。
まあ、気持ちよさそうに歌う歌う

人間、力があるとこんなこともできちゃうんだなあ、と妙に感心しちゃった不思議で楽しい夜でした。