地元埼玉県三郷市の「防災訓練指導者養成講座」の第1回に参加した。このような講座は三郷市独自のものだそうだ。もう10年以上も歴史がある。今まで2,100人が参加して600人が修了している。そして指導者ネットワークに参加している人は三郷市全体で200人以上に及ぶ。

この組織は自主防災会であり、総理大臣から表彰も受けているほどだ。講座は第1回から第3回があり、これらに継続して参加して、3回目を終了すると、指導者になる。2回目、3回目になるにつれてだんだん参加者が減って来るそうだ。費用は無料、しかし、なかなか継続できないようだ。
私は、管理組合の理事会で知って参加を立候補したものだ。さて第1回の内容は、午前は応急救護訓練だ。三角巾、止血、搬送、応急担架など。そして心臓マッサージとAED。私は、消防の救急訓練で何度もやっているやつだ。
三角巾は指導が下手。私はコードの結び方をマネジメント研修でやっている。コードを結んで見せて、受講生にやってもらう。簡単そうだが、これがなかなかできない。受講生には、あなたの部下もよくわかっていないんですよと、気付きを与えるものだ。今回の先輩指導者の方もまったく同じ。1,2回やって見せて、さあやってください、と言う。できるわけがない。5~10回も手取り足取りやってやっとわかるレベルのものだ。イライラして思わず、「わかるわけないだろ!」と怒鳴ってやりたかったがやめた。
この指導者の方々、ボランティアで防災指導者の生きがいを持ってらっしゃるようだ。それはそれで結構なことだが、皆、後期高齢者クラスだ。悪い言い方をすると、年金が入って、働く必要もなく、やることもないから防災をやってるとも言える。私のような60歳代前半以下の若い世代は全くいないのだ。若い人は、子育て、教育、ウチを買うなど、生活に一生懸命で、ボランティアなどやってる暇などない。
仮にほんとに地震が起きたら、この後期高齢者の方々を転倒家具から助け出すようになる気もするが・・、その方々から研修を受けている。
昼食は、炊き出し訓練の昼食、トン汁だ。午後は外に出て、まずは、転倒家具からの救出訓練、消火器、天ぷら火災の消火、最後は、バケツリレーだ。

蒸し暑い日の訓練であった。あと2回、今度は秋、その次が真冬だ。続くかな。
















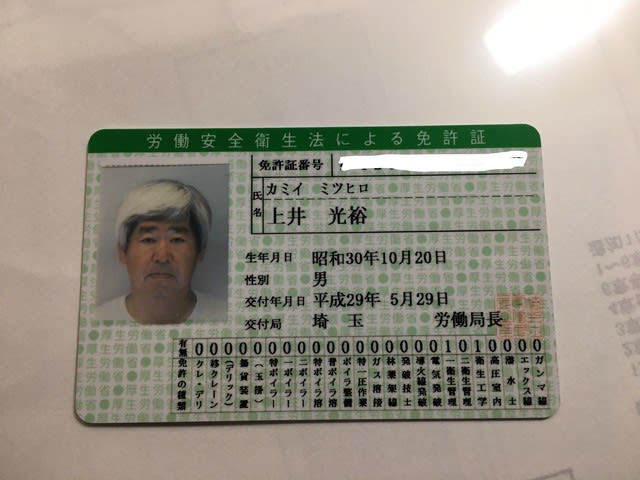


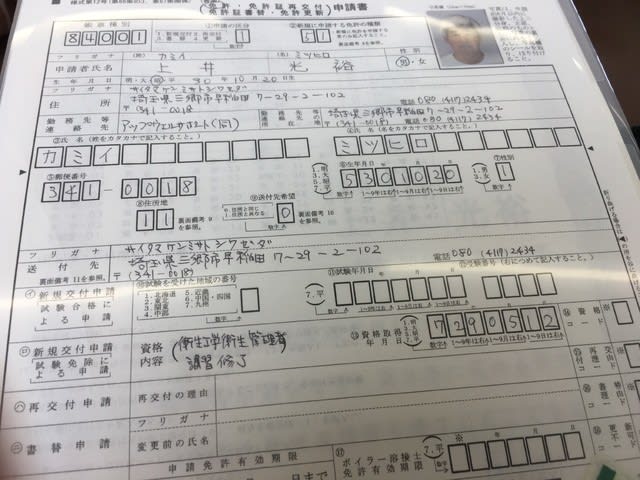
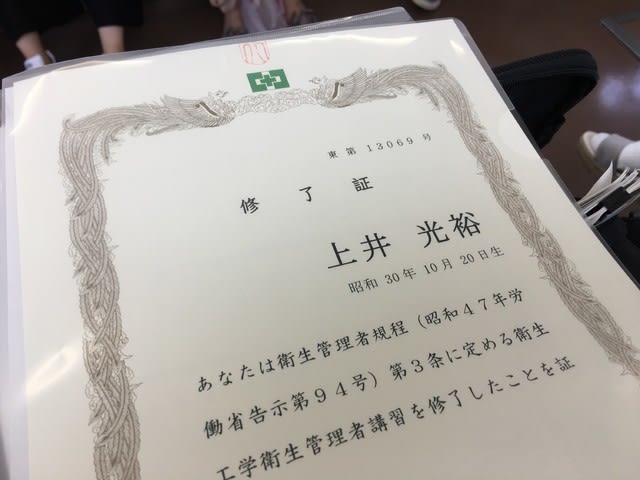



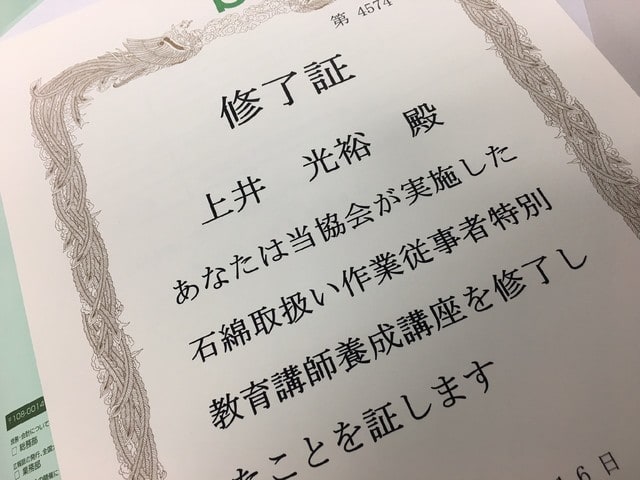


 測定
測定








