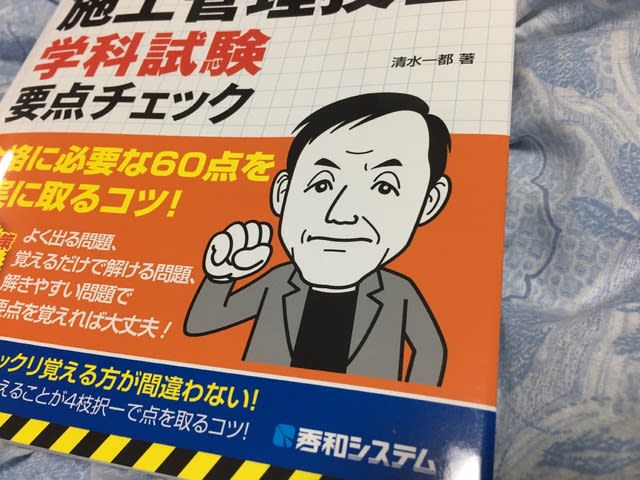建設不動産総合建設研修センター(略して、CECC)から2018年度の土木施工管理技士2級の講座を開講した。この講座、もう3年目になる。今年の改訂は、平成29年度本試験の解答解説を入れたことだ。

その経緯を少し話すと、もともと私は土木が専門だが、企業時代はガス工事、いわゆるライフラインだった。そのため当初の講座は、土木のうち、ライフライン技術者向けのものに絞った。ダムやトン熱、港湾や海岸などは実務経験がないためだった。翌年は、かなり勉強してライフライン以外の、ゼネコンとしてフル講座に拡充した。そして今年は、ポイント解説は変更が必要ないと判断し、取り入れていない、平成29年度本試験(学科、実地とも)に解答解説を入れてリニューアルしたものだ。
昨年はかなりの数の方に講座を視聴していただいた。こちらが通販会社のサンプル講座になります。講座価格は27,000円ですが、しばらくは5,000円引きの2,2000円で発売します。27,000円は、数ある土木講座の中でも最も安い部類だと思います。
昨年からこの試験、年に2回実施されるようになったようだ。土木の登竜門、土木施工管理技士、2級は1級に比べて取り組みやすいし、自信をつけて1級にチャレンジできますかな、まだ持ってない方、お勧めですよ。受験の際はこちらの受験資格を確認してくださいな。




















 あと
あと