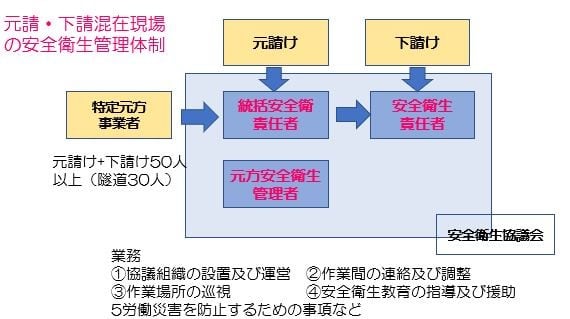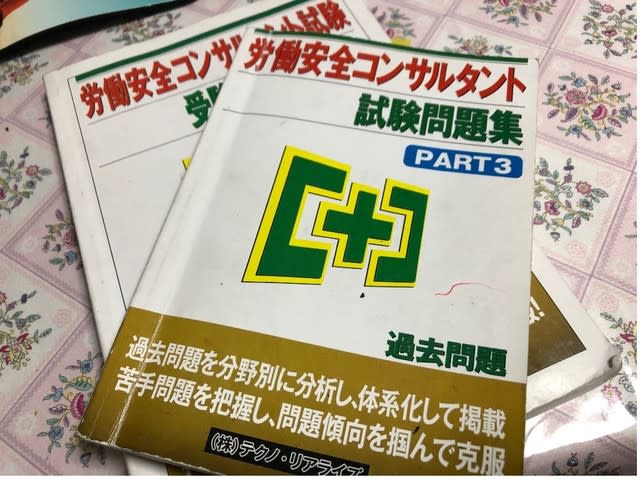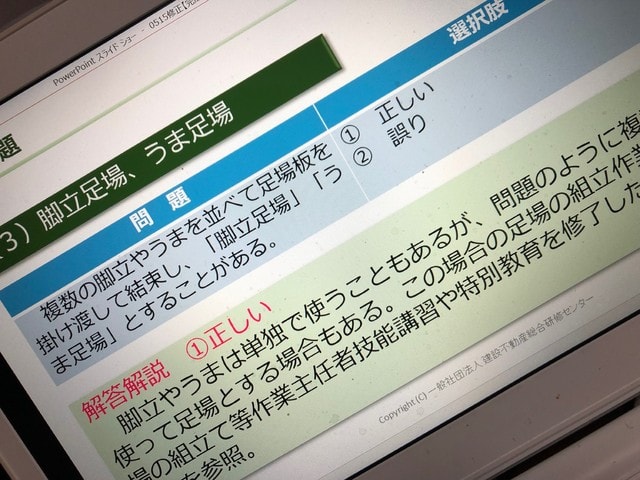労働安全コンサルタントの学習、その2。機械による危険防止。ここは掘削など土木工学ならわかるが、機械工学の分野、実はちょっと苦手だ。
そして、初めて聞く機械の用語が結構ある。プーリー、プレーナー、割刃、バフ盤などだ。プーリーとは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品、プレーナーとは、木材をつやつやに仕上げる加工の工具、割刃は、回転する刃を覆うカバーのようなもの、バフ盤は、表面仕上げの工程で使うが、柔らかい布の上に研磨剤を塗って回転させるもの。いろいろあるな。

それに条文によって、特徴がある。例えば、労安法106条 切削くずが飛来し、危険がある場合は機械に覆い又は囲いを設けなければならない、但し作業の性質上困難な場合は保護具を使用させると作業ができる。一方、126条手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。とある。こちらは但し書きはない。
つまり条文によって、但し書きがあるものとそうでないものがある。そして出題はこの辺のことを突いてくる問題が多い。と言う訳で、条文1つずつ、但し書きを確認して、覚えていく。もちろん短期記憶だ。試験が終われば忘れていい。(1月に面接があるから、その時にはまた覚えるないといけないけどね)同じような条文は、荷役運搬機械もたくさんある。ああ大変だ。