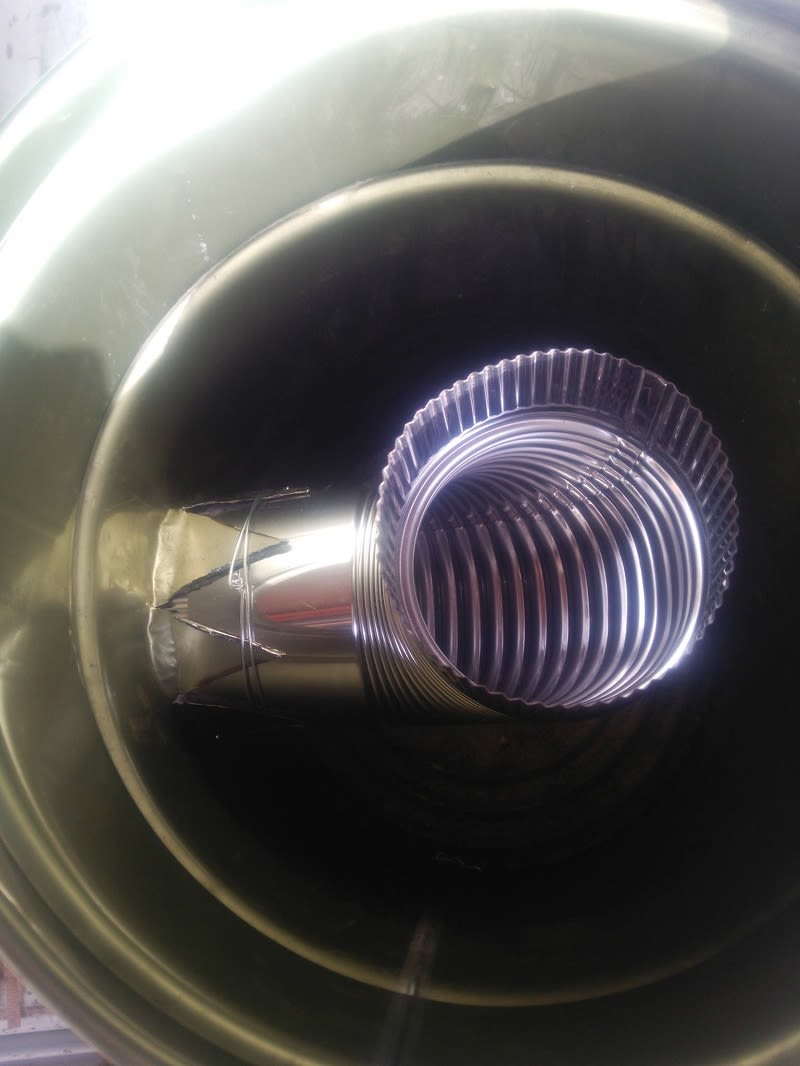今回、再び節電要請が取扱われる番組や報道内容は相も変わらずといった印象を受けました。マスコミからすれば目新しいトピックに飛びつくだけで、内容なんてどうでも良いのではないかという位に当時と似たような内容です。再び注意喚起を促さないと無用な混乱を招きそうです。
そこで私が投稿した記事を調べてみますと「誤解を招きかねない節電方法に関する報道」というのがありました。
そしてまたも繰り返される電力と電力量の混同(参考:「ティータイム 第8話 電力と電力量」)です。この混同が不要な混乱を招き不必要な節電によって熱中症の危険にさらされ命を失ってしまうという重大な結果をもたらしてしまうということにもなりかねません。他にも突っ込みたいことは沢山ありますが、既に記事にして投稿しておりますので今更という感じです。
そんな中でも電力会社が実施予定(既に実施している電力会社もあり)だという節電ポイント制度というのは比較的効果がありそうです。今回の節電要請の本来の趣旨はピーク電力をカットすることです。そこで電力会社が逼迫しそうな時間帯に登録ユーザー(?)に節電要請をスマホ経由で通知し、それを受けた需要家が節電行動を行い、その実績に応じたポイント還元を行うといったものです。逼迫した時間帯以外には普通に使っても構いませんので、負担の少ない良い方法だと考えます。ただし、これは実施者数が多くなければ効果が出ませんので、その有効性は今後のPRに掛かっているものと思います。