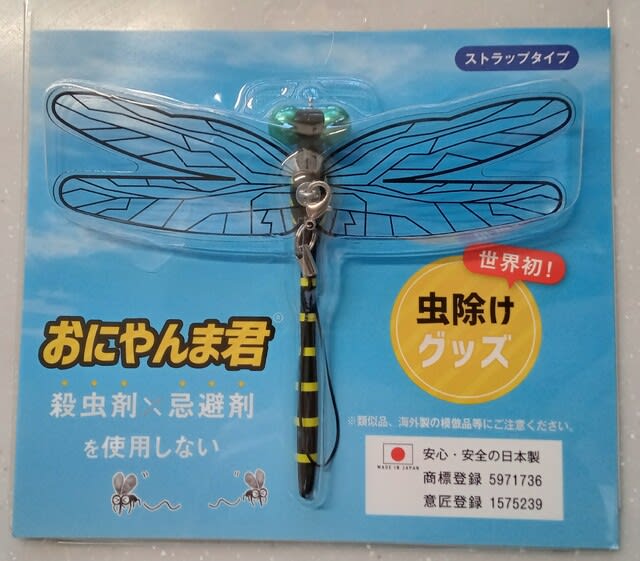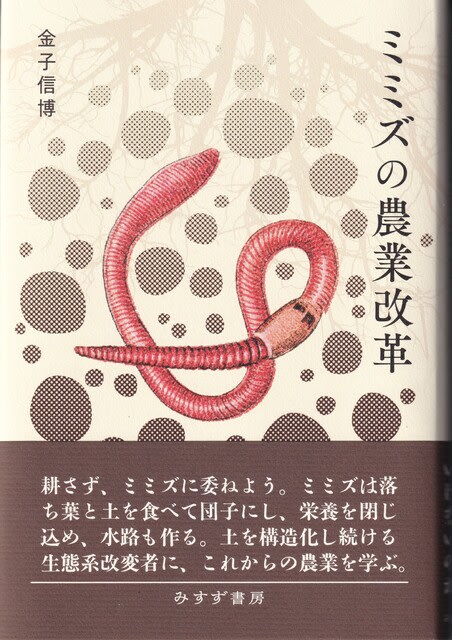ちょっと油断すると畑が草だらけになってしまいます。次の画像は落花生の畝です。

落花生の間からツユクサが繁って落花生を覆いつくしてしまう勢いです。ツユクサはそんなに根が張らないので、上方に引っ張ってあげれば容易に抜くことが出来ます。下手に鎌などを使うと作物まで刈ってしまうことになりますので私はあまりやりません。ツユクサや他の草を抜いてやると落花生が表れてきました。日光があまり当たっていなかったので弱々しい感じです。

バターナッツやマクワ瓜も草に埋もれていました。

除草作業中、何の拍子かツユクサが食べられることを思い出しました。そう言えば最近菜っ葉類を食べていないことに思い当たりました。せっかく抜いたツユクサですから、このままにしておくのも勿体ないので、試しに食べてみることにしました。茎の方は硬そうなので、新芽の部分だけかき取りました。取り敢えずは、2分程湯がいてみました。

試食してみましたところ、苦み、渋み、えぐみなどなく、ちょうど甘みの無いほうれん草みたいな感じでした。さすがに美味いとまでは言えませんが、菜っ葉類が無いときの代用にはなりそうです。調理次第では立派な食材になるかも知れません。
ツユクサは謂わば畑の厄介者なのですが、これを野菜だと思えば除草作業ではなく収穫ということになります(笑)
そういえば、スベリヒユも見かけたな。これも食べられるとのことです。他にも食べられる野草が多々あると思います。そうなんです、畑は食材の宝庫なのです。それも何もせずとも毎年勝手に生えてきてくれるのですから・・・。そう言った目で畑を眺めてみると今までと違った地平が見えてきそうです。

落花生の間からツユクサが繁って落花生を覆いつくしてしまう勢いです。ツユクサはそんなに根が張らないので、上方に引っ張ってあげれば容易に抜くことが出来ます。下手に鎌などを使うと作物まで刈ってしまうことになりますので私はあまりやりません。ツユクサや他の草を抜いてやると落花生が表れてきました。日光があまり当たっていなかったので弱々しい感じです。

バターナッツやマクワ瓜も草に埋もれていました。

除草作業中、何の拍子かツユクサが食べられることを思い出しました。そう言えば最近菜っ葉類を食べていないことに思い当たりました。せっかく抜いたツユクサですから、このままにしておくのも勿体ないので、試しに食べてみることにしました。茎の方は硬そうなので、新芽の部分だけかき取りました。取り敢えずは、2分程湯がいてみました。

試食してみましたところ、苦み、渋み、えぐみなどなく、ちょうど甘みの無いほうれん草みたいな感じでした。さすがに美味いとまでは言えませんが、菜っ葉類が無いときの代用にはなりそうです。調理次第では立派な食材になるかも知れません。
ツユクサは謂わば畑の厄介者なのですが、これを野菜だと思えば除草作業ではなく収穫ということになります(笑)
そういえば、スベリヒユも見かけたな。これも食べられるとのことです。他にも食べられる野草が多々あると思います。そうなんです、畑は食材の宝庫なのです。それも何もせずとも毎年勝手に生えてきてくれるのですから・・・。そう言った目で畑を眺めてみると今までと違った地平が見えてきそうです。