「国民の祝日に関する法律」の第1条には、
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築き上げるために、ここ国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
とあります。
日本の国民の祝日は、16日あります。
が、「春分の日」と「秋分の日」は、前年2月1日に官報で発表されます。
2007年から4月29日の「みどりの日」が「昭和の日」と変わります。
又、5月4日の「国民の祝日」が「みどりの日」となります。

今日の絵は、イタリア カプリ島 F6号
第3条第2項が、2007年から「国民の祝日」が日曜日に当たる時は、その後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とすると変更されます。
2007年には月曜日が振替休日となるのは、2月12日、4月30日、9月24日、12月24日の4回ありますが、第3条第2項が該当する休日は、2008、09年に発生します。
つまり、5月3日(土)憲法記念日、5月4日(日)みどりの日、5月5日(月)こどもの日となり、ここで初めて月曜日以外の振替休日が5月6日(火)となります。
第3条3項も 休日前日及び翌日が「国民の休日」である場合は、その日を休日とすると変更されます。
この休日の発生は2009年9月21日(月)敬老の日、9月23日(水)秋分の日でその間の9月22日(火)が振替休日となります。
要は、振替休日を増やすことにありますが、この恩恵に与るのは2008年からになります。










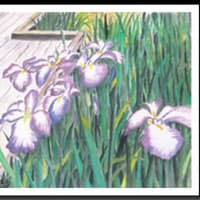


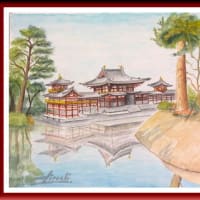



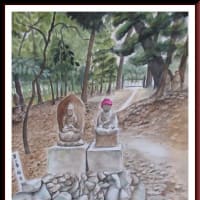

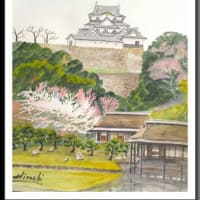
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます