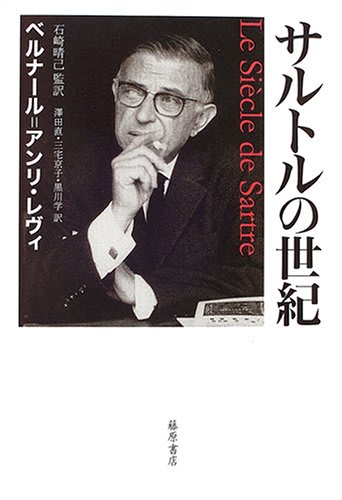ゲルハルト・ヴェーア「評伝マイスター・エックハルト」
翻訳がもうちょっとどうかなってたら、エックハルトの入門書として面白かったかもしれない。
昔エックハルトの説教集を読んで、一遍上人の考えとかなり近いんじゃないか、と感心したことがあった。生まれは一遍上人の方がちょっと早いが、まあ同時期の中世、片や鎌倉、片やドイツ。どちらも求めたいものを厳密に求めようとして、それが対象として求められるものではないことを痛感したのではないか、と思う。法や神や仏、など言葉は違うにしても。
エックハルトの言う一者と一遍の言う不二はまさに通じ合う。
「神はまったくの一であり、どのような様態も特異性もないのであるから、神とは父でもなければ子でもなく、聖霊でもないのである。」(ここにこれと対応する一遍上人の言葉を入れられたらいいのだが、引っ越しのためその本はまだ段ボールの中………)。
このようなことを中世に言ってしまったエックハルトは、やはり異端審問の標的となる(全然関係ないがぼくは「まさかのときにスペインの異端審問」というモンティ・パイソンのギャグが大好きである)。
栄達きわまりない前半生に比べ、年を取ってからのエックハルトの姿は悲しい。
さて、この本の特徴は、最後の3章にある。エックハルトの生涯(分からない部分も多いが)や説教の解説を書いてある本は多いが、その思想が今日どのような影響をもたらしたのか、あるいは現代の作家や思想家の中にどのようなエコーを響かせているのか考察した本は少ない。ナチス、マルティン・ブーバー、エーリッヒ・フロム、カール・グスタフ・ユングなどなど。しかし、限られた紙数のせいか、どれもが舌足らずな印象をぬぐえない。
つまり、この本の立ち位置が分からないのだ。初心者に読ませるには、説明が足りないし、エックハルト好きな人間に読ませるには食い足りない内容。翻訳ともども、ちょっと不満。
「神秘思想家とは今ここで信じる者である。キリスト教の神秘を今ここで覚りそれによって生きる者である。」
空海の即身成仏にもつながる概念である。
翻訳がもうちょっとどうかなってたら、エックハルトの入門書として面白かったかもしれない。
昔エックハルトの説教集を読んで、一遍上人の考えとかなり近いんじゃないか、と感心したことがあった。生まれは一遍上人の方がちょっと早いが、まあ同時期の中世、片や鎌倉、片やドイツ。どちらも求めたいものを厳密に求めようとして、それが対象として求められるものではないことを痛感したのではないか、と思う。法や神や仏、など言葉は違うにしても。
エックハルトの言う一者と一遍の言う不二はまさに通じ合う。
「神はまったくの一であり、どのような様態も特異性もないのであるから、神とは父でもなければ子でもなく、聖霊でもないのである。」(ここにこれと対応する一遍上人の言葉を入れられたらいいのだが、引っ越しのためその本はまだ段ボールの中………)。
このようなことを中世に言ってしまったエックハルトは、やはり異端審問の標的となる(全然関係ないがぼくは「まさかのときにスペインの異端審問」というモンティ・パイソンのギャグが大好きである)。
栄達きわまりない前半生に比べ、年を取ってからのエックハルトの姿は悲しい。
さて、この本の特徴は、最後の3章にある。エックハルトの生涯(分からない部分も多いが)や説教の解説を書いてある本は多いが、その思想が今日どのような影響をもたらしたのか、あるいは現代の作家や思想家の中にどのようなエコーを響かせているのか考察した本は少ない。ナチス、マルティン・ブーバー、エーリッヒ・フロム、カール・グスタフ・ユングなどなど。しかし、限られた紙数のせいか、どれもが舌足らずな印象をぬぐえない。
つまり、この本の立ち位置が分からないのだ。初心者に読ませるには、説明が足りないし、エックハルト好きな人間に読ませるには食い足りない内容。翻訳ともども、ちょっと不満。
「神秘思想家とは今ここで信じる者である。キリスト教の神秘を今ここで覚りそれによって生きる者である。」
空海の即身成仏にもつながる概念である。