
江戸時代は石高1万石以上が大名で、それ以下が旗本であるが、本多家の祖、正重は、大阪の陣の功績により、相馬藩1万石の譜代大名となった。しかし、その子の代に2000石減らされ、相馬藩は廃藩、8000石の旗本(1617~1664)となった。その石高の内訳は、葛飾・相馬の2郡、28ケ村(6000石)、香取郡2ケ所(2000石)であり、柏市の布施弁天様がある布施村も本多家の知行地となっている。その後、布施弁天に絵馬等を奉納し手厚く弁天様を庇護した4代正永の時に4万石(1703~1711)となり、沼田藩主となる。そして、6代正矩の時に駿河国の田中藩(現在の静岡県藤枝市)に4万石のまま配置換え(1730年)されたが、柏の村々は飛び地の知行地のままで明治維新まで続いたのである。
享保のころ、柏市には22の村があったが、うちの14カ村が本多家の領地で、これを治めるため、市内の藤心と船戸に代官所をおいていた。一説によると、元和4年(1618)船戸村字久保内屋敷の地には船戸役所があったともいわれるが、写真はその船戸の代官所跡であり、近くにある代官の墓地が唯一往時を忍ばせるものである。先般、記したが、布施弁天は、この本多侯の祈願所となったため、繁栄したのであり、本多侯には感謝しても感謝仕切れないが、その本多侯が寄贈した鳥居が1200年祭を前にしても、広場に無惨に放置されているのはいかがなものであろうか。そして、布施弁天には、もう庇護者は現れないのであるうか?布施弁天の文化財を守る会に、それを要求するのは酷というものであろう。
享保のころ、柏市には22の村があったが、うちの14カ村が本多家の領地で、これを治めるため、市内の藤心と船戸に代官所をおいていた。一説によると、元和4年(1618)船戸村字久保内屋敷の地には船戸役所があったともいわれるが、写真はその船戸の代官所跡であり、近くにある代官の墓地が唯一往時を忍ばせるものである。先般、記したが、布施弁天は、この本多侯の祈願所となったため、繁栄したのであり、本多侯には感謝しても感謝仕切れないが、その本多侯が寄贈した鳥居が1200年祭を前にしても、広場に無惨に放置されているのはいかがなものであろうか。そして、布施弁天には、もう庇護者は現れないのであるうか?布施弁天の文化財を守る会に、それを要求するのは酷というものであろう。















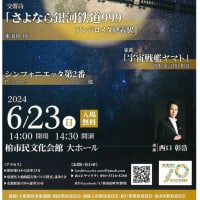


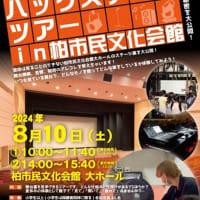






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます