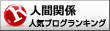礼拝宣教 ルカ6章1-11節
本日は安息日に起こった2つの出来事から、御言葉に聴いていきたいと思います。
ここに登場するファリサイ派の人々たちというのは、律法を厳格に守り、聖なる者として生きるために、自ら世俗と分離させる考えに立つ人たちでした。彼らは「神の救いによる復活の信仰」を持っていましたが、残念ながら目の前におられるイエスさまを受け入れることができませんでした。それどころか、イエスさまのお言葉とそのなされる行いに反感と敵意を燃やします。それはイエスさまが規定に縛られるのではなく、律法の本質とその精神を体現なさったからです。しかも前の4章、5章に記されたようにイエスさまの言葉とその教えには「神の子としての権威」があったということです。そのためすでに多くの民衆がイエスさまを慕い求めて従おうとしていましたから、一部のファリサイ派の人たちや律法の専門家たちは自分たちの地位をも脅かしかねないと、イエスさまに対して激しい怒りと嫉妬の念を持っていたのです。そこで彼らは何とかしてイエスさまの揚げ足を取って貶めようと策略を図るのです。
その最初の策略は、安息日にイエスさまの弟子たちがあまりの空腹のため麦の穂を手で摘んで食べたことを問題にして、ファサイ派の人たちは、「律法では安息日に労働することを禁じているのに、手で穂を摘んで手で揉み、殻をとって食べた。それ安息日に働いた律法違反じゃないか」と、訴えるのです。
それに対してイエスさまは、「安息日は、人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない」と、ズバッとお答えになるのですね。
イエスさまはユダヤ人として生まれ、ユダヤの宗教教育や律法について学ばれ、それを大事にされていました。マタイ福音書の5章のところでイエスさまは、「わたしが来たのは律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである」と、おっしゃっているとおりです。
律法とは、そもそも人が人として生きるためにあるもので、神の御心に適う祝されたあゆみをなすために与えられたものなのです。そもそも人を縛り、裁くためにあるのではない。「安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない」と、おっしゃるのです。
出エジプト記には、安息日に関する様々な規定が記されています。その20章8節以降に、律法の大本となる十戒の1つとして、「安息日を心に留めこれを聖別せよ」との主のお言葉がこう記されています。それは「6日の間働いて、7日目は主の安息日だから如何なる仕事もしない。息子も娘も、さらに奴隷も、家畜も寄留者も安息日とする。なぜなら主なる神さまご自身6日の間天地創造のみ業をなされ、7日目に休まれたから。主がそうして安息日を祝福し聖別なさったから」、というのですね。又、23章12節以降には、「奴隷や寄留者や家畜を休ませて、元気を回復させ、過酷な労働から保護する」規定が記されています。さらに31章13節以降には「過酷な労働から弱者や奴隷を保護せず、安息日を侵害する者に対する厳格な裁き」について記されています。
それらはかつてエジプトで奴隷の状態にされていたイスラエルの民を神が救い出されたその恵みの出来事に、応答してそのようにしなさい、ということであります。
もう、おわかりですね。そもそも「安息日とは、人間が神の御業と祝福に応えるべく聖別された日であると共に、苦役や過酷な搾取から人間を解放し、安息して生きる力を取り戻す日である」のです。
私たちも又、主イエスによって救われ、解放を受け、その感謝と喜び、又救いを求める願いがあるからこそ、こうして時間を聖別し、ここに集うのであります。そこに安息を見出すからです。
私たちも又、主イエスによって救われ、解放を受け、その感謝と喜び、又救いを求める願いがあるからこそ、こうして時間を聖別し、ここに集うのであります。そこに安息を見出すからです。
聖書に戻りますが。そのような祝福の安息日のはずが、一部の熱心なファリサイ派の人々たちは、その規定の精神や心を大切にすることよりも、ただ規定を杓子定規に、マニュアルどおり厳守することにこそ神に従うことだと考え違いするようになったのです。
そうなりますと、自分たちがそのことに捕らわれるだけでなく、人を裁くようになっていきます。様々な事情を抱えて安息日も労働して生活を守らなければならない人たちもいました。規定を守ることが難しい事情があったのです。又、社会的に弱く貧しい人たちは、宗教教育も受けられず律法の知識を持てないまま厳しい境遇や貧しさのため、その日暮らしで精いっぱいです。神の聖別された安息日とその精神は活かされず、格差と分断が惹き起こしていたのです。
さて、もう一つの安息日に起こった出来事について見ていきましょう。
ある安息日にイエスさまが会堂にお入りになると片手の萎えた人がいました。ファリサイ派の人たちは、「イエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気をいやされるかどうか、注目していた」とあります。彼らは、ここでイエスが「いやし」を行えば、安息日に労働して規定を破るとは何事か、とイエスを訴えようとしたのであります。
すると、イエスさまはこのファリサイ派の人たちの思いを見抜いて彼らに言います。「安息日に律法で許されているのは、善を行うことか。悪を行うことか。命を救うことか、殺すことか。」
このイエスさまの権威あるお言葉に対して、ファリサイ派の人たちはただ沈黙するほかありませんでした。仮に彼らがここで、「善を行うことです」「命を救うことです」と答えるなら、それはイエスさまのなさったことを認めることになります。結果的に益々民衆はイエスさまに従うようになっていくでしょう。
反対に病人を見捨てるともとれるような発言をすれば、彼ら自身の倫理性や人間性が問われることになるのです。だから彼らは「黙りこむしかなかった」のです。
この「ファリサイ」という名称は、「分離する」という意味がありました。
自らを律法の細かな規定まで厳格に守っている者と自負し、規定を守れない人を罪人として見なし、見下して隔ての壁をつくっていたのです。この見下して隔ての壁をつくることが、どれほど人の尊厳を傷つけ損なう事でしょう。
イエスさまご自身、敵意の目で見られていることをご存じでしたが。何より居たたまれなかったのは、目の前にいる手の萎えた人がご自分をおとしめる道具として扱われたことであったのです。
皮肉と申しましょうか。怖ろしいことに、律法の規定を厳格に守り、それを第一としていた人々が神の憐れみと愛に満ちた律法の精神から離れ、人を蔑視し、恨み憎む者となるのです。
ここを読む時、「原理主義」のもつ恐ろしさを感じました。社会の安定や秩序が守られるため原理原則も必要でしょう。しかし、それが絶対化され自分たちだけが正しい、誤りがないというふうになりますと、閉鎖的で硬直化し、自分たちと異なるものを排除してく非寛容なものとなり、本来の善い教えの精神が相反するものに変質してしまうのです。
それはこのファリサイ派の人たちだけに起こったことではありません。地上に起こっている諸所の争い事はじめ、実に私たちの生活の中にも起こり得ることなのです。倫理や道徳でさえ排他的な原理主義になることがあるのです。
では、どうすればこの原理主義的な指向を回避することができるでしょうか。
私たちがそこに陥らないためには、自分と考え方やモノの見方の異なる人、又国や文化、様々な立場の人との出会いを大切にすることです。実際それは神がお造りになった世界のゆたかさに目を向けて、自分の世界が開かれ拡げられていくことからそのゆたかさを知ることになるでしょう。
ちなみに、イエスさまがここで「命を救うことか」とおっしゃったこの「命」は、原語で「プシュケー」、それは人間の肉体・身体(ソーマ)だけでなく、霊的な命をもつ存在であるという事です。それをプシュケー「魂」と訳されます。
イエスさまはこの一人の魂に熱いまなざしを注いで、神さまとの交わりにおける「魂の救い」、その命の回復を切に願われたのです。
さて、本日の箇所には、「会堂に一人の人がいて、その右手が萎えた人がいた」と記されてありますが。マタイ、マルコの福音書には「片手の萎えた人」と記されています。このルカのその萎えた人の手が「右手」であったとは、まあ普通右の手とは、人にとって利き手、働きの手であります。しかしその手が萎えて、動かなくなったということを強調しているのでしょう。この人はどういう仕事していたんだろうかと想像することもできるでしょう。何か仕事をするにも日常の生活をするにも、その利き手、働き手が動かなくなってしまう。それは致命的なことで、先行き、将来に対しての望みが断たれてしまったのも同然であったと言えるでしょう。その人の心の悲しみは如何ほどであったことでしょう。すべてに自信を無くし、顔を上げることもできず、もしかすると、会堂の目立たない片隅でうずくまるように座っていたのかも知れません。
イエスさまは、その手の萎えた人に、「真ん中に立ちなさ」と、呼びかけられるのです。
「真ん中に立ちなさい」。このイエスさまの呼びかけ。それは、「あなたは神の御前にあって尊い一人の人間である」という祝福の招きであります。
「真ん中に立ちなさい」。このイエスさまの呼びかけ。それは、「あなたは神の御前にあって尊い一人の人間である」という祝福の招きであります。
旧約聖書のイザヤ書43章4節に、神さまが民に語りかけられた御言葉としてこういうお言葉がございます。「わたしの目にはあなたは価高く、尊い。」
この世界では多くの場合、社会的に弱い立場の人たちは脇へ脇へとおいやられる、まるで無いモノのように扱われ、疎んじられ、忘れ去られます。。
けれどもイエスさまはこの身体の萎えた人に、「あなたの存在そのものが大切なのだ。神の前に価高く尊い存在なのだから」と、そのような思いを込めて「真ん中に立ちなさい」と、招かれたのですね。
すると、この人は身を起こして立ったのです。
イエスさまはさらにその人に言われます。「手を伸ばしなさい。」
逆境にある時に、一歩を踏み出すというのは本当に勇気がいる事です。この人は人々の見下しと敵意の視線を浴びる中で、イエスさまのお言葉に応えていくには大きな緊張と恐れがあったことでしょう。けれども彼はイエスさまのお言葉どおりに、イエスさまに信頼してその手を伸ばしたのです。
すると、その手は元どおりになった、というのです。
その人にとって萎えた右の手が元どおりになったことは喜びであったことでしょう。しかしそれにもまして、彼自身が神の御前に価高く尊い存在として見出されたこと。その魂が回復されたこと。その救いこそが、何よりも喜びの出来事であったのです。
言換えれば、彼はこの安息日に・・・本当の意味で、神の御前における真の安息を得たのであります。律法の本質である、「善を行うこと、命を救うこと」の祝福を私たちはこのイエス・キリストから聞き、主に祈りつつ、そのお姿に倣ってまいりたいと願うものです。
最後に、先週の火曜日は阪神淡路大震災から18年目を迎え、関西地方連合でも1・17祈念集会がオンラインで行われました。今回は東日本大震災後、長い間現地震災委員長としお働きくださった、仙台長命ヵ丘キリスト教会牧師の金丸真さんから、「震災と備え」についてお話を伺いました。
その中で特に心に残った一つは、「私たちは震災後にではなく、今も震災と震災の間に生きていることを自覚しておく、目を覚ましておく」という言葉です。その意識をもって防災に備える必要があるということですね。
二つ目は、教会のなすべき最大の備えは、「み言葉に聴く」こと。世の声でなく、神に聴き続けることが大切ということでありました。マタイ7章12節には、「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。これこそ律法と預言者である」という聖書の黄金律の尊さのもと、その例として「善いサマリア人」(ルカ10章)の個所を引用されました。
ある律法の専門家がイエスさまに「何をしたら永遠の命を得られるのですか」と尋ねると、イエスさまは「律法に何と書いてあるか。あなたはそれをどう読んでいるか」と問い返されます。彼は「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また、隣人を自分のように愛しなさい」とありますと答えます。すると、イエスさまは「正しい答えだ。それを実行しなさい、そうすれば命を得られる」とおっしゃるのです。が、彼は「では、わたしの隣人とは誰ですか」と言って、自分を正当化しようとします。そこでイエスさまは彼に善いサマリア人のたとえ話しをなさったのです。
このたとえ話は、律法を学ぶユダヤの指導者や宗教家が追剥に遭って瀕死の状態で横たわる同胞を見捨てるのですが、ユダヤ人から信仰観が堕落していると見なされ、軽蔑されていたサマリア人が、その瀕死の状態のユダヤ人に犠牲を払ってまで助けたのです。
イエスさまはこの律法の専門家に対して「だれがその傷んだ人の隣人になったか」と問うと、彼は「そのサマリア人です」と答えます。するとイエスさまは彼に、「行ってあなたも同じようにしなさい」と言われるのです。
金丸さんはこうおっしゃいました。「この律法の専門家は、『律法に何と書いてあるか』については理解していた。しかし、『それをあなたはどう読んでいるか』ということが答えられなかった。聖書の言葉をただマニュアルどおりにするのと、考えてするのとは違いがある。考えないで行う中に、思い込みやすれ違いが生じる。本人は相手が傷ついていると考えられない。だからこそ、私たちはみ言葉に聴くことが最大の備えになる。」
この話を伺いなるほどなあと思いながら、本日の個所のファリサイ派の人たちがそこに重なって見えました。
私たちは、このところにあらわされた「安息日の主」なるお方、イエス・キリストのお姿に、神の愛と隣人愛の尊さを知らされます。私たちも又、この安息をいただてこの一週間それぞれの場へと遣わされてまいりましょう。