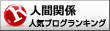礼拝宣教 使徒言行録15章1節~21節
先週は中野先生(日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会牧師・ピアニスト)をお迎えしての特別礼拝と午後からのピアノコンサートが主の先立ちと導きのもと行われました。コンサートには初めて教会に訪れる方、久しぶりの方と、多くの方々が集われ盛会となりました。うれしかったですね。中野先生のメッセージ、ピアノ演奏と語りも素晴らしく、心に沁み入るように響き、平安と潤いをいただきました。こうして教会堂が用いられコンサートや催しを重ねていくことによって、福音の種が蒔かれていくなら何と幸いなことでしょう。ここから、いつの日か必ず主イエスの救いの実を結んでゆくにちがいないと、喜びと希望が与えられました。
今日は又、日本国憲法が1946年(昭和21年)に公布されて69回目の憲法記念日であります。改憲の動きが急速化するなか、これまで国家権力の暴走を防ぎ、国民の基本的人権や生存権を保証してきた日本国憲法が変容されようとしていることに、危機感を強くおぼえます。この改憲の動きに対し見張り人として警鐘を促し、現憲法のもつ尊さを発信していきたいと願うものです。
さて、本日から使徒言行録15章の方へ戻りまして、本日は15章のいわゆるエルサレムの使徒会議の記事です。この箇所はキリスト教が広義の意味でユダヤ人以外の異邦人に伝えられることになった大きな分岐点となったところでありますが。その議論の中心は、そもそも、主イエスの救いに与ったクリスチャンも、ユダヤの律法の戒律を厳守すべきか否かという大変大きな問題であったのです。それは、主イエスによって成し遂げられた「神の救い」の働きを否定するまさに福音の危機にあったのです。
主イエスが十字架の救いと復活の栄光を顕わされ天に昇られた後、約束された聖霊が降りキリストの教会が誕生します。神の御業はユダヤ人の間だけに留まりませんで、12使徒をはじめ先々週読みましたパウロとバルナバらの働きをとおして、異邦人にも主の御救いが起こされてまいります。本日の15章の前にでてまいりますアンティオキアの教会は、パウロやバルナバを送り出すなど異邦人伝道の拠点となりました。そんな主の恵みがあふれ出るような教会に、今日の1節の冒頭にありますように、「ある人々がユダヤから下って来て、『モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない』(アンティオキアの教会)と兄弟たちに教えていた」というのです。
割礼というのは、イスラエルを神の民とする約束のしるしとして、男子の包皮を切り取ることで、その共同体の一員とみなされという慣習でありますが。アンティオキアの教会にはバルナバやパウロの福音伝道によって救われた、多くのユダヤ人以外のクリスチャンがいたわけですから、「モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない」と言われると、それは大変な問題であったのですね。まさに、割礼という律法の慣習的儀式が神の救いにとって替えられてしまう。そういった危機感がパウロとバルナバに生じたのです。それは異邦人に割礼を受けさせてユダヤ人となる同化を強要することであり、神の救いの業よりも、人の業を重視することでもあったんですね。
神は御独り子イエスを通してすべての人びとの罪を贖い、救いの道を開いてくださいました。それにも拘わらず、その神の一方的救いの業を阻むように、「いや、割礼を受けなければ救われない」というのは、聖霊の働きを邪魔する、それは聖霊を汚すことに外ならなかったんですね。ですからパウロとバルナバは毅然と立ち上がり、そう主張する人々と激しい議論をしたのですね。
パウロが断固そのことに対して譲れないのにはわけがありました。彼もかつては非常に熱心なユダヤ教徒としてモーセの慣習や割礼を忠実に守り仕えていたのです。けれども主イエスとの出会いによって、彼は自分の義を立てようとするところに救いは得られないこと、そればかりか、自分の正しさを貫こうとしてクリスチャンを迫害してきたことが、実は主であるお方を苦しめ傷めつけてことを思い知らされるのです。彼は主イエスの十字架の苦難と死を目の当たりにし、打ち砕かれます。そしてそのような罪深い自分が神さまを傷めつけていたにもかかわらず、その主の贖いの恵みによって救われるという経験をしたのですね。だから、パウロは「ユダヤの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない」という神の恵みを否定する教えに対して、自分の存在をかけて断固立ち向かうのです。
これは私たちも忘れてはならないことです。クリスチャンは何か立派な行いをしたかたクリスチャンなのではないんですよね。又、聖書の学びや知識があるからクリスチャンとされたのではないのです。私たちは、ただ主イエスの恵みによって救われている。
もっといえば、私たちは主のおそばにいつもおいていだだかなければ、滅びゆくほかないような者なのです。そのような者の救いのために、主イエスは十字架にかかり、血潮を流され、御体を裂かれて私たちが負うべき裁きを受け、神の義を全うなさったのです。主イエスの恵みによって救われるというのは、そういう非常に重たい出来事をとおしてもたらされたものなのであります。
さて、「この件(福音の危機の問題)について、使徒や長老たちと協議するために、パウロとバルナバ、そのほか数名の者がエルサレムへ上った」とあります。「一行は(アンティオキア)教会の人々から送り出された」とありますから、そこにはアンティオキアの兄弟姉妹たちの委託と派遣の祈りがあったことでしょう。一行がエルサレムに到着しますと使徒や長老たちの歓迎を受けます。その中で彼らは4節にあるように、「神が自分たちと共にいて行われたことを、ことごとく報告し」ます。
彼らは又、その議論の中でも、12節「自分たちを通して神が異邦人の間で行われた、あらゆるしるしと不思議な業について話した」とあります。
エルサレムの教会の使徒ペトロも又8節で、「神は、わたしたちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて、彼らも受け入れられたことを証明なさったのです。(神は)彼らの心を信仰によって清め、わたしたちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした」と立って証言します。ペトロも、かつて自分が固執していた思いが壊される経験をしていました。彼はそのことをとおして、神が恵みによって、異邦人も福音を聞いて信じ、救われることを願っておられることを示されます。それは自分の心から出たことではなく、神さまのご意志から出たことであったと、明言するのです。
このバルナバ、パウロ、そしてペトロといずれにも共通しているのは、それが自分の思いではなく、神を主として、その「神がなさったことについての証し」をしていることです。
このペトロの証言の中で大事なのは、割礼によっては人は救われない、ということです。「神は、ユダヤ人だけでなく、律法を知らない異邦人にも聖霊を与えて、受け入れられた。神は彼らの心を信仰によって聖なる者として聖別してくださった。そこには何ら差別はない。それなのに、先祖も負いきれなかった律法の重荷を、異邦人の信徒に負わせ、神を試みようとするのか。」
ペトロは自分たちユダヤ人が救われたのは、律法によるのではなく、主イエスの恵みによるもの。このことは「異邦人たちも同様だ」と語りました。
このペトロの言葉を聞いたエルサレム教会の全会衆は静かになったとあります。
「異邦人にも割礼をうけさせて、モーセの律法を守るように命じるべきだ」と主張していた人たちは、そこで救いの原点について深く問われたのではないでしょうか。
今日のエルサレム使徒会議の場において、エルサレム教会の実質的な指導者であったヤコブが最後に意見を述べます。彼はイエスの弟子のゼベタイの子ヤコブではなく、イエスの兄弟の一人であったヤコブだとされる人ですが。彼はシメオン、これはペトロのことですが、その彼が証言したことを受けて、その根拠を旧約聖書の預言者アモスの書から引用し、16節「その後、わたしは戻って来て、倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊された所を建て直して、元どおりにする」と語ります。
この「わたし」というのは主ご自身です。主イエスの救いの到来によって倒れたダビデの幕屋、それは神の目からご覧になったイスラエルの民の霊的な姿を表わしているのでしょうが。それを主は元どおりにする、と言われるのです。これは主イエスによる救いの御業を示しています。
さらに17節~18節『「それは、人々のうちで残った者や、わたしの名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためだ。」昔から知らされていたことを行う主は、こう言われる。』
ヤコブはこのように旧約聖書で示された、主を求める異邦人についての預言が、今成就したとして、「神に立ち返った異邦人を悩ませてはなりません」との判断を示します。
それは主イエスの御業における救いが、人のどのような行いにも勝って完全であることが確認された何とも感動的な瞬間でもありました。
ところが、ヤコブはそれに加えて、異邦人クリスチャンたちに4つの提案を示します。
それは偶像に供えた汚れた肉と、みだらな行いと、絞め殺した動物の肉と、血とを避けることでした。これらは、ユダヤ人が非常に忌み嫌うことでした。しかしこれらとて、異邦人クリスチャンたちを「悩ませる」ことと変わりないように見えるのですが。
実はこのヤコブの提案にはある意図があったのです。
21節に「モーセの律法は、昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに会堂で読まれているからです」とヤコブが述べたように、異邦人クリスチャンの周りには、安息日ごとにユダヤ教会堂で律法朗読を聞いているユダヤ教徒がいるわけで、そういう人々の躓きにならないように配慮する、気づかうようにと言っているのですね。別にこの4つの提案は救いに必要だということではないのです。しかし、長い間守られ、受け継がれてきたユダヤ社会の背景と律法の教育の中にある人たちに対する心づかいとして、この4つのことは避けるように心がけてほしいと呼びかけているのですね。もしそれに反して自由だと主張し、勝手気ままなことをしてしまえば、ユダヤ人たちは、異邦人クリスチャンたちとの交流に心閉ざし、福音の拡がりを妨げることになることをヤコブは知っていたのですね。
ここに私たちも学ぶべき点が語られているように思えます。
教会生活に慣れてしまうと、ある意味兄弟姉妹への感謝も配慮も希薄になり、それが言葉や態度となって傷つけてしまったり、裁いてしまったりということも起こり得ます。私たちも弱く罪深い者であります。しかし、もう一度、自分自身が主イエスの十字架の苦難と死によって勝ち取られた者、ゆるされている者であることを、主の恵みによって立ち返るとき、主は兄弟姉妹お一人おひとりのうちにいまし、生きてお働きくださっていることを、信仰によって知ることができるのであります。
最後に使徒パウロの言葉をいくつか読んで本日の宣教を閉じます。
「キリスト・イエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。」ガラテヤ5章6節
「割礼の有無は問題ではなく、大切なのは、新しく創造されることです。」
ガラテヤ6章15節
「兄弟たち、あなたがたは、自由を得るために召し出されたのです。ただ、この自由を、肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさい。律法全体は、『隣人を自分のように愛しなさい』という一句によって全うされるからです。」
ガラテヤ5章13-14節
先週は中野先生(日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会牧師・ピアニスト)をお迎えしての特別礼拝と午後からのピアノコンサートが主の先立ちと導きのもと行われました。コンサートには初めて教会に訪れる方、久しぶりの方と、多くの方々が集われ盛会となりました。うれしかったですね。中野先生のメッセージ、ピアノ演奏と語りも素晴らしく、心に沁み入るように響き、平安と潤いをいただきました。こうして教会堂が用いられコンサートや催しを重ねていくことによって、福音の種が蒔かれていくなら何と幸いなことでしょう。ここから、いつの日か必ず主イエスの救いの実を結んでゆくにちがいないと、喜びと希望が与えられました。
今日は又、日本国憲法が1946年(昭和21年)に公布されて69回目の憲法記念日であります。改憲の動きが急速化するなか、これまで国家権力の暴走を防ぎ、国民の基本的人権や生存権を保証してきた日本国憲法が変容されようとしていることに、危機感を強くおぼえます。この改憲の動きに対し見張り人として警鐘を促し、現憲法のもつ尊さを発信していきたいと願うものです。
さて、本日から使徒言行録15章の方へ戻りまして、本日は15章のいわゆるエルサレムの使徒会議の記事です。この箇所はキリスト教が広義の意味でユダヤ人以外の異邦人に伝えられることになった大きな分岐点となったところでありますが。その議論の中心は、そもそも、主イエスの救いに与ったクリスチャンも、ユダヤの律法の戒律を厳守すべきか否かという大変大きな問題であったのです。それは、主イエスによって成し遂げられた「神の救い」の働きを否定するまさに福音の危機にあったのです。
主イエスが十字架の救いと復活の栄光を顕わされ天に昇られた後、約束された聖霊が降りキリストの教会が誕生します。神の御業はユダヤ人の間だけに留まりませんで、12使徒をはじめ先々週読みましたパウロとバルナバらの働きをとおして、異邦人にも主の御救いが起こされてまいります。本日の15章の前にでてまいりますアンティオキアの教会は、パウロやバルナバを送り出すなど異邦人伝道の拠点となりました。そんな主の恵みがあふれ出るような教会に、今日の1節の冒頭にありますように、「ある人々がユダヤから下って来て、『モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない』(アンティオキアの教会)と兄弟たちに教えていた」というのです。
割礼というのは、イスラエルを神の民とする約束のしるしとして、男子の包皮を切り取ることで、その共同体の一員とみなされという慣習でありますが。アンティオキアの教会にはバルナバやパウロの福音伝道によって救われた、多くのユダヤ人以外のクリスチャンがいたわけですから、「モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない」と言われると、それは大変な問題であったのですね。まさに、割礼という律法の慣習的儀式が神の救いにとって替えられてしまう。そういった危機感がパウロとバルナバに生じたのです。それは異邦人に割礼を受けさせてユダヤ人となる同化を強要することであり、神の救いの業よりも、人の業を重視することでもあったんですね。
神は御独り子イエスを通してすべての人びとの罪を贖い、救いの道を開いてくださいました。それにも拘わらず、その神の一方的救いの業を阻むように、「いや、割礼を受けなければ救われない」というのは、聖霊の働きを邪魔する、それは聖霊を汚すことに外ならなかったんですね。ですからパウロとバルナバは毅然と立ち上がり、そう主張する人々と激しい議論をしたのですね。
パウロが断固そのことに対して譲れないのにはわけがありました。彼もかつては非常に熱心なユダヤ教徒としてモーセの慣習や割礼を忠実に守り仕えていたのです。けれども主イエスとの出会いによって、彼は自分の義を立てようとするところに救いは得られないこと、そればかりか、自分の正しさを貫こうとしてクリスチャンを迫害してきたことが、実は主であるお方を苦しめ傷めつけてことを思い知らされるのです。彼は主イエスの十字架の苦難と死を目の当たりにし、打ち砕かれます。そしてそのような罪深い自分が神さまを傷めつけていたにもかかわらず、その主の贖いの恵みによって救われるという経験をしたのですね。だから、パウロは「ユダヤの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない」という神の恵みを否定する教えに対して、自分の存在をかけて断固立ち向かうのです。
これは私たちも忘れてはならないことです。クリスチャンは何か立派な行いをしたかたクリスチャンなのではないんですよね。又、聖書の学びや知識があるからクリスチャンとされたのではないのです。私たちは、ただ主イエスの恵みによって救われている。
もっといえば、私たちは主のおそばにいつもおいていだだかなければ、滅びゆくほかないような者なのです。そのような者の救いのために、主イエスは十字架にかかり、血潮を流され、御体を裂かれて私たちが負うべき裁きを受け、神の義を全うなさったのです。主イエスの恵みによって救われるというのは、そういう非常に重たい出来事をとおしてもたらされたものなのであります。
さて、「この件(福音の危機の問題)について、使徒や長老たちと協議するために、パウロとバルナバ、そのほか数名の者がエルサレムへ上った」とあります。「一行は(アンティオキア)教会の人々から送り出された」とありますから、そこにはアンティオキアの兄弟姉妹たちの委託と派遣の祈りがあったことでしょう。一行がエルサレムに到着しますと使徒や長老たちの歓迎を受けます。その中で彼らは4節にあるように、「神が自分たちと共にいて行われたことを、ことごとく報告し」ます。
彼らは又、その議論の中でも、12節「自分たちを通して神が異邦人の間で行われた、あらゆるしるしと不思議な業について話した」とあります。
エルサレムの教会の使徒ペトロも又8節で、「神は、わたしたちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて、彼らも受け入れられたことを証明なさったのです。(神は)彼らの心を信仰によって清め、わたしたちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした」と立って証言します。ペトロも、かつて自分が固執していた思いが壊される経験をしていました。彼はそのことをとおして、神が恵みによって、異邦人も福音を聞いて信じ、救われることを願っておられることを示されます。それは自分の心から出たことではなく、神さまのご意志から出たことであったと、明言するのです。
このバルナバ、パウロ、そしてペトロといずれにも共通しているのは、それが自分の思いではなく、神を主として、その「神がなさったことについての証し」をしていることです。
このペトロの証言の中で大事なのは、割礼によっては人は救われない、ということです。「神は、ユダヤ人だけでなく、律法を知らない異邦人にも聖霊を与えて、受け入れられた。神は彼らの心を信仰によって聖なる者として聖別してくださった。そこには何ら差別はない。それなのに、先祖も負いきれなかった律法の重荷を、異邦人の信徒に負わせ、神を試みようとするのか。」
ペトロは自分たちユダヤ人が救われたのは、律法によるのではなく、主イエスの恵みによるもの。このことは「異邦人たちも同様だ」と語りました。
このペトロの言葉を聞いたエルサレム教会の全会衆は静かになったとあります。
「異邦人にも割礼をうけさせて、モーセの律法を守るように命じるべきだ」と主張していた人たちは、そこで救いの原点について深く問われたのではないでしょうか。
今日のエルサレム使徒会議の場において、エルサレム教会の実質的な指導者であったヤコブが最後に意見を述べます。彼はイエスの弟子のゼベタイの子ヤコブではなく、イエスの兄弟の一人であったヤコブだとされる人ですが。彼はシメオン、これはペトロのことですが、その彼が証言したことを受けて、その根拠を旧約聖書の預言者アモスの書から引用し、16節「その後、わたしは戻って来て、倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊された所を建て直して、元どおりにする」と語ります。
この「わたし」というのは主ご自身です。主イエスの救いの到来によって倒れたダビデの幕屋、それは神の目からご覧になったイスラエルの民の霊的な姿を表わしているのでしょうが。それを主は元どおりにする、と言われるのです。これは主イエスによる救いの御業を示しています。
さらに17節~18節『「それは、人々のうちで残った者や、わたしの名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためだ。」昔から知らされていたことを行う主は、こう言われる。』
ヤコブはこのように旧約聖書で示された、主を求める異邦人についての預言が、今成就したとして、「神に立ち返った異邦人を悩ませてはなりません」との判断を示します。
それは主イエスの御業における救いが、人のどのような行いにも勝って完全であることが確認された何とも感動的な瞬間でもありました。
ところが、ヤコブはそれに加えて、異邦人クリスチャンたちに4つの提案を示します。
それは偶像に供えた汚れた肉と、みだらな行いと、絞め殺した動物の肉と、血とを避けることでした。これらは、ユダヤ人が非常に忌み嫌うことでした。しかしこれらとて、異邦人クリスチャンたちを「悩ませる」ことと変わりないように見えるのですが。
実はこのヤコブの提案にはある意図があったのです。
21節に「モーセの律法は、昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに会堂で読まれているからです」とヤコブが述べたように、異邦人クリスチャンの周りには、安息日ごとにユダヤ教会堂で律法朗読を聞いているユダヤ教徒がいるわけで、そういう人々の躓きにならないように配慮する、気づかうようにと言っているのですね。別にこの4つの提案は救いに必要だということではないのです。しかし、長い間守られ、受け継がれてきたユダヤ社会の背景と律法の教育の中にある人たちに対する心づかいとして、この4つのことは避けるように心がけてほしいと呼びかけているのですね。もしそれに反して自由だと主張し、勝手気ままなことをしてしまえば、ユダヤ人たちは、異邦人クリスチャンたちとの交流に心閉ざし、福音の拡がりを妨げることになることをヤコブは知っていたのですね。
ここに私たちも学ぶべき点が語られているように思えます。
教会生活に慣れてしまうと、ある意味兄弟姉妹への感謝も配慮も希薄になり、それが言葉や態度となって傷つけてしまったり、裁いてしまったりということも起こり得ます。私たちも弱く罪深い者であります。しかし、もう一度、自分自身が主イエスの十字架の苦難と死によって勝ち取られた者、ゆるされている者であることを、主の恵みによって立ち返るとき、主は兄弟姉妹お一人おひとりのうちにいまし、生きてお働きくださっていることを、信仰によって知ることができるのであります。
最後に使徒パウロの言葉をいくつか読んで本日の宣教を閉じます。
「キリスト・イエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。」ガラテヤ5章6節
「割礼の有無は問題ではなく、大切なのは、新しく創造されることです。」
ガラテヤ6章15節
「兄弟たち、あなたがたは、自由を得るために召し出されたのです。ただ、この自由を、肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさい。律法全体は、『隣人を自分のように愛しなさい』という一句によって全うされるからです。」
ガラテヤ5章13-14節