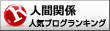宣教 創世記11章1~9節
序 バベルの塔は実在していた
この聖書に記述がありますバベルの塔は古代バビロニア・今のイラクのあたりに実在したそうでありますが。考古学による発掘調査と同時代の文書によれば、バベルの塔はジグラトと呼ばれる巨大な宗教的建造物だとされ、7階建てで高さが90メートル。1階が長さ90メートル、幅90メートル。2階以降はその容積が下の階よりも小さくなっていたそうです。今度2013年か2014年に完成する阿倍野近鉄デバートの高さが200メートルですか、300メートルですか。まあそれに比べればあまり大した事はないように思えますが。当時として多大な動員とものすごい労働力と最新技術を駆使しての建築であった事でしょう。
② 同じ言葉
さて、1節「世界中は同じ言葉を使って、同じように話していた」とあります。
この世界中とは、全世界という意味ではなくこの時代のバビロニア(シンアル)一帯に住む人々のことを指しています。しかし古代バビロニアは学校で「世界の発祥バビロニア」などと習いましたように、ある意味において世界の中心的な地であったということです。まあ世界中と表現されるくらいですから、かなりの広さと人々が多くいて、そこに住む大勢の人々が、「同じ言葉を使って、同じように話していた」ということですので、「全体なおれ!」ではありませんが、皆が同じ方向に進んで、力が結集され、そういった中でバビロ二アの町はものすごい発展を遂げていったのでありましょう。そして3節にあるように、彼らは、「れんがを作り、それをよく焼こう」と話し合った。石の代わりにれんがを、しっくいの代わりにアスファルトを用いた」とあります。これは文明の発展や進化を指しています。彼らは、「話し合って」、れんがとアスファルトを用いて町に先進的な塔を立てようと企てるのであります。しかしこれは神に一切相談することなく自分たちの判断だけでそれを行ったということであります。古代の世界において塔という重要な宗教的施設を建立する場合、たいがいは神へお伺いを立てて祈りつつ、神と共同で行なうものです。しかしこの塔の建設の場合、そういった祭儀が行なわれていたとは何も記されておりません。人々は何ら神に問いかけることも、お尋ねすることもなしに、いわば「神不在」のなか、自分たちの思いだけを先行させ、判断をなし、塔の建築へと舵をきったのであります。かつてアダムとエバ、又カインもそうでしたが。彼らは神に問うことも、お伺いを立てることもせずに、自分勝手に判断して事をなすという同じ過ちを犯し、神の祝福を損ねてしまいました。バベルの塔のある町の建設も、まさにそのような中で進められていったのであります。
② 不安
その人々は4節でこう言っています。「さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして、全地に散らされることのないようにしよう」。
先ほど申しましたように、彼らは「神に問い、尋ねる」ことなし、神不在の中で、自分たちの欲求だけに従いで天まで届く塔のある町を立てようと事を運びます。それは「名をあげ、全地に散らされないために」という理由から企てられるのであります。
つまり、裏を返せば彼らの思いの根底に、「全地に散らされてしまうという不安があった」ということです。日々築かれてゆく一大文明・文化。力強い国家の一員であるという誇りと安心感。彼らはそれをより確かなものとしたいとの願望が増し、それと共に、これが散らされてしまっては大変だと言う不安も又、増していったということです。そして人びとはその不安を解消するために、強く団結し、一丸となって天に届く塔のある町を建てよう企てるのであります。それは神に問いかけ、尋ねることを一切せず、どこまでも人の企てでありました。この「神不在」の中の、どこに平安があるのでしょうか。そこに彼らの根源的な問題があったのです。
現代社会もまさにそのようでありましょう。どんなにそびえるような高層マンションの最上階に住もうとも、最高の地位、権力を手に入れようとも、神不在の人の企てがもたらすものは、不安と虚しさだけです。社会全体もそうであります。人は神と共にあゆんでこそ、夢や希望を心から楽しむことができ、御心を思うことで、仕事にしろ、生きがいにしろ、本来の生きる意味と目的を見出し、平安のうちに務めることができるのです。
さて、先に、「同じ言葉」を使い、同じように話す彼らの結束力と、それによりもたらされる繁栄について述べましたが。それは一見、大変よいことのように思えますが、果たしてそうなのでしょうか? この「同じように話す」というのは、画一的思想をもっていたということでしょうが。人間の社会生活において、それは本当によいことばかりなのでしょうか? 5節以降にこうあります。「主は降って来て、人の子らが建てた、塔のあるこの町を見て言われた。「彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは、彼らが何を企てても、妨げることはできない」」。
これはですね、例えば、国や団体組織が画一的思想やそういったスローガンを掲げ、個人に押し付けようとするとき、異論を持つ少数者を数の論理のもと圧力や怖れで抑えこもうとしたり、排除しようすることが起こっていきます。そのような企てでもって起こってくる悲劇は後を絶ちません。かつて日本は戦時下にあって同じような過ちを犯しました。
軍国教育と皇国史観が絶対化される中、戦争反対者は非国民扱い、選別されました。よく戦争は軍部の独走と言われますが、それだけではできないことです。国民の心と協力がその場合不可欠です。それは本日の聖書にあるように、「同じ言葉を使い、同じように話す」、つまり人間が作った画一的思想信条を押し付け、強化と団結力を計る中、愛国心や心の教育という名のマインドコントロールを行っていった。それが人々の心を昂揚させてあの戦争へと向かわしめたのです。ですから、教育ってほんとうに大切であります。今日にあっても国家や公権力による「愛国心や心の教育」の強要や強制に対して、神経質なくらい敏感に目を注いで見極めていくことは、殊に宗教者として大切な使命であります。二度と正しいものを正しい、間違いを間違いと言えないような世の中が来ないように、戦争の過ちを繰り返えして起こさないためにもそうです。人は不安や怖れを抱く時に、一丸となること。皆同じであること。また名誉や地位を持つことによって不安が解消し、安心を手にすることができるように思うのでありますが。それは幻想です。
③ 現代のバベルの塔
現代の社会にはそういった不安解消の装置として、いくつものバベルの塔が立ち並んでいるといえないでしょうか。神に問い、お伺いを立てることをしないで、自分たちの判断だけで自己完結する神不在のバベルの塔が私たちの文明社会に立ち並んでいます。例えばその一つとして、原子力発電所にみられる安全神話がそうです。想定外ではすまされません。原子力発電は安全・安い・クリーンということでの国策であったのですが。実際に事故が起こってから明らかになったのは、その恐ろしさであります。核は人類の手にあまるものであります。膨大な放射性物質が大気・土壌・海水に漏れ、放出し、汚染されて生態系がおかしくなっている事実であります。莫大な事故処理の費用が圧し掛かっています。人間の傲慢さと浅はかさを思い知らされますが。今回のこの事故(人災)を通して、危機管理のこと、又少なくとも実際に日本中に住む私たちの問題として、電気の節電やライフスタイルについてそれぞれが真剣に向き合い、取り組んでいく必要に迫られているという認識を肌身に感じることができました。しかしその代償はあまりにも大き過ぎます。
さて7節、主は「降って行って、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉を聞き分けられぬようにしてしまおう」となさいます。
造られた塔は宗教的な建築物であったといわれていますが。それは人が1階、2階と高く高く上るごとに、神々に近づくことができるという、あくまでも人の側のための建築物であったということです。
人は上へ上へと天に届くように一番頂上の天に届けとばかりに上りつめようとしますが、主なる神は下へ下へと地に向かい、人々のもとへ降りて来てくださるのです。そこに大きな違いがあります。神は罪と死へと向かう人のところに降りてきてくださるのです。これまで神を見上げずに自分を高めようとしてきた人々は、ここで天から降って来られた神を見て、どう思ったことでしょうか?
今、私たちには、まさに人の罪のどん底にまで、苦しみ悩みのどん底まで降りて来られ、痛みを共にされる神、救い主イエス・キリストがおられます。このお方が十字架にかけられた姿を思う時、私どもの高慢は打ち砕かれ、罪からの解放が起こされるのであります。
もう一つ心に留まりましたのは、主なる神は、人々が建てた塔のある町を破壊されたのではなく、人々の言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにされて、そこから全地に人々を散らされたということであります。私は最初にこのバベルの塔のお話を聞いた時の印象が強く、この塔を含め町は倒壊してしまったとずっと思い込んでいたのですが。そうではなく、人々は言葉の混乱と、互いの言葉が聞き分けられなくなり、この町の建設を中止し、全地に散らされるのです。それは神の断罪というものではなく、神が多様性をもって生きることの意義と幸いを人々に託して、地に散らされたのです。
もちろん言葉が通じなければ混乱も起こります、あゆみ寄る努力が必要となります。議論もその都度行なわなければなりません。しかし神は、それらは人の社会が築かれるための大事なプロセスとなるだろう、とお考えになったのではないでしょう? しかしそれだけで人の社会が成熟するかといえば、そうでないことは歴史を見れば一目瞭然です。
最後になりますが、教会も主の宮なる教会堂を建てようとする時、一致や団結というものが必要でありますが。しかし、まず何よりも、その建設の最初から終わりまで、主に御心とその幻を尋ね求めながら主と共に建設の業を進めていく事がとても大事であります。
それともう一つ、私たちはみな同じではないということです。それぞれに違いがあり、異なる者同士であるということであります。それに不安や怖れを持つことはありません。
同じ考えを持つ者も、違う考えを持つも者もいてあたりまえです。大切なのは互いに思いを出し合い、最後は一つになって主にみ心がどこにあるのかを尋ね求めて共に祈ることができるという幸いと平安があるということであります。違いを乗り越え、各々がキリストの御体を形成するかけがえのない部分として教会が建てあげられてゆく時、本当に素晴らしい主の御業を拝することになると、信じております。
序 バベルの塔は実在していた
この聖書に記述がありますバベルの塔は古代バビロニア・今のイラクのあたりに実在したそうでありますが。考古学による発掘調査と同時代の文書によれば、バベルの塔はジグラトと呼ばれる巨大な宗教的建造物だとされ、7階建てで高さが90メートル。1階が長さ90メートル、幅90メートル。2階以降はその容積が下の階よりも小さくなっていたそうです。今度2013年か2014年に完成する阿倍野近鉄デバートの高さが200メートルですか、300メートルですか。まあそれに比べればあまり大した事はないように思えますが。当時として多大な動員とものすごい労働力と最新技術を駆使しての建築であった事でしょう。
② 同じ言葉
さて、1節「世界中は同じ言葉を使って、同じように話していた」とあります。
この世界中とは、全世界という意味ではなくこの時代のバビロニア(シンアル)一帯に住む人々のことを指しています。しかし古代バビロニアは学校で「世界の発祥バビロニア」などと習いましたように、ある意味において世界の中心的な地であったということです。まあ世界中と表現されるくらいですから、かなりの広さと人々が多くいて、そこに住む大勢の人々が、「同じ言葉を使って、同じように話していた」ということですので、「全体なおれ!」ではありませんが、皆が同じ方向に進んで、力が結集され、そういった中でバビロ二アの町はものすごい発展を遂げていったのでありましょう。そして3節にあるように、彼らは、「れんがを作り、それをよく焼こう」と話し合った。石の代わりにれんがを、しっくいの代わりにアスファルトを用いた」とあります。これは文明の発展や進化を指しています。彼らは、「話し合って」、れんがとアスファルトを用いて町に先進的な塔を立てようと企てるのであります。しかしこれは神に一切相談することなく自分たちの判断だけでそれを行ったということであります。古代の世界において塔という重要な宗教的施設を建立する場合、たいがいは神へお伺いを立てて祈りつつ、神と共同で行なうものです。しかしこの塔の建設の場合、そういった祭儀が行なわれていたとは何も記されておりません。人々は何ら神に問いかけることも、お尋ねすることもなしに、いわば「神不在」のなか、自分たちの思いだけを先行させ、判断をなし、塔の建築へと舵をきったのであります。かつてアダムとエバ、又カインもそうでしたが。彼らは神に問うことも、お伺いを立てることもせずに、自分勝手に判断して事をなすという同じ過ちを犯し、神の祝福を損ねてしまいました。バベルの塔のある町の建設も、まさにそのような中で進められていったのであります。
② 不安
その人々は4節でこう言っています。「さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして、全地に散らされることのないようにしよう」。
先ほど申しましたように、彼らは「神に問い、尋ねる」ことなし、神不在の中で、自分たちの欲求だけに従いで天まで届く塔のある町を立てようと事を運びます。それは「名をあげ、全地に散らされないために」という理由から企てられるのであります。
つまり、裏を返せば彼らの思いの根底に、「全地に散らされてしまうという不安があった」ということです。日々築かれてゆく一大文明・文化。力強い国家の一員であるという誇りと安心感。彼らはそれをより確かなものとしたいとの願望が増し、それと共に、これが散らされてしまっては大変だと言う不安も又、増していったということです。そして人びとはその不安を解消するために、強く団結し、一丸となって天に届く塔のある町を建てよう企てるのであります。それは神に問いかけ、尋ねることを一切せず、どこまでも人の企てでありました。この「神不在」の中の、どこに平安があるのでしょうか。そこに彼らの根源的な問題があったのです。
現代社会もまさにそのようでありましょう。どんなにそびえるような高層マンションの最上階に住もうとも、最高の地位、権力を手に入れようとも、神不在の人の企てがもたらすものは、不安と虚しさだけです。社会全体もそうであります。人は神と共にあゆんでこそ、夢や希望を心から楽しむことができ、御心を思うことで、仕事にしろ、生きがいにしろ、本来の生きる意味と目的を見出し、平安のうちに務めることができるのです。
さて、先に、「同じ言葉」を使い、同じように話す彼らの結束力と、それによりもたらされる繁栄について述べましたが。それは一見、大変よいことのように思えますが、果たしてそうなのでしょうか? この「同じように話す」というのは、画一的思想をもっていたということでしょうが。人間の社会生活において、それは本当によいことばかりなのでしょうか? 5節以降にこうあります。「主は降って来て、人の子らが建てた、塔のあるこの町を見て言われた。「彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは、彼らが何を企てても、妨げることはできない」」。
これはですね、例えば、国や団体組織が画一的思想やそういったスローガンを掲げ、個人に押し付けようとするとき、異論を持つ少数者を数の論理のもと圧力や怖れで抑えこもうとしたり、排除しようすることが起こっていきます。そのような企てでもって起こってくる悲劇は後を絶ちません。かつて日本は戦時下にあって同じような過ちを犯しました。
軍国教育と皇国史観が絶対化される中、戦争反対者は非国民扱い、選別されました。よく戦争は軍部の独走と言われますが、それだけではできないことです。国民の心と協力がその場合不可欠です。それは本日の聖書にあるように、「同じ言葉を使い、同じように話す」、つまり人間が作った画一的思想信条を押し付け、強化と団結力を計る中、愛国心や心の教育という名のマインドコントロールを行っていった。それが人々の心を昂揚させてあの戦争へと向かわしめたのです。ですから、教育ってほんとうに大切であります。今日にあっても国家や公権力による「愛国心や心の教育」の強要や強制に対して、神経質なくらい敏感に目を注いで見極めていくことは、殊に宗教者として大切な使命であります。二度と正しいものを正しい、間違いを間違いと言えないような世の中が来ないように、戦争の過ちを繰り返えして起こさないためにもそうです。人は不安や怖れを抱く時に、一丸となること。皆同じであること。また名誉や地位を持つことによって不安が解消し、安心を手にすることができるように思うのでありますが。それは幻想です。
③ 現代のバベルの塔
現代の社会にはそういった不安解消の装置として、いくつものバベルの塔が立ち並んでいるといえないでしょうか。神に問い、お伺いを立てることをしないで、自分たちの判断だけで自己完結する神不在のバベルの塔が私たちの文明社会に立ち並んでいます。例えばその一つとして、原子力発電所にみられる安全神話がそうです。想定外ではすまされません。原子力発電は安全・安い・クリーンということでの国策であったのですが。実際に事故が起こってから明らかになったのは、その恐ろしさであります。核は人類の手にあまるものであります。膨大な放射性物質が大気・土壌・海水に漏れ、放出し、汚染されて生態系がおかしくなっている事実であります。莫大な事故処理の費用が圧し掛かっています。人間の傲慢さと浅はかさを思い知らされますが。今回のこの事故(人災)を通して、危機管理のこと、又少なくとも実際に日本中に住む私たちの問題として、電気の節電やライフスタイルについてそれぞれが真剣に向き合い、取り組んでいく必要に迫られているという認識を肌身に感じることができました。しかしその代償はあまりにも大き過ぎます。
さて7節、主は「降って行って、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉を聞き分けられぬようにしてしまおう」となさいます。
造られた塔は宗教的な建築物であったといわれていますが。それは人が1階、2階と高く高く上るごとに、神々に近づくことができるという、あくまでも人の側のための建築物であったということです。
人は上へ上へと天に届くように一番頂上の天に届けとばかりに上りつめようとしますが、主なる神は下へ下へと地に向かい、人々のもとへ降りて来てくださるのです。そこに大きな違いがあります。神は罪と死へと向かう人のところに降りてきてくださるのです。これまで神を見上げずに自分を高めようとしてきた人々は、ここで天から降って来られた神を見て、どう思ったことでしょうか?
今、私たちには、まさに人の罪のどん底にまで、苦しみ悩みのどん底まで降りて来られ、痛みを共にされる神、救い主イエス・キリストがおられます。このお方が十字架にかけられた姿を思う時、私どもの高慢は打ち砕かれ、罪からの解放が起こされるのであります。
もう一つ心に留まりましたのは、主なる神は、人々が建てた塔のある町を破壊されたのではなく、人々の言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにされて、そこから全地に人々を散らされたということであります。私は最初にこのバベルの塔のお話を聞いた時の印象が強く、この塔を含め町は倒壊してしまったとずっと思い込んでいたのですが。そうではなく、人々は言葉の混乱と、互いの言葉が聞き分けられなくなり、この町の建設を中止し、全地に散らされるのです。それは神の断罪というものではなく、神が多様性をもって生きることの意義と幸いを人々に託して、地に散らされたのです。
もちろん言葉が通じなければ混乱も起こります、あゆみ寄る努力が必要となります。議論もその都度行なわなければなりません。しかし神は、それらは人の社会が築かれるための大事なプロセスとなるだろう、とお考えになったのではないでしょう? しかしそれだけで人の社会が成熟するかといえば、そうでないことは歴史を見れば一目瞭然です。
最後になりますが、教会も主の宮なる教会堂を建てようとする時、一致や団結というものが必要でありますが。しかし、まず何よりも、その建設の最初から終わりまで、主に御心とその幻を尋ね求めながら主と共に建設の業を進めていく事がとても大事であります。
それともう一つ、私たちはみな同じではないということです。それぞれに違いがあり、異なる者同士であるということであります。それに不安や怖れを持つことはありません。
同じ考えを持つ者も、違う考えを持つも者もいてあたりまえです。大切なのは互いに思いを出し合い、最後は一つになって主にみ心がどこにあるのかを尋ね求めて共に祈ることができるという幸いと平安があるということであります。違いを乗り越え、各々がキリストの御体を形成するかけがえのない部分として教会が建てあげられてゆく時、本当に素晴らしい主の御業を拝することになると、信じております。