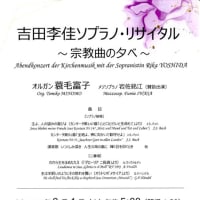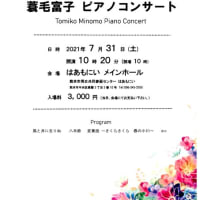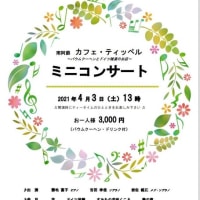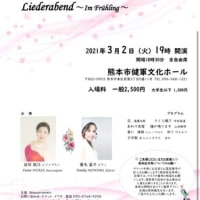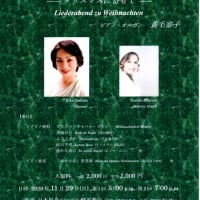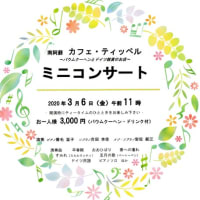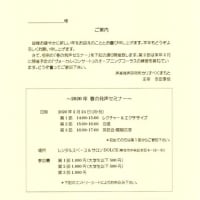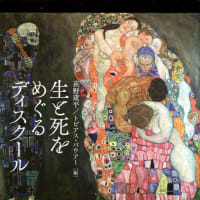W先生の資料から、今回は「呼吸のメカニズム」の項を少しご紹介します。
いきなり話が逸れますが、以前うちにレッスンに来られていた女医さんが、「最近では肺呼吸は二次呼吸で、脳脊髄液の還流が第一次呼吸であると言われているんですよ」とおっしゃっていたことがあります。W先生から頂いた資料にも、カイロプラクティクの教本に「頭蓋骨は呼吸とともに微視的な動きをすることが解明された」と記載されている、と書いてありました。呼吸と共に頭蓋骨が伸展したり屈曲したりして、一種のポンプ作用をしている、というのです。
W先生のレッスンで習ったことですが、発声時に骨盤の中の仙骨を動かすことで脳脊髄液が上がり、その時に蝶形骨が喉頭骨に押されて篩骨、鋤骨がほんの少し持ちあがるのだそうです。確かに、軟口蓋を上げておいてこの動きをすると声の抜けがよくなるのが自分でもわかります。
息の流れは目に見えないので、感覚で掴むしかありませんが、とにかく息(呼気)はいついかなる時も高速で蝶形骨に向かって垂直に飛ばさなくてはいけません。それにつけても喉の奥を開けて息の道を作っておくことが前提条件です。
呼気が垂直に飛ばないとどうなるでしょうか。息が口腔から出て行くと、息モレのしたかさついた声になります。後鼻孔に流れると鼻声っぽくなります。マスケラ(鼻根)に息を当てると、よく共鳴はするものの硬い声になります。こうした声に対して、息が蝶形骨に垂直に流れると、蝶形骨と接合している各骨洞に共鳴し、特に背後と頭上の空間が良く鳴ります。広い骨洞で共鳴するので、響きの密度が高く透明感があり、明るく輝く立体的な声になります。
このように、息の流れる方向によって共鳴は確実に変わります。うちにいらっしゃる生徒さん方も、まずしっかりと喉の奥を開けておいて呼気を垂直に高速で上げる練習をすると、明るくきらめくとても響きの良い声になり、初めての方でも金属製の譜面台がビーンと共鳴したりします。
呼吸(呼気流)の大切さはどんなに力説しても足りない、と思います。どうぞ強く速く高く呼気を飛ばす練習を大事にして下さい。トランペットのマウスピースを吹くのが一番効果的です。
いきなり話が逸れますが、以前うちにレッスンに来られていた女医さんが、「最近では肺呼吸は二次呼吸で、脳脊髄液の還流が第一次呼吸であると言われているんですよ」とおっしゃっていたことがあります。W先生から頂いた資料にも、カイロプラクティクの教本に「頭蓋骨は呼吸とともに微視的な動きをすることが解明された」と記載されている、と書いてありました。呼吸と共に頭蓋骨が伸展したり屈曲したりして、一種のポンプ作用をしている、というのです。
W先生のレッスンで習ったことですが、発声時に骨盤の中の仙骨を動かすことで脳脊髄液が上がり、その時に蝶形骨が喉頭骨に押されて篩骨、鋤骨がほんの少し持ちあがるのだそうです。確かに、軟口蓋を上げておいてこの動きをすると声の抜けがよくなるのが自分でもわかります。
息の流れは目に見えないので、感覚で掴むしかありませんが、とにかく息(呼気)はいついかなる時も高速で蝶形骨に向かって垂直に飛ばさなくてはいけません。それにつけても喉の奥を開けて息の道を作っておくことが前提条件です。
呼気が垂直に飛ばないとどうなるでしょうか。息が口腔から出て行くと、息モレのしたかさついた声になります。後鼻孔に流れると鼻声っぽくなります。マスケラ(鼻根)に息を当てると、よく共鳴はするものの硬い声になります。こうした声に対して、息が蝶形骨に垂直に流れると、蝶形骨と接合している各骨洞に共鳴し、特に背後と頭上の空間が良く鳴ります。広い骨洞で共鳴するので、響きの密度が高く透明感があり、明るく輝く立体的な声になります。
このように、息の流れる方向によって共鳴は確実に変わります。うちにいらっしゃる生徒さん方も、まずしっかりと喉の奥を開けておいて呼気を垂直に高速で上げる練習をすると、明るくきらめくとても響きの良い声になり、初めての方でも金属製の譜面台がビーンと共鳴したりします。
呼吸(呼気流)の大切さはどんなに力説しても足りない、と思います。どうぞ強く速く高く呼気を飛ばす練習を大事にして下さい。トランペットのマウスピースを吹くのが一番効果的です。