大橋巨泉は才能溢れる自由人であった。「安倍晋三に一泡吹かせて下さい」という遺言よりも、惜しむらくは議会や党議拘束に絶望して参議院議員を辞職しないで、自由人として参議院に旋風を引き起こして頂きたかった。死人に鞭ではない。参議院まで沈着した個人を拘束する習慣を否定できるのは、巨泉のような自由人かも知れない。それが現代の政治を変えるのではないかとも思ったが、選択肢が多い自由人にはその覚悟はなかったということだろう。
明治時代には足尾鉱毒事件に挑んだ田中正造がいた。戦前も軍部の暴走から国民を守ろうとした斉藤隆夫がいた。立憲君主制の帝国憲法のもとでも、徳川の封建制より希望があり、田中正造は農民を救うために政府に質問書を提出し続けて無視され、議員を辞職して死刑覚悟で天皇直訴をした。斉藤隆夫は暗殺覚悟で国会で反軍演説をして議員を除名された。いずれも国民の側から国民の生活を守ることに頑固で命を懸けた。安倍首相は国民主権の憲法のどこを改正したいのか。それは首相の妄想と信念という実存であって、国民の生活を守る憲法の本質をつくるものではなく、むしろ国民の希望を奪うものだ。
動画: NHK その時歴史が動いた「田中正造 足尾鉱毒事件に挑む」
NHK 英雄たちの選択 「開戦前夜!政治家 斉藤隆夫の挑戦」
(1)斉藤隆夫 開戦前夜 決死の演説
(2)2・26事件と粛軍演説
(3)斉藤隆夫の素顔と苦悩
(4)反軍演説と議員除名
(5)斉藤隆夫からのメッセー
参考: 田中正造に見る「人の為に生きる」ということ
田中正造その行動と思想
不屈の田中正造伝
斎藤隆夫衆議院議員の反軍演説(全文)
斎藤隆夫 - NPO法人 国際留学生協会/向学新聞
江川紹子の事件ウオッチ第27回「いまだ非公開の反軍演説」
参院選で憲法改正を発起できる2/3が得られたと騒いでいるが、この参議院は戦前は貴族院であった。憲法はGHQに押し付けられたと言うが、GHQ草案で示されていたのは衆議院のみの一院制であり、憲法で衆議院と参議院の二院制になった。先のブログの最後で指摘したように、参議院は「チェック機能」を果たす良識の府としての役割を担う。新憲法が可決された1946年の衆議院の特別委員会でも「衆院と重複する機関となればその存在意義を没却するものである」(衆院憲法改正特別書・付帯決議)と参議院独自の役割が期待された。」 本来の趣旨から言えば参議院は個人が埋没する政党の争いではなく、田中正造や斎藤隆夫のように本質を求めて権力を監視する個人の主張の場にすべきであろう。しかし、それは夢のまた夢、国民主権の現代においてさえ、政治から離れて憲法を要とした法律を守るのが任務の司法まで、政治に関わり支配者に組し、権力は腐敗していく。
参考: 日本会議トップが記者クラブで時代錯誤の会見&改憲運動を全国展開
【日本会議】の勢力拡大の最大の理由は、二人の元最高裁長官の深い関与!
<不正選挙疑惑2>「裁判所は開票の不正の話をすり替えた」
今ではメディアも国会議員も当然のことのように「衆議院の解散権」を「首相の専権事項」としているが、これはGHQの支配下にあった吉田内閣において最初から意図的に「天皇の国事行為」を利用して実施されたものであり、戦前の軍部が天皇の統帥権を悪用したのと同様に、時代は変わっても権力が象徴天皇を利用しようとする動きが始めからある。また、反共の砦として日本を利用するためにGHQが戦争責任者の公職追放を解除したことで新しい憲法の考え方に馴染まない政治家が増えたことも関係しているのかも知れない。いずれにしても吉田内閣が憲法7条を利用した抜き打ち解散が悪しき「首相の解散専権事項」のはじめである。吉田内閣が憲法69条を形式的に使用した「馴れ合い解散」で衆議院を解散して以来、日本の政治は最初から憲法に書かれた趣旨からではなく、支配者の都合の良い解釈で運用を始めているのである。
自民党から民主党に政権が移った時、人々は政治が変わると期待したが、長い自民党政権で出来上がった司法、立法、行政における組織と人間関係で生まれ根付いた政治が現実を動かしていた。民主党政権下で東日本大震災の原発事故に見舞われたが、それを実質的に裏で対応していたのは、形式的な制度ではなく自民党政権時代に培われた人脈であった。同じ民主党政権下で発生した鳥インフルエンザと口蹄疫事件 (2) (3)に際しても、現場で対応したのは民主党議員ではなく自民党議員との古くからの現場の人間関係であり、それは日本人の常識的行動でもあったのだろう。
現実の政治に近づけば近づくほど制度は仮の棲家という実存で、組織と古くからの人間関係が政治を動かしている。自立した個人の孤独と不安よりも、集団に安心して依存する日本では権力に近い政治家についていく。それが長く続くと権力は腐敗しても、自分が守られていると思えば「政治と誠実」の関係を気にすることはなく、そのうちゆでガエルとなり自民党政権を長持ちさせるのだろう。
政治の古い人間関係は政治家が世襲となることで、まるで北朝鮮と同質のアジアの文化かと思うように続いているので、新しい政治は若い世代に期待するしかない。しかし、教育やメディアに政治は多様性ではなく中立性を求め、メディアは権力批判ではなくエリートの職場となり、若い人が自分たちを拘束している社会と政治の問題を語ることから遠ざかっている。若者たちの生きていく希望は、社会を変えることよりも与えられた状況から見つけるしかないようだ。
太宰治もサルトルも生きていくには十分のお金は得られていた。それだけのお金を得られたのは、その人の才覚のお蔭だと考える人もいるだろう。99%の国民にとって生きていくためのお金が必要で、お金をどう使ったかの関心は低いかもしれない。1%のためのアベノミクスではなく、99%の国民の生活のための政治によって今よりは暮らしやすくなると思うが、バラバラになっていく国民には社会に順応することが精一杯で、社会を変えることへの実感はないのかもしれない。
学者(公務員)として仕事をさせていただいた恩返し(正義)のつもりでこのブログを書いているが、家業を断念して学者として現場に学問の道を求めることができたのも、ちょっぴり頑固でわがままな私が定年まで仕事をできた環境があったからこそと感謝している。
今も99%の国民の側に立ち、わがままだと受け取られるかもしれない頑固な公務員(政治家)が現状を変えるかも知れない。そう思いつつ希望だけは死ぬまで持ち続けたい。
初稿 2016.7.23










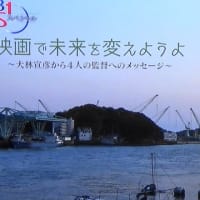



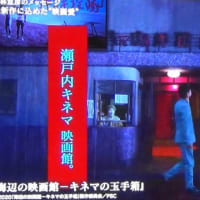
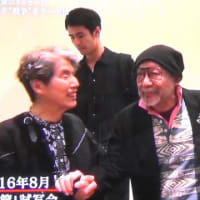

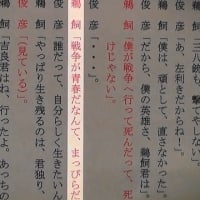



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます