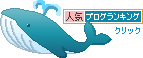周りの人たちへの理解が深まるにつれ、
周りの人たちへの理解が深まるにつれ、その人たちの人間的価値が見え、
敬虔な気持ちを抱くようになる。
他者を理解し、その人の魂に触れることは、
神聖な場所に足を踏み入れるのと同じである。
今すぐにでも実行に移すことができる。
今度誰かと話をするとき、
自分の自叙伝を持ち出すのはやめて、
その人を本気で理解する努力をして見る。
その人が心を開いて悩みを打ち明けなくとも、
その人の身になり、共感することはできる。
その人の気持ちを察し、心の痛みを感じとって、
「今日は元気がないね」
と言ってあげる。
その人は何も言わないかもしれない。
それでもいい。
あなたの方から、その人を理解しようとし、
その人を思いやる気持ちを表したのだから。
 「七つの習慣」
「七つの習慣」スティーブン・コビナー 著

 今、僕は子供達に
今、僕は子供達に水泳を教えるインストラクター
定年後の新しいチャレンジと
頑張って子供達とのスキンシップを
楽しませてもらっている
ある女の子が
「先生、今日は元気がないね!」
と言って近寄ってきた
驚きと嬉しさ...!というか感動の瞬間
子供達は僕を先生として、一人の大人として
しっかりと観察していることを実感
もう孫とお爺ちゃんくらいの年の差なのだが
水泳の先生としっかり位置付けて
見ているんだなと痛感
でも自分ときたら、
悪ガキにばかり目をやり、
叱り声で感情をもろに出している
なんと浅はかな...!
子供達の行動についぞ反応的に言動している
自分が稚拙すぎて恥ずかしい
そんな感情のコントロールに戸惑っている時に
ある女の子の一言
「先生、今日は元気がないね!」
この言葉は最高のプレゼント
見てくれている喜び、それも大人じゃなく子供達
以前、こんなことも言われたことがある
「先生は何歳...!」
こんな僕のことを気にしているんだなと思うと
胸がキュンとなる
一番純粋な心の子供達と本気で接することの難しさ
叱ると、
「いうことを聞かない」という言動が返ってくる
でも「今日は元気がいいな、
力が有り余っているようだね、
でも他の人に迷惑をかけちゃダメだよ!」
叱らずに子供達の懐に入っていけたら
良いなって思っている
 早起き鳥
早起き鳥 人気ブログランキングに参加
人気ブログランキングに参加
読者の皆様のご支援に心から感謝申し上げます。