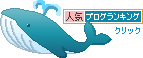娘のジェニーが
娘のジェニーが生後二ヶ月目に病気になった
具合が悪くなったのは土曜日で、
その日はちょうど私たちが住んでいる地域で
アメリカンフットボールの大きな試合が行われており、
私も妻も行きたかったが、
幼いジェニーを置いていくわけにはいかなかった
そのうち吐いたり下痢をしたりしている
ジェニーの容態が心配になり、
医者に見せようと電話した。
ところが医者も試合を見に行っていた。
その医者は我が家の主治医ではなかったが
彼を呼び出しすしかなかった。
妻はスタジアムに電話し、医者を呼び出してもらった
試合が山場を迎えたところで
医者は迷惑そうな声で応じた
「はいどうしました?」
「コヴィーと申します。
実は娘のジェニーの具合がひどくて・・・」
「どんな様子ですか?」
妻がジェニーの症状を説明すると、医者は
「わかりました。薬局に処方を伝えましょう」
妻は受話器を置くと
「慌てていたからちゃんを説明できたが不安だわ。
でも、たぶん大丈夫」
「ジェニーが生まれたばかりだということは言ったのか?」
と私は聞いた。
「わかっていると思うけど・・・」
「はっきり確信が持てないのに、
その医者が処方した薬を飲ませるつもりなのか?」
「もう一度電話した方がいい」
今度は私が電話した。
「先生、先ほど娘の件でお電話しましたが
娘が生後二ヶ月の赤ん坊だということはご存知でしたか?」
「なんですって、知りませんでした。
電話してくれてよかった。すぐに処方を変えます」
 「七つの習慣」
「七つの習慣」スティーブン・コビナー 著

 状況からすると
状況からするととても緊迫したシーンである
医師とは電話でつながっていたとしても
医師は患者を直接診ることができない状況
医師に伝える方は
極めて事細かく正確に説明をする必要がある
医師はその症状の聞き取りから処方するわけで
正確な理解が何よりも医師に求められている
でもこのスタジアムにいた医師だが
基本的に患者の歳が幾つなのか聞いていない点で、
問題があるように思う
伝える母親にもその大切な基本的なことを
説明していないミスはあったにせよ
処方する医師が
患者の年齢を確認せずに処方するなど
大きなミスではないかと僕は思う
まあ誰に責任があろうと
処方する前には十分な診断が必要なのは
自明の理まさに原則
この原則を怠ったら
そのリスクは大きいということを
このエピソードは物語っている
それにしても、それに気づいた旦那さん、
そして自分自ら電話をかけた事実
確かに大切なこと、
でも当たり前のことが確実に行動できる人、
僕も最低限、原則を守り
適切な行動を取れるように生きていかなければ...!
 早起き鳥
早起き鳥 人気ブログランキングに参加
人気ブログランキングに参加
読者の皆様のご支援に心から感謝申し上げます。