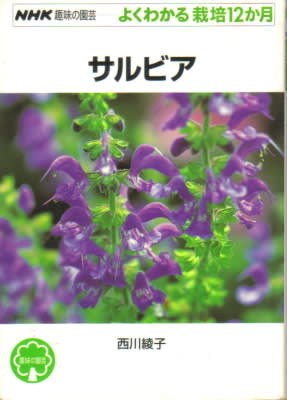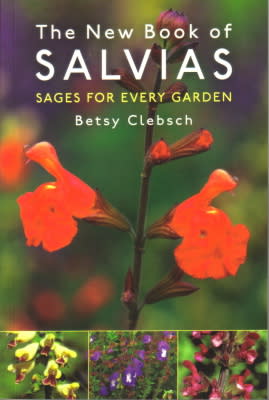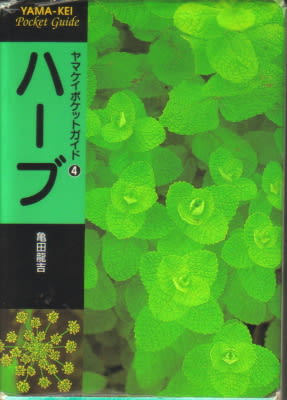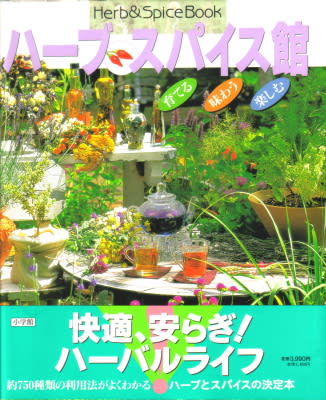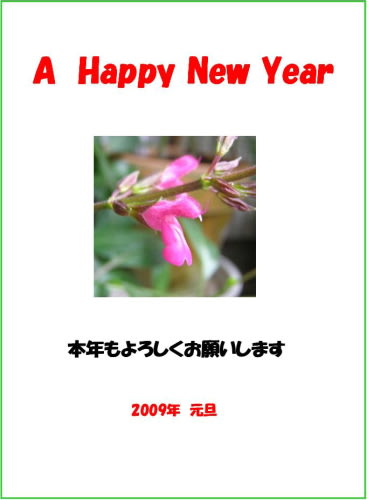連休後半から天気が悪くなり気温が下がったためか、本来の「ホットリップス」の姿が見られるようになった。
気温が高すぎると赤一色となり、サルビア・グレッギーと区別がつかないが、気温が下がると「サルビア・ミクロフィラ“ホットリップス”」らしく、花の上部が白で、下唇部分が赤というバイ・カラー(bi-color)の姿に近づく。
(写真)本来の姿が出てきたホットリップス・セージの花

「ホットリップス・セージ」と、その親「サルビア・ミクロフィラ」発見のストリー
この花は、最近では「ホットリップス・セージ('Hot Lips' Sage)」と呼ばれているが、「サルビア・ミクロフィラ」の園芸品種で、サンフランシスコの園芸雑誌の編集者リチャード・ターナ(Richard Turner, editor of Pacific Horticulture Magazine)によって発見され導入された。
その発見の経緯は、何と彼の新築祝いのパーティーにメキシコ人の家政婦がお祝いとしてメキシコのオアハカ州(Oaxaca State)にある自宅からプレゼントとして持って来たという。
この「ホットリップス・セージ」は、自己のユニークなところを知っていて、気づいて欲しいがために、そして雑誌に取り上げてもらいたいがために園芸雑誌の編集者のところに来たのかもわからない。
偶然には必然が隠されているのだろうか。
「ホットリップス・セージ」の親は、サルビア・ミクロフィラであり、キュー王立植物園の記録では、アメリカのナチュラリスト、プラントハンターのプリングル(Cyrus Guernsey Pringle 1838-1911)によって1885年にメキシコで発見された。
(プリングルに関してはこちらを参照)
セントルイスにあるミズリイ植物園(Missouri Botanical Garden)のデータを見ていると面白いものに気づいた。
プリングルの発見時期よりも早い1878年にメキシコ・サン・ルイス・ポトシで「サルビア・ミクロフィラ」が発見されている。
発見・採取者は、パリー(Charles Christopher Parry 1823-1890)とパーマ(Edward Palmer 1829-1911)。
二人とも英国生まれでパリーは1832年9歳の時に両親とともに移住。パーマは1849年彼が20歳の時にアメリカに移住し似たようなキャリアを経験するが、パリーが学歴エリートだとするとパーマはたたき上げという違いがある。
しかし二人の共通点は、学術的な名誉よりも生涯一プラントハンターでありたいというところにあり、ミクロフィラの公式的な発見者プリングル、グレッギーの発見者グレッグともども米国南西部からメキシコにかけてのフロンティアに魅せられた冒険者の意気込みが感じられて好感が持てる。
彼らは地位・名誉を得ようとしなかったが、数多くの新種の発見という魔物に取り付かれ結果としての植物の歴史への貢献は素晴らしいものがある。フロンティアを見つけたものだけが体験できる陶酔の境地なのだろう。
パリーは、オンタリオ医科大学の1846年の卒業生で医者だが、この当時のアメリカの植物学会をリードしていたトーリー(John Torrey 1796-1873)、その弟子で後に米国植物学会での第一人者となるグレイ(Asa Gray 1810-1888)、そしてグレッグも採取した植物を送っていたミズリイ植物園の創始者ともなるエンゲルマン(George Engelmann1809–1884)に医学及び植物学を師事して学ぶ。というめぐまれた経歴を有するエリートだが、師匠たちと同じ世界を目指さずロッキー山脈を走破し30,000ものユニークな種を採取し、その植物カタログを作る第一人者となった。
 パリーは、山歩きをするにふさわしい姿しか撮らせなかったという。スタイルに主義・主張がある、或いは、主義主張がスタイルになったという確信犯的な生き方に共感を覚える。
パリーは、山歩きをするにふさわしい姿しか撮らせなかったという。スタイルに主義・主張がある、或いは、主義主張がスタイルになったという確信犯的な生き方に共感を覚える。
1700年代中頃から1800年代は、このような実地探索・フィールドワークを経験しない限り象牙の塔に入れないというスウェーデンのリンネイズムも強烈な主張があるが、英国にもフランスにもそして米国にも、「フィールドワークがあってその先がある」ということがコモンセンスとしてあり、行動規範の柱となって毅然と存在したという感がある。
“書を捨てて野に出よ!”と言いたいが、いまはその前に書を読めということからはじめなければならないのだろうか?
(写真)ホットリップス・セージの葉と花

サルビア・ミクロフィラ‘ホットリップス’
・シソ科アキギリ属の小低木で2年目から木質化する。
・学名はサルビア・ミクロフィラ‘ホットリップス’(Salvia microphylla 'Hot Lips’)、英名は、'Hot Lips' Sage。
・原産地は、アメリカのテキサス州からメキシコに分布する。
・草丈 50~60センチ(摘心で大きさを作る。)
・開花期 4月~10月
・耐寒性 普通だが丈夫。(霜に当てなければ大丈夫)
・耐暑性 強い
・土壌 適湿(乾いたらたっぷりと)
・ふやし方 さし芽(5月頃に形を整えるために摘心を行うのでこの時期にさし芽)

<Contents of the last year>
ミクロフィラにまつわる歴史
真っ赤なチェリーセージサルビア・グレッギーは、1848年にグレッグ(1809–1884)によって発見されたが、サルビア・ミクロフィラは、1885年にアメリカのナチュラリスト、プリングル(Cyrus Guernsey Pringle 1838-1911)によってメキシコで発見された。
彼は、35年にわたりメキシコを中心とした北アメリカの植物調査を行い、おおよそ1200の新種を発見したという偉大な成果を残している。
また、サルビア・ミクロフィラにはいくつかの種があるが、その新種の名前には、大航海時代のスペイン統治の植物学者の名残りがある。
Martínとその盟友José Mariano Mociño(1756-1820)の名がついたミクロフィラの種(Salvia microphylla Sessé & Moc)がある。
Martín Sessé y Lacasta (1751-1808)は、スペインの医者でナチュラリスト。
彼は、スペイン国王カルロス三世にメキシコでの大規模な植物相の調査・探検を提案し実施することになった。
大航海時代は、香辛料・薬用植物・金を東洋に求めてはじまったが、重要植物は機密としてスペインが秘匿してきただけでなく、よく知られない植物が多々あった。
マーティンは、メキシコの植物相の調査・植物学の発展に貢献したが、彼が集めた植物のコレクション及び原稿はまた秘匿され、死後約2世紀後に世に出てくるという不思議なことになっている。
またということは、16世紀後半のフランシスコ・エルナンデスの植物調査の成果が公開されないという同じようなことが以前にもあったが、重要な情報は集めるが秘匿するだけで活用されないという体質が伺える。
http://blog.goo.ne.jp/tetsuo_shiga/d/20080222
活用するために集めるという原点を忘れた体質が、頂点から滑り落ちたのであろうか?
スペインに取って変わったイギリスは、キュー王立植物園を植物情報を収集する戦略拠点として構築・活用していくことになる。
さて日本では??
<チェリーセージシリーズ>
チェリーセージ①:サルビア・ヤメンシスの花
チェリーセージ②:サルビア・グレッギーの花
気温が高すぎると赤一色となり、サルビア・グレッギーと区別がつかないが、気温が下がると「サルビア・ミクロフィラ“ホットリップス”」らしく、花の上部が白で、下唇部分が赤というバイ・カラー(bi-color)の姿に近づく。
(写真)本来の姿が出てきたホットリップス・セージの花

「ホットリップス・セージ」と、その親「サルビア・ミクロフィラ」発見のストリー
この花は、最近では「ホットリップス・セージ('Hot Lips' Sage)」と呼ばれているが、「サルビア・ミクロフィラ」の園芸品種で、サンフランシスコの園芸雑誌の編集者リチャード・ターナ(Richard Turner, editor of Pacific Horticulture Magazine)によって発見され導入された。
その発見の経緯は、何と彼の新築祝いのパーティーにメキシコ人の家政婦がお祝いとしてメキシコのオアハカ州(Oaxaca State)にある自宅からプレゼントとして持って来たという。
この「ホットリップス・セージ」は、自己のユニークなところを知っていて、気づいて欲しいがために、そして雑誌に取り上げてもらいたいがために園芸雑誌の編集者のところに来たのかもわからない。
偶然には必然が隠されているのだろうか。
「ホットリップス・セージ」の親は、サルビア・ミクロフィラであり、キュー王立植物園の記録では、アメリカのナチュラリスト、プラントハンターのプリングル(Cyrus Guernsey Pringle 1838-1911)によって1885年にメキシコで発見された。
(プリングルに関してはこちらを参照)
セントルイスにあるミズリイ植物園(Missouri Botanical Garden)のデータを見ていると面白いものに気づいた。
プリングルの発見時期よりも早い1878年にメキシコ・サン・ルイス・ポトシで「サルビア・ミクロフィラ」が発見されている。
発見・採取者は、パリー(Charles Christopher Parry 1823-1890)とパーマ(Edward Palmer 1829-1911)。
二人とも英国生まれでパリーは1832年9歳の時に両親とともに移住。パーマは1849年彼が20歳の時にアメリカに移住し似たようなキャリアを経験するが、パリーが学歴エリートだとするとパーマはたたき上げという違いがある。
しかし二人の共通点は、学術的な名誉よりも生涯一プラントハンターでありたいというところにあり、ミクロフィラの公式的な発見者プリングル、グレッギーの発見者グレッグともども米国南西部からメキシコにかけてのフロンティアに魅せられた冒険者の意気込みが感じられて好感が持てる。
彼らは地位・名誉を得ようとしなかったが、数多くの新種の発見という魔物に取り付かれ結果としての植物の歴史への貢献は素晴らしいものがある。フロンティアを見つけたものだけが体験できる陶酔の境地なのだろう。
パリーは、オンタリオ医科大学の1846年の卒業生で医者だが、この当時のアメリカの植物学会をリードしていたトーリー(John Torrey 1796-1873)、その弟子で後に米国植物学会での第一人者となるグレイ(Asa Gray 1810-1888)、そしてグレッグも採取した植物を送っていたミズリイ植物園の創始者ともなるエンゲルマン(George Engelmann1809–1884)に医学及び植物学を師事して学ぶ。というめぐまれた経歴を有するエリートだが、師匠たちと同じ世界を目指さずロッキー山脈を走破し30,000ものユニークな種を採取し、その植物カタログを作る第一人者となった。
 パリーは、山歩きをするにふさわしい姿しか撮らせなかったという。スタイルに主義・主張がある、或いは、主義主張がスタイルになったという確信犯的な生き方に共感を覚える。
パリーは、山歩きをするにふさわしい姿しか撮らせなかったという。スタイルに主義・主張がある、或いは、主義主張がスタイルになったという確信犯的な生き方に共感を覚える。1700年代中頃から1800年代は、このような実地探索・フィールドワークを経験しない限り象牙の塔に入れないというスウェーデンのリンネイズムも強烈な主張があるが、英国にもフランスにもそして米国にも、「フィールドワークがあってその先がある」ということがコモンセンスとしてあり、行動規範の柱となって毅然と存在したという感がある。
“書を捨てて野に出よ!”と言いたいが、いまはその前に書を読めということからはじめなければならないのだろうか?
(写真)ホットリップス・セージの葉と花

サルビア・ミクロフィラ‘ホットリップス’
・シソ科アキギリ属の小低木で2年目から木質化する。
・学名はサルビア・ミクロフィラ‘ホットリップス’(Salvia microphylla 'Hot Lips’)、英名は、'Hot Lips' Sage。
・原産地は、アメリカのテキサス州からメキシコに分布する。
・草丈 50~60センチ(摘心で大きさを作る。)
・開花期 4月~10月
・耐寒性 普通だが丈夫。(霜に当てなければ大丈夫)
・耐暑性 強い
・土壌 適湿(乾いたらたっぷりと)
・ふやし方 さし芽(5月頃に形を整えるために摘心を行うのでこの時期にさし芽)

<Contents of the last year>
ミクロフィラにまつわる歴史
真っ赤なチェリーセージサルビア・グレッギーは、1848年にグレッグ(1809–1884)によって発見されたが、サルビア・ミクロフィラは、1885年にアメリカのナチュラリスト、プリングル(Cyrus Guernsey Pringle 1838-1911)によってメキシコで発見された。
彼は、35年にわたりメキシコを中心とした北アメリカの植物調査を行い、おおよそ1200の新種を発見したという偉大な成果を残している。
また、サルビア・ミクロフィラにはいくつかの種があるが、その新種の名前には、大航海時代のスペイン統治の植物学者の名残りがある。
Martínとその盟友José Mariano Mociño(1756-1820)の名がついたミクロフィラの種(Salvia microphylla Sessé & Moc)がある。
Martín Sessé y Lacasta (1751-1808)は、スペインの医者でナチュラリスト。
彼は、スペイン国王カルロス三世にメキシコでの大規模な植物相の調査・探検を提案し実施することになった。
大航海時代は、香辛料・薬用植物・金を東洋に求めてはじまったが、重要植物は機密としてスペインが秘匿してきただけでなく、よく知られない植物が多々あった。
マーティンは、メキシコの植物相の調査・植物学の発展に貢献したが、彼が集めた植物のコレクション及び原稿はまた秘匿され、死後約2世紀後に世に出てくるという不思議なことになっている。
またということは、16世紀後半のフランシスコ・エルナンデスの植物調査の成果が公開されないという同じようなことが以前にもあったが、重要な情報は集めるが秘匿するだけで活用されないという体質が伺える。
http://blog.goo.ne.jp/tetsuo_shiga/d/20080222
活用するために集めるという原点を忘れた体質が、頂点から滑り落ちたのであろうか?
スペインに取って変わったイギリスは、キュー王立植物園を植物情報を収集する戦略拠点として構築・活用していくことになる。
さて日本では??
<チェリーセージシリーズ>
チェリーセージ①:サルビア・ヤメンシスの花
チェリーセージ②:サルビア・グレッギーの花