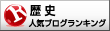(写真)ルー(Ruta graveolens)の花

ヘンルーダ、コモンルーなどと呼ばれるヨーロッパ南東部・バルカン半島が原産地のルー(Ruta graveolens)の花が咲いた。
花としての優雅さ・華麗さはなく、レトロなロボット工学の部品の集合体といった感じがする。部品点数はちょっと少ないが・・・・。
宮崎駿のアニメ「風の谷のナウシカ」にこんな飛行物体がなかったかな~と思い見直してみたぐらい近い世界感がある。
しかし、いにしえでは高く評価されたハーブで、風邪の発熱、月経不順、ヒステリー、虫刺され、化膿したおでき、打撲などだけでなく目薬としても使われたほどの万能薬だった。
解毒王として有名な、現在のトルコにあたるポントゥスとアルメニアの王ミトリダテス6世(Mithridates VI 134 BC-63 BC)は、彼が12歳のとき父親のMithridates Ⅴ世が毒殺され、母親が摂政となり弟とともに共同の王となった。母親は弟をかわいがっていたので、毒殺を恐れ逃げて隠れることになり、この間に毒に強い身体づくりと解毒剤を開発したという。この解毒剤にルーも使われていたようだ。
キリスト教が支配し合理性が欠落した暗黒の中世には“魔よけ”としても使われ、日曜日のミサでは聖水をつけるブラシにルーが使われたという。
切実で面白い使い方としては、裁判所に引き出される容疑者は、暗く汚い牢屋でノミ・ダニなどにたかられているので、座る椅子の周囲にルーが置かれたという。
我が家では、猫の忌避効果があるらしいので、その通り道に置くことで栽培しているが、この鉢の近くで子猫が昼寝しているのを見てしまった。最初は死んでいるのかなと思いルーの効力の強さに驚いてしまったが、近づくと逃げてしまい昼寝のようだった。
猫には効かないようだ。
防虫効果はあるのだろうか?と本来のハーブとしての効果にも疑いが生じてしまったが、シソ科のいい香りとは比べるまでもなく、好ましくない香りなので防虫効果には期待しておこう。
効果がないからといって、口に入れることは止めておきたい。
いまではイタリア特産の蒸留酒グラッパ (grappa)の香り付けに唯一に近くこのルーが使われているそうだ。
グラッパは飲んだこともなくよく知らなかったが、ワインを造る際に出る搾りかすのブドウの皮と種を発酵させ、蒸留して造るブランデーという。
香り付けには、ブルーベリー、オレンジ、蜂蜜、アーモンド、クミン、ペパーミント、ルー等のフルーツやハーブがアルコール含有量の3%まで使用される。
ルーが使われたのは、原産地であり安価に大量に手に入り、香り付けだけでなく防腐剤としての役割もあったのだろう。
(写真)ルーの立ち姿

ルー(Ruta graveolens)
・ミカン科ルタ(ヘンルーダ)属の半耐寒性の常緑の小低木。
・学名はRuta graveolens(ルタ グラビオレンス)、種小名のgraveolensは“臭い・刺激的な香り”という意味。 和名はヘンルーダ 、英名はCommon Rue
・原産地はヨーロッパ南東部・バルカン半島で、日本には江戸時代に渡来する。
・ヨーロッパでは古くからハーブとして通経剤・鎮痙剤・駆虫剤・料理の香り付けなどに使われた。現在は毒性があるとされているので、口に入れるものとしては使用しない。防虫・猫よけなどで花壇の縁取りで使われる。
・丈は50-100cmで青灰色の葉が対生につく。
・乾燥に強く過湿に弱い。梅雨時は風通しの良い半日陰などが適している。また枝葉をカットするのも良い。
・開花期は5月から夏場で、黄色の花が咲く。
古から存在したルーではあるが、植物の学名としてリンネが登録した際に参照した採取者(プラントコレクター)は、ナポリ大学の植物学教授ミケーレ・テノーレ(Michele Tenore 1780 - 1861)だった。
そして、下記の植物画を描いたのはドイツの植物学者でアーティストのオットー・ウイルヘルム・トーミ(Otto Wilhelm Thomé 1840-1925)。ボタニカルアートの素晴らしさが味わえる。
(写真)ルーの植物画

出典:Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé 「Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz」 1885, Gera, Germany

ヘンルーダ、コモンルーなどと呼ばれるヨーロッパ南東部・バルカン半島が原産地のルー(Ruta graveolens)の花が咲いた。
花としての優雅さ・華麗さはなく、レトロなロボット工学の部品の集合体といった感じがする。部品点数はちょっと少ないが・・・・。
宮崎駿のアニメ「風の谷のナウシカ」にこんな飛行物体がなかったかな~と思い見直してみたぐらい近い世界感がある。
しかし、いにしえでは高く評価されたハーブで、風邪の発熱、月経不順、ヒステリー、虫刺され、化膿したおでき、打撲などだけでなく目薬としても使われたほどの万能薬だった。
解毒王として有名な、現在のトルコにあたるポントゥスとアルメニアの王ミトリダテス6世(Mithridates VI 134 BC-63 BC)は、彼が12歳のとき父親のMithridates Ⅴ世が毒殺され、母親が摂政となり弟とともに共同の王となった。母親は弟をかわいがっていたので、毒殺を恐れ逃げて隠れることになり、この間に毒に強い身体づくりと解毒剤を開発したという。この解毒剤にルーも使われていたようだ。
キリスト教が支配し合理性が欠落した暗黒の中世には“魔よけ”としても使われ、日曜日のミサでは聖水をつけるブラシにルーが使われたという。
切実で面白い使い方としては、裁判所に引き出される容疑者は、暗く汚い牢屋でノミ・ダニなどにたかられているので、座る椅子の周囲にルーが置かれたという。
我が家では、猫の忌避効果があるらしいので、その通り道に置くことで栽培しているが、この鉢の近くで子猫が昼寝しているのを見てしまった。最初は死んでいるのかなと思いルーの効力の強さに驚いてしまったが、近づくと逃げてしまい昼寝のようだった。
猫には効かないようだ。
防虫効果はあるのだろうか?と本来のハーブとしての効果にも疑いが生じてしまったが、シソ科のいい香りとは比べるまでもなく、好ましくない香りなので防虫効果には期待しておこう。
効果がないからといって、口に入れることは止めておきたい。
いまではイタリア特産の蒸留酒グラッパ (grappa)の香り付けに唯一に近くこのルーが使われているそうだ。
グラッパは飲んだこともなくよく知らなかったが、ワインを造る際に出る搾りかすのブドウの皮と種を発酵させ、蒸留して造るブランデーという。
香り付けには、ブルーベリー、オレンジ、蜂蜜、アーモンド、クミン、ペパーミント、ルー等のフルーツやハーブがアルコール含有量の3%まで使用される。
ルーが使われたのは、原産地であり安価に大量に手に入り、香り付けだけでなく防腐剤としての役割もあったのだろう。
(写真)ルーの立ち姿

ルー(Ruta graveolens)
・ミカン科ルタ(ヘンルーダ)属の半耐寒性の常緑の小低木。
・学名はRuta graveolens(ルタ グラビオレンス)、種小名のgraveolensは“臭い・刺激的な香り”という意味。 和名はヘンルーダ 、英名はCommon Rue
・原産地はヨーロッパ南東部・バルカン半島で、日本には江戸時代に渡来する。
・ヨーロッパでは古くからハーブとして通経剤・鎮痙剤・駆虫剤・料理の香り付けなどに使われた。現在は毒性があるとされているので、口に入れるものとしては使用しない。防虫・猫よけなどで花壇の縁取りで使われる。
・丈は50-100cmで青灰色の葉が対生につく。
・乾燥に強く過湿に弱い。梅雨時は風通しの良い半日陰などが適している。また枝葉をカットするのも良い。
・開花期は5月から夏場で、黄色の花が咲く。
古から存在したルーではあるが、植物の学名としてリンネが登録した際に参照した採取者(プラントコレクター)は、ナポリ大学の植物学教授ミケーレ・テノーレ(Michele Tenore 1780 - 1861)だった。
そして、下記の植物画を描いたのはドイツの植物学者でアーティストのオットー・ウイルヘルム・トーミ(Otto Wilhelm Thomé 1840-1925)。ボタニカルアートの素晴らしさが味わえる。
(写真)ルーの植物画

出典:Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé 「Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz」 1885, Gera, Germany