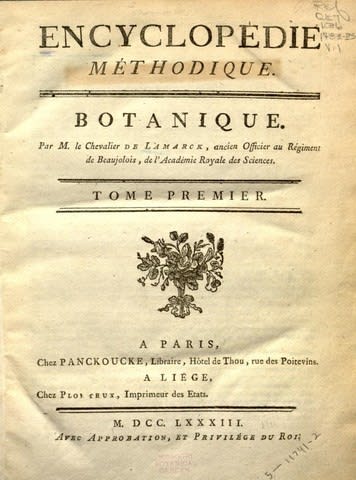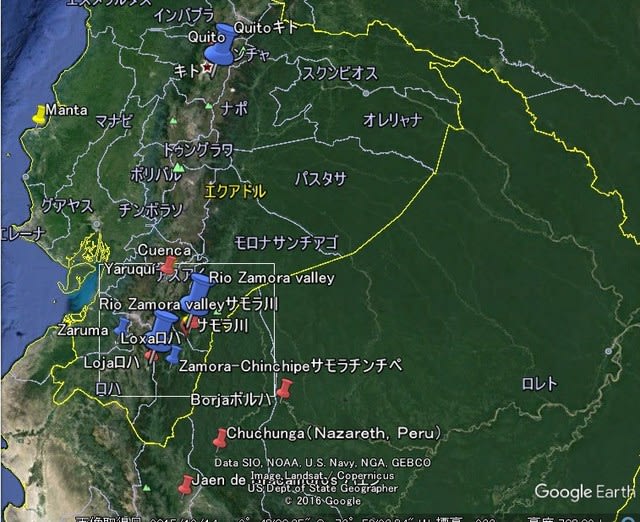(写真)カランコエ・ブロスフェルディアーナの立ち姿

あるところからこのカランコエを頂戴した。
最初は、よく出来た造花だな~と、最近の造花作品のリアリティとレパートリーの広さに感心した。
特に、肉厚の葉はゴムのような感触で手触りも良く、自然界には見慣れない程光輝いている。
本物に似せて作る素材の進化はすごいモノがあると感心した。
丁度、上野・合羽橋(カッパバシ)の道具街に食品サンプルの店があるが、そこで見る本物そっくりの食品のサンプル、或いは、100円ショップにある造花コーナーで色鮮やかな造花が際立っていて、本物よりも魅力を感じる瞬間がある。
こんな気分だった。
(写真)寿司のサンプル(本物ではありません)

(出典)JAPAN TRAVEL WEB MAGAZINE MATCHA
初めてのカランコエは、こんな強烈なインパクトを与えてくれた。
これがカランコエ・ブロスフェルディアーナ(Kalanchoe blossfeldiana)というマダガスカル原産の植物の園芸品種だと分かるのにちょっと時間がかかった。
バオバブの木があるくらいだからマダガスカル原産の植物には日本の園芸常識では計れないモノがあるのだろう! と納得した。
(写真)バオバブの木

(出典) 「ぱんさのマイナー植物園/バオバブ王国」
(写真)カランコエ・ブロスフェルディアーナの葉・・・どう見ても良くできた造花だね!

カランコエ・ブロスフェルディアーナの歴史
カランコエは、ベンケイソウ科の1属で、この中には分類方法にもよるが約140種が含まれ、マダガスカル、アフリカ南西部、熱帯・亜熱帯のアジアに分布する多肉植物で、わが日本でも園芸品種が結構販売されているという。
カランコエ・ブロスフェルディアーナ(Kalanchoe blossfeldiana)の原産地はアフリカ東側のインド洋にあるマダガスカルで、島の北部の都市アンツィラナナ(Antsiranana)のツァラタナナ山中で1927年に発見・採取されたというから植物の世界ではつい最近発見されたことになる。
発見・採取したのは1896‐1933年まで37年間マダガスカルの植物を調査研究してきたマダガスカルの植物のスペシャリスト、フランス人のジョセフ・マリー・ヘンリー・アルフレッド・ペリエ・デ・ラ・バシィー(Joseph Marie Henry Alfred Perrier de la Bâthie 1873 – 1958)という長い名前を持っているヒトだった。
名前にマリー(Marie)がはいっていたので女性かと思ったが男性だった。
ペリエ・デ・ラ・バシィーは、この原種を1927年にパリに送り、ドイツ・ポツダムで育種業をしているロバート・ブロスフェルド(Robert Blossfeld 1882–1945)によってハイブリッドされ、1932年に室内植物のカランコエ(=Kalanchoe blossfeldiana)として売り出された。日本でも第二次世界大戦前に導入されたという。
学名のカランコエ・ブロスフェルディアーナ(Kalanchoe blossfeldiana Poelln.(1934))は、ドイツの多肉植物の権威、ポエニーズ(Karl von Poellnitz 1896‐1945)によって1934年に命名された。
リンネの二命名法では、属名+種小名で生物の名前を付けるが、種小名のブロスフェルディアーナ(blossfeldiana)は、カランコエのハイブリッドを開発したRobert Blossfeldを記念してつけられた。
一方、属名のカランコエ(Kalanchoe)は、中国語の“落ちて育つもの”という意味の「加籃菜」( jia lan cai )の音読みによるという説がある。
何故かというと、カランコエの仲間は、葉の鋸歯部分に生長点を持っているので葉が脱落すると、ここから発芽し新しい個体になるのでこの特長をさしている。
最近の言葉ではこれを「ハカラメ(葉から芽)」と呼び、葉を水に浮かべて沢山の芽を出させるので「マザーリーフ」とも言っているようだ。
まるでこのような名前の展開は、赤提灯の定番ホルモン焼きのホルモンの語源の一つである、「大阪弁で捨てる物にあたる“放るもん”」に良く似ている。
本題に戻ると、この属名をつけたのはフランスの植物学者でリンネに対抗する植物の分類体系を発表したMichel Adanson(1727-1806)で、1763年に命名されたというから二名法初期の頃だった。
ところで多少気になることがあったが、ドイツの学名命名者ポエニーズ(Karl von Poellnitz 1896‐1945)とカランコエの園芸品種の作出者で学名の種小名に名を残すブロスフェルド(Robert Blossfeld 1882–1945)は、二人とも1945年に死亡している。
ブロスフェルドは確認できなかったが、ポエニーズは彼の家族とともに連合国の爆撃の犠牲となった。戦争というものはこのような現実をいくつも作って来たということに気づかされてしまった。
(写真)カランコエ・ブロスフェルディアーナの花

カランコエ(Kalanchoe blossfeldiana)
・ベンケイソウ科カランコエ属の小さい潅木のような多年草。
・原産地:アフリカ東側のインド洋にあるマダガスカルが原産地。
・学名:カランコエ・ブロスフェルディアーナ(Kalanchoe blossfeldiana Poelln.(1934))は、ドイツの多肉植物の権威、ポエニーズ(Karl von Poellnitz 1896‐1945)によって1934年に命名された。
・英名でのコモンネームは、flaming Katy,Christmas kalanchoe,florist kalanchoe等で、日本でカランコエの名で最も多く流通しているのは,マダガスカル北部のツァラタナナ山脈に生育するKalanchoe blossfeldianaの園芸品種である。
・草丈15-80cmの低木で、多肉質の葉を持つ多年草。
・短日植物である。つまり、連続した暗期(夜)が一定時間より長くなると花芽が形成される植物なので、この性質を使い花を開花させる時期をコントロールすることが出来るので1年中販売されている鉢物になっている。
・花弁は5枚でやや反り返っていて星の形に開花する。開花時期は秋から春。花色は、白、黄色、ピンク、オレンジ等豊富。クリスマス、バレンタイン、ホワイトデーなどのイベントでのギフトとしても重宝。
・耐寒性はあまりなく12~15℃の温度で育てる。冬も5℃以上に保つ。
・多湿を嫌い、排水のよい用土に植え,日当りのよい場所で育てる。
・繁殖は挿木によって行われる。

あるところからこのカランコエを頂戴した。
最初は、よく出来た造花だな~と、最近の造花作品のリアリティとレパートリーの広さに感心した。
特に、肉厚の葉はゴムのような感触で手触りも良く、自然界には見慣れない程光輝いている。
本物に似せて作る素材の進化はすごいモノがあると感心した。
丁度、上野・合羽橋(カッパバシ)の道具街に食品サンプルの店があるが、そこで見る本物そっくりの食品のサンプル、或いは、100円ショップにある造花コーナーで色鮮やかな造花が際立っていて、本物よりも魅力を感じる瞬間がある。
こんな気分だった。
(写真)寿司のサンプル(本物ではありません)

(出典)JAPAN TRAVEL WEB MAGAZINE MATCHA
初めてのカランコエは、こんな強烈なインパクトを与えてくれた。
これがカランコエ・ブロスフェルディアーナ(Kalanchoe blossfeldiana)というマダガスカル原産の植物の園芸品種だと分かるのにちょっと時間がかかった。
バオバブの木があるくらいだからマダガスカル原産の植物には日本の園芸常識では計れないモノがあるのだろう! と納得した。
(写真)バオバブの木

(出典) 「ぱんさのマイナー植物園/バオバブ王国」
(写真)カランコエ・ブロスフェルディアーナの葉・・・どう見ても良くできた造花だね!

カランコエ・ブロスフェルディアーナの歴史
カランコエは、ベンケイソウ科の1属で、この中には分類方法にもよるが約140種が含まれ、マダガスカル、アフリカ南西部、熱帯・亜熱帯のアジアに分布する多肉植物で、わが日本でも園芸品種が結構販売されているという。
カランコエ・ブロスフェルディアーナ(Kalanchoe blossfeldiana)の原産地はアフリカ東側のインド洋にあるマダガスカルで、島の北部の都市アンツィラナナ(Antsiranana)のツァラタナナ山中で1927年に発見・採取されたというから植物の世界ではつい最近発見されたことになる。
発見・採取したのは1896‐1933年まで37年間マダガスカルの植物を調査研究してきたマダガスカルの植物のスペシャリスト、フランス人のジョセフ・マリー・ヘンリー・アルフレッド・ペリエ・デ・ラ・バシィー(Joseph Marie Henry Alfred Perrier de la Bâthie 1873 – 1958)という長い名前を持っているヒトだった。
名前にマリー(Marie)がはいっていたので女性かと思ったが男性だった。
ペリエ・デ・ラ・バシィーは、この原種を1927年にパリに送り、ドイツ・ポツダムで育種業をしているロバート・ブロスフェルド(Robert Blossfeld 1882–1945)によってハイブリッドされ、1932年に室内植物のカランコエ(=Kalanchoe blossfeldiana)として売り出された。日本でも第二次世界大戦前に導入されたという。
学名のカランコエ・ブロスフェルディアーナ(Kalanchoe blossfeldiana Poelln.(1934))は、ドイツの多肉植物の権威、ポエニーズ(Karl von Poellnitz 1896‐1945)によって1934年に命名された。
リンネの二命名法では、属名+種小名で生物の名前を付けるが、種小名のブロスフェルディアーナ(blossfeldiana)は、カランコエのハイブリッドを開発したRobert Blossfeldを記念してつけられた。
一方、属名のカランコエ(Kalanchoe)は、中国語の“落ちて育つもの”という意味の「加籃菜」( jia lan cai )の音読みによるという説がある。
何故かというと、カランコエの仲間は、葉の鋸歯部分に生長点を持っているので葉が脱落すると、ここから発芽し新しい個体になるのでこの特長をさしている。
最近の言葉ではこれを「ハカラメ(葉から芽)」と呼び、葉を水に浮かべて沢山の芽を出させるので「マザーリーフ」とも言っているようだ。
まるでこのような名前の展開は、赤提灯の定番ホルモン焼きのホルモンの語源の一つである、「大阪弁で捨てる物にあたる“放るもん”」に良く似ている。
本題に戻ると、この属名をつけたのはフランスの植物学者でリンネに対抗する植物の分類体系を発表したMichel Adanson(1727-1806)で、1763年に命名されたというから二名法初期の頃だった。
ところで多少気になることがあったが、ドイツの学名命名者ポエニーズ(Karl von Poellnitz 1896‐1945)とカランコエの園芸品種の作出者で学名の種小名に名を残すブロスフェルド(Robert Blossfeld 1882–1945)は、二人とも1945年に死亡している。
ブロスフェルドは確認できなかったが、ポエニーズは彼の家族とともに連合国の爆撃の犠牲となった。戦争というものはこのような現実をいくつも作って来たということに気づかされてしまった。
(写真)カランコエ・ブロスフェルディアーナの花

カランコエ(Kalanchoe blossfeldiana)
・ベンケイソウ科カランコエ属の小さい潅木のような多年草。
・原産地:アフリカ東側のインド洋にあるマダガスカルが原産地。
・学名:カランコエ・ブロスフェルディアーナ(Kalanchoe blossfeldiana Poelln.(1934))は、ドイツの多肉植物の権威、ポエニーズ(Karl von Poellnitz 1896‐1945)によって1934年に命名された。
・英名でのコモンネームは、flaming Katy,Christmas kalanchoe,florist kalanchoe等で、日本でカランコエの名で最も多く流通しているのは,マダガスカル北部のツァラタナナ山脈に生育するKalanchoe blossfeldianaの園芸品種である。
・草丈15-80cmの低木で、多肉質の葉を持つ多年草。
・短日植物である。つまり、連続した暗期(夜)が一定時間より長くなると花芽が形成される植物なので、この性質を使い花を開花させる時期をコントロールすることが出来るので1年中販売されている鉢物になっている。
・花弁は5枚でやや反り返っていて星の形に開花する。開花時期は秋から春。花色は、白、黄色、ピンク、オレンジ等豊富。クリスマス、バレンタイン、ホワイトデーなどのイベントでのギフトとしても重宝。
・耐寒性はあまりなく12~15℃の温度で育てる。冬も5℃以上に保つ。
・多湿を嫌い、排水のよい用土に植え,日当りのよい場所で育てる。
・繁殖は挿木によって行われる。