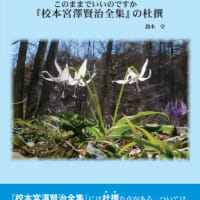”羅須地人協会について(その1)”の続きである。
では、ここは下根子桜の
《1 宮沢賢治詩碑入り口》(平成20年12月11日撮影)

である。
この道を真っ直ぐ進むと
《2 ギンドロの木と井戸》(平成20年12月15日撮影)

見えてくる。
そこまで行くと目の前が開けて
《3 『雨ニモマケズ詩碑』の標石》(平成20年12月11日撮影)

が立ててあり、その
《4 説明プレート》(平成20年12月11日撮影)

には
大正15年(1926)3月、花巻農学校を30歳で退職した賢治は、宮沢家別宅で独居自炊しながら、羅須地人協会を設立して理想の実現にいどんだ。ここがゆかりの場所である。
この詩碑は、没後3年目の昭和11年(1936)に教え子たちをはじめ多くの方々の協力によって建てられた。石巻産稲井石の碑面には高村光太郎の揮毫で「雨ニモマケズ」の後半が刻まれている。さらに昭和21年(1946)に追コクの文字を、光太郎自らが碑面に書き込み完成した。
賢治詩碑の第1号であり、碑の下には遺骨と経文が納められている。
と記されている。
《5 『雨ニモマケズ詩碑』》(平成20年12月11日撮影)

《6 碑前の広場》(平成20年12月11日撮影)

毎年9月21日、この広場で『賢治祭』が行われている。
そしてこの度、『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)により、この場所に宮沢家の別宅(羅須地人協会の建物)が次のような配置で建てられていたことが分かった。
《7 詩碑付近略図》(平成20年12月11日撮影)

<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)より>
もちろんいまは羅須地人協会の建物はここにないが、広場の端の
《8 説明板》(平成20年12月11日撮影)

の中に
《9 羅須地人協会の建物》(平成20年12月11日撮影)

の写真がある。
《10 建物部分を拡大》(平成20年12月11日撮影)

つまり、これがかつての宮沢家別宅である。
『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)によれば
私は序説で、豊沢町の宮沢家の別宅と書いたが、この地方では昔「田屋」と呼んでいたものとのこと。元来、豊沢町の宮沢家の始祖で賢治の祖父喜助の病気療養のために建てたもので、一時は賢治の妹年の病室にもなっていたという。賢治も亦、この家でやがて病気になったのである。父政次郎翁は引続いて三人の病舎になったので、この家を他に譲ってしまった。買った人はほぼ原形で移転したが、たまたま賢治在職中に新築された花巻農学校の後身花巻農業高等学校が、花巻空港に近い現在地に移転新築された時、その敷地に隣接した所にあったのを、同窓会の手で譲り受け、現状に復元したのであるとのことである。 それは、「小サナ萱ブキノ小屋」ではなく柿葺木造二階建ての普通の家で、階下に二間・階上一間あり、二階と下の一間の八畳の座敷には押入と床の間がついており、玄関・風呂場・便所もあり、下の八畳は三方をめぐって長い板廊下になっていた。炊事場は北裏の井戸端から一段低い所に別棟になっていたが、賢治は風呂をたてず、ここで水浴していたとのことである。
と記されている。
因みに、
《10 北裏の井戸端の一段低い所周辺》(平成20年12月11日撮影)

《11 一段低い所》(平成20年12月11日撮影)

がここであり、別棟(炊事場等)がここにあったことになる。
さて、気になるのは『おくら』のことである。『詩碑付近略図』にはこの『おくら』は記載されていないから別棟のことだったのだろうか。
そこで、まずは『おくら』をもう一度確認した上で、近々花巻農業高等学校を訪ねてみたい。
なお、『おくら』を見に行く前に、いままでに報告していなかった
《12 『農民芸術概論網要より』の木標》(平成20年12月11日撮影)

を報告する。かなり文字は薄れてしまっていて
風とゆききし雲からエネルギーをとれ
の一部がかろうじて読み取れる。以前にはもう一本の木標があったはずだが現在は見あたらなくなっている。
では、次は『おくら』へ行ってみよう。宮沢賢治詩碑入り口に戻ると茅葺きの
《13 同心屋敷》(平成20年12月15日撮影)

が見えるはずである。なお、写真の右端の白い標識は『弥助橋跡』のものである。
同心屋敷の前の駐車場の『新奥の細道』
《14 コース案内図》(平成20年12月15日撮影)

の現在地、赤丸付近が『おくら』のある場所である。
具体的にはこの案内図の逆方向の
《15 同心屋敷側》(平成20年12月15日撮影)

方向を見わたせば、写真の右奥のような小屋が見つかるはずである。つまり、
《16 これが『おくら』》(平成20年12月15日撮影)

《17 〃 》(平成20年12月11日撮影)

である。
『おくら』の側の説明柱には
この「おくら」は「羅須地人協会」が桜の地にあった頃、その庭にあった建物である。
1936(昭和十一)年十一月、羅須地人協会が宮野目に移築される時、これを譲りうけた近所の一青年(投稿者註*)のもとに、ひそかに保存されていた。最近その経緯が明らかになったことから、地元の有志が相はかり、羅須地人協会ゆかりの建物としてここに移築、一部手を加え復元した。
羅須地人協会で、賢治の教えを受けていた地元の青年たちは、当時この建物を「おくら」と呼んでいたという。
呼び名の由来は賢治が名付けたものと言われている。「おくら」は、肥料や農具などを入れておく物置と厠を兼ねていた。
とある。
<*:この青年とは高橋慶吾のことであり、彼はこの「おくら」を看板にあるように『宮澤賢治遺墨の店』として経営したいたようだ。>
《18 〃 》(平成20年12月11日撮影)

《19 〃 》(平成20年12月11日撮影)

《20 〃の屋根》(平成20年12月11日撮影)

では近々花巻農業高等学校へ行ってみることにしよう。
続きの
 ”羅須地人協会について(その3)”のTOPへ移る。
”羅須地人協会について(その3)”のTOPへ移る。
前の
 ”羅須地人協会について(その1)”のTOPに戻る。
”羅須地人協会について(その1)”のTOPに戻る。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。
では、ここは下根子桜の
《1 宮沢賢治詩碑入り口》(平成20年12月11日撮影)

である。
この道を真っ直ぐ進むと
《2 ギンドロの木と井戸》(平成20年12月15日撮影)

見えてくる。
そこまで行くと目の前が開けて
《3 『雨ニモマケズ詩碑』の標石》(平成20年12月11日撮影)

が立ててあり、その
《4 説明プレート》(平成20年12月11日撮影)

には
大正15年(1926)3月、花巻農学校を30歳で退職した賢治は、宮沢家別宅で独居自炊しながら、羅須地人協会を設立して理想の実現にいどんだ。ここがゆかりの場所である。
この詩碑は、没後3年目の昭和11年(1936)に教え子たちをはじめ多くの方々の協力によって建てられた。石巻産稲井石の碑面には高村光太郎の揮毫で「雨ニモマケズ」の後半が刻まれている。さらに昭和21年(1946)に追コクの文字を、光太郎自らが碑面に書き込み完成した。
賢治詩碑の第1号であり、碑の下には遺骨と経文が納められている。
と記されている。
《5 『雨ニモマケズ詩碑』》(平成20年12月11日撮影)

《6 碑前の広場》(平成20年12月11日撮影)

毎年9月21日、この広場で『賢治祭』が行われている。
そしてこの度、『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)により、この場所に宮沢家の別宅(羅須地人協会の建物)が次のような配置で建てられていたことが分かった。
《7 詩碑付近略図》(平成20年12月11日撮影)

<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)より>
もちろんいまは羅須地人協会の建物はここにないが、広場の端の
《8 説明板》(平成20年12月11日撮影)

の中に
《9 羅須地人協会の建物》(平成20年12月11日撮影)

の写真がある。
《10 建物部分を拡大》(平成20年12月11日撮影)

つまり、これがかつての宮沢家別宅である。
『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)によれば
私は序説で、豊沢町の宮沢家の別宅と書いたが、この地方では昔「田屋」と呼んでいたものとのこと。元来、豊沢町の宮沢家の始祖で賢治の祖父喜助の病気療養のために建てたもので、一時は賢治の妹年の病室にもなっていたという。賢治も亦、この家でやがて病気になったのである。父政次郎翁は引続いて三人の病舎になったので、この家を他に譲ってしまった。買った人はほぼ原形で移転したが、たまたま賢治在職中に新築された花巻農学校の後身花巻農業高等学校が、花巻空港に近い現在地に移転新築された時、その敷地に隣接した所にあったのを、同窓会の手で譲り受け、現状に復元したのであるとのことである。 それは、「小サナ萱ブキノ小屋」ではなく柿葺木造二階建ての普通の家で、階下に二間・階上一間あり、二階と下の一間の八畳の座敷には押入と床の間がついており、玄関・風呂場・便所もあり、下の八畳は三方をめぐって長い板廊下になっていた。炊事場は北裏の井戸端から一段低い所に別棟になっていたが、賢治は風呂をたてず、ここで水浴していたとのことである。
と記されている。
因みに、
《10 北裏の井戸端の一段低い所周辺》(平成20年12月11日撮影)

《11 一段低い所》(平成20年12月11日撮影)

がここであり、別棟(炊事場等)がここにあったことになる。
さて、気になるのは『おくら』のことである。『詩碑付近略図』にはこの『おくら』は記載されていないから別棟のことだったのだろうか。
そこで、まずは『おくら』をもう一度確認した上で、近々花巻農業高等学校を訪ねてみたい。
なお、『おくら』を見に行く前に、いままでに報告していなかった
《12 『農民芸術概論網要より』の木標》(平成20年12月11日撮影)

を報告する。かなり文字は薄れてしまっていて
風とゆききし雲からエネルギーをとれ
の一部がかろうじて読み取れる。以前にはもう一本の木標があったはずだが現在は見あたらなくなっている。
では、次は『おくら』へ行ってみよう。宮沢賢治詩碑入り口に戻ると茅葺きの
《13 同心屋敷》(平成20年12月15日撮影)

が見えるはずである。なお、写真の右端の白い標識は『弥助橋跡』のものである。
同心屋敷の前の駐車場の『新奥の細道』
《14 コース案内図》(平成20年12月15日撮影)

の現在地、赤丸付近が『おくら』のある場所である。
具体的にはこの案内図の逆方向の
《15 同心屋敷側》(平成20年12月15日撮影)

方向を見わたせば、写真の右奥のような小屋が見つかるはずである。つまり、
《16 これが『おくら』》(平成20年12月15日撮影)

《17 〃 》(平成20年12月11日撮影)

である。
『おくら』の側の説明柱には
この「おくら」は「羅須地人協会」が桜の地にあった頃、その庭にあった建物である。
1936(昭和十一)年十一月、羅須地人協会が宮野目に移築される時、これを譲りうけた近所の一青年(投稿者註*)のもとに、ひそかに保存されていた。最近その経緯が明らかになったことから、地元の有志が相はかり、羅須地人協会ゆかりの建物としてここに移築、一部手を加え復元した。
羅須地人協会で、賢治の教えを受けていた地元の青年たちは、当時この建物を「おくら」と呼んでいたという。
呼び名の由来は賢治が名付けたものと言われている。「おくら」は、肥料や農具などを入れておく物置と厠を兼ねていた。
とある。
<*:この青年とは高橋慶吾のことであり、彼はこの「おくら」を看板にあるように『宮澤賢治遺墨の店』として経営したいたようだ。>
《18 〃 》(平成20年12月11日撮影)

《19 〃 》(平成20年12月11日撮影)

《20 〃の屋根》(平成20年12月11日撮影)

では近々花巻農業高等学校へ行ってみることにしよう。
続きの
 ”羅須地人協会について(その3)”のTOPへ移る。
”羅須地人協会について(その3)”のTOPへ移る。前の
 ”羅須地人協会について(その1)”のTOPに戻る。
”羅須地人協会について(その1)”のTOPに戻る。
”みちのくの山野草”のトップに戻る。