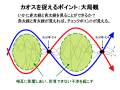トヨタのリコール問題について、公聴会が開かれ、社会の耳目を集めています。この報道を見ていると、訴訟大国とも言われるアメリカの限界を感じるとともに、同国の行く末も見えるような気がしてきます。
今回の一連の流れの中で、トヨタに非がないとは言いません。顧客の声を真摯に受け止めず、問題と向き合ってこなかった姿勢は、厳に反省を求めるべきでしょうし、またそれは至極、理に叶っているものだと思います。ただ、今回の公聴会の議論には、そうしたトヨタの隙を突いて、過度な言いがかりをつけている可能性も否定できず、それは偏に今日のアメリカ社会の限界であるかもしれないと思うのです。
公聴会の最初の証人、ロンダ・スミスさんの証言は非常に興味深いです。
============================
2006年10月、新車の「レクサスES350」を運転中、高速道路に合流したところで、アクセルの制御が利かなくなった。ギアをニュートラルやバックに変えたり、両足でブレーキを踏みながらハンドブレーキを使ったりしたが、車は時速160キロまで加速を続けた。
============================
この証言から、当初、アクセルの不具合はフロアマット等の物理的要因と言われていましたが、電子制御部分の問題である可能性が指摘されているわけです。これに対して、トヨタ側はその可能性を否定し続けています。こうした問題について、断定することは極めて難しいですが、私の感覚として、指摘されているような電子制御系の問題であるとするならば、これは自動車が自動車として成り立たなくなるほどの極めて重大な欠陥であろうと思います。ブレーキ、それもハンドブレーキやミッションも効かないというのは、自動車の基本的な機能障害と言わざるを得ません。
要はアクセルを踏まず、一方でブレーキを踏んでも、ミッションを切り替えても、勝手に走ってしまうのですから、もうどうすることもできないわけです。ほとんど自動車が勝手に動き出す、SF映画の世界に近い状態です。これについて、トヨタはいろいろな調査をしており、電子制御には問題ないと言っていますが、それは当り前でしょう。なぜなら、そんなことが本当にあり得るのであれば、もっといろいろなところで(SF映画でロボットが人間に反乱を起こすように)自動車が暴走しているはずです。同型車種が、どれくらい出回っているのか分かりませんが、少なくともトヨタが作っている大量の車が走っている中で、(単なるアクセルが戻らないというレベルではない)そんな暴走車両の事例がろくに報告されていないのに、その証言をそのまま信じろというのは、いささか無理がある話です。この無理な話を円滑に説明しようとなると、二つの可能性に絞られます。それは、それだけあり得ないことが証言者であるロンダ・スミスさんの車に起こったか、あるいはロンダ・スミスさんが偽証しているかのどちらかということです。
この公聴会は、そうした可能性があるにもかかわらず、証人の発言に対する信憑性を見極める機能が不十分で、かつその証人に「恥を知れ」等という一方的な罵声を許すという極めて歪な仕組みであると言わざるを得ません。
私なりに、ここには訴訟大国とも言われるアメリカの事情が、深く関わっているのだろうと考えます。そして、そのことから今後のアメリカという国の衰退への道筋も見えてくるではないかとも思っています。
以下、ロンダ・スミスさんが偽証しているという可能性に絞って、訴訟大国アメリカの限界について考察してみたいと思います。
今回のトヨタの件もそうですが、消費者が企業等を相手取って行なう集団訴訟というものがあります。これについての詳述は避けますが、要は、企業の商品やサービスに問題があった場合、消費者が企業を相手取って多額の損害賠償を求められるのです。この方式自体、善良な消費者を守るためという目的で、きちんと作用していれば、特段、問題が認められるものではないでしょう。むしろ消費者を守るための社会システムとして、有効なものであると考えるべきだと思います。しかし、実情を見ると、金銭目的で訴訟を起こすような人々がいたり、日本に比べて大量に存在する弁護士を食わすためのシステムとして機能しているような側面を否定できないのも事実です。
もちろん、広義における集団訴訟自体は、アメリカ特有のものではなく、またそれは単にそうしたネガティブな側面があるというだけなので、それで事の善悪が決するわけではありません。ただし、今回の公聴会に登場しているロンダ・スミスさんのケースを含めて考えた時、その原告となり得る人々の言い分、立ち振る舞いを想像しないわけにはいかないのです。
即ち、アメリカで事業を行なう場合には、そうした消費者たちによる集団訴訟リスクをどのように考えるかということが、非常に大きな課題であろうということです。逆の言い方をすると、そうした事業リスクを抱えるような国において、真剣に事業を展開しようとする企業は、今後、減っていくかもしれないということです。順調に事業がうまくいっているかと思ったら、言いがかりのような理由から高額の賠償金を支払わされるようでは、たまったものではありません。これは企業にとってのマイナス以上に、世界の企業が撤退してしまうアメリカという国にとってのネガティブインパクトにもなるでしょう。そして、私なりには、こうした状況が続くようなら、その流れは間違いなく顕在化し、結果として、アメリカという国にとって非常に大きな打撃になるだろうと思います。
別に、アメリカという国が嫌いなわけではありません。むしろ、これまでアメリカという国が、世界をリードしてきたことについて、素直に敬意を表したいと思います。ただし、今回のトヨタリコール問題を巡る一連の議論から、訴訟大国とも言われるアメリカの限界について、ちょっと考えてみたのでした。
《おまけ》
アメリカという国の流儀に沿って、同地にて事業を展開し、それによって収益を得てきた企業については、上記のようなリスクと向き合って然るべきだろうと考えます。そういう意味で、今回のトヨタの件、特段、同情したり肩を持ったりというつもりはありません。トヨタという会社がアメリカという国のおかげで、これまで享受できた恩恵を考えれば、今回の件でのダメージは、それほど大きなものではないとも言えます。ただし、「どこで事業を展開するか」ということは、それだけ慎重に考えなければならないということは間違いないでしょう。例えば、今日、「中国が成長市場」等と言って、次々と中国に進出していく企業がありますが、それらには必ずリスクがあるということも重要です。それをきちんと認識せず、不用意に他国に出ていくということは、後々、相応の代償を払わなければならなくなるかもしれない点、注意を払う必要があるだろうと考えます。