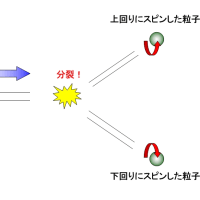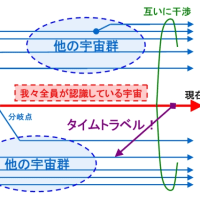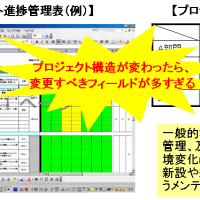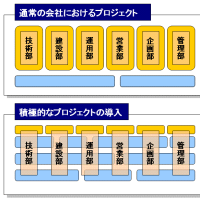『日本の戦後補償問題』、1996年執筆
1990年8月、サハリン残留韓国人の問題について、残留者と韓国の留守家族21人が、日本政府に対して一人1000万円の支払い要求をおこなった。1991年1月には大阪で、日本軍の軍属として爆撃で負傷した韓国人が援護法の受給資格の確認と1000万円の支払いを要求した。同年12月には、元挑戦人慰安婦が東京地裁に提訴した。このほかにも、韓国からの日本政府に対する補償要求は多数なされている。日本政府の基本的な立場は、韓国との戦後補償問題は1965年の日韓基本条約、「財産及び請求権・経済協力協定」によって解決されたというものである。
にもかかわらず、韓国側からこのような訴えが頻発するひとつの理由として、韓国政府が当時、日韓条約締結に際し大きな譲歩をしすぎたためという指摘がされうる。
李庭植氏は、過去の行為に対する日本側の謝罪は日韓条約の文書に盛り込まれることはなく、韓国に提供されたのは、日本の寛大さのしるしとしての経済援助であった。大韓民国憲法は「大韓民国の領土は韓半島とその付属島嶼とする」と規定していたにもかかわらず、条約は韓国の管轄権を南朝鮮に限定するなど、韓国はあらゆる問題で譲歩したと主張する(59)。たしかに、当初韓国側が提示した資金提供額が20億ドルであったにもかかわらず、最終的に「無償提供3億ドル、長期低利借款2億ドル、民間信用提供3億ドル」で決着するという結末をみたのは、韓国政府の譲歩によるところが大きいだろう。
しかし一方で、当時の韓国にそれだけの譲歩をせざるをえない理由が存在したこともまた事実である。韓国側の譲歩は、日本の一方的な交渉戦略によって引き出されたものではないのである。1961年のクーデター以降、政権を握ることになった朴正熙率いる軍事政権は経済発展を最優先課題としており、これを自らの正統性の根拠とし維持し続けようとしていた。そのために彼らが必要としていたのは、ほかでもない海外からの経済援助だったのであり、1950年代後半までは、そのなかでもとくにアメリカの果たす役割が大きかった。
アメリカの援助額は、1954年の1億840万ドルから着実に増加し続け、1957年にはついに3億6880万ドルにまで達した。だが1959年になると、その額は2億1970万ドルと現象傾向をみせはじめ、1962年にはついに1億5千万ドルにまで落ち込んだ。5ヵ年計画を継続して推進していきたい韓国にとっては、この落ち込みは深刻で、経済危機を醸成しかねなかった。その代替的な役割を期待されるようになったのがまさに日本であった。加えてアメリカの強い介入政策に直面した韓国政権は、日本側の従来の交渉ペースを基本的に承認することを余儀なくされたのである(60)。
そのような韓国の対日政策の変化は、1953年の第三次会談における久保田主席代表の発言と、64年の高杉晋一の発言に対する反応の違いによっても説明することができる。
1953年10月15日の請求権分科委員会の席上、久保田主席は「日本が進出しなかったら韓国は、中国もしくはロシアに占領され、日本による占領よりもはるかに惨めな経験をしたであろう」、「韓国を日本との事前協議なしに日本から分離、独立させた措置は国際違反である」などの発言をおこない、韓国を激怒させた。この結果、20日に会談は決裂し、1957年の発言取消まで、韓国の強硬な撤回要求が継続しておこなわれ、日韓会談は3年半あまりの中断を余儀なくされた。
その久保田発言のほぼ10年後の1964年、今度は高杉晋一が「日本は朝鮮をより豊かにするために支配した」、「引き続き日本が20年くらい支配していたらよかった」という主旨の発言をおこない、またもや韓国を激怒させた。
前例に従えば、当然これに対して韓国は猛抗議をし、会談は中断されたであろう。しかし韓国がとった選択は、その発言をいかに無効力化するかであった。韓国側は発言当時、高杉があくまで主席代表の内定者であり公的立場ではないことや、発言の場が会談の席上ではなく、外務省担当記者との会見という私席であったことに注目し、それを利用して物議の拡大を阻止したのである(61)。
それはほかでもない、当時の韓国経済の状況を含んだ両国をとりまく環境のなかで、朴正熙が下した決断でもある「先国交・後懸案妥結」(62)という韓国側の基本方針のあらわれでもあった。
日韓基本条約が締結された1960年代は、韓国にとっては経済開発の資金確保と、そのための日本との国交回復が最優先課題となっており、このことは日本にとっても、韓国との請求権問題を片づけるには絶好の条件をもたらした。しかし一方で、それがゆえに本条約では解決されない問題が残されることになり、しばしばそれが表舞台に上がり、両国間のきしみを生むようになった。過去の歴史認識をめぐる両国の溝については、当時の条約の文言のすりあわせによって問題の妥結をはかったが、両国の共通認識の確立といったような根本的解決はなされなかった。
1995年10月5日の「日韓併合条約は法的に有効に締結された」という村山首相の発言に対し、27日、韓国の国会議員100余名が基本条約破棄を要求する決議案を国会に提出した。決議案では、日韓基本条約は「日本が太平洋戦争を挑発した責任と韓半島を不法的、強圧的に植民地化し、残忍な方法で支配した責任をきちんと問わないまま免罪符を与えた韓国の屈辱外交の標本であり、日本の過去の罪悪を生産した免罪符として働いてきた」と指摘したうえで、新しい条約案を提示している。新しい条約には「日本が犯した侵略と過酷な植民地支配に対する謝罪と反省の意を明らかにする」、「1910年に結んだ日韓併合条約は締結当初から無効だったことを確認する」、「基本条約とともに結んだ諸協定も韓国政府が主張すべき権利が放棄されたままになっているので放棄し、再協議して新協定を結ぶ」などの内容を盛り込むべきであるとしている(63)。
日本の過去認識に対して、韓国の国民感情レベルでこのような議論が展開されるといのは、そう理解に難しくない。自分の国が他国によって植民地支配を受けていたという歴史を、やすやすと受け入れることができないという国民感情の次元では、「解釈に幅のある現条約を破棄したい」、「新しい条約をつくりたい」といった考え方が十分に生まれうる。
しかし、このような論理をもってして、国家間の条約破棄が可能であるならば、元来、国際社会に条約など存在しないことになる。それゆえに当然のことながら、韓国政府は、議員たちのこのような動きに対して冷静な対応をとってきた。
ところで、この決議案は新条約の締結とならんで、当時基本条約とともに締結された諸協定の破棄と、それに代わる新協定の締結も提案している。もちろんここでいう協定には、日韓の請求権問題の解決を目的とした「財産及び請求権・経済協力に関する協定」も含まれている。
1961年4月6日の第5次日韓会談の席上、韓国の対日請求権について吉田委員は「韓国は日本に対する交戦国でも平和条約の署名国でもなく、同条約の第14条の利益を受ける立場にはない」として、韓国側の賠償請求権を否定した(64)。
また韓国側も、日韓会談開始当初から1945年12月の米軍政法政33号32条「日本国および日本人の在韓財産は米軍政庁に帰属する」と、1948年に発効したアメリカ・韓国間の「財政および財産に関する最初の協定」を根拠に、日本の在韓財産はすでに韓国に引き渡されるべきものであると主張してきた。こうした財産処理の手順は、サンフランシスコ平和条約4条b項「日本は韓国などの地域でアメリカによって、あるいはその指令によって施行されたに日本および日本国民の財産処理効力を承認する」で明確に規定されていた(65)。つまり日韓会談時における韓国側の請求は、サンフランシスコ平和条約第14条にもとづく「賠償」要求ではなく、平和条約第4条にもとづく「返還」要求だったのである。
金明基・明知大法政学長は「『請求権協定』は『対日平和条約』の規定中、韓国側が日本側に対し効力がある、同条約第4条に依拠し締結されたものであり、韓国に対して効力が及ばない第14条に依拠して締結されたものではない。「請求権協定」上の請求権は補償請求権を意味するものであり、賠償請求権はこれに含まれているものではない」とし、韓国の対日賠償請求権を主張している(66)。事実、日韓会談の開始当初から、韓国の平和条約4条にもとづく請求権は認められても、14条の請求権についてはまったく認められていなかった。度々同協定が示す「請求権」の定義づけが問題としてとりあげられるが、その議論のなかに、この14条に依拠した賠償請求権を持ち込むことはできないのである。
しかしもし仮に、今回提出された決議案がいう「韓国政府が主張すべき放棄された権利」が平和条約14条にもとづくものであるとするならば、「戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して」連合国が有する請求権を、韓国がもつというその主張の妥当性がまず証明されなければならない。
また、李長熙・韓国外大教授は「韓日基本条約と請求権協定は、財産的価値侵害に対する国際民事責任を規定したものであり、人権侵害に対する損害賠償責任と、国際犯罪行為に対する刑事責任は、相変わらず有効であるというのが国際法上の解釈だ」と指摘する(67)。しかし国際法上の人権侵害に対する損害賠償責任や、国際犯罪に対する刑事責任とはいったい具体的に何を指しているのか、また何を根拠にしているのかが問題である。先述の通りドイツ・ナチズムを例にとって、国際法上解釈とし、日本の責任を追及できないことは明白である。日韓条約で解決されなかった韓国に対する日本の責任を問うのであれば、その根拠を固める別の論法が必要である。ただ、人権侵害に対する損害賠償責任については、国内法的な観点からの議論の余地があると思われるので、後述したいと思う。
いずれにせよ、「財産及び請求権・経済協力に関する協定」は「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)項に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認」したものとして依然有効なのである。たとえ上述のような日本の対韓責任が新たに証明されたとしても、日韓政府間の請求権問題はすでに決着しているのであるから、同協定を破棄するなどということは到底許されるものではない。
だが、また一方で日本政府は、1991年8月の参議院予算委員会で、財産及び請求権・経済協力協定について「日韓両国が国家として持っている外交保護権を相互に放棄したということで、個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。両国間で外交保護権の講師として取り上げることはできないという意味だ」という主旨の答弁をおこなった。これは日韓慮国政府間の請求権交渉はすでに終了しているが、日本の司法機関を通じた日本国政府に対する韓国国民個人の請求権については認めたというものである。1992年1月に訪韓した宮沢首相は、元従軍慰安婦個人への補償について「日本国内で訴訟が継続中であり、その行方を見守っている」と述べている。
1965年の日韓基本条約と各種協定の締結は、日本の対韓補償全般において以上のような意味をもつ。ただし日本の対韓補償は、その対象項目によっていくつかの分類が可能であり、また必要であると考えられる。そこで以下、いくつかの日本の具体的な対韓補償項目をあげ、そのひとつひとつについて検討していきたいと思う。
| 2.5 ドイツとの比較 << | >> 3.2 旧軍人・軍属への補償 |