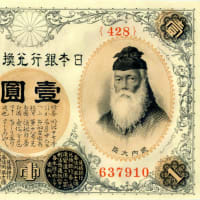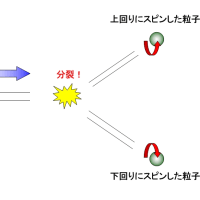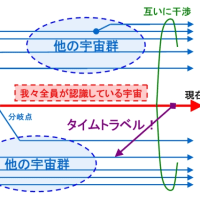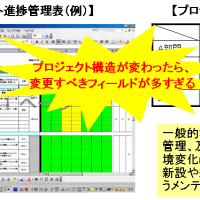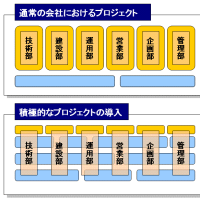『日本の戦後補償問題』、1996年執筆
1994年10月24日、衆議院税制特別委員会において橋本通産大臣は「先の戦争は、西欧列強との戦争であったが、アジアの人々には多大な迷惑をかけた」という主旨の発言をおこなった。この発言は十五年戦争を、対米英蘭の戦争と、対アジアの戦争とに分ける二元認識にもとづいてなされた発言である(39)。
戦争の二元認識とは、事実上一体化している戦争について、論理上は区別されなければならないとし、それを対米英蘭と対アジアに分離させ認識しようとするものである。
たとえば竹内好氏は十五年戦争について、「日本が行った戦争は侵略戦争であったが、同時に帝国主義対帝国主義の戦争でもあり、侵略戦争の側面に関しては日本に責任があるが、対帝国主義戦争の側面に関しては日本だけが一方的に責任を負ういわれはない」と主張しているが、これがまさに二元認識にもとづいた十五年戦争に対する評価であるといえる(40)。
しかし、このようのあ戦争の二元認識論に対しては、米英蘭に対する戦争も、結局は中国という在外権益防衛のための戦争であって、自衛のための戦争ではなかったという反論がある(41)。1941年11月26日、米国務長官ハルが野村大使に交付した通牒(ハル・ノート)が提示した主な条件は、中国とインドネシアからの日本軍の撤退、蒋介石政権以外の中国政府の不承認などであり、これを受け入れることなく開戦に踏み切ったのであるから、自存自衛のための戦争とは到底いえないというのがその論拠である。つまり、日本は中国侵略戦争を継続するために、これを中止させようとする米英蘭と開戦することになったのであって、対帝国主義との戦争は、中国侵略戦争の延長線上に発生した。したがって中国との戦争と対米英蘭戦争とを分離して、個別の戦争と考えることは到底できないというのである(42)。
中西功氏は、戦争を通じての日本の目的は、日本にとってのアジア太平洋地域の安定であり、対アジアの戦争も、対米英蘭の戦争もその目的のため遂行されたものである。にもかかわらず、戦う相手によって、日本の責任を多元的に規定するのは誤りであると主張する(43)。
しかし、そうであるならば日本と併せて、米英蘭の責任も同時に追及されなければならない。当時、米英蘭もフィリピン、マレーシア、インドネシアなどを植民地支配していたが、それを留保したもまの、日本に対する一方的な中国撤退要求は、問題解決の方策としてあまりにも非現実的である。ハルはのちに「日本がこの提案(ハル・ノート)を受諾するだろうと本気で考えていなかった」と語っている(44)。しかし日本と同様に米英蘭にも、アジア太平洋地域における平和的解決への道が真剣に模索されていなかった点は非難されなければならない。それはけっして「彼もやっているから、自分は悪くない」という論理なのではなく、同じ帝国主義としてアジアに植民地を有していた米英蘭、その意味では「同類の彼ら」に対して負うべき責任はないという主張である。
だがアジア地域に対する日本の行為の性格は、根本的に米英蘭に対するものと異なる。それは日本がアジア各国に対しては、侵略をしたという認識によるのであるが、この「侵略」の意味についても微妙な問題が含まれている。
1993年8月10日、細川首相は首相官邸で行われた就任初めての記者会見で、「先の戦争をどう認識しているか」という記者の質問に対し「私自身は、侵略戦争であった。間違った戦争であったと認識している」と答えた。しかし、この首相の発言は、政府部内で準備されたものではなく、「侵略戦争」についての厳密な定義をふまえたわけでもなかったようだ(45)。
その後、8月19日の閣僚懇談会では、「国家間の補償問題はすでに決着済み」であることが確認され(46)、23日の所信表明演説には「侵略戦争」という言葉は使われず、「過去の我が国の侵略行為や植民地支配などが多くの人々に耐えがたい苦しみと悲しみをもたらした」という表現が使われた。
その後も、政府の基本的立場は変わっていない。1994年5月24日の衆議院予算委員会で羽田首相は、「戦争についてはいろんな議論がある」と述べ、先の戦争を「侵略戦争」と位置付ける考えはないことを強調した(47)。
この羽田首相の発言に対して、志位議員は「なぜ『侵略戦争』と言えないのか」とただした上で、「『侵略行為』はここの軍隊に出先で間違いがあった、と言い抜けもできる。『侵略戦争』は全体の性格、目的を指す」と追及した。
だがこの問題に関しては、いまだ国内のコンセンサスも得られておらず、94年10月の「侵略戦争であるかどうかは、いろいろな意見があるから、そういう意見の混乱の中に私は巻き込まれたくない」という村山首相の発言は問題の微妙さをよく表しているといえる。
過去において日本がアジアにおこなった行為が「侵略行為」であったのか「侵略戦争」であったのかの議論はあるにせよ、しかし過去にアジアに対して侵略をおこなったということに関しては、日本政府も認めるところであるというのは間違いない。
しかし侵略によって、日本の戦争責任を問えるのかの問題も存在する。侵略(aggression)という用語は、第一次大戦終結間際に賠償問題にはじめて導入された。ドイツが負うべき賠償責任は、進入(invasion)ではなく侵略(aggression)によるものであり、侵略によって連合国の民間人及びその財産に与えられた損害に対して、ドイツは賠償すべきであるとされたのである(48)。だが実際に、侵略の定義がなされたのは、第二次大戦後であった。1974年、「侵略の定義」に関する国連総会決議がなされ、侵略は武力による威嚇及び武力の行使として一般国際法化された。「侵略行為」の認定についても、国連憲章39条によって安保理の裁量に委ねられているのである。こうした戦後社会に誕生した概念である「侵略」を、日本の戦争責任の根拠とするのが、適当かどうかの疑問はたしかに提起されうる。
しかし家永三郎氏は、具体的な日本の中国に対する行為として、南京大虐殺、中国全戦線にわたる残虐行為、毒ガス戦、七三一部隊の残虐行為、阿片密貿易による日本の巨利獲得と中国人民の心身腐蝕、中国官民の利用などをあげ、これらに日本の戦争責任があると指摘する(49)。さらに家永氏は、日本の殖民としてその主権の下に置かれていた朝鮮民族に対する罪として、精神面での強要と人身を提供しての犠牲の強要との二つに大別して論じている。前者は学校での朝鮮語の使用禁止や創氏改名をはじめとする「皇民化政策」によるものであり、後者としては、強制連行や朝鮮人BC級戦犯、従軍慰安婦問題などがそれにあたるとしている(50)。
たとえ当時、「侵略」の定義が確立していなくても、今日の法論理に照らせば日本のその行為はやはり「侵略」であった。そしてそれは、アジア地域の人々に苦痛を与えたのであって、日本はその事実を率直に認めなければならない。それが当時の異常状態のもとでなされた行為であった、あるいは他の戦争・地域にもみられる悲劇であったというのは免責の理由にはならないし、もちろん正当化する理由にもなりえない。ただ実際に、そうした行為に対する償いとして、どのように責任がとられるべきかについては、その行為内容がどのようなものであるかの考察がなされなければならないし、また同時にこれまでどのような償いがなされてきたのかの検証もなされなければならない。そうした手順を踏んで、はじめてこの問題に対する今後の「戦後補償」のあり方を論じることができるのである。
| 2.3 日本の政治家による「妄言」 << | >> 2.5 ドイツとの比較 |