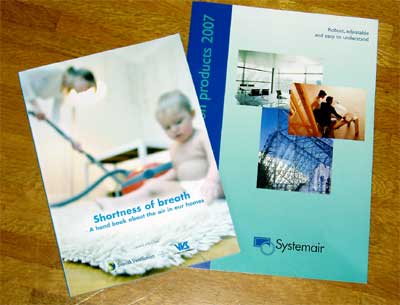北総研、正しくは「北海道立 北方建築総合研究所」。
北海道の外郭組織で、旭川市郊外にあります。
前身は「寒地都市住宅研究所」で、当時は札幌市西区にありました。
北海道は、その前身の「北海道開拓使」の時代から、一貫して、
「寒冷地における住宅」というテーマを
日本民族が北方圏に居住するための基本要件と認識し続けて、
そのための研究努力を継続してきた、ということができます。
その意味では、日本国家の意思としての北方圏開拓の
基本条件をずっと、研究し続けてきた組織である、とも言えると思います。
で、今日的意義でいえば、
このようにして蓄積されてきた北方建築技術が、
同時に省エネルギーで、地球温暖化に抗する技術として
脚光を浴びるようになってきていると言えますね。
実際に、日本全国から「共同研究」の申し出が後を絶たず、
近い将来、民営化したとしても、十分に自立していけそうな組織のように思います。
写真は、庁舎の全景模型ですが、
建物それ自体としても、IBECの省エネルギー賞を受賞しています。
基本的な断熱気密の性能に加えて、
日中勤務稼働時間での照明用電気使用率が10%以下というレベル。
これはいかに、太陽光利用率が高い設計になっているかを表しています。
手前側の事務スペースと、奥の実験棟とをつなぐ巨大な採光吹き抜けアトリウムには、
Low-Eペアガラスを介して制御されながら、たっぷりの昼光が降り注いでいます。
また、開口部周りの換気口などの工夫は、
自然換気の利用による室内環境のコントロールを入念に計画していることが明白。
こうしたポイントに徹底的に集中することで、
デザインとしてもたいへん清々しい建築に仕上がっていると思います。
というようなお話を聞くことが出来たのは、今回が初めて。
実は何回も訪問していましたが、いつも他の要件で来ていたもので、
自分自身は初めてディテールを聞くことが出来たワケなんです(汗)。
実務に関わった研究者の方から、
細部のお話を伺ったのですが、こうした立派な建物でも、
実際の設計、施工の段階では、いろいろな問題点もあったそうです。
しかし、今後の建築が目指していくべき基本方向をきわめて明確に示している、
という意味では、わかりやすい近未来を感じさせる建物だと思います。