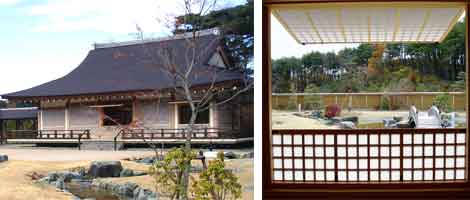最近はすっかり目にしなくなったものですが、
わたしが子どもの頃には、どの家も、といっていいくらい下がっていたのが氷柱(つらら)。
断熱ということに無自覚に建築を建てていた時代なんですね。
家並みの軒先まで雪が堆積し、
その軒先からは、氷柱が「しばれ」とともに成長し続けている。
というのが、ごく当たり前の冬の札幌の街並み。
札幌は道路幅がゆったりとした街割りなのですが、
冬になると道路幅が、東北以南地域とそう大差がないほどに狭くなった。
きのう書いた「視覚記憶」ということでいえば、
この氷柱だけは、なかなかお目に掛かることがなくなっています(笑)。
これはやっぱり、良くなっていると言うことなのでしょう。
そんななか、時々通る道沿いにあるのがこの工場。
冬場になると、みごとな氷の芸術(笑)を見せてくれています。
氷柱は、建物内部から上昇気流に乗って暖気が屋根面を暖め、
屋根上の雪を融かし、それが屋根板金の隙間を通って軒先に滞留して
やがて、軒先から落ちるときに氷点下の空気で冷やされてできる。
ちょうどすがもりと同時に起きる現象。
断熱ができていなくて、雪と寒さが厳しい、という条件があれば、
ほぼ間違いなく発生する。
この時代の暖房は、豊富にあった石炭が主流。
より火力が強い「コークス」というのも流通していた。
そういう暖房方式も同時に氷柱生成に大いに寄与していた。
こういった氷柱が、たまにくる暖気のときに、
屋根雪崩と共に通行人を襲う、という悲惨な事件を引き起こしてもいた。
そんなことから、雪止めを設置したり、屋根の落雪方向を良く検討してください、
というようなキャンペーンがあったと思う。
現に、わたしたちの通学路でも、氷柱の近くを通らないように
というような先生たちからの生活指導があった記憶があります。
そんなことから、「無落雪屋根」という画期的な工法が開発された。
なぜか、毎年のように増改築工事をしていたわが家では
そういう情報をもたらしてくれる建築業者さんが来ていた記憶があります。
まぁ、しかし、家の中の寒さは、暖房が消えている朝方など、
想像を絶するレベルだったものです。
家風呂がある家庭では、たいてい、朝になると風呂の湯が結氷して
大きく盛り上がっている、というのが一般的だったもの。
ここのところ、1週間くらいでしょうか、
北海道全域、本格的な寒波の襲来で、
札幌でも最低気温がマイナス12度まで下がっています。
各地から、マイナス20度超という話題が飛び交ってきています(笑)。
おりからの灯油の大高騰。
住宅相談の投稿にも、灯油の節約はどうしたらいいか、
というような切実なものも増えてきています。
いろいろ、考えていかなければならない問題は続きますね。