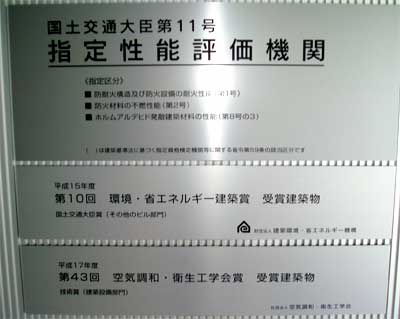この時期になると、毎年、東北から
北海道への住宅見学ツアーが来られます。
やはり冬真っ盛りの北海道での住宅性能を確かめたいという
そういう見学目的ですね。
北海道の住宅業界人は、いわゆる性能のことでは本州地域に行くことは少ない。
そうした目的の場合には、やはり北米・北欧に見に行く。
逆に言うと、世界の寒冷地技術を北海道がまず消化吸収して
実際に日本人の暮らしにフィットさせてみてから
それから本州で、活かせる部分を取り入れていく、という流れ。
大体がそういう位置関係にあるので、北海道は元気を出さなければならないですね。
寒いからといって縮こまるのではなく、
寒さを産業的に活かす努力が必要なのだと言われている気がします。
そんなお客様を迎えるようなことが多くなってきて、
他の日本からの目で北海道を見てみると、
そういう違いもやっぱり面白いものがあります。
きのうは山形県からのお客様をお迎えしたのですが、
何人かの方たちから、「和室、目にしませんね」というお言葉。
聞いてみると、山形ではまず、2間3間と和室が続く設計プランが
ユーザー側からの要望条件にふつう、入ってくる。
そういうポイントを基本にしながらプランを組み上げていくことになる。
それに対して、北海道では一般的には、
客間の機能を果たす畳の1部屋、という範囲での注文。
それすらなくなって、居間に隣接しての「ゴロッと横になる」スペースとしての和室コーナー。
というようなケースが一般的にも多い。
まったくない、というのもごくふつうにある。
まぁ合理精神の方が強くて、和室という生活様式的部分はあっさり乗り越えちゃう。
そういった意味では、日本の中で一番インターナショナルな暮らしよう。
とはいっても、合理性重視の現代生活ということで、
欧米的なスタイル、というものとも少し違う。
しかし、インターナショナルであることは間違いないので
たぶん、外国から来るとわかりやすいような部分は強く感じるのではないでしょうか?
そんな自己認識を確認させられることも多いと言えますね。
最近はとくに省エネという部分で、
暖房形式についての変化の行方を見定めたいという部分も強くなってきた。
写真は空気熱源のヒートポンプ利用のお宅。
暖房も給湯もこの外部本体でまかなっているのですね。
もちろん、そのためには建物の性能が絶対条件で、
この家は断熱厚みが200mmのグラスウール+ロックウールで、
熱損失係数(Q値)が0.87という高性能レベル。
窓もすべてが3重ガラス入りの木製サッシ。
そうした仕様で、外気温マイナスのなかで実にマイルドな暖かさという
そういった部分を体感していっていただくわけですね。
ということで、わが社のオープンスペースでのムービー上映、
写真のプレゼンなど、いろいろな仕掛けも準備。
慣れてはいるのですが、なにせ、14人という大勢のみなさん。
なかなか、満足にはお迎えできないのですが、
いろいろな体験をしていって欲しいものと思っております。