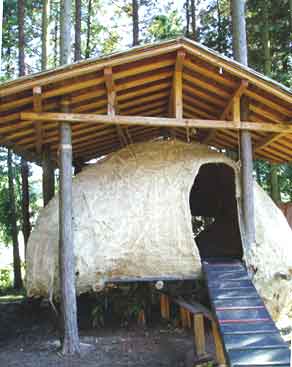みなさん、とくに寒冷地のみなさん、玄関土間は広く計画しましょうね。
わが家では、当初は広く取れていて、
「家としての使い心地」がとってもよかったものでしたが、
やむなく床面積を増築したときに、玄関がぐっと狭くなってしまいました。
かえすがえすも、残念でなりません。
いまは家族が暮らしているだけなので、なんとかできてはいますが、
それでも玄関の狭さからくる「家全体の窮屈感」は言葉にできない部分。
なんといったらいいのか、
入り口の狭いトンネルだと入ってくるのに気を使う。
とか、高速道路で、出入りに気を使うパーキングなんて、
もしあったら、誰も停まらないのじゃないかという感じ。
どうもそんな印象に近い。
出入りがゆったりしているのと、そうでないのとでは、
長い人生の時間の中で、大きな心理的違いが表れるのではないか、と思います。
で、毎日「帰ってくる」建物である家には、
そういう意味での安心感が欠かせないと思うのです。
写真は弘前の古い街並みの中の住宅。
間口が狭く、奥行きが長い敷地を表すように
長いエントランス空間が実現しています。
ちょうど、長い敷地の中間くらいに玄関を持ってきているのですね。
ですから、長い半外部的な通路空間を通って玄関にたどりつく。
そんな空間を壁・天井とも板張りで仕上げていました。
こういう木の質感って、肌触りがあって、
ひとのこころに潤いを感じさせてくれる。
床はコンクリートの土間なので、気を使わず、
大きくて、どっしりとした「家に帰ってきた安心感」を増幅してくれる。
で、写真左の引き戸を通って、2階の生活空間に至る。
そういうシチュエーションを仕掛けてあるのですね。
こういう「公私の別」を心理的にハッキリ認識させる空間の用、って見えにくい。
少なくとも平面図的には、意味のない広い空間になってしまう。
公団住宅的な○LDK思想から、まっさきに排除された空間だと思うのです。
しかし、毎日の暮らしの中で、こういう「心配り」の部分こそ、
家というものの本質を表してもいると思います。
ぜひ、可能な限り、広い玄関土間計画を。