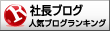こんにちは。落雷抑制の松本です。
雷保護の世界では、落雷が生じないであろう範囲を落雷からの「保護範囲」とし、これを決めるのに「回転球体法」を用います。放電の先端が地面付近のある一地点にまで降りてきた時、次にどこに向かうかは、雷電流の強さに応じた距離になり、方向性は真下とは限らずにどこにでも向いますから、その点を中心とした球体表面のどこかになるというので「球体」の半径の外側にいれば、落雷が落ち難い「保護域」とする考え方です。 この理屈では半径を大きくすれば大きくするほど陰になる部分も大きくなり、保護範囲も大きくなります。そこで、回転球体法による球体半径を200mとし、抑制範囲100mが常に有効であるという説明に対し、これはPDCEでしょうかとの問い合わせを受けますが、弊社では、この回転球体法による説明(球体半径200m)は科学的合理性を欠くと考えています。その理由として、
- 回転球体法自体は、球体の半径が大きければ大きいほど、保護範囲も広くなります。しかしながら、その半径とは雷撃が1回の放電で伝わる距離ですから、物理的な限度があり、JIS規格では最大で60mと規定されています。これを超える200mもの半径を想定することは現実的ではありません。JIS規格では、大気中の放電の98%をカバーする半径は20mと規定されています。半径を200mとするのは、単純な誤りと言うより、保護半径100mを導き出すための意図的な数字です。
- また、この放電の距離は、大気中の放電と言う自然現象ですから、人が制御できるものでもなく、ましてや地上に設置した機器により変化するものでもありません。地面に何を置こうが、それにより回転球体の半径を大きくできるものではありません。
- かりに地面に接地した機器の影響で回転球体の半径が大きくなったとしますと、それは雷電流の強度が大きくなったと言う事であり、地面側においては頭上の雷雲の強さが増したという事で、より危険な状況になったとも言えることです。
JIS規格と言う工業規格なのですから、厳密なものかと思えば、この「回転球体法」、抜けているのは上空から一方的に雷撃が地面に向かうことを想定しているのです。ところが、実際には、地面から「お迎え放電」が上昇し、上空で雷雲から降りてきた放電と「お迎え放電」が結合することを想定していません。という事で、工業規格とするには完全ではないのですが、これが建築基準法にまで及んで、この不完全な理論によるルールが定められ、この不完全なルールにより建物の雷保護が決められています。いくら不完全であっても、一応、法律ともなると、強制力がありますので、人はその意味も考えずに盲目的に従わざるを得ません。 この建築基準法、JIS規格の2004年版を使用しています。 JIS規格自体は更新され新しいものが出ているのですが、法律は古い熟成モノがお好きなようです。お役所に行くと何かカビ臭いのは、この古いもの好きのせいでしょうか? 周回遅れのような古い規格を使いながら、ディジタル庁は何をデジタル化するのか? お役所のDX、何か順番に違和感が残ります。
人は数字で説明されると正しいことのように錯覚します。 しかし、その数字の出どころ、どのような理由でその数字が使用できるのかまでジックリ考えることが重要です。 このような説明がされたら、では、日常で一番多いとされる半径20mの場合は? と問い返してみてください。
〒220-8144
神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1
横浜ランドマークタワー 44階 4406
落雷対策専門の株式会社落雷抑制システムズ
電話 045-264-4110
公式サイト http://www.rakurai-yokusei.jp/
Eメール info@rakurai-yokusei.jp