
とある当ブログ読者の方に、東京模型ショーの入場券を、
例によって名前を明かさずにアドレスだけで物をやり取りできる
便利な宅配を使って差し上げたことがあります。
今までのやり取りから模型がお好きなのだろうと思い、
それまで裏米でのお付き合いで知っていたメールアドレス宛に
送らせていただいたのですが、そのお礼に、なんと
組み立て前の模型が
送られてきたのです。
東京模型ショーで「たまごヒコーキ」シリーズに萌えまくり、
これが欲しいとお星さまにお願いしたところ、たまたま近くに
模型を作れるお星さまがいたので作っていただけることになった、
ということを模型ショー体験記に書いたら、ちびつながりで
こちらの方は「雪風」を下さったというわけです。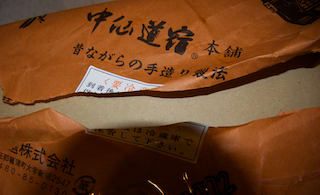
そしてある日我が家に届いた宅配便。
何も考えずにびりりと包装を破ってから気がつきました。
それが「要冷蔵」であることに。
宅配便は冷蔵扱いで配送されていなかったので、
「これはネタとして扱え、とそういう意味であるな」
と送り手の意図を鋭く察知したエリス中尉、カメラを持ってきて
その破いた包装の状態から記録することにしました。
「中山道宿本舗」が一体なんの会社であるかまでは
面倒なので調べませんでしたが、何しろこれも大事なネタです。
要冷蔵の包み紙の下からは、畏れ多くも軍艦旗が!
思わず台所の隅で冷凍庫の上に置かれたその物体に対し
威儀を正し海軍式敬礼をするエリス中尉。
というのは嘘ですが、心の中で敬意を表しつつ、
ついでに
「ネタのためにここまでやるか」
と心底呆れながら、中身を取り出したのでした。
ちび丸艦隊シリーズはフジミ模型というやはり静岡の会社が発売していて、
「大和」「金剛」「赤城」「榛名」「霧島」「武蔵」
という、超有名どころの種類があります。
(今見たら大和は売り切れてました)
ところで、模型の会社がどうして静岡に集中しているのかというと、
その理由らしきことを、先日模型ファンから伺いました。
模型会社というのは、大抵が学校教材の製作会社から出発していて、
今のような素材がなかった時代は、木を使っていたというのです。
静岡といえば、ヤマハ、カワイなどのピアノメーカーが、
ことごとく浜松にあるわけは、浜松が
「比較的木を扱うのに適した気候」
ということもありますが、なんといってもヤマハの創立者、
山葉寅楠が会社を構えたのがここだったという理由が大です。
カワイの創立者河合小市は11歳でヤマハの技術者だった人(!)
ですから、会社をその近所に作ったわけですしね。
ちなみに、戦時中、ヤマハもカワイも、ご時世柄ピアノを作れず、
その間木製のプロペラなんかを作っていた時期があって、わたしは
「河合」と名前の入った軍用機プロペラの写真を見たことがあります。
もひとつついでに、ヤマハの歴史のコピペを貼っておくと、
ヤマハの歴史
・最初は輸入ピアノの修理→楽器関係作る
・楽器やってた流れで電子楽器も作る→DSPも作る
・DSPを他に利用しようとして→ルータ作る
という流れで、楽器、電子機器、ネットワーク関係の製品を作るようになった。
発動機・家具製造の歴史
・ピアノの修理で木工のノウハウが溜まる→家具を作る→住宅設備も作る
・戦時中に軍から「家具作ってるんだから木製のプロペラ作れるだろ」
といわれて戦闘機のプロペラ作る→ついでにエンジンも作る
・エンジン作ったから→バイクも作る
・エンジン作ったから→船も作る→船体作るのにFRPを作る
・FRPを利用して→ウォータスライダー→ついでにプールも作る
つまりこのような会社がひしめき合う浜松には木材が集まる
→小さな木材を使う教材制作会社は便利→そこで営業しているうち
模型が専門になる→教材をやめても会社はそのまま←イマココ
という理由なのだろうと思われます。
多分間違ってないと思いますが、違ってたら誰か訂正してください。
さて、届いた「ちび丸艦隊_雪風」ですが、蓋を開け中を見て、
瞬時にわたしには自分がこれを作る技術も時間も根気もないということを
悟ってしまったのです。
あまりにも絶望したせいで、部品の写真を撮るのを忘れましたが、
今ネタのためにも撮っておけばよかったと激しく後悔しています。
「もしかしたらこれは何かの嫌がらせだろうか」
お礼にもらっておいて、(しかも今改めて値段を見たら結構高い)
この言い草はなんだ、と思われそうですが、そのとき
脳裏をかすめたのがこんな考えでした。
ところで「たまごヒコーキ」を作ってもらえることになった方から
ちょうどそんな時に連絡が入りました。
「たまごヒコーキと普通のバージョンのブラックバードできました」
というわけでうちに嫁入りしてきたブラックバーズ。
たまごヒコーキの方はピトー管ありません(笑)
ピアノの黒の上に置くと、あんまりブラックバードの黒が映えませんね。どうも。
部隊マークや機体ナンバーは実在したものでしょうか。
ついでにこのとき遊びに来ていた、こちらはブラックキャット。
ところで、このブラックバードのやり取りをしている時に、
「ピコーン」と閃いた考えがありました。
「ついでに『雪風』も作って貰えばいいのではないか」
たかだかこんな小さな模型くらい、比較的器用なわたしにできないはずはない。
作ってみれば案外簡単かも?しかも失敗したらしたでブログネタにもなるし。
という考えもあったのですが、面倒臭さがチャレンジ精神を凌駕しました。
その依頼を快く引き受けてくださった件の「お星様」は、
制作の途中経過として、

「あなどれません」
というメールを送ってきました。
それによると
「このフジミというメーカーはタミヤやハセガワに比べると、
パーツの合いが甘いのですが、ちび丸艦隊はなかなかしっかりしています。
デフォルメで武装や電探(レーダー)が強調されていて、
これらのパーツはもっと大きなスケールのキットよりメリハリがあり、
面白いキットです。侮れません。」
それはともかく、わたしはこの説明書に書いてあることを読んで
「自分でやろうなんて早まった考えを起こさなくてよかった」
と胸をなでおろしたのです。
「説明書の番号の部品をニッパーで丁寧に切り取ります」
こんな小さなニッパーなんてわたし持ってませんし。
さらには
「海面に苦労しています」
ということでした。
一応海面模型にもなるので、海面を作って下さろうとしたようです。
ちなみにこんな感じですね。
力作だ~!
思わずボートの中で中腰になっている要救助者もいいですが、
それよりこの湖面のような海面に立つ白い航跡がいいですわー。
こんな海面を作ってくれるのかな?
わくわく。
そして、製造元からは完成した「雪風」と製造元所有の「大和」を並べて
「最後の出撃!」と遊んでいる様子が送られてきました。
ちょっとアスペクト比がおかしいですが、実際の対比も
1キロくらい離れればこれくらいになったのではないかと思われます。

というわけで、「雪風」が届きました。
思わず白黒にしてしまったのですが、どうやら製造元では
海面の出来上がりに満足がいかず、妥協を許さない職人気質は
そういうものを人に渡すわけにいかん!ということで、
プラスチックの海面板を送ることにしたようでした。
画像をソフトで加工してみました。
他に海面らしいものはなにかないかと探したところ、「MIKIMOTO」の
ブルーの紙箱が色といい波といい、ちょっといい感じだったので使ってみました。
ブラーで海面をぼかしたのが冒頭画像です。
ここでふと「水に浮かべられる!」というのを思い出し
ガラスボウルに水を張って浮かべてみました。
よく考えたらこれがこの「雪風」にとっての進水式です。
進水方法は海面に直接進水する「投げ込み式」です。
まっすぐ進まないのでよく見たらなんだか右舷側に傾いております。
よくよく見たら、ちゃんとパーツがはまっていませんでした。
それでも全く問題なく浮いているのでバランスとか大したものだと思いました。
武蔵だって進水式の時は最終的には左に触れましたよねー。(←覚えたての知識)
しばらく見ていたらだんだん沈んできたのでやめました。
「雪風」は決して沈まず。
他に何かないかと思って部屋を見回したら、昔息子が宿題で
ジオラマを作ることになったとき、その「予行演習」として
買ってきたジオラマキットがあったので、無理やり
川を航行させてみました。
川の真ん中に大きな岩があって、座礁しているところです。
ここまでやって来れたのが奇跡。
「雪風」が船頭多くて山に登るを体現しているの図。
ところで、この「雪風」のとき、わたしは厚かましくも、
別口でもらっていたけどどうしたらいいのかわからない
飛行機の模型がもう一点あったのを思い出し、これも
また託して作っていただいたのでした。
それがこれ。
滑走路がなく、道路に不時着したところです。
複葉機で「報国号」と機体にあることから、
戦時中の寄付で作られた飛行機であることだけわかりましたが、
これがなんであるかは作った方もわからないとのことでした。
ちなみに二枚羽は前後に少しずれている仕様です。
海軍機か陸軍機かもわかりません。
これ、なんだかご存知の方おられますか?
今から不時着するというこの飛行機が、山の頂上に
機体をこすりながら突っ込んでいく様子。
これ、「あゝ陸軍隼戦闘隊」の特撮よりはいい線いってないか?
なぜ墜落させたし。
というわけで、散々楽しませていただきました。
関係者の皆様、本当に有難うございました。
模型の世界って楽しいですね!
自分自身は何一つ作らずにこんなことを言うのもなんですが。




















座礁している
不時着した
墜落した
悲しい響きなのに模型だと笑えてしまいます(゜Д゜;)
必死に不時着しようとする円谷氏もびっくりなショットから、すでに失敗し墜落したショットの速さにお腹痛いです…(>_<)
現実なら決して笑えませんが、こういったおふざけも模型ならではですね(^o^)/~~~
うちも小さい零戦さんがおりますが、小さな巨人の2歳児(♀)に無惨にも真っ二つにへし折られたのでした。
私が泣き崩れたのは言うまでもありません(ToT)
エリス中尉様の模型シリーズの続編を待ちます(笑)
「コシ」が有る歯ごたえ、でした。
90式艦戦、無理やり川に突っ込ませられて赤い
お尻が痛々しいですが、この赤い塗装、戦前の海軍機
の尾翼廻りは、海上への不時着時に、目立ち易いようにとこの様に塗装されていたそうです。
源田サーカス、見事な編隊宙返り中。
http://www.ne.jp/asahi/airplane/museum/cl-pln2/TW013.html
一型は下翼に3度の上反角、
三型は上翼に5度の上反角
をつけたとあります。
消去法でいっても二型に間違いはないのですが、おっしゃるように
「機銃の設置方法を改良し機首の上面に移して、胴体側面に燃料タンクを装備した」
なのですが、今確かめてもついてないですね。機銃。
これ、実はある会社社長で、海兵卒のそれはそれは切れ者の番頭さんに若い時に鍛えられ、
海軍ファンになった方にいただいたものなのですが、番頭さんは「彩雲」に乗っていたため、
会社には大きな彩雲のモデルが飾ってあるのです。
器用な方でそれもご自分で作られたそうですが、どうしてこれを下さったのかナゾです(笑)
外側の包装とか説明とかがなかったので、もしかしたら一度作って置いてあったものを
下さった(どこかで機銃紛失)のかもしれません。
しかし、こんなことまでわかってしまうとは・・。
このころの航空機は開発が早く旧式化するのも早かったので、悲劇的な歴史を持ちません。
だから
だんだん沈んでいくのを眺めたり
座礁させたり
不時着させたり
墜落させたり
ということに気を使わずにやってしまいましたというのは嘘で実は何も考えてませんでした。(顰蹙)
さぞかし当時の人々は湧いたんだろうなあ。
ところで、
おまえ、だれ?(お約束)
船屋としては、8番艦の雪風を含め18隻建造された陽炎型駆逐艦には惚れ惚れします。昭和18年9月頃対空兵装強化のため2番12.7センチ連装砲塔を撤去し、25ミリ3連装機銃を中心線上に装備、電探も付けてありますね。マリアナ海戦以降さらに機銃を増備しましたが。
雪風は生き残り、台湾の海軍で長く使用されましたが、海戦が建造当初考えていたものと全く異なり、ほとんどの艦艇が武運拙く消えて逝きました。
戦後の建造技術は進みましたが、将来の使用期間を考えて、要求性能が決定され、設計、予算等が決められ建造しますが、建造期間は数年を要します。
将来に合った艦とするのは大変難しい事と思います。
雪風を見ながらちょっと感傷的になりました。
陽炎型の建造が始まった昭和14年には、すでに航空機が脅威になることが予想されていて、同じ年に防空駆逐艦「秋月」型の建造が開始されています。
秋月型は、5インチ砲より高初速の長10センチ連装砲4基に換装され、魚雷発射管は4連装1基(4射線)と、対艦戦闘より対空戦闘を重視しています。当初、設計陣は発射管の廃止を唱えたそうですが、用兵側からの要求で、陽炎型では、4連装2基だったところを1基搭載することで妥協したようです。
陽炎型は、昭和30年から建造された海上自衛隊の「あやなみ」型に引き継がれていると思います。戦後最初の「はるかぜ」型はどちらかというと米海軍の駆逐艦似ですが「あやなみ」型は長船首楼(陽炎型は艦橋までですが、あやなみ型は船体後部まで伸ばして美しいオランダ坂を形成)、二本煙突、連装砲3基(陽炎型は5インチ連装砲が前部1基、後部2基に対して、あやなみ型は3インチ連装砲が前部2基、後部1基)、中央部の魚雷発射管(陽炎型の4連装2基に対してあやなみ型は4連装1基)や後部の爆雷投射機(側方投射型2基、陽炎型は投下軌条2基に対して、あやなみ型は1基)等「パクった」と言ってもいい程、よく似ています。
太平洋戦争では、散々な目に遭った陽炎シスターズですが、設計陣は、あの美しい艦型に思い入れがあったのではないのでしょうか。だからこそ、戦後10年経って、思い通りに戦闘艦を作れるようになった時、もう一度「陽炎型」を作ったのではないかと思います。
海上自衛隊のホームページに自衛艦の進水式の動画が投稿されていますが、船台進水とドック進水式があります。潜水艦も川崎重工神戸と三菱重工神戸と違いが分かります。ただ三菱重工のドックは潜水艦専用で他の建造ドックとは全く違いますのでジァパンマリンユナイテッド磯子の「いずも」等を見られるの分かり易いと思います。ドック進水式は予め注水しておいて命名、支綱切断等の式典実施、式典終了後、タグボートで引き出すやり方が多く、本当の進水式は船台から着水する事です。商船はほぼ費用から進水式は造船所任せ、引き渡し時、命名完成式が多くなっています。船台進水は前にヘッドとボールがあると書きましたがエリス中尉のご指摘のとおり、ヘッドは季節、温度により硬軟度が違い、気象の変化によって海軍艦艇で失敗があり、進水式をやり直した事もあります。皇族の臨席を得ますので失敗した場合は大変だったと思います。上手く出来れば大変醍醐味があり、船が生まれたと感激します。ヘッドの回収を小舟で実施しなければなりませんので後が大変ですが。ボール進水は進水台の後端に大きな篭がありその中に入りますので回収は難しくありません。ただ風が強く、風向きが悪ければサビが飛んできます。ドック進水が多くなったのは重量からと船台はレーキと呼ばれる傾斜がありますので建造時位置決めが難しいためと思います。船台進水が見る者にとって迫力がありますが、船屋は船体の中にすべてが入ってないので左右傾斜の計算をしバラストを入れるなど、防水について確認する等が必要で大イベントです。ひっくり返ったり、そのまま沈没したりした船もあります。船屋は縁起を担ぐのでうまくいって当たり前、失敗しなくてもちょっとした事故でも船の一生に響くと考えます。戦艦「信濃」はドック建造でしたが注水でミスがありドック内で移動し、艦首等を損傷、空母に改造後、呉に回航時、1本の魚雷で艦内の防水も悪く沈没しました。長くなりましたのでこの辺で。
エリス中尉のご指摘のあります進水後の左右の振れですが舵は真っ直ぐに固定していますが、後進は制御が難しく振れ始めると修正は困難となります。進水式では真っ直ぐ進んでくれることを船屋としては祈る思いですが。対岸が近い造船所は行き足止めの錨と錨鎖を船首に用意したり、タグボートを多く用意しますが、それぞれの乗船所の立地条件と経験で相当違います。
>対艦戦闘より対空戦闘を重視しています。
陽炎型も秋月型も、南方での輸送に投入されることが多くなり、そのほとんどが
潜水艦にやられてしまった、つまりこの「対空戦闘重視」が災いして次々と失われ、
結局陽炎型は「雪風」しか生き残ることができなかったと言われていますよね。
もちろん防御能力もかなり手薄だったという点も大きな理由でしょうが。
戦後の技術陣が思い入れを持っていたという説、わたしもそう思います。
「お節介船屋」さんのコメントを読んでいつも思うのですが、物作りにかける思い入れにおいて、
飛行機や艦船に関わる人々のそれはただの機械を製造するというだけでは決して生まれないような、
生きている人間に対する愛情に勝るとも劣らない濃密さが感じられます。
特に戦後、平和の世にあの姿をもう一度甦らせたい、今度は平穏な人生を送らせてやりたい、
という願いがこめられて開発されたり復刻されたりしたものは多いのではないでしょうか。