
昔、我が連れ合いであるところのTOが小学校の修学旅行でここに来たとき、
この「大井肉店」の前を通り、
「いいなあ、牛鍋。いつか大人になったら、これを食べてみたい」
と思ったそうです。
かく言うわたしは、結構な大人になってからも一度ここに来ていますが、
その時、この牛鍋の「お値段」を見て
「こんな高いすき焼きを食べる人がいるのね・・・」
大人になったら、というより、いつかこれくらいお金を払えるようになったら、食べてみたい、
という風に思いました。
以来幾星霜、このような二人が出会い、結婚し所帯を持ち、一人の生命体を生み出して、
再び同じ場所に訪れたわけです。
もう、これは食べるしかないでしょう。牛鍋。いざ。

この建物は、1863年、神戸開港に合わせて、居留地に建てられました。
そう、前日までいた、あの神戸居留地です。
当時も一階で牛肉販売、二階で牛鍋を供する店でした。
美しいレースのような飾りがついたこの建築物は、当時すでに神戸に点在していた
外国人の商館や住宅を模して造られた「最新のデザイン」。
今、一階にはショウケースの中に肉の蝋見本があり、購入も同じようにすることができます。
二階で牛鍋を食べたい人は、階下のインターフォンを鳴らして、二階に上がって行きます。
横浜で最初に牛鍋屋がオープンしたのが1862年のこと。
この神戸の店は、流行りを読むに敏な大井肉店の店主が、最初の牛鍋店オープンの
一年後に作ったということになります。
何しろ当時は今と違って、流行り全国に伝播するのにも時間がかかった頃ですから、
一年というのは「先取り」と言ってもいい時期だったのではないでしょうか。
最初の頃の牛鍋は「肉が固くて、お世辞にも美味しいと言えない状態」であったと、
うちにあった「漫画日本の歴史」には書いてありました。
「うまいうまい」と口では言いつつ内心、
「流行ってるからには美味いんだろうが、オレ的には正直そうでもないんだよな。
でも、この味が判らないなんて、恥ずかしくって言えない」
などとみな思っていたようです。
何しろトレンドは「文明開化」ですからね。
1871年に書かれた仮名垣魯文の「安愚楽鍋」には、
「士農工商老若男女賢愚貧福おしなべて、牛鍋食わねば開化不進奴」
とあります。
つまり
「文明開化真っ盛りのいまどき、牛鍋を食べないなんて、遅れてるぅー」
と言いきってるわけですね。
全てに魔改良を加える日本人のこと。
ことに食べ物の工夫に関しては、それはあっという間であったらしく、
「これ不味いんじゃね?」という正直な言葉を誰かが言いだす前に、
牛鍋はすっかり「誰が食べても美味しいもの」に変化していたようですね。


お昼の時間を大幅に過ぎていたわけでもないのですが、何しろ平日のため、
客は私達だけ。
いこっていた炭をあらためて熾すところから支度が始まりました。

コースは松5000円、竹4000円。
さすがにこの値段では若い女の子など、気軽に入れませんね。
今日は竹しかございません、ということで、竹二人前+肉追加で行くことにしました。
(松があったらTOがここぞと頼んでいたかもしれないので、ご予算的によかったかも)
小さいお膳を人数で囲むのですが、正座ができないので小さいスツールのようないすを
お尻の下に敷いて、キャンプファイアーのように座りました。
仲居さんに最初をやっていただくのですが、なんと!
最初に白砂糖をお鍋に敷き詰めてしまいました。
そして、明治村秘伝のわりしたを投入後、肉を焼いて行きます。
お店の方によると、これが「関西風」であるとのこと。
そういえば我が家のすき焼きの作り方は、ほぼこの通りだったように思います。
鍋に砂糖を入れることはせず、最初に牛脂で鍋に油を敷いていましたが、
ここのやり方は「肉の脂が多いので、油は敷かない」とのことです。
仲居さんは、如才なく店の歴史などの説明をしながら手際良く肉を焼いてくれました。
普段牛肉のあまり好きでない我が家の面々(特に息子)ですが、牛肉の美味しさと言うより、
わりしたの甘辛さでご飯がすすんだ、って感じです。
このわりしたは「秘伝のたれで門外不出」。
よく聞かれるのですが、決して売ったりはしないで、全国でここでだけ味わうことができるのだ
と仲居さんは胸を張っておっしゃっていました。
しかしTOは後で一言、
「関西風にしては辛くなかった?」
まあ、関西と言っても京都と神戸はだいぶ違うんですよね。
このお店ももともと「外国人相手に肉を売る店」であったそうですから、
どちらかというと「外国風」=「こってり」という解釈で味付けをしたのかもしれません。
ところで。
我々はこの日、昔の「夢」を叶えることができたわけですが、息子は初めての明治村で、
「いつか大きくなったら」「いつかもう少しお金が使えるようになったら」
という人生の「いつになるかわからないけど叶えたい目標」を持つこともなく、
なんとなくいきなり牛鍋を食べて終わってしまったわけです。
どんなつまらないことでもいいから「いつかは・・・」という先の目標があった方が、
それが叶ったときの嬉しさが、人生をよりオトクにしてくれる気がするんですよね。
息子は、いつかここで牛鍋を食べることがあっても、懐かしさを感じるくらいで、
おそらく今日の我々のような感慨は持たないでしょう。
日頃の「何かと与えすぎる罪」についても、心の中で軽く反省した次第です。

その昔はこの窓から神戸港に行き交う船が望めたのであろう窓。
もしかしたら連合艦隊の艦船が見えたこともあるかもしれません。






















































 作品その3。潜む力。坪井由香梨さん作。
作品その3。潜む力。坪井由香梨さん作。














 ちなみにこれが神戸の市章です。
ちなみにこれが神戸の市章です。











































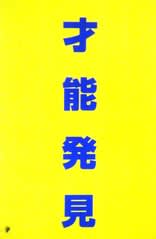

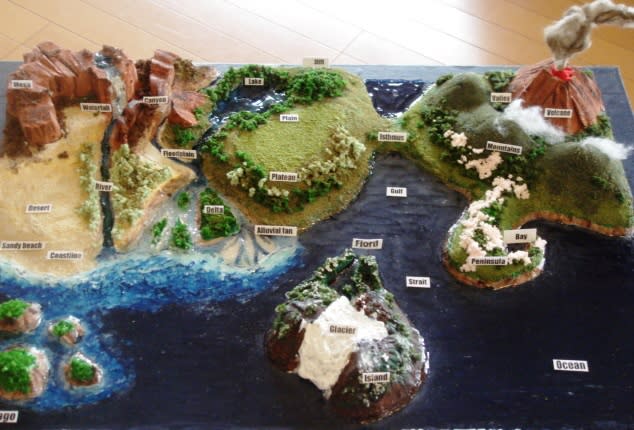





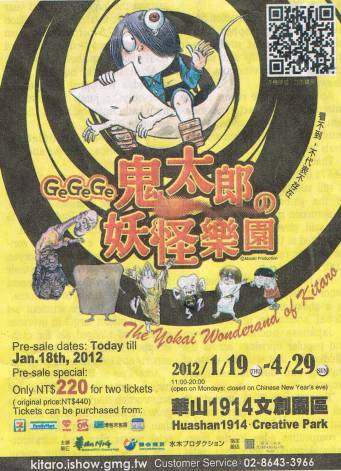
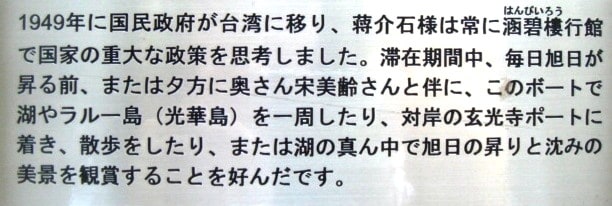

 茶店のランプの下に立つ愚息。
茶店のランプの下に立つ愚息。
 ちょっと台湾の皆さんのお願い事拝見。
ちょっと台湾の皆さんのお願い事拝見。

 故宮博物館に行く途中のドライブウェイで見た巨大うさぎ。
故宮博物館に行く途中のドライブウェイで見た巨大うさぎ。
 そして、極めつけ、この店のこんなもの誰が買うのか大賞。
そして、極めつけ、この店のこんなもの誰が買うのか大賞。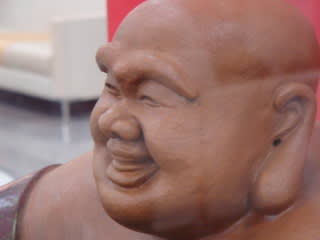



 タイガーバームと並んで売っていた白花油。
タイガーバームと並んで売っていた白花油。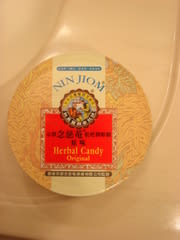
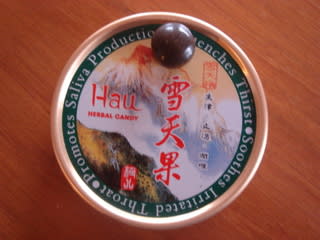



































 売ってくれたお洒落な鯉の餌、50円。
売ってくれたお洒落な鯉の餌、50円。





















