集団自決で、文科省が「軍による強制」を削除しましたが、沖縄の人たちは黙っていませんでした。大きな抗議の声を上げ、示威行動を取り、文科省をはじめ政府を動揺させることを成し遂げました。しかしそれでも、「軍による強制」という文言はそのまま回復させることはむずかしいとのことです。「検定意見に政府が介入することはできない」という口上になっていますが、実際は、教科書審議会の議論はほとんど行われておらず、官僚主導で一方的に削除されていたのです。
歴史の恥部を隠蔽しようとするこの圧力はどこから出てくるのでしょうか。なぜ、本土のわたしたちは、こういうことを脅威と見なさず、醒めた目でしか眺めないのでしょうか。歴史を粉飾しようとする空気はどのようにわたしたち本土の国民に浸透したのか、その事情の根元を垣間見せる文献を見つけたので、今回はこれをご紹介します。どうやらおおもとは、アメリカによる対ソ戦略にあったようです。
------------------------
1.池田ロバートソン会談
敗戦の1945年から50年代にかけての戦後期の国民の平均的な歴史認識は、戦争とその敗北の根本原因は、結局日本の社会が全体としてまだ「『半封建制』性」「封建遺制」を克服しえていなかった後進性にあり、経済力・技術の劣勢も、戦争での軍部の独走や天皇制的な人命軽視・人権言論抑圧もすべてその社会的後進性に根を持っている、といったものだったと述べてよい。
国民が戦後の民主主義的改革を受け入れたのも、占領政策としてただおしつけられたからではなく、生活実感にもとづく国民意識がそれを必要と考えていたからである。学問・思想の分野で、マルクス主義や近代主義(*)が大きな信頼を受けたのも、その言説が、敗戦を見つめ、自国の社会改革、「近代化」を自分たちの力で進めなくてはならない、と考える人々の心に響くものがあったからである。
(*)近代主義
ヨーロッパの近代社会を「近代」という理念のモデルとして設定し、そのモデルによって日本の近代社会を批判し、日本の「近代」の後進性を浮き彫りにし、ヨーロッパ的な「近代」社会へ向けて以下に純化発展させてゆくか、ということをテーマに掲げた思想潮流。大塚久雄、丸山真男、川島武宜氏らが代表的。
この時代、多数の日本人の意識はそうした面では自省的で、アジア・太平洋戦争についても、日本の中国侵略が基本原因だという理解を共有していた。
しかし、1948年からいちはやく表面化した米ソ冷戦の激化の中で、占領政策が急激に転換されたため(*)、侵略戦争についての反省は曖昧にされ、多くは戦争被害者的記憶や戦争はこりごりといった心情だけにとどまり、アジアの民衆に対する加害者的側面についての認識は、「事実的」の面でも「理論的」の面でも深められることなく、反動的な状況に押し流されてゆく傾向が強まった。
(*)
1953年、吉田首相特使、池田勇人と米国務次官補ロバートソンの間でのMSA(相互安全保障条約)をめぐる日米会談が設けられた。文字通りに「池田・ロバートソン会談」と呼称されている。
これによって日本は事実上の再軍備に踏み切らされたが、その「防衛力漸増政策の遂行に妨げになる空気を除去するように、教育を通じて日本の国民意識を誘導する」ことが決められた。
これを転機に教育は反動的旋回を始め、「憂うべき教科書の問題」(1955年、「日本民主党」による、当時の自省的歴史教科書への非難・攻撃したパンフレット)が発行され、文部省(当時)による教科書検定(組織・内容)強化が進められだした。
こうした国民意識の旋回に強い影響をもたらしたのは1960年代の高度経済成長である。60年代を通じて進行したその動きの中で、日本は先進国のひとつとなり、「経済大国」といわれるようになった。それによって「半封建的後進性」は克服された、明治以来の、「欧米に追いつけ追い越せ」の目標は達成された、と多くの人が心に感じるようになった。アジアの途上国からの留学生には、日本の成功は自分たちのこれからのモデルになる、と思う人も多くなった。アメリカの日本史学者は、日本の「成功」の要因を江戸時代までを含めてとらえる「近代化論」(*)を提起した。
(*)
近代化論;
マルクス主義史観(資本主義から社会主義へ、という発展・移行・革命理論)に対し、資本主義の後進国における近代化の可能性を「離陸」「産業化」という概念をキーワードとして理論化しようとして1950年代にアメリカの学者ロストウが提唱した経済発展理論が原型。社会主義革命を相対化し、ソ連の路線に対抗するという政治性が強い。ライシャワーはそれらを背景に、日本の「近代化」の条件を江戸時代の見直しから始め、60年代には日本の歴史学会にもその影響が広まった。
60年代の終わりから70年代にかけて「戦後歴史学」への批判的検討が盛んになり、さまざまの角度からの “日本史再考” (*)が盛んになった。「戦後民主主義」や「戦後歴史学」が批判的検討の対象になったということは、時代が移ったということを意味している。その中で戦後の国民意識を広くとらえてきた(自省的な)歴史認識は揺らぎだし、歴史学でも “多様化” の時代に入った。「太平洋戦争見直し論」も、また性質はちがうが「社会史」も、そのひとつとして登場した。
(*)
日本史再考;
戦後、60年代初頭ころまでに、マルクス主義と近代主義(前出)の歴史学の主導によって展開された「戦後歴史学」の日本史認識・日本史像への批判を意図して、さまざまの立場からその見直しが開始され、60年代後半から70年代にさかんとなった。
一律にはいえないが、中世・近世については、領主-農民の封建的支配被支配関係と、階級的矛盾からその社会の基本構造をとらえるマルクス歴史学理論の視角を拒否して、民衆生活の明るさ、経済的水準の高さを強調する説もそのひとつである。
近現代史では、講座派(日本の支配構造を絶対主義的天皇制、地主的土地所有、独占資本主義の三者によって分析する歴史学。野呂栄太郎『日本資本主義発達史講座』によって打ち出された)がその制約的側面を重視してきた明治維新の理解やそれをふまえた日本資本主義特質論の見直しなどがそれである。
アジア諸民族を解放したという見解に結びつけようとする「大東亜戦争」見直し論もそうした一連の動向の中で登場した。
一方、「戦後民主主義」の再検討とともに、太平洋戦争における日本の加害者的側面が本格的に検討されるようになり、それに関わる事実の発掘と意味を問う仕事も盛んになった。日本の台湾・朝鮮植民地支配の実態、アジア太平洋戦争における戦争犯罪的諸事実の解明などがその代表的なテーマである。併行して沖縄・アイヌなど本土から差別されがちであった弱者・マイノリティの史的研究も急速に進められていった。
こうして日本歴史への関心と研究が二極分化の色合いを濃くしてゆく。
ひとつは「近代の達成」を楽天的に受けとめ、「日本の成功と自信」を歴史の中に求め、それを明るく描こうとする方向である。もうひとつは、とくに日本の近現代史に忘れることのできない、また忘れてはならないさまざまの「負」の側面の認識を深めることを通じて歴史の展開と課題を見きわめようとする方向である。前者を東京大学教育学教授の藤岡信勝氏と西尾幹二・電気通信大学文学部教授は「自由主義史観」と名づけ、それに対照して後者を「自虐史観」と称し、ここに両者の対立構図が現れた。
ただし、「自虐史観」はこの時点で新たに登場したものでなく、戦後歴史学の一貫した基本思考のひとつであったが、「自由主義史観」側がこれを「自虐史観」と名づけたことによってこの図式がつくりだされた。
この間、1965年には家永三郎氏が「教科書検定訴訟」(「教科書裁判」と略称)を提起し、これに対する日本史研究者・教育者の強い支持運動が広い範囲に起こされた。国の行う検定が、教科書記述の細部にまで干渉して学問・思想・教育の自由を犯す危険、本来政治・権力から独立して行われるべき教育の内面にまで介入する国家の教育支配の危険を眼前にして、戦前型の教育への回帰は何としても阻止しなくてはならないというのが、広く共通する受けとめ方であった。
この「教科書裁判」はじつに32年にわたって、原告家永氏とこれを支援する歴史学・法律学・教育学などの数多くの研究者・教育者・弁護士。市民などの良心をかけた戦いとして最高裁まで争われ、重要な幾つかの争点について、原告の主張が認められた。この長い裁判期間中に、教科書の改訂は国の規定に従っていくたびも行われたが、多くの日本史教科書は「南京大虐殺」「七三一部隊」「従軍慰安婦」など、戦争犯罪の重要な事実を逐次、新たに取り上げるようになった。これに対して一部の保守党政治家や財界人などが「教科書に暗いことばかり書くな、国を愛する心が育つような教科書を」という声をだんだん大きくするようになった。
「暗い」といわれるものは、教科書筆者やそれに共感する人々の側から言えば、おおむねこれまで隠蔽されたり研究が至らなかったりして取り上げられてこなかった事実であって、戦争というものの本質や、日本の戦争責任・平和にかかわる重要な問題である。だからこそそれらは次代の記憶に残さなくてはならない、と考えたのである。
この両者の乖離と対立は、70年代末から80年代初めにかけていっそう厳しい状況を生み出してゆく。
2. 80年代、国際的圧力に屈した反動勢力
70年代は歴史認識の二極分化がはっきりとしはじめた時期であるが、中・高校用日本史教科書の内容は筆者・編集者等の努力と市民の関心の高まりによって、検定による歪曲をはねかえし改善が進んだ。「暗い」「自虐的」と攻撃する側から見ればいちだんと「悪く」なったということにもなろう。
70年代の終わりころから80年代初めにかけて、これに危機感をもった自民党は機関紙『自由新報』などに関連記事を連載し、大々的な教科書攻撃を始めた。政権を担当する政党が、教育の内面(教科書等)にまでなりふりかまわず踏み込んですでに検定済みとなっている教科書やその筆者への非難・攻撃を行うというのは異常である。
しかし、文部省(当時)はこれに力を得て、81~82年の「現代社会」(新設)や「歴史」の教科書の検定では、有名な「侵略-進出問題」からもうかがえるように、史実の正確性をねじまげても「暗い」記述をおさえこもうとする強硬姿勢をとった。
これに対して、教科書筆者はもとより、マスコミも共通に批判の姿勢を強めた。そうした中で82年、中国・韓国をはじめとするアジア諸国からの抗議の声も厳しくあげられた。歴史的事実を隠したり歪曲したりすることは有効と交流の基礎を破壊するものだというのがその趣旨である。保守党政治家の中には「内政干渉ではないか」と反発する人もいた。政府と文部省(当時)は陳弁をつづけたが、結局、検定基準に「近隣諸国への配慮」という一項を加え、以後、「侵略」の文字を使わせないとか侵略行為や戦争犯罪の事実を隠蔽したりねじまげるような検定強制はしないという譲歩を行ってひとまず落着した。
しかしこれは日本の為政者たちが国家権力による教育の内面への介入や、いわゆる「暗い」諸事実の隠蔽をほんとうに誤りとして認めたことを必ずしも意味しない。「近隣食への配慮」という言葉自体がそれを示唆するように、本音は別だが、ひとまず譲る、ということにほかならなかった。
86年には「日本を守る国民会議」という改憲派民族主義グループが『新編日本史』という教科書(高校用)を編集・発行した。そこでは、
(1)日本の伝統文化の流れと特色を重視する
(2)天皇に関する歴史的記述を充実する
(3)国家として自主独立の精神が大切であることを理解させる
(4)古代史については神話を通じて古代人の思想を明らかにする
(5)近現代については、戦争に関わる記述を極力客観的なものにする
(=日本だけが悪いのではないということをはっきりさせる、という意)
…と編集の狙いを説明している。
これだけ(つまり、「編集のねらい」だけ)を見ると国家主義的だが、複数の検定教科書のなかのひとつとしては許容の範囲内ではないかという感じもある(筆者の「感じ」)。しかしその実際の記述は、史実を無視ないし歪曲をしていて、筆者たちの独断的な考え方があまりにも露骨だった。そのため『新編日本史』は教育現場でごくわずかしか採用されず、いくばくもなく事実上消滅した。
この『新編日本史』の編集方針は、明言されているわけではないが、西尾幹二氏の『国民の歴史』にそっくり引き継がれた。90年代の「自由主義史観」グループは80年代の「日本を守る国民会議」の主張をそのまま継承したと考えるべきところが多い。この点は「自由主義史観」の背景や根強い底流を確認するためにも重要である。
こう見ると80年代には教科書検定に対する国際的批判、日本政府の一定の譲歩があったにもかかわらず、国家主義的日本史観がいっそう根をはりだしたという側面も見逃せない。すでに70年代以降、戦争・敗戦を体験した戦後の第一世代の退場が始まり、「暗い」過去を知らない「経済大国」世代が世の中の主役に上がってきており、
「いつまで戦争責任や戦争犯罪をしつこく問題にするのか」
「『謝罪外交』のくりかえしはもうたくさんだ」
「われわれ(戦争・敗戦不体験世代)には責任はない」
…といった国民感情が次第に強まってきた。
個人に責任がないことでも国家・社会全体としては負わなければならない、というそんな種類の責任もある、ということを理屈の上では認める人でも、戦後に形づくられた自国史像のままでは何となく納得できないという気持ちを強めるようにもなっていった。学会でもこれに応ずるような形で前記のような “日本史再考” の試みが活発になった。農民闘争や労働運動への関心を失い、民衆の暮らしや経済・社会を明るく描く歴史書が人々の心をとらえだした。
「自由主義史観」は、「日本を守る国民会議」と同じ発想、論法、同根のものであるが、『新編日本史』の失敗を経て、われわれは「大東亜戦争肯定派」ではないといいながら、よりソフトなネーミングで “再考” 気流に乗って90年代に登場するのである。
3. 90年代、国民統合への不安とあせり
80年代後半から90年代にかけての世界史は激動をきわめた。ベルリンの壁が解体され、東欧諸国の社会主義体制に終止符が打たれ、91年、ソ連が崩壊した。この間に、日本はいわゆるバブル景気にわいたが、91年初めに株価・地価の暴落が始まり、経済界は泥沼の長期低迷に追い込まれた。それを横目に見るかのように、中国・韓国・ベトナム・マレーシア・タイなどのアジア諸国は経済の飛躍的発展期にはいった。
90年代初頭は20世紀の世界史を動かしつづけてきたソ連が消滅し、「冷戦」が終わったという点で、21世紀に向けての新しい歴史が動きはじめた時期といえる。しかし日本はバブル崩壊の痛手から立ち直れず、ついには金融危機、外国資本の日本企業買収、生き延びるための大リストラといった窮地に追い込まれた。
大企業の経営者たちが危機感を強め、生きのび作戦を模索し、政府は将来の国民負担をかえりみず国家資金をそれら企業の救済につぎこんでいる。90年代の日本と日本人は自信を喪失し、暗い気持ちに追い込まれている。社会面では、官・財界上層から警察官に至るまで腐敗・汚職が広まり、教育界でも問題続発である。大学生や世に出た若年世代は政治や社会への主体的関心が薄く、「私」の世界に生きがいを見いだし、「公」への目を喪失したかのようである。戦後教育の失敗がきびしく指摘されるようになった。
為政者の動揺と焦燥は深刻で、指導要綱では「国を愛する心」を強調し、カリキュラムでは「総合学習」を新設して社会・「公」への目ざめを促そうとしている。ここにきて文部省(当時)が長年にわたって「平和教育」や教育基本法に明記されている「政治的教養」のための教育を抑制してきたツケ(池田・ロバートソン会談の方針に則ってきたツケ)がどうにもならないところまで来たようである。(*)
(*)
旧教育基本法
第8条1項
良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
〃 2項
法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
「自由主義史観」グループはこうした状況に対応する形で登場した。その前提は、すでに述べてきたように、高度成長による「経済大国」化、日本社会の構造変化の中で進められてきた自国史像の “見直し” 、“再考” 気流の中に胚胎していた。それが90年代日本の経済的低迷と社会的意識における「公」の喪失という危機的状況の中で、登場を促されてきたのである。
こう見てくると、今の日本には1930年代と通底するものがあるのではないかという不吉な予感を否定することができない。昨99年(このブックレットは2000年発行)5月には安保体制=対米軍事従属の拡大を意味するガイドライン関連法が成立し、8月には国旗国歌法が成立した。日本のナショナリズムが対米軍事従属とセットで存続してきた戦後の歴史をふりかえると、このふたつの法がほとんど同時に成立した意味も見えてくる。国会の憲法調査会も改憲を意中にした与党中心に推進されはじめた。
それにつづく99年10月、西尾幹二氏の『国民の歴史』が刊行されたが、その基調は、これまでに見られなかったアメリカ非難をも辞さない独善的ナショナリズムである。「大東亜戦争」における開戦責任の「6~7割」はアメリカ側にある、日本がほんとうに敗れたのは「戦後の戦争」だ、という。「戦後の戦争」とは、日本人の常識化している「太平洋戦争」観や、それをふくむ近現代日本史像はアメリカ中心の見かたのおしつけであり、それが日本史教科書にも強烈な影響を与えている、これこそ戦後の情報戦争における日本の敗北でありアメリカの勝利を物語るものだ、というのである。
(「自由仕儀史観批判」/ 永原慶二・著)
↓(下)へつづく
歴史の恥部を隠蔽しようとするこの圧力はどこから出てくるのでしょうか。なぜ、本土のわたしたちは、こういうことを脅威と見なさず、醒めた目でしか眺めないのでしょうか。歴史を粉飾しようとする空気はどのようにわたしたち本土の国民に浸透したのか、その事情の根元を垣間見せる文献を見つけたので、今回はこれをご紹介します。どうやらおおもとは、アメリカによる対ソ戦略にあったようです。
------------------------
1.池田ロバートソン会談
敗戦の1945年から50年代にかけての戦後期の国民の平均的な歴史認識は、戦争とその敗北の根本原因は、結局日本の社会が全体としてまだ「『半封建制』性」「封建遺制」を克服しえていなかった後進性にあり、経済力・技術の劣勢も、戦争での軍部の独走や天皇制的な人命軽視・人権言論抑圧もすべてその社会的後進性に根を持っている、といったものだったと述べてよい。
国民が戦後の民主主義的改革を受け入れたのも、占領政策としてただおしつけられたからではなく、生活実感にもとづく国民意識がそれを必要と考えていたからである。学問・思想の分野で、マルクス主義や近代主義(*)が大きな信頼を受けたのも、その言説が、敗戦を見つめ、自国の社会改革、「近代化」を自分たちの力で進めなくてはならない、と考える人々の心に響くものがあったからである。
(*)近代主義
ヨーロッパの近代社会を「近代」という理念のモデルとして設定し、そのモデルによって日本の近代社会を批判し、日本の「近代」の後進性を浮き彫りにし、ヨーロッパ的な「近代」社会へ向けて以下に純化発展させてゆくか、ということをテーマに掲げた思想潮流。大塚久雄、丸山真男、川島武宜氏らが代表的。
この時代、多数の日本人の意識はそうした面では自省的で、アジア・太平洋戦争についても、日本の中国侵略が基本原因だという理解を共有していた。
しかし、1948年からいちはやく表面化した米ソ冷戦の激化の中で、占領政策が急激に転換されたため(*)、侵略戦争についての反省は曖昧にされ、多くは戦争被害者的記憶や戦争はこりごりといった心情だけにとどまり、アジアの民衆に対する加害者的側面についての認識は、「事実的」の面でも「理論的」の面でも深められることなく、反動的な状況に押し流されてゆく傾向が強まった。
(*)
1953年、吉田首相特使、池田勇人と米国務次官補ロバートソンの間でのMSA(相互安全保障条約)をめぐる日米会談が設けられた。文字通りに「池田・ロバートソン会談」と呼称されている。
これによって日本は事実上の再軍備に踏み切らされたが、その「防衛力漸増政策の遂行に妨げになる空気を除去するように、教育を通じて日本の国民意識を誘導する」ことが決められた。
これを転機に教育は反動的旋回を始め、「憂うべき教科書の問題」(1955年、「日本民主党」による、当時の自省的歴史教科書への非難・攻撃したパンフレット)が発行され、文部省(当時)による教科書検定(組織・内容)強化が進められだした。
こうした国民意識の旋回に強い影響をもたらしたのは1960年代の高度経済成長である。60年代を通じて進行したその動きの中で、日本は先進国のひとつとなり、「経済大国」といわれるようになった。それによって「半封建的後進性」は克服された、明治以来の、「欧米に追いつけ追い越せ」の目標は達成された、と多くの人が心に感じるようになった。アジアの途上国からの留学生には、日本の成功は自分たちのこれからのモデルになる、と思う人も多くなった。アメリカの日本史学者は、日本の「成功」の要因を江戸時代までを含めてとらえる「近代化論」(*)を提起した。
(*)
近代化論;
マルクス主義史観(資本主義から社会主義へ、という発展・移行・革命理論)に対し、資本主義の後進国における近代化の可能性を「離陸」「産業化」という概念をキーワードとして理論化しようとして1950年代にアメリカの学者ロストウが提唱した経済発展理論が原型。社会主義革命を相対化し、ソ連の路線に対抗するという政治性が強い。ライシャワーはそれらを背景に、日本の「近代化」の条件を江戸時代の見直しから始め、60年代には日本の歴史学会にもその影響が広まった。
60年代の終わりから70年代にかけて「戦後歴史学」への批判的検討が盛んになり、さまざまの角度からの “日本史再考” (*)が盛んになった。「戦後民主主義」や「戦後歴史学」が批判的検討の対象になったということは、時代が移ったということを意味している。その中で戦後の国民意識を広くとらえてきた(自省的な)歴史認識は揺らぎだし、歴史学でも “多様化” の時代に入った。「太平洋戦争見直し論」も、また性質はちがうが「社会史」も、そのひとつとして登場した。
(*)
日本史再考;
戦後、60年代初頭ころまでに、マルクス主義と近代主義(前出)の歴史学の主導によって展開された「戦後歴史学」の日本史認識・日本史像への批判を意図して、さまざまの立場からその見直しが開始され、60年代後半から70年代にさかんとなった。
一律にはいえないが、中世・近世については、領主-農民の封建的支配被支配関係と、階級的矛盾からその社会の基本構造をとらえるマルクス歴史学理論の視角を拒否して、民衆生活の明るさ、経済的水準の高さを強調する説もそのひとつである。
近現代史では、講座派(日本の支配構造を絶対主義的天皇制、地主的土地所有、独占資本主義の三者によって分析する歴史学。野呂栄太郎『日本資本主義発達史講座』によって打ち出された)がその制約的側面を重視してきた明治維新の理解やそれをふまえた日本資本主義特質論の見直しなどがそれである。
アジア諸民族を解放したという見解に結びつけようとする「大東亜戦争」見直し論もそうした一連の動向の中で登場した。
一方、「戦後民主主義」の再検討とともに、太平洋戦争における日本の加害者的側面が本格的に検討されるようになり、それに関わる事実の発掘と意味を問う仕事も盛んになった。日本の台湾・朝鮮植民地支配の実態、アジア太平洋戦争における戦争犯罪的諸事実の解明などがその代表的なテーマである。併行して沖縄・アイヌなど本土から差別されがちであった弱者・マイノリティの史的研究も急速に進められていった。
こうして日本歴史への関心と研究が二極分化の色合いを濃くしてゆく。
ひとつは「近代の達成」を楽天的に受けとめ、「日本の成功と自信」を歴史の中に求め、それを明るく描こうとする方向である。もうひとつは、とくに日本の近現代史に忘れることのできない、また忘れてはならないさまざまの「負」の側面の認識を深めることを通じて歴史の展開と課題を見きわめようとする方向である。前者を東京大学教育学教授の藤岡信勝氏と西尾幹二・電気通信大学文学部教授は「自由主義史観」と名づけ、それに対照して後者を「自虐史観」と称し、ここに両者の対立構図が現れた。
ただし、「自虐史観」はこの時点で新たに登場したものでなく、戦後歴史学の一貫した基本思考のひとつであったが、「自由主義史観」側がこれを「自虐史観」と名づけたことによってこの図式がつくりだされた。
この間、1965年には家永三郎氏が「教科書検定訴訟」(「教科書裁判」と略称)を提起し、これに対する日本史研究者・教育者の強い支持運動が広い範囲に起こされた。国の行う検定が、教科書記述の細部にまで干渉して学問・思想・教育の自由を犯す危険、本来政治・権力から独立して行われるべき教育の内面にまで介入する国家の教育支配の危険を眼前にして、戦前型の教育への回帰は何としても阻止しなくてはならないというのが、広く共通する受けとめ方であった。
この「教科書裁判」はじつに32年にわたって、原告家永氏とこれを支援する歴史学・法律学・教育学などの数多くの研究者・教育者・弁護士。市民などの良心をかけた戦いとして最高裁まで争われ、重要な幾つかの争点について、原告の主張が認められた。この長い裁判期間中に、教科書の改訂は国の規定に従っていくたびも行われたが、多くの日本史教科書は「南京大虐殺」「七三一部隊」「従軍慰安婦」など、戦争犯罪の重要な事実を逐次、新たに取り上げるようになった。これに対して一部の保守党政治家や財界人などが「教科書に暗いことばかり書くな、国を愛する心が育つような教科書を」という声をだんだん大きくするようになった。
「暗い」といわれるものは、教科書筆者やそれに共感する人々の側から言えば、おおむねこれまで隠蔽されたり研究が至らなかったりして取り上げられてこなかった事実であって、戦争というものの本質や、日本の戦争責任・平和にかかわる重要な問題である。だからこそそれらは次代の記憶に残さなくてはならない、と考えたのである。
この両者の乖離と対立は、70年代末から80年代初めにかけていっそう厳しい状況を生み出してゆく。
2. 80年代、国際的圧力に屈した反動勢力
70年代は歴史認識の二極分化がはっきりとしはじめた時期であるが、中・高校用日本史教科書の内容は筆者・編集者等の努力と市民の関心の高まりによって、検定による歪曲をはねかえし改善が進んだ。「暗い」「自虐的」と攻撃する側から見ればいちだんと「悪く」なったということにもなろう。
70年代の終わりころから80年代初めにかけて、これに危機感をもった自民党は機関紙『自由新報』などに関連記事を連載し、大々的な教科書攻撃を始めた。政権を担当する政党が、教育の内面(教科書等)にまでなりふりかまわず踏み込んですでに検定済みとなっている教科書やその筆者への非難・攻撃を行うというのは異常である。
しかし、文部省(当時)はこれに力を得て、81~82年の「現代社会」(新設)や「歴史」の教科書の検定では、有名な「侵略-進出問題」からもうかがえるように、史実の正確性をねじまげても「暗い」記述をおさえこもうとする強硬姿勢をとった。
これに対して、教科書筆者はもとより、マスコミも共通に批判の姿勢を強めた。そうした中で82年、中国・韓国をはじめとするアジア諸国からの抗議の声も厳しくあげられた。歴史的事実を隠したり歪曲したりすることは有効と交流の基礎を破壊するものだというのがその趣旨である。保守党政治家の中には「内政干渉ではないか」と反発する人もいた。政府と文部省(当時)は陳弁をつづけたが、結局、検定基準に「近隣諸国への配慮」という一項を加え、以後、「侵略」の文字を使わせないとか侵略行為や戦争犯罪の事実を隠蔽したりねじまげるような検定強制はしないという譲歩を行ってひとまず落着した。
しかしこれは日本の為政者たちが国家権力による教育の内面への介入や、いわゆる「暗い」諸事実の隠蔽をほんとうに誤りとして認めたことを必ずしも意味しない。「近隣食への配慮」という言葉自体がそれを示唆するように、本音は別だが、ひとまず譲る、ということにほかならなかった。
86年には「日本を守る国民会議」という改憲派民族主義グループが『新編日本史』という教科書(高校用)を編集・発行した。そこでは、
(1)日本の伝統文化の流れと特色を重視する
(2)天皇に関する歴史的記述を充実する
(3)国家として自主独立の精神が大切であることを理解させる
(4)古代史については神話を通じて古代人の思想を明らかにする
(5)近現代については、戦争に関わる記述を極力客観的なものにする
(=日本だけが悪いのではないということをはっきりさせる、という意)
…と編集の狙いを説明している。
これだけ(つまり、「編集のねらい」だけ)を見ると国家主義的だが、複数の検定教科書のなかのひとつとしては許容の範囲内ではないかという感じもある(筆者の「感じ」)。しかしその実際の記述は、史実を無視ないし歪曲をしていて、筆者たちの独断的な考え方があまりにも露骨だった。そのため『新編日本史』は教育現場でごくわずかしか採用されず、いくばくもなく事実上消滅した。
この『新編日本史』の編集方針は、明言されているわけではないが、西尾幹二氏の『国民の歴史』にそっくり引き継がれた。90年代の「自由主義史観」グループは80年代の「日本を守る国民会議」の主張をそのまま継承したと考えるべきところが多い。この点は「自由主義史観」の背景や根強い底流を確認するためにも重要である。
こう見ると80年代には教科書検定に対する国際的批判、日本政府の一定の譲歩があったにもかかわらず、国家主義的日本史観がいっそう根をはりだしたという側面も見逃せない。すでに70年代以降、戦争・敗戦を体験した戦後の第一世代の退場が始まり、「暗い」過去を知らない「経済大国」世代が世の中の主役に上がってきており、
「いつまで戦争責任や戦争犯罪をしつこく問題にするのか」
「『謝罪外交』のくりかえしはもうたくさんだ」
「われわれ(戦争・敗戦不体験世代)には責任はない」
…といった国民感情が次第に強まってきた。
個人に責任がないことでも国家・社会全体としては負わなければならない、というそんな種類の責任もある、ということを理屈の上では認める人でも、戦後に形づくられた自国史像のままでは何となく納得できないという気持ちを強めるようにもなっていった。学会でもこれに応ずるような形で前記のような “日本史再考” の試みが活発になった。農民闘争や労働運動への関心を失い、民衆の暮らしや経済・社会を明るく描く歴史書が人々の心をとらえだした。
「自由主義史観」は、「日本を守る国民会議」と同じ発想、論法、同根のものであるが、『新編日本史』の失敗を経て、われわれは「大東亜戦争肯定派」ではないといいながら、よりソフトなネーミングで “再考” 気流に乗って90年代に登場するのである。
3. 90年代、国民統合への不安とあせり
80年代後半から90年代にかけての世界史は激動をきわめた。ベルリンの壁が解体され、東欧諸国の社会主義体制に終止符が打たれ、91年、ソ連が崩壊した。この間に、日本はいわゆるバブル景気にわいたが、91年初めに株価・地価の暴落が始まり、経済界は泥沼の長期低迷に追い込まれた。それを横目に見るかのように、中国・韓国・ベトナム・マレーシア・タイなどのアジア諸国は経済の飛躍的発展期にはいった。
90年代初頭は20世紀の世界史を動かしつづけてきたソ連が消滅し、「冷戦」が終わったという点で、21世紀に向けての新しい歴史が動きはじめた時期といえる。しかし日本はバブル崩壊の痛手から立ち直れず、ついには金融危機、外国資本の日本企業買収、生き延びるための大リストラといった窮地に追い込まれた。
大企業の経営者たちが危機感を強め、生きのび作戦を模索し、政府は将来の国民負担をかえりみず国家資金をそれら企業の救済につぎこんでいる。90年代の日本と日本人は自信を喪失し、暗い気持ちに追い込まれている。社会面では、官・財界上層から警察官に至るまで腐敗・汚職が広まり、教育界でも問題続発である。大学生や世に出た若年世代は政治や社会への主体的関心が薄く、「私」の世界に生きがいを見いだし、「公」への目を喪失したかのようである。戦後教育の失敗がきびしく指摘されるようになった。
為政者の動揺と焦燥は深刻で、指導要綱では「国を愛する心」を強調し、カリキュラムでは「総合学習」を新設して社会・「公」への目ざめを促そうとしている。ここにきて文部省(当時)が長年にわたって「平和教育」や教育基本法に明記されている「政治的教養」のための教育を抑制してきたツケ(池田・ロバートソン会談の方針に則ってきたツケ)がどうにもならないところまで来たようである。(*)
(*)
旧教育基本法
第8条1項
良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
〃 2項
法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
「自由主義史観」グループはこうした状況に対応する形で登場した。その前提は、すでに述べてきたように、高度成長による「経済大国」化、日本社会の構造変化の中で進められてきた自国史像の “見直し” 、“再考” 気流の中に胚胎していた。それが90年代日本の経済的低迷と社会的意識における「公」の喪失という危機的状況の中で、登場を促されてきたのである。
こう見てくると、今の日本には1930年代と通底するものがあるのではないかという不吉な予感を否定することができない。昨99年(このブックレットは2000年発行)5月には安保体制=対米軍事従属の拡大を意味するガイドライン関連法が成立し、8月には国旗国歌法が成立した。日本のナショナリズムが対米軍事従属とセットで存続してきた戦後の歴史をふりかえると、このふたつの法がほとんど同時に成立した意味も見えてくる。国会の憲法調査会も改憲を意中にした与党中心に推進されはじめた。
それにつづく99年10月、西尾幹二氏の『国民の歴史』が刊行されたが、その基調は、これまでに見られなかったアメリカ非難をも辞さない独善的ナショナリズムである。「大東亜戦争」における開戦責任の「6~7割」はアメリカ側にある、日本がほんとうに敗れたのは「戦後の戦争」だ、という。「戦後の戦争」とは、日本人の常識化している「太平洋戦争」観や、それをふくむ近現代日本史像はアメリカ中心の見かたのおしつけであり、それが日本史教科書にも強烈な影響を与えている、これこそ戦後の情報戦争における日本の敗北でありアメリカの勝利を物語るものだ、というのである。
(「自由仕儀史観批判」/ 永原慶二・著)
↓(下)へつづく














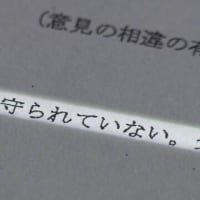
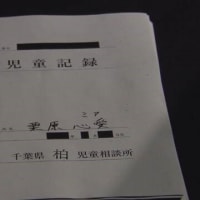







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます