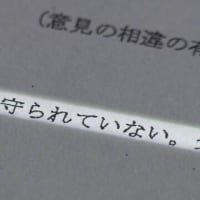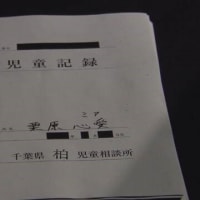ロシア、アメリカが日本に来航するようになった時期に幕政を担っていたのは、老中阿部正弘。開明的な人で、それまで徳川一門で行っていた幕政を改め、雄藩外様大名との強調を進めました。雄藩大名たちもこの機会を逃さず、幕政に食い込んでいこうと企てるようになり、薩摩藩主島津斉彬(なりあきら)は自分の養女篤姫を時の将軍家定の夫人として送り込むことに成功しましたが、それも阿部正弘の協力があったのです。
ヨーロッパの歴史では、封建制は諸荘園領主の割拠から国王に富と権力が集中する絶対王政へと移行するようになり、商業が十分発達するようになると、封建制が崩されてゆきました。自由に商業を行うためには、封建制のような、土地と交通を封建領主が一手に掌握するような社会の仕組みが邪魔になります。ある封建的土地所有者の領地から別の封建的土地所有者の領地へと移動するのに、いちいち関税を支払っていたのでは、高くつきます。ですから商売人たちは「自由」を求めて戦ったのでした。彼らが求めた自由は、私的所有の自由、通行の自由、ギルドなどの地元の職人組合による独占からの自由などです。自由と民主主義はもともとは資本主義の発達によって主張され、闘い取られてきたイデオロギーだったのです。
日本でも、資本主義は芽を吹き始めていました。徳川施政は各藩の経済力が幕府を圧倒しないように、参勤交代という制度を設けて、各藩にたくさんのお金を出費させていました。また、身分位階制度を徹底させることによって、武士が農業に携わることのないようにし、農業と農村から武士を切り離して、城下町に住まわせて統制しました。ところがこの身分位階制と参勤交代という制度が、逆に商業を発達させる原因になったのです。武士たちは農工業生産を行わないので、農民から農産物を年貢として取立て、それを貨幣に換え、その貨幣で必要な物資を買い入れる必要が生じたのです。これが社会的分業を生じさせ、封建制とは相容れない商品経済の必要性を、幕府の考えの及ばないところで生じさせたのでした。
幕末には、幕府の経済は疲弊しきっていましたが、薩摩藩のような先見性の高い藩は、琉球を隠れ蓑とした外国との密貿易や、大坂を通らない日本海ルートの開発による商品流通経路の新設などによって、財政を潤すようになっていたのです。そこへアメリカによる開国要求に直面した幕府から、諮問が行われました。幕府は事態に対処するに当たって、協力を要請してきたのです。金持ち藩はこの機会を捉え、幕政に参加しようと企てたのです。その政策の一環として、島津斉彬は阿部正弘の協力を得て、篤姫を将軍家定に嫁入りさせました。将軍家との縁をつくったのです。
さて、阿部正弘率いる幕府からの開国要求にどう対処するか諮問を受けた諸雄藩大名たちは、だいたい三つの意見に分かれました。強硬打ち払い派、戦争を避けようとする消極的開国派、積極的開国派です。島津斉彬は最初に積極的通商派に変わりました。すでに日本全国に大交易網を作り上げていた実績がそうさせたのでしょう。
---------------------------
斉彬はハリス来日のころには、「交易が盛んになり、武備が十分になり、世界中の(つまり欧米列強に比肩できるような)強国」をめざす、と述べる。
改革派の旗頭、越前藩松平慶永(よしなが)も、鎖国し続けることができないのは「具眼のもの、瞭然、我より航海をはじめ、諸州(世界)へ交易に出る」と、日本のほうから海外へ進出する通商意見を上申した。
最後まで打ち払い策を上申した大名は少数で、徳川家門の尾張藩、水戸藩、そして鳥取藩、川越藩の4藩だったといわれている。
しかし、尾張藩は、老中の最後の諮問には、たびたびの諮問の上、「別段のご処置になったので、今更言うべきことはない。日本の難儀が予想される。十全のご処置、ご考慮を」という上申をし、条約承認に妥協する意見を出した。
攘夷論の中心であった水戸藩徳川斉昭(なりあき)すら、条約の勅許が要請されるようになってからは、「いわれなく打ち払いは不可能」という意見を朝廷に送る。「ハリスの無礼の申し立て少なからず、痛憤に堪えず」と言って、条約に批判的だった土佐藩山内豊信(とよしげ)も、翌年には「戦えないという兵」に戦争を求めるのは「無謀」であり、今は条約承認を求める、という意見を朝廷に説くのである。
戦争論も出たのだが、「衆議」を重ねて、条約はやむをえないという、大名の合意が作り出されたというのが、条約承認問題の真相である。それが大名の世論であった。通商条約の是非は、日本の「万民の生命」がかかわる現実の問題であり、尾張藩や土佐藩のような拒絶論、批判論の雄藩も、度重なる諮問の後には「衆議」に加従うのであった。
(「幕末・維新」/ 井上勝生・著)
---------------------------
こうして有力大名たちの合意もおおかたでき上がったところで、安政四年10月にアメリカ駐日総領事タウンゼント・ハリスが江戸城に登城し、将軍家定に謁見したのでした。ハリスは謁見のようすを日記に書き記しています。
---------------------------
1857年12月7日 (安政四年10月21日)
やがて合図があると、信濃守は手をついて、膝行しはじめた。私は半ば右に向かって謁見室へ入っていった。その時、一人の侍従が高声で、「アメリカ使節!」と叫んだ。私は入り口から6尺(約1.8m)ばかりのところで立ち止まって、頭を下げた。それから室のほとんど中央まで進み、再び立ちどまって頭を下げ、又進んで、室の端から10尺(約3m)ばかり、私の右手の備中守と丁度相対するところで停止した。
そこには備中守と、他の5人の閣老とが、顔を向けて平伏していた。私の左手には大君の3人の兄弟が同様に平伏し、そして彼らのいずれも、私の方へ殆ど「真ん向き」になっていた。数秒の後、私は大君に次のような挨拶の言葉をのべた。
「陛下よ、合衆国大統領よりの私の信任状を呈するにあたり、私は陛下の健康と幸福を、また陛下の領土の繁栄を、大統領が切に希望していることを陛下に述べるように命ぜられた。私は陛下の宮廷において、合衆国の全権大使たる高く且つ重い地位を占めるために選ばれたことを、大なる光栄と考える。そして、私の熱誠な願いは、永続的な友誼(ゆうぎ)の紐によって、より親密に両国を結ばんとするにある。よって、その幸福な目的の達成のために、私は不断の努力を注ぐであろう」。
ここで、私は言葉を止めて、そして頭を下げた。短い沈黙ののち、大君は自分の頭を、その左肩をこえて、後方へぐいっと反らしはじめた。同時に右足を踏み鳴らした。これが3,4回くり返された。それから彼は、よく聞こえる、気持ちのよい、しっかりとした声で、次のような意味のことを言った。
「遠方の国から、使節をもって送られた書簡に満足する。同じく、使節の口上に満足する。両国の交際は、永久に続くであろう」。
謁見室の入り口に立っていたヒュースケン君は、このとき大統領の書簡をささげて、三度お辞儀をしながら、前に進んだ。彼が近寄ったとき、外国事務相は起立して、私のそばに寄った。私は箱にかけた絹布の覆紗(ふくさ=袱紗)を取って、それを開いた。そして書簡の被覆(カバー)をあげて、外国事務相がその文書を見ることができるようにした。それから、私はその箱を閉じ、絹の覆紗(6,7条の紅白の縞模様があった)をかけ、そして、それを外国事務相に手渡した。
彼は両手で受け取って、彼よりも少し上座に置かれている美しい漆塗りの盆にそれを載せた。それから彼は再び元のところへ座った。
次いで私は大君の方へ向き直った。大君は丁寧に私にお辞儀をし、これによって謁見の式がおわったことを私に知らせた。私はお辞儀をして後へさがり、停止してお辞儀をし、再び退って、また停止し、またもお辞儀をして、それで終わった。
(「日本滞在記」/ T.ハリス・著)
---------------------------
この日はこうして合衆国大統領の親書を手渡すだけで終わったようです。5日後、ハリスは再び「外国事務相」を訪ねて、通商条約を結びたい合衆国の意図を延々二時間に亘って述べます。12月12日に日記にはこのように記されています。
---------------------------
1857年 12月12日 土曜日 (日本の当時の暦では、安政四年10月26日)
私は、スチーム(蒸気)の利用によって世界の情勢が一変したことを語った。日本は鎖国政策を放棄せねばならなくなるだろう。日本の国民に、その器用さと勤勉さを行使することを許しさえするならば、日本は遠からずして偉大な、強力な国家となるだろう。
貿易に対する適当な課税は、間もなく日本に大きな収益をもたらし、それによって立派な海軍を維持することができるようになろうし、自由な貿易の活動によって日本の資源を開発するならば、莫大な交換価値を示すに至るだろう。この生産は、国民の必要とする食料の生産を少しも阻害するものではなく、日本の現在有する過剰労働などを使用することによって振興するだろう。
日本は屈服するか、然らざれば戦争の惨苦をなめなければならない。戦争が起きないにしても、日本は絶えず外国の大艦隊の来航に脅かされるに違いない。何らかの譲歩をしようとするならば、それは適当な時期にする必要がある。
艦隊の要求するような条件は、私のような地位の者が要求するものよりも、決して温和なものではない。平和の外交使節に対して拒否したものを、艦隊に対して屈服的に譲歩することは、日本の全国民の眼前に政府の威信を失墜し、その力を実際に弱めることになると述べ、この点はシナの場合、すなわち1839年から1841年に至る(阿片)戦争と、その戦争につづいた諸事件、および現在の戦争とを例にとって説明した。
私は外国事務相に、一隻の軍艦をも伴わずして、殊更に単身江戸へ乗り込んできた私と談判をすることは、日本の名誉を救うものであること。問題となる点は、いずれも慎重に討議さるべきこと。日本は漸を追うて開国を行うべきことを説き、これに附随して、次の三つの大きな問題を提出した。
1.江戸に外国の公使を迎えて居住させること。
2.幕府の役人の仲介なしに、自由に日本人と貿易させること。
3.開港場の数を増加させること。
私は更に、アメリカ人だけの特権を要求するものではなく、アメリカ大統領の満足するような条約ならば、西洋の諸大国はみな直ちに承認するだろうと附言した。
私は、外国が日本に阿片の押し売りをする危険があることを強く指摘した。そして私は、日本に阿片を持ち込むことを禁ずるようにしたいと述べた。
私の使命は、あらゆる点で友好的なものであること。私は一切の威嚇を用いないこと。大統領は単に、日本を脅かしている危険を日本人に知らせて、それらの危険を回避することができるようにするとともに、日本を繁栄な、強力な、幸福な国にするところの方法を指示するものであることを説いて、私の言葉を終わった。
私の演説は二時間以上におよんだ。外国事務相は深い注意と関心をもって傾聴した。そして、私の言うところを十分了解できぬときには、度々質問を発した。私の演説が終わったとき、外国事務相は私の通報に感謝し、これを大君(たいくん:徳川将軍のこと)に伝達し、然るべく考慮することにすると述べ、これは、これまで幕府にもたらされた問題の中で最も重大なものであると語った。
外国事務相は、これに附言して、日本人は重要な用務をアメリカ人のように迅速に処理することなく、大勢の人々に相談しなければならぬことになっているから、これらの目的のために十分な時日を与えてもらわねばならぬと述べた。これは万事延引を事とする日本人のやりかたを私に諒承させんがためであった。
私は、私の述べた一切の事について、十分な考慮を彼らに希望し、そして、質問されることがあるならば、どんな事でも喜んで詳細の説明をしようと答えた。
外国事務相は親切に私の健康をたずね、私の病気に対し篤く遺憾の意を表した。例のように茶菓のもてなしがあって、私は4時ごろ宿所へ帰った。
(「日本滞在記」/ タウンゼント・ハリス・著)
---------------------------
通商条約の草案作りの実務交渉は和暦安政四年12月11日から開始されました。この内容もハリスは日記に書き記しています。この内容についてはまた別の機会に書きます。交渉が始まった日の翌日、日本側の全権委員であった岩瀬忠震(ただなり)と井上清直は二人の連名で上申書を老中に提出しています。
---------------------------
「天下の大事」は「天下と共に」議論し「同心一致」の力を尽くし、末々にいたるまで異論がないように「衆議一定」で「国是」を定めるべきである。そのために将軍が臨席し、御三家・譜代・外様の諸大名を召し出して、「隔意」なく「評論」をいたさせた上で「一決」する。ここで議決されたものを、速やかに天皇に奏聞し天皇の許可を得た上で天下に令する。
(「大日本古文書 幕末外国関係文書」18)
この文書で、もっとも注目すべき点は、日本国家における天皇の位置・政治的役割が明快に示されていることである。国家の最高基本方針である「国是」を、まず武家の衆議で「一決(多数決ではなく近世的慣行である全員合意方式)」し、それを天皇に報告し、天皇が朝廷に諮り、その上で勅許を得て、さらにそれを天下に布告すべし、という意見である。
通商条約を結ぶこと(開国)は、単に幕府の鎖国の法を改めるのではなく、新しく国是を定めることである、という解釈である。したがってその新たな国是は、将軍ではなく、天皇が全国に布告するものであるべきだ、という主張であった。この意見だけでは、天皇と将軍、朝廷と幕府との、政治的位置関係が見えてこないが、天皇の政治的役割をはっきりと示した点において、画期的な主張であった。
この上申に対して老中がどのような意見を述べたのか、よくわからない。
しかしこの後、明けて安政5年正月5日に、幕府がハリスに、天皇・朝廷の承認を得てから通商条約に調印する運びにしたいことを告げ、老中堀田備中守正睦(まさよし)が21日に上京の途についたのは、幕府首脳部が上申の趣旨を受け止めたものであったことを示している。堀田は2月5日に京都に着く。彼自身は天皇と朝廷の承認を得ることは可能だと見通していた。
(「幕末の天皇・明治の天皇」/ 佐々木克・著)
---------------------------
幕府にとって天皇や朝廷は法的には「下」にあるものでした。幕府は摂政や朝廷を通して天皇を監視し、封圧していたのです。しかし、いざ「国是」の大改定を前にすると、天皇という古代の権威を借りようとするのでした。征夷大将軍の承認は天皇が行っていたので、深層意識では、天皇という制度について、神がかり的な認識は受け継がれてきたのでしょう。
しかし、幕閣の説得や工作にもかかわらず、孝明天皇は拒絶し、戦争をも辞さない決意を表明するのです。そしてこのときに孝明天皇が持ち出したのが「万王一系」という概念でした。いうまでもなく、明治時代になって「万世一系」と呼ばれた考え方です。これは天皇家に代々伝わる神国思想でした。長い間幕府に封圧されていた天皇が幕末にその存在を顕示するようになります。そして天皇のこういう神国思想は、国学を重んじていた井伊直弼が大老に就任したときに、勢力を得、大名が参画し始めた幕政に粛清を生むのです。再び徳川宗家による幕政を取り戻そうという反動勢力が席巻するようになるのでした。
以下、続きます。
ヨーロッパの歴史では、封建制は諸荘園領主の割拠から国王に富と権力が集中する絶対王政へと移行するようになり、商業が十分発達するようになると、封建制が崩されてゆきました。自由に商業を行うためには、封建制のような、土地と交通を封建領主が一手に掌握するような社会の仕組みが邪魔になります。ある封建的土地所有者の領地から別の封建的土地所有者の領地へと移動するのに、いちいち関税を支払っていたのでは、高くつきます。ですから商売人たちは「自由」を求めて戦ったのでした。彼らが求めた自由は、私的所有の自由、通行の自由、ギルドなどの地元の職人組合による独占からの自由などです。自由と民主主義はもともとは資本主義の発達によって主張され、闘い取られてきたイデオロギーだったのです。
日本でも、資本主義は芽を吹き始めていました。徳川施政は各藩の経済力が幕府を圧倒しないように、参勤交代という制度を設けて、各藩にたくさんのお金を出費させていました。また、身分位階制度を徹底させることによって、武士が農業に携わることのないようにし、農業と農村から武士を切り離して、城下町に住まわせて統制しました。ところがこの身分位階制と参勤交代という制度が、逆に商業を発達させる原因になったのです。武士たちは農工業生産を行わないので、農民から農産物を年貢として取立て、それを貨幣に換え、その貨幣で必要な物資を買い入れる必要が生じたのです。これが社会的分業を生じさせ、封建制とは相容れない商品経済の必要性を、幕府の考えの及ばないところで生じさせたのでした。
幕末には、幕府の経済は疲弊しきっていましたが、薩摩藩のような先見性の高い藩は、琉球を隠れ蓑とした外国との密貿易や、大坂を通らない日本海ルートの開発による商品流通経路の新設などによって、財政を潤すようになっていたのです。そこへアメリカによる開国要求に直面した幕府から、諮問が行われました。幕府は事態に対処するに当たって、協力を要請してきたのです。金持ち藩はこの機会を捉え、幕政に参加しようと企てたのです。その政策の一環として、島津斉彬は阿部正弘の協力を得て、篤姫を将軍家定に嫁入りさせました。将軍家との縁をつくったのです。
さて、阿部正弘率いる幕府からの開国要求にどう対処するか諮問を受けた諸雄藩大名たちは、だいたい三つの意見に分かれました。強硬打ち払い派、戦争を避けようとする消極的開国派、積極的開国派です。島津斉彬は最初に積極的通商派に変わりました。すでに日本全国に大交易網を作り上げていた実績がそうさせたのでしょう。
---------------------------
斉彬はハリス来日のころには、「交易が盛んになり、武備が十分になり、世界中の(つまり欧米列強に比肩できるような)強国」をめざす、と述べる。
改革派の旗頭、越前藩松平慶永(よしなが)も、鎖国し続けることができないのは「具眼のもの、瞭然、我より航海をはじめ、諸州(世界)へ交易に出る」と、日本のほうから海外へ進出する通商意見を上申した。
最後まで打ち払い策を上申した大名は少数で、徳川家門の尾張藩、水戸藩、そして鳥取藩、川越藩の4藩だったといわれている。
しかし、尾張藩は、老中の最後の諮問には、たびたびの諮問の上、「別段のご処置になったので、今更言うべきことはない。日本の難儀が予想される。十全のご処置、ご考慮を」という上申をし、条約承認に妥協する意見を出した。
攘夷論の中心であった水戸藩徳川斉昭(なりあき)すら、条約の勅許が要請されるようになってからは、「いわれなく打ち払いは不可能」という意見を朝廷に送る。「ハリスの無礼の申し立て少なからず、痛憤に堪えず」と言って、条約に批判的だった土佐藩山内豊信(とよしげ)も、翌年には「戦えないという兵」に戦争を求めるのは「無謀」であり、今は条約承認を求める、という意見を朝廷に説くのである。
戦争論も出たのだが、「衆議」を重ねて、条約はやむをえないという、大名の合意が作り出されたというのが、条約承認問題の真相である。それが大名の世論であった。通商条約の是非は、日本の「万民の生命」がかかわる現実の問題であり、尾張藩や土佐藩のような拒絶論、批判論の雄藩も、度重なる諮問の後には「衆議」に加従うのであった。
(「幕末・維新」/ 井上勝生・著)
---------------------------
こうして有力大名たちの合意もおおかたでき上がったところで、安政四年10月にアメリカ駐日総領事タウンゼント・ハリスが江戸城に登城し、将軍家定に謁見したのでした。ハリスは謁見のようすを日記に書き記しています。
---------------------------
1857年12月7日 (安政四年10月21日)
やがて合図があると、信濃守は手をついて、膝行しはじめた。私は半ば右に向かって謁見室へ入っていった。その時、一人の侍従が高声で、「アメリカ使節!」と叫んだ。私は入り口から6尺(約1.8m)ばかりのところで立ち止まって、頭を下げた。それから室のほとんど中央まで進み、再び立ちどまって頭を下げ、又進んで、室の端から10尺(約3m)ばかり、私の右手の備中守と丁度相対するところで停止した。
そこには備中守と、他の5人の閣老とが、顔を向けて平伏していた。私の左手には大君の3人の兄弟が同様に平伏し、そして彼らのいずれも、私の方へ殆ど「真ん向き」になっていた。数秒の後、私は大君に次のような挨拶の言葉をのべた。
「陛下よ、合衆国大統領よりの私の信任状を呈するにあたり、私は陛下の健康と幸福を、また陛下の領土の繁栄を、大統領が切に希望していることを陛下に述べるように命ぜられた。私は陛下の宮廷において、合衆国の全権大使たる高く且つ重い地位を占めるために選ばれたことを、大なる光栄と考える。そして、私の熱誠な願いは、永続的な友誼(ゆうぎ)の紐によって、より親密に両国を結ばんとするにある。よって、その幸福な目的の達成のために、私は不断の努力を注ぐであろう」。
ここで、私は言葉を止めて、そして頭を下げた。短い沈黙ののち、大君は自分の頭を、その左肩をこえて、後方へぐいっと反らしはじめた。同時に右足を踏み鳴らした。これが3,4回くり返された。それから彼は、よく聞こえる、気持ちのよい、しっかりとした声で、次のような意味のことを言った。
「遠方の国から、使節をもって送られた書簡に満足する。同じく、使節の口上に満足する。両国の交際は、永久に続くであろう」。
謁見室の入り口に立っていたヒュースケン君は、このとき大統領の書簡をささげて、三度お辞儀をしながら、前に進んだ。彼が近寄ったとき、外国事務相は起立して、私のそばに寄った。私は箱にかけた絹布の覆紗(ふくさ=袱紗)を取って、それを開いた。そして書簡の被覆(カバー)をあげて、外国事務相がその文書を見ることができるようにした。それから、私はその箱を閉じ、絹の覆紗(6,7条の紅白の縞模様があった)をかけ、そして、それを外国事務相に手渡した。
彼は両手で受け取って、彼よりも少し上座に置かれている美しい漆塗りの盆にそれを載せた。それから彼は再び元のところへ座った。
次いで私は大君の方へ向き直った。大君は丁寧に私にお辞儀をし、これによって謁見の式がおわったことを私に知らせた。私はお辞儀をして後へさがり、停止してお辞儀をし、再び退って、また停止し、またもお辞儀をして、それで終わった。
(「日本滞在記」/ T.ハリス・著)
---------------------------
この日はこうして合衆国大統領の親書を手渡すだけで終わったようです。5日後、ハリスは再び「外国事務相」を訪ねて、通商条約を結びたい合衆国の意図を延々二時間に亘って述べます。12月12日に日記にはこのように記されています。
---------------------------
1857年 12月12日 土曜日 (日本の当時の暦では、安政四年10月26日)
私は、スチーム(蒸気)の利用によって世界の情勢が一変したことを語った。日本は鎖国政策を放棄せねばならなくなるだろう。日本の国民に、その器用さと勤勉さを行使することを許しさえするならば、日本は遠からずして偉大な、強力な国家となるだろう。
貿易に対する適当な課税は、間もなく日本に大きな収益をもたらし、それによって立派な海軍を維持することができるようになろうし、自由な貿易の活動によって日本の資源を開発するならば、莫大な交換価値を示すに至るだろう。この生産は、国民の必要とする食料の生産を少しも阻害するものではなく、日本の現在有する過剰労働などを使用することによって振興するだろう。
日本は屈服するか、然らざれば戦争の惨苦をなめなければならない。戦争が起きないにしても、日本は絶えず外国の大艦隊の来航に脅かされるに違いない。何らかの譲歩をしようとするならば、それは適当な時期にする必要がある。
艦隊の要求するような条件は、私のような地位の者が要求するものよりも、決して温和なものではない。平和の外交使節に対して拒否したものを、艦隊に対して屈服的に譲歩することは、日本の全国民の眼前に政府の威信を失墜し、その力を実際に弱めることになると述べ、この点はシナの場合、すなわち1839年から1841年に至る(阿片)戦争と、その戦争につづいた諸事件、および現在の戦争とを例にとって説明した。
私は外国事務相に、一隻の軍艦をも伴わずして、殊更に単身江戸へ乗り込んできた私と談判をすることは、日本の名誉を救うものであること。問題となる点は、いずれも慎重に討議さるべきこと。日本は漸を追うて開国を行うべきことを説き、これに附随して、次の三つの大きな問題を提出した。
1.江戸に外国の公使を迎えて居住させること。
2.幕府の役人の仲介なしに、自由に日本人と貿易させること。
3.開港場の数を増加させること。
私は更に、アメリカ人だけの特権を要求するものではなく、アメリカ大統領の満足するような条約ならば、西洋の諸大国はみな直ちに承認するだろうと附言した。
私は、外国が日本に阿片の押し売りをする危険があることを強く指摘した。そして私は、日本に阿片を持ち込むことを禁ずるようにしたいと述べた。
私の使命は、あらゆる点で友好的なものであること。私は一切の威嚇を用いないこと。大統領は単に、日本を脅かしている危険を日本人に知らせて、それらの危険を回避することができるようにするとともに、日本を繁栄な、強力な、幸福な国にするところの方法を指示するものであることを説いて、私の言葉を終わった。
私の演説は二時間以上におよんだ。外国事務相は深い注意と関心をもって傾聴した。そして、私の言うところを十分了解できぬときには、度々質問を発した。私の演説が終わったとき、外国事務相は私の通報に感謝し、これを大君(たいくん:徳川将軍のこと)に伝達し、然るべく考慮することにすると述べ、これは、これまで幕府にもたらされた問題の中で最も重大なものであると語った。
外国事務相は、これに附言して、日本人は重要な用務をアメリカ人のように迅速に処理することなく、大勢の人々に相談しなければならぬことになっているから、これらの目的のために十分な時日を与えてもらわねばならぬと述べた。これは万事延引を事とする日本人のやりかたを私に諒承させんがためであった。
私は、私の述べた一切の事について、十分な考慮を彼らに希望し、そして、質問されることがあるならば、どんな事でも喜んで詳細の説明をしようと答えた。
外国事務相は親切に私の健康をたずね、私の病気に対し篤く遺憾の意を表した。例のように茶菓のもてなしがあって、私は4時ごろ宿所へ帰った。
(「日本滞在記」/ タウンゼント・ハリス・著)
---------------------------
通商条約の草案作りの実務交渉は和暦安政四年12月11日から開始されました。この内容もハリスは日記に書き記しています。この内容についてはまた別の機会に書きます。交渉が始まった日の翌日、日本側の全権委員であった岩瀬忠震(ただなり)と井上清直は二人の連名で上申書を老中に提出しています。
---------------------------
「天下の大事」は「天下と共に」議論し「同心一致」の力を尽くし、末々にいたるまで異論がないように「衆議一定」で「国是」を定めるべきである。そのために将軍が臨席し、御三家・譜代・外様の諸大名を召し出して、「隔意」なく「評論」をいたさせた上で「一決」する。ここで議決されたものを、速やかに天皇に奏聞し天皇の許可を得た上で天下に令する。
(「大日本古文書 幕末外国関係文書」18)
この文書で、もっとも注目すべき点は、日本国家における天皇の位置・政治的役割が明快に示されていることである。国家の最高基本方針である「国是」を、まず武家の衆議で「一決(多数決ではなく近世的慣行である全員合意方式)」し、それを天皇に報告し、天皇が朝廷に諮り、その上で勅許を得て、さらにそれを天下に布告すべし、という意見である。
通商条約を結ぶこと(開国)は、単に幕府の鎖国の法を改めるのではなく、新しく国是を定めることである、という解釈である。したがってその新たな国是は、将軍ではなく、天皇が全国に布告するものであるべきだ、という主張であった。この意見だけでは、天皇と将軍、朝廷と幕府との、政治的位置関係が見えてこないが、天皇の政治的役割をはっきりと示した点において、画期的な主張であった。
この上申に対して老中がどのような意見を述べたのか、よくわからない。
しかしこの後、明けて安政5年正月5日に、幕府がハリスに、天皇・朝廷の承認を得てから通商条約に調印する運びにしたいことを告げ、老中堀田備中守正睦(まさよし)が21日に上京の途についたのは、幕府首脳部が上申の趣旨を受け止めたものであったことを示している。堀田は2月5日に京都に着く。彼自身は天皇と朝廷の承認を得ることは可能だと見通していた。
(「幕末の天皇・明治の天皇」/ 佐々木克・著)
---------------------------
幕府にとって天皇や朝廷は法的には「下」にあるものでした。幕府は摂政や朝廷を通して天皇を監視し、封圧していたのです。しかし、いざ「国是」の大改定を前にすると、天皇という古代の権威を借りようとするのでした。征夷大将軍の承認は天皇が行っていたので、深層意識では、天皇という制度について、神がかり的な認識は受け継がれてきたのでしょう。
しかし、幕閣の説得や工作にもかかわらず、孝明天皇は拒絶し、戦争をも辞さない決意を表明するのです。そしてこのときに孝明天皇が持ち出したのが「万王一系」という概念でした。いうまでもなく、明治時代になって「万世一系」と呼ばれた考え方です。これは天皇家に代々伝わる神国思想でした。長い間幕府に封圧されていた天皇が幕末にその存在を顕示するようになります。そして天皇のこういう神国思想は、国学を重んじていた井伊直弼が大老に就任したときに、勢力を得、大名が参画し始めた幕政に粛清を生むのです。再び徳川宗家による幕政を取り戻そうという反動勢力が席巻するようになるのでした。
以下、続きます。