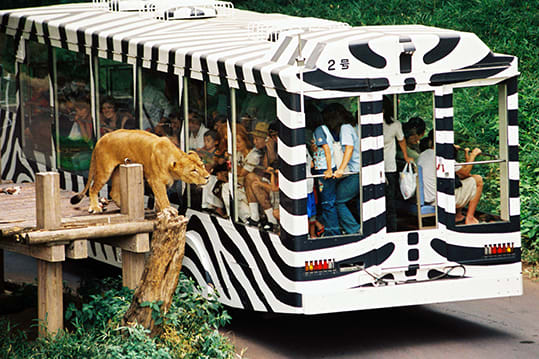さて道東撮影ツアーの三日目になります。初日二日目と予想以上に温かく、とはいっても氷点下10前後なので小樽さっぽろに比べれば相当な冷え込みです。氷点下15度以下を期待していたのですが、なかなか思い通りにはいかないのが撮影ツアーです。今日の早朝は、一応細岡展望台から湿原に差し込む朝日を撮影する、予備日としておりましたが、前夜の内に断念して、三日目の朝はホテルの朝食を済ませてから行程を検討しようということになりました。
事前の予定では、釧路川のケアラシ、和商市場、湿原号の撮影、厚岸のコンキリエで昼食、豊頃のハルニレの夕景、音更彩凛華の撮影というスケジュールでした。写友4人で相談の結果、本日の行程は、釧路市郊外の空港付近、谷内坊主の湿原展望台、然別湖のコタン祭り、豊頃のハルニレの夕景、音更の彩凛華という行程に組み直しです。まずは車に撮影機材を積み込みます。このときホテルの玄関前の植え込みの灌木が白くきらきら光っています。そうです待望の樹氷がやっとあらわれたのです。一路国道を帯広方面に車を進め、大楽毛から釧路湿原に入ってゆきます。何とも目の覚めるような樹氷林が続きます。

ホテル横隣りの公園の垣根は真っ白。

湿原の樹木はどれも真っ白。

朝日を浴びてキラキラ光っている部分も…カメラでは再現しにくい。

踊っているような木々にもびっしり樹氷がついている。なお、根釧地方には大木はありません。平均気温が低くて育ちにくいのです。

ホワイトバランスを調整して青味を強調。
車をさらに脇道に進めます。見渡す限りの樹氷林。無我夢中でシャッターを切ります。かなり温度が低いのか、今までに感じなかったほど手足や指が冷たく感じました。おそらく氷点下15度を下回っているのではないでしょうか。ここで大事なのはカメラのリチュウム電池は寒さに弱いことです。氷点下20度を下回ると急速に消耗し、場合によってはエラーマークが出ます。そこでバッテリーのグリップ部分に携帯用カイロを貼り付けます。見てくれは悪いですが、これで対策はバッチリ。

遠方の山の樹木には樹氷がついておりません。樹氷は近くに川があると発生しやすくなります。

近寄ってみると、雪の結晶が積み重なってこのようになっています。

撮って、撮ってと言わんばかりに、ポーズを撮っているようにも見えます。

湿原展望台の近く北斗地区で見かけた倒木と馬たち。倒木にも樹氷の華が咲いている。

樹氷の部分をモノクロ変換してみました。

湿原展望台から大楽毛方面を見ると、製紙工場がかすんで見えます。この画像もモノクロ変換したものです。湿原一面樹氷で覆われています。
釧路最後の日に樹氷に出会えたのはラッキーでした。2時間以上も撮影して、写友4人とも満足のようでした。車はいったん国道38号線に出て、白糠町に向かいます。白糠からは、茶路川沿いを北上し本別に出ます。本別から士幌を通って然別湖に向かいます。

途中茶路川沿いで丹頂の夫婦を見かけました。

然別湖畔の温泉旅館の前の駐車場から結氷した湖畔にかけて会場があります。氷でできた建物に入ると…

ビヤホール?があってカウンター内でウェイトレス(観光協会の職員?)がにっこり、

先客があって、氷の器に入れたワインを楽しんでおりました。1杯いかがと勧められましたが、車の運転がありますので丁重にお断りしました。それにしても氷の器に入ったお酒はうまそう。

冷蔵庫は不要、氷漬けのお酒の瓶。
一旦このハウスを出てみると大小の氷のの建物があちこちに点在しています。最奥のドームでは切り出した氷を加工して、室内の装飾にしておりました。

湖の氷の厚さは約30cmほどあるそうです。その氷を積み重ねて建物を作ります。その一つを覗いてみると…

中央に氷のテーブルがあって4隅にはウレタンの椅子があります。積み重ねた氷の模様が美しい。

ところどころ壁にはこのような飾りつけがあります。氷漬けの鳥。

アルバイトの女性はチェーンソウで氷の切り割り中。ポーズに注文を付けている写友Y氏。この娘さん日本人とは言っておりましたが、イントネーションが違うような…ちなみにドームの中で作業している男性は二人とも台湾人でここでアルバイトしていますとのこと。

コタン祭りは夜間がメインのようで、日中は補修作業に追われているようです。

露天風呂に男性客が、声をかけると両手を上げて応えてくれました。
やはり、このコタン祭りは夜間のほうがいいようです。会場のあちこちに夜間用の照明が設置されています。夜間だともっと幻想的になるんでしょうね。時間的に無理ですので、今夜のホテルを予約している帯広に向かいます。次の撮影目的地である豊頃には午後4時半頃につきそうです。夕景に染まる春楡が撮れるかもしれません。しかしながら、これまで時折顔を見せていた太陽がだんだんと分厚い雲の中に入っていきます。豊頃近くに来た時にはほとんど太陽が望めない状況となってしまいました。

豊頃に着いた時にはこのような状況で、残念ながらもくろみは外れてしまいました。
音更の彩凛華開始までは時間があります。一旦ホテルに入ることにしますが…何分然別でアルコールを我慢したこともあって、とにかく飲みたいという欲望に勝てずに、午後7時からの彩凛華の撮影を断念することに、意見が一致してしまいました。思い起こせば、昨年も彩凛華の撮影を前にしてアルコール派が勝ってしまったことを思い出しました。う~ん、酒飲みの写友と同道する限り彩凛華の撮影は無理か…。
撮影ツアー4日目は更別の霧氷、十勝川の霧氷、帯広ばんえい競馬の撮影予定です。早朝ホテルを出て更別方向に南下しますが、どうも日の具合がよくありません。分厚い雲に隠れて陽が顔を出しません。そのうちに、雪が舞い始めときおり地吹雪となります。断念するかどうか判断の難しいところ。とにかくビューポイントに向かいます。

十勝らしい光景。やや露出オーバー、このところCASIO EXILIM Z3000はご機嫌斜め。

車の中から180度ほどの画角。

十勝らしい光景はあちこちで見られます。やっと松林の上方に太陽が見えてきました。

モノクロにしてみました。

振り返れば、道路には地吹雪模様が、よく見ると結構きれいかも。
結局更別の霧氷には、去年に引き続き出会えませんでした。自然が相手ですからこんなことはしょっちゅうです。帯広に引き返します。この調子ですと十勝川の霧氷も無理のようです。帯広競馬場に向かいます。本場のばんえい競馬の撮影と意気込んでみたものの、午前10時半に到着すると、係員が寄ってきて、競技開始は午後からとのこと、それ以前は場内にも立ち入りが出来ませんと、冷たい宣告。1時間半もとても待てません。もうどうでもいいやという気分です。結局高速に入り小樽に戻ることとなりました。
事前の予定では、釧路川のケアラシ、和商市場、湿原号の撮影、厚岸のコンキリエで昼食、豊頃のハルニレの夕景、音更彩凛華の撮影というスケジュールでした。写友4人で相談の結果、本日の行程は、釧路市郊外の空港付近、谷内坊主の湿原展望台、然別湖のコタン祭り、豊頃のハルニレの夕景、音更の彩凛華という行程に組み直しです。まずは車に撮影機材を積み込みます。このときホテルの玄関前の植え込みの灌木が白くきらきら光っています。そうです待望の樹氷がやっとあらわれたのです。一路国道を帯広方面に車を進め、大楽毛から釧路湿原に入ってゆきます。何とも目の覚めるような樹氷林が続きます。

ホテル横隣りの公園の垣根は真っ白。

湿原の樹木はどれも真っ白。

朝日を浴びてキラキラ光っている部分も…カメラでは再現しにくい。

踊っているような木々にもびっしり樹氷がついている。なお、根釧地方には大木はありません。平均気温が低くて育ちにくいのです。

ホワイトバランスを調整して青味を強調。
車をさらに脇道に進めます。見渡す限りの樹氷林。無我夢中でシャッターを切ります。かなり温度が低いのか、今までに感じなかったほど手足や指が冷たく感じました。おそらく氷点下15度を下回っているのではないでしょうか。ここで大事なのはカメラのリチュウム電池は寒さに弱いことです。氷点下20度を下回ると急速に消耗し、場合によってはエラーマークが出ます。そこでバッテリーのグリップ部分に携帯用カイロを貼り付けます。見てくれは悪いですが、これで対策はバッチリ。

遠方の山の樹木には樹氷がついておりません。樹氷は近くに川があると発生しやすくなります。

近寄ってみると、雪の結晶が積み重なってこのようになっています。

撮って、撮ってと言わんばかりに、ポーズを撮っているようにも見えます。

湿原展望台の近く北斗地区で見かけた倒木と馬たち。倒木にも樹氷の華が咲いている。

樹氷の部分をモノクロ変換してみました。

湿原展望台から大楽毛方面を見ると、製紙工場がかすんで見えます。この画像もモノクロ変換したものです。湿原一面樹氷で覆われています。
釧路最後の日に樹氷に出会えたのはラッキーでした。2時間以上も撮影して、写友4人とも満足のようでした。車はいったん国道38号線に出て、白糠町に向かいます。白糠からは、茶路川沿いを北上し本別に出ます。本別から士幌を通って然別湖に向かいます。

途中茶路川沿いで丹頂の夫婦を見かけました。

然別湖畔の温泉旅館の前の駐車場から結氷した湖畔にかけて会場があります。氷でできた建物に入ると…

ビヤホール?があってカウンター内でウェイトレス(観光協会の職員?)がにっこり、

先客があって、氷の器に入れたワインを楽しんでおりました。1杯いかがと勧められましたが、車の運転がありますので丁重にお断りしました。それにしても氷の器に入ったお酒はうまそう。

冷蔵庫は不要、氷漬けのお酒の瓶。
一旦このハウスを出てみると大小の氷のの建物があちこちに点在しています。最奥のドームでは切り出した氷を加工して、室内の装飾にしておりました。

湖の氷の厚さは約30cmほどあるそうです。その氷を積み重ねて建物を作ります。その一つを覗いてみると…

中央に氷のテーブルがあって4隅にはウレタンの椅子があります。積み重ねた氷の模様が美しい。

ところどころ壁にはこのような飾りつけがあります。氷漬けの鳥。

アルバイトの女性はチェーンソウで氷の切り割り中。ポーズに注文を付けている写友Y氏。この娘さん日本人とは言っておりましたが、イントネーションが違うような…ちなみにドームの中で作業している男性は二人とも台湾人でここでアルバイトしていますとのこと。

コタン祭りは夜間がメインのようで、日中は補修作業に追われているようです。

露天風呂に男性客が、声をかけると両手を上げて応えてくれました。
やはり、このコタン祭りは夜間のほうがいいようです。会場のあちこちに夜間用の照明が設置されています。夜間だともっと幻想的になるんでしょうね。時間的に無理ですので、今夜のホテルを予約している帯広に向かいます。次の撮影目的地である豊頃には午後4時半頃につきそうです。夕景に染まる春楡が撮れるかもしれません。しかしながら、これまで時折顔を見せていた太陽がだんだんと分厚い雲の中に入っていきます。豊頃近くに来た時にはほとんど太陽が望めない状況となってしまいました。

豊頃に着いた時にはこのような状況で、残念ながらもくろみは外れてしまいました。
音更の彩凛華開始までは時間があります。一旦ホテルに入ることにしますが…何分然別でアルコールを我慢したこともあって、とにかく飲みたいという欲望に勝てずに、午後7時からの彩凛華の撮影を断念することに、意見が一致してしまいました。思い起こせば、昨年も彩凛華の撮影を前にしてアルコール派が勝ってしまったことを思い出しました。う~ん、酒飲みの写友と同道する限り彩凛華の撮影は無理か…。
撮影ツアー4日目は更別の霧氷、十勝川の霧氷、帯広ばんえい競馬の撮影予定です。早朝ホテルを出て更別方向に南下しますが、どうも日の具合がよくありません。分厚い雲に隠れて陽が顔を出しません。そのうちに、雪が舞い始めときおり地吹雪となります。断念するかどうか判断の難しいところ。とにかくビューポイントに向かいます。

十勝らしい光景。やや露出オーバー、このところCASIO EXILIM Z3000はご機嫌斜め。

車の中から180度ほどの画角。

十勝らしい光景はあちこちで見られます。やっと松林の上方に太陽が見えてきました。

モノクロにしてみました。

振り返れば、道路には地吹雪模様が、よく見ると結構きれいかも。
結局更別の霧氷には、去年に引き続き出会えませんでした。自然が相手ですからこんなことはしょっちゅうです。帯広に引き返します。この調子ですと十勝川の霧氷も無理のようです。帯広競馬場に向かいます。本場のばんえい競馬の撮影と意気込んでみたものの、午前10時半に到着すると、係員が寄ってきて、競技開始は午後からとのこと、それ以前は場内にも立ち入りが出来ませんと、冷たい宣告。1時間半もとても待てません。もうどうでもいいやという気分です。結局高速に入り小樽に戻ることとなりました。