佐藤優『プラハの憂鬱』(新潮社、2015)
 あとがきを読むと、人生で最も重大な時期の一つに位置づけられると書いている、イギリス陸軍語学学校での1年、とくにその時にであったインタープレスという古本屋のズデニェク・マストニークというチェコからの亡命人との交流とのことがメインに書かれている。
あとがきを読むと、人生で最も重大な時期の一つに位置づけられると書いている、イギリス陸軍語学学校での1年、とくにその時にであったインタープレスという古本屋のズデニェク・マストニークというチェコからの亡命人との交流とのことがメインに書かれている。
内容は、どんな問題意識で同志社大学神学部に入って、どんな勉強をし、どんな先生たちと出会ったかということから、チェコの宗教者フロマートカのことを勉強したいと考え、そのための手段として外務省に入り、イギリスでロシア語を勉強し、さらに語学研修を続けるためにモスクワに出発するまで、である。
きちんとした目的意識をもって日々を生きていた人のようで、行動に移す前に自分のしたいこと、しようとしていることのために、どういう方向に進んだらいいか、そのために何をしたらいいのかを考え、コマを進めている。
さらに読書を単なる知識吸収ではなく自分のものとして咀嚼している。だから、イギリスで出会ったズデニェク・マストニークとの会話でも表面的なものにならずに、最終的には彼から50回ものチェコに関する講義を受けたのと同じくらいの会話に発展していったという。
以前からどうして同志社大学神学部なのと思っていたが、マルクス主義とキリスト教という、キリスト教の文化が薄い日本ではあまり問題にならないが、ヨーロッパのように、決して避けて通れない問題として根を張っているこの問題を重視していたこと、そして同志社大学だけがクリスチャンでなくても神学部に入れたことから、ここが選択されたという。
それにしても、彼の私的先生となったズデニェク・マストニークも語学学校での先生であったブラシュコもそうだが、みんな佐藤優のことを人間洞察力のある人だと見抜いている。大抵の日本人は当たり障りのない人付き合いしかしないものだ。変な人間関係に巻き込まれて、自分の将来を無駄にしたくないという恐怖心のほうが先にあるからだ。
そういう意味では、この人が鈴木宗男事件に巻き込まれて外務省から抹殺されることになるという将来はすでに既定のものだったのかもしれない。
適度な長さで章分けがされており(というか初出は『小説新潮』なので、一回分の長さということ)、読みやすかった。もちろん内容がチェコの民族問題だとかキリスト教の問題とはいえ、会話体が中心なのも読みやすい原因だろう。
以前読んだ『自壊する帝国』が同じ時期をさっと通って、ロシアに赴任していた8年近くのことを中心に書いているので、その前編と言っていいだろう。『自壊する帝国』についてはこちら
『世界認識のための情報術』についてはこちら
『インテリジェンス武器なき戦争』についてはこちら
『反省』についてはこちら
 あとがきを読むと、人生で最も重大な時期の一つに位置づけられると書いている、イギリス陸軍語学学校での1年、とくにその時にであったインタープレスという古本屋のズデニェク・マストニークというチェコからの亡命人との交流とのことがメインに書かれている。
あとがきを読むと、人生で最も重大な時期の一つに位置づけられると書いている、イギリス陸軍語学学校での1年、とくにその時にであったインタープレスという古本屋のズデニェク・マストニークというチェコからの亡命人との交流とのことがメインに書かれている。内容は、どんな問題意識で同志社大学神学部に入って、どんな勉強をし、どんな先生たちと出会ったかということから、チェコの宗教者フロマートカのことを勉強したいと考え、そのための手段として外務省に入り、イギリスでロシア語を勉強し、さらに語学研修を続けるためにモスクワに出発するまで、である。
きちんとした目的意識をもって日々を生きていた人のようで、行動に移す前に自分のしたいこと、しようとしていることのために、どういう方向に進んだらいいか、そのために何をしたらいいのかを考え、コマを進めている。
さらに読書を単なる知識吸収ではなく自分のものとして咀嚼している。だから、イギリスで出会ったズデニェク・マストニークとの会話でも表面的なものにならずに、最終的には彼から50回ものチェコに関する講義を受けたのと同じくらいの会話に発展していったという。
以前からどうして同志社大学神学部なのと思っていたが、マルクス主義とキリスト教という、キリスト教の文化が薄い日本ではあまり問題にならないが、ヨーロッパのように、決して避けて通れない問題として根を張っているこの問題を重視していたこと、そして同志社大学だけがクリスチャンでなくても神学部に入れたことから、ここが選択されたという。
それにしても、彼の私的先生となったズデニェク・マストニークも語学学校での先生であったブラシュコもそうだが、みんな佐藤優のことを人間洞察力のある人だと見抜いている。大抵の日本人は当たり障りのない人付き合いしかしないものだ。変な人間関係に巻き込まれて、自分の将来を無駄にしたくないという恐怖心のほうが先にあるからだ。
そういう意味では、この人が鈴木宗男事件に巻き込まれて外務省から抹殺されることになるという将来はすでに既定のものだったのかもしれない。
適度な長さで章分けがされており(というか初出は『小説新潮』なので、一回分の長さということ)、読みやすかった。もちろん内容がチェコの民族問題だとかキリスト教の問題とはいえ、会話体が中心なのも読みやすい原因だろう。
以前読んだ『自壊する帝国』が同じ時期をさっと通って、ロシアに赴任していた8年近くのことを中心に書いているので、その前編と言っていいだろう。『自壊する帝国』についてはこちら
『世界認識のための情報術』についてはこちら
『インテリジェンス武器なき戦争』についてはこちら
『反省』についてはこちら










 ヴォルテール、言わずと知れた、18世紀最大のフランスの劇作家、歴史家、哲学者、いわゆる啓蒙思想家である。かたやプロイセンのフリードリヒ大王といえば、フルートを愛し、自分でも作曲をしたりしたという「啓蒙君主」と言われた国王である。
ヴォルテール、言わずと知れた、18世紀最大のフランスの劇作家、歴史家、哲学者、いわゆる啓蒙思想家である。かたやプロイセンのフリードリヒ大王といえば、フルートを愛し、自分でも作曲をしたりしたという「啓蒙君主」と言われた国王である。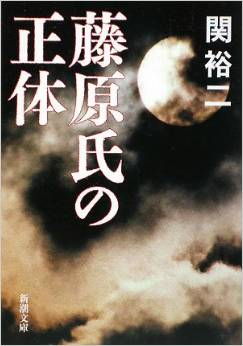 苗字に藤のつくもの(伊藤、加藤、佐藤など)は藤原一族のもとで家臣をしていた者たちで、その仕事内容や働いていた場所からそのような苗字をつけることを許されたのだという話を聞いたことがあるが、佐藤なんて日本の最多数を誇る苗字だから、もしそれが本当なら、藤原一族の家臣が日本にはそんなにいたのかと驚くほどだ。
苗字に藤のつくもの(伊藤、加藤、佐藤など)は藤原一族のもとで家臣をしていた者たちで、その仕事内容や働いていた場所からそのような苗字をつけることを許されたのだという話を聞いたことがあるが、佐藤なんて日本の最多数を誇る苗字だから、もしそれが本当なら、藤原一族の家臣が日本にはそんなにいたのかと驚くほどだ。 米子に行くと、バスで往復する場合でも、電車を使う場合でも、起点は米子駅になる。少し前まで駅の中に本屋があった。もちろん山陰と言えば、出雲=古代となり、その関係の本と並んで、関裕二の本がたくさん売られていた。その中の一つで「「出雲抹殺」の謎 ヤマト建国の真相を解き明かす 」(PHP文庫)」をバスの中で夢中になって読んだ記憶がある。
米子に行くと、バスで往復する場合でも、電車を使う場合でも、起点は米子駅になる。少し前まで駅の中に本屋があった。もちろん山陰と言えば、出雲=古代となり、その関係の本と並んで、関裕二の本がたくさん売られていた。その中の一つで「「出雲抹殺」の謎 ヤマト建国の真相を解き明かす 」(PHP文庫)」をバスの中で夢中になって読んだ記憶がある。
 読後感がすごく不愉快な小説。なぜこんなに不愉快なのかあれこれ考えてみるといくつか理由が見えてくる。
読後感がすごく不愉快な小説。なぜこんなに不愉快なのかあれこれ考えてみるといくつか理由が見えてくる。 「草にすわる」と「砂の城」という二編の短編が収録されている。
「草にすわる」と「砂の城」という二編の短編が収録されている。 たしかこないだの直木賞を受賞した人だ。新人どころか、もう確たる世界を持っているし、文章も素晴らしい。しかも、普通の小説だと、字の文章は読まずに飛ばして会話の部分だけを読んでも別に作品の理解や作品の味わいというものにたいした違いはない(要するに地の文章にたいしたことは書いていない)から、そういうところはぶっ飛ばして読むのだが、この小説は字の文章にけっこう味わい深いことが書いてあるし、この部分を読み飛ばしたら、作品の味わいがまったく違ったものになるということが読みながら分かったので、丁寧に読んだ。
たしかこないだの直木賞を受賞した人だ。新人どころか、もう確たる世界を持っているし、文章も素晴らしい。しかも、普通の小説だと、字の文章は読まずに飛ばして会話の部分だけを読んでも別に作品の理解や作品の味わいというものにたいした違いはない(要するに地の文章にたいしたことは書いていない)から、そういうところはぶっ飛ばして読むのだが、この小説は字の文章にけっこう味わい深いことが書いてあるし、この部分を読み飛ばしたら、作品の味わいがまったく違ったものになるということが読みながら分かったので、丁寧に読んだ。 とうとう最後まで来てしまった。何度か同じことを書いたことがあると思うが、読み終えてしまうのが寂しい小説というものがある。たとえば奥田英朗の『サウスバウンド』だとか重松清の『いとしのヒナゴン』などがそうだった。そして『龍馬がゆく』もそういう小説の一つの仲間に入る。そして改めて第一巻からまた読み直したくなってくるから不思議だ。
とうとう最後まで来てしまった。何度か同じことを書いたことがあると思うが、読み終えてしまうのが寂しい小説というものがある。たとえば奥田英朗の『サウスバウンド』だとか重松清の『いとしのヒナゴン』などがそうだった。そして『龍馬がゆく』もそういう小説の一つの仲間に入る。そして改めて第一巻からまた読み直したくなってくるから不思議だ。 三巻を読んだ後、なかなか四巻が戻ってこなくて、いらいらしつつ待っていたところ、やっと数日前に図書館の本棚に戻っていた。ついでに一気に七巻まで借りてきて、読んでいるが、六巻まで来て、少々疲れてきたので、このへんで一休み入れて、ちょっと感想を書いておこう。
三巻を読んだ後、なかなか四巻が戻ってこなくて、いらいらしつつ待っていたところ、やっと数日前に図書館の本棚に戻っていた。ついでに一気に七巻まで借りてきて、読んでいるが、六巻まで来て、少々疲れてきたので、このへんで一休み入れて、ちょっと感想を書いておこう。