加藤晴久『憂い顔の「星の王子さま」』(書肆心水、2007年)
 サン=テグジュペリの『星の王子さま』は2005年に独占的出版権が切れて、それまで岩波書店の内藤濯訳だけだったのが、続々と翻訳本が出版された。この時点で13本もあったという。内藤濯訳の誤訳を中心に、これらの後継翻訳本のすべての誤訳を検討して、書いたのが、この本だということだ。
サン=テグジュペリの『星の王子さま』は2005年に独占的出版権が切れて、それまで岩波書店の内藤濯訳だけだったのが、続々と翻訳本が出版された。この時点で13本もあったという。内藤濯訳の誤訳を中心に、これらの後継翻訳本のすべての誤訳を検討して、書いたのが、この本だということだ。
私も、少し前に加藤恭子の『星の王子さまをフランス語で読む』を読んだのがきっかけで、『星の王子さま』を少しずつ読んで、自分なりの感想を書いたりしたことがあったが、この時に指摘した、加藤恭子の説明の間違いが、当たり前のことだが、この本でも136~140ページで指摘されている。
上の本については、こちら
私自身による読みの試みについては、(1)、(2)、(3)、(4)
ただ、だれがこのreflexionsの主なのかという問題は、やはり難しいようだ。前後の関係から星の王子さまであると書いているが、ではなぜきちんと所有形容詞を明記しなかったのかと問われば、実際にreflexionsの前に所有形容詞を明記している場合もいくつかあり、理由を説明することは難しいという。
私はフランス語で読むのを途中でやめてしまったが、昨日知り合いのフランス語の先生に話してみたところ、この先生も授業で『星の王子さま』をフランス語で読み通したが、解釈が難しいところがたくさんあったと言っていた。
自信があるのなら自分で翻訳を出すのもいいが、自信のないところがあるのなら、翻訳本など出すべきではない。どう見ても、そういうことを考えもしないで分からないところは「意訳」すればいいやみたいな調子で出している本が多いというのが、この著者の批判である。
 サン=テグジュペリの『星の王子さま』は2005年に独占的出版権が切れて、それまで岩波書店の内藤濯訳だけだったのが、続々と翻訳本が出版された。この時点で13本もあったという。内藤濯訳の誤訳を中心に、これらの後継翻訳本のすべての誤訳を検討して、書いたのが、この本だということだ。
サン=テグジュペリの『星の王子さま』は2005年に独占的出版権が切れて、それまで岩波書店の内藤濯訳だけだったのが、続々と翻訳本が出版された。この時点で13本もあったという。内藤濯訳の誤訳を中心に、これらの後継翻訳本のすべての誤訳を検討して、書いたのが、この本だということだ。私も、少し前に加藤恭子の『星の王子さまをフランス語で読む』を読んだのがきっかけで、『星の王子さま』を少しずつ読んで、自分なりの感想を書いたりしたことがあったが、この時に指摘した、加藤恭子の説明の間違いが、当たり前のことだが、この本でも136~140ページで指摘されている。
上の本については、こちら
私自身による読みの試みについては、(1)、(2)、(3)、(4)
ただ、だれがこのreflexionsの主なのかという問題は、やはり難しいようだ。前後の関係から星の王子さまであると書いているが、ではなぜきちんと所有形容詞を明記しなかったのかと問われば、実際にreflexionsの前に所有形容詞を明記している場合もいくつかあり、理由を説明することは難しいという。
私はフランス語で読むのを途中でやめてしまったが、昨日知り合いのフランス語の先生に話してみたところ、この先生も授業で『星の王子さま』をフランス語で読み通したが、解釈が難しいところがたくさんあったと言っていた。
自信があるのなら自分で翻訳を出すのもいいが、自信のないところがあるのなら、翻訳本など出すべきではない。どう見ても、そういうことを考えもしないで分からないところは「意訳」すればいいやみたいな調子で出している本が多いというのが、この著者の批判である。










 私にとって荒木一郎といえば何と言ってもシンガー・ソングライターのはしりだった『空に星があるように』(下にyoutubeの動画を張ってある)という名曲を歌った歌手であり、少女淫行事件で捕まって(これは無罪放免になった)、母親の荒木道子という、いかにも良妻賢母を絵に描いたような女優さんが言った「本当はいい子なんです」という言葉として残っているばかりだった。
私にとって荒木一郎といえば何と言ってもシンガー・ソングライターのはしりだった『空に星があるように』(下にyoutubeの動画を張ってある)という名曲を歌った歌手であり、少女淫行事件で捕まって(これは無罪放免になった)、母親の荒木道子という、いかにも良妻賢母を絵に描いたような女優さんが言った「本当はいい子なんです」という言葉として残っているばかりだった。 私は小学校2年生の時に担任の先生から『ああ無情』という子供向けの本をもらったことがある。なぜ私だけにくれたのか、分からない。祖母が担任に付け届けでもしたお礼だったのだろうか?
私は小学校2年生の時に担任の先生から『ああ無情』という子供向けの本をもらったことがある。なぜ私だけにくれたのか、分からない。祖母が担任に付け届けでもしたお礼だったのだろうか? ユダヤ人を救ったヴィザを発給して、たくさんのユダヤ人を助けたことで、テレビでもときどき放送されるので、よく知られるようになった杉原千畝の外交官活動を、外務省の資料を駆使して、調査し、優れたインテリジェンス・オフィサーとしての杉原千畝像を示した本ということらしい。
ユダヤ人を救ったヴィザを発給して、たくさんのユダヤ人を助けたことで、テレビでもときどき放送されるので、よく知られるようになった杉原千畝の外交官活動を、外務省の資料を駆使して、調査し、優れたインテリジェンス・オフィサーとしての杉原千畝像を示した本ということらしい。 戦後の計算機メーカーを主導した伝説的なエンジニア(というよりもビジネスマン)の伝記みたいな本。
戦後の計算機メーカーを主導した伝説的なエンジニア(というよりもビジネスマン)の伝記みたいな本。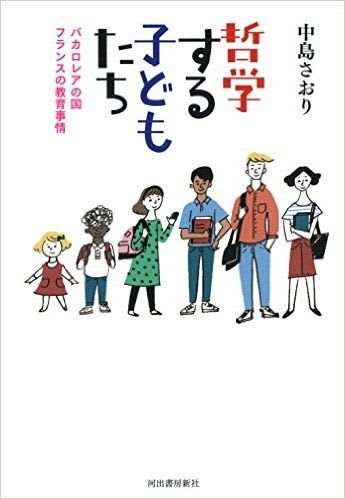 実際にパリ近郊でフランス人との間にできた子ども二人を育てた経験をもとにして、小学校から高校卒業(バカロレア受験)までのフランスの学校教育の姿を書いた本。
実際にパリ近郊でフランス人との間にできた子ども二人を育てた経験をもとにして、小学校から高校卒業(バカロレア受験)までのフランスの学校教育の姿を書いた本。 フランスは58基の原発を有する世界第二の原発大国である。しかも全電力のなかで原発依存度は75%で、世界一の原発を有するアメリカよりも高い。
フランスは58基の原発を有する世界第二の原発大国である。しかも全電力のなかで原発依存度は75%で、世界一の原発を有するアメリカよりも高い。 先日読んだばかりの村上春樹の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の解説本を見つけたので、読んでみた。
先日読んだばかりの村上春樹の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の解説本を見つけたので、読んでみた。 年末に『古舘トーキングヒストリー~忠臣蔵、吉良邸討ち入り完全実況~』というのがテレビ朝日で放送された。ドラマ仕立てで大石内蔵助を始めとした四十七士と吉良上野介が登場する現場に古舘伊知郎が居合わせて実況中継風に解説をするという番組で、非常に興味深かった。
年末に『古舘トーキングヒストリー~忠臣蔵、吉良邸討ち入り完全実況~』というのがテレビ朝日で放送された。ドラマ仕立てで大石内蔵助を始めとした四十七士と吉良上野介が登場する現場に古舘伊知郎が居合わせて実況中継風に解説をするという番組で、非常に興味深かった。 今ちょうどNHKの大河ドラマ『真田丸』で描き始めた大阪の陣(まだ冬の陣の前だが)で引き起こされた、徳川諸大名と、大阪城に終結した豊臣側の浪人たちの戦い、そして敗走する戦闘員と大阪町民たちを襲う徳川方の戦闘員や追い剥ぎたちの阿鼻叫喚の地獄絵図を描いたのがこの「大阪夏の陣図屏風」だという。
今ちょうどNHKの大河ドラマ『真田丸』で描き始めた大阪の陣(まだ冬の陣の前だが)で引き起こされた、徳川諸大名と、大阪城に終結した豊臣側の浪人たちの戦い、そして敗走する戦闘員と大阪町民たちを襲う徳川方の戦闘員や追い剥ぎたちの阿鼻叫喚の地獄絵図を描いたのがこの「大阪夏の陣図屏風」だという。