加藤秀一『<恋愛結婚>は何をもたらしたか』(ちくま新書、2004年)

 恋愛結婚という絶対不動の真実と思われている人間関係がじつは歴史的にはごく最近のことであり、恋愛結婚はつねに、あの悪名高き優生思想と結びついてきたことを論じた本である。
恋愛結婚という絶対不動の真実と思われている人間関係がじつは歴史的にはごく最近のことであり、恋愛結婚はつねに、あの悪名高き優生思想と結びついてきたことを論じた本である。
悪名高きと書いたのは、ナチス・ドイツで種の純化という優生思想によってユダヤ人へのホロコーストが行われたからだ。またつい最近の日本でも戦中だか戦後だかに優生思想の名において精神障害者たちへの断種手術が行われたことが新聞でも記事になっていたからだ。
ここで扱われている問題は、この恋愛結婚を中心にして、結婚制度、結婚と国家の関係、男尊女卑の問題、女性解放、母性保護、などなどいろんな問題と結びつているので、こうしたこんがらがった諸問題を、手際よくまとめたこの著者の力量には感服する。
私自身は、制度としての結婚はいずれなくなると思う。現在の、とりわけ日本の結婚は、旧弊な家制度の名残にすぎない。○○家を残すための制度にすぎず、すでに○○家などというものが空中楼閣に過ぎない以上、そんなもののために結婚という制度を残しても意味がない。
フランスのように自由な男女の結合関係を尊重するような方向になるべきだと思う。なんかこういうことを書くと無責任な輩ばかりになるという意見が必ず出てくるが、人間そんな奴もいるだろうが、そんな人ばかりではない。別に結婚という制度がなくても、最初にできた相手と一生暮らすようなカップルだってたくさんいる。
では国家は何をすべきか。国家は、親が子育てしながら働くためにいい環境を作ること、すべての子どもが親の財産などに関係なく十分な教育を受けられるような環境を作ること。たぶん理念的にはフランスはこういう方向に向かっていると思うが、日本は理念さえもない。
個人の領域の問題と国家の領域の問題の重なり合い、感情と制度のからみあいなど、これらは、なかなか難しい問題だと思う。
『恋愛結婚は何をもたらしたか (ちくま新書)』のアマゾンのコーナーはこちら
スマホの料金や速度で悩んでいる人は「格安SIMとスマホ比較」を参考にするといいですよ。私もここを参考にして格安SIMを導入して、節約できてます。

悪名高きと書いたのは、ナチス・ドイツで種の純化という優生思想によってユダヤ人へのホロコーストが行われたからだ。またつい最近の日本でも戦中だか戦後だかに優生思想の名において精神障害者たちへの断種手術が行われたことが新聞でも記事になっていたからだ。
ここで扱われている問題は、この恋愛結婚を中心にして、結婚制度、結婚と国家の関係、男尊女卑の問題、女性解放、母性保護、などなどいろんな問題と結びつているので、こうしたこんがらがった諸問題を、手際よくまとめたこの著者の力量には感服する。
私自身は、制度としての結婚はいずれなくなると思う。現在の、とりわけ日本の結婚は、旧弊な家制度の名残にすぎない。○○家を残すための制度にすぎず、すでに○○家などというものが空中楼閣に過ぎない以上、そんなもののために結婚という制度を残しても意味がない。
フランスのように自由な男女の結合関係を尊重するような方向になるべきだと思う。なんかこういうことを書くと無責任な輩ばかりになるという意見が必ず出てくるが、人間そんな奴もいるだろうが、そんな人ばかりではない。別に結婚という制度がなくても、最初にできた相手と一生暮らすようなカップルだってたくさんいる。
では国家は何をすべきか。国家は、親が子育てしながら働くためにいい環境を作ること、すべての子どもが親の財産などに関係なく十分な教育を受けられるような環境を作ること。たぶん理念的にはフランスはこういう方向に向かっていると思うが、日本は理念さえもない。
個人の領域の問題と国家の領域の問題の重なり合い、感情と制度のからみあいなど、これらは、なかなか難しい問題だと思う。
『恋愛結婚は何をもたらしたか (ちくま新書)』のアマゾンのコーナーはこちら
スマホの料金や速度で悩んでいる人は「格安SIMとスマホ比較」を参考にするといいですよ。私もここを参考にして格安SIMを導入して、節約できてます。















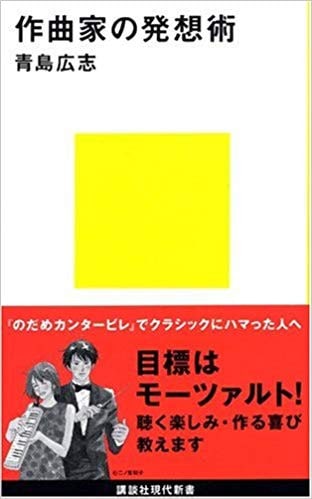 この芸人のような顔で得しているのか、損しているのか、私にはわからないが、作曲家?と思わず首を傾げてしまいそうな雰囲気を持った人で、なんどかテレビでも見たことがある。
この芸人のような顔で得しているのか、損しているのか、私にはわからないが、作曲家?と思わず首を傾げてしまいそうな雰囲気を持った人で、なんどかテレビでも見たことがある。
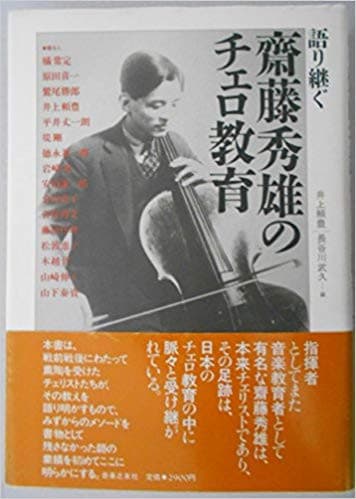
 在日のエッセイストの本で、小説でも書いているのなら読んでみたいと思ったのだが、どうも小説は書いていないよう。
在日のエッセイストの本で、小説でも書いているのなら読んでみたいと思ったのだが、どうも小説は書いていないよう。 先にフランクルの『夜と霧』を読みたかったのだが、解説書のほうが先に図書館から来てしまった。
先にフランクルの『夜と霧』を読みたかったのだが、解説書のほうが先に図書館から来てしまった。