原田マハ『ジヴェルニーの食卓』(集英社、2013年)
 じつは、原田マハって読みたいと思いながら、読んでいないな、と思い、図書館でこれと一緒に『楽園のカンヴァス』も借りてきたのだが、その表紙絵を見ているうちに、これってもう読んだかもと思い出したので、このサイト内検索をしてみたら、あった。
じつは、原田マハって読みたいと思いながら、読んでいないな、と思い、図書館でこれと一緒に『楽園のカンヴァス』も借りてきたのだが、その表紙絵を見ているうちに、これってもう読んだかもと思い出したので、このサイト内検索をしてみたら、あった。
2012年の暮に読んでいたのだ。こちら
それはそうとして、『ジヴェルニーの食卓』は、短編集である。アンリ・マティスを主題にした「うつくしい墓」、エドガー・ドガを題材にした「エトワール」、セザンヌがメインの「タンギー爺さん」、そしてクロード・モネのジヴェルニーを描いた「ジヴェルニーの食卓」。
どれも詩情あふれる文章で、印象派の偉大な画家たちによりそった人々から見た画家たちの日常生活を描き、それを通して彼らの喜びや苦悩を描き出している。
マティスの死の数ヶ月前から彼のアパルトマンに世話係として雇われて、彼の死を看取ったマリアという若い女性が年老いてから、その時のことを回想して語る「うつくしい墓」は、かつてフランス語の勉強のためによく見ていたフランス制作のヴィデオのワン・レッスンにマティスの絵が題材になっていたこともあって、親しみを感じた。
もちろんジヴェルニーのモネ美術館となっている屋敷のことは、テレビでもよく見かける。この間もやってきた番組で、あの庭園や池の世話をしていたのはモネ自身であったということを知っていたので、この小説も興味深く読めた。
これらの画家に興味がある人には、なかなかいい作品だと思う。
 じつは、原田マハって読みたいと思いながら、読んでいないな、と思い、図書館でこれと一緒に『楽園のカンヴァス』も借りてきたのだが、その表紙絵を見ているうちに、これってもう読んだかもと思い出したので、このサイト内検索をしてみたら、あった。
じつは、原田マハって読みたいと思いながら、読んでいないな、と思い、図書館でこれと一緒に『楽園のカンヴァス』も借りてきたのだが、その表紙絵を見ているうちに、これってもう読んだかもと思い出したので、このサイト内検索をしてみたら、あった。2012年の暮に読んでいたのだ。こちら
それはそうとして、『ジヴェルニーの食卓』は、短編集である。アンリ・マティスを主題にした「うつくしい墓」、エドガー・ドガを題材にした「エトワール」、セザンヌがメインの「タンギー爺さん」、そしてクロード・モネのジヴェルニーを描いた「ジヴェルニーの食卓」。
どれも詩情あふれる文章で、印象派の偉大な画家たちによりそった人々から見た画家たちの日常生活を描き、それを通して彼らの喜びや苦悩を描き出している。
マティスの死の数ヶ月前から彼のアパルトマンに世話係として雇われて、彼の死を看取ったマリアという若い女性が年老いてから、その時のことを回想して語る「うつくしい墓」は、かつてフランス語の勉強のためによく見ていたフランス制作のヴィデオのワン・レッスンにマティスの絵が題材になっていたこともあって、親しみを感じた。
もちろんジヴェルニーのモネ美術館となっている屋敷のことは、テレビでもよく見かける。この間もやってきた番組で、あの庭園や池の世話をしていたのはモネ自身であったということを知っていたので、この小説も興味深く読めた。
これらの画家に興味がある人には、なかなかいい作品だと思う。










 国際的な数学者にして、大道芸人という変わった人、テレビでときおり見かけるが、いったい何をして生計を立てているのか、さっぱりわからない人、ピーター・フランクルの青春記。
国際的な数学者にして、大道芸人という変わった人、テレビでときおり見かけるが、いったい何をして生計を立てているのか、さっぱりわからない人、ピーター・フランクルの青春記。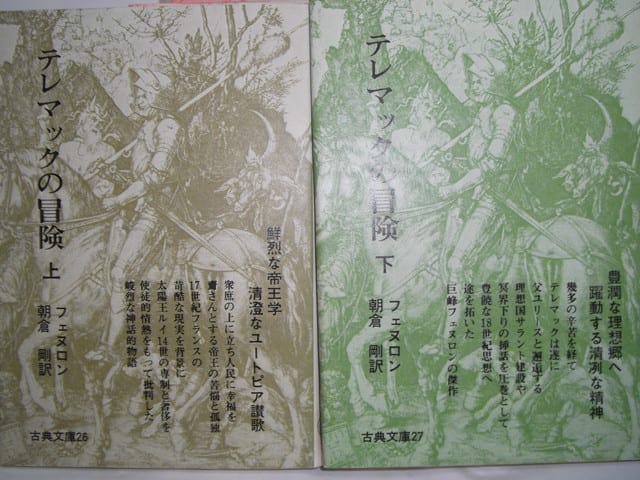 時はルイ14世の統治の後半の17世紀末のこと。度重なる領土拡大戦争と疫病や冷害などのために国民は疲弊し、国庫は底をつきそうになっていたが、ルイ14世は、国民を犠牲にして、さらにかつての大貴族を没落させて得た栄光にすがりついて、政策を変更しようという気はまったくなかった。
時はルイ14世の統治の後半の17世紀末のこと。度重なる領土拡大戦争と疫病や冷害などのために国民は疲弊し、国庫は底をつきそうになっていたが、ルイ14世は、国民を犠牲にして、さらにかつての大貴族を没落させて得た栄光にすがりついて、政策を変更しようという気はまったくなかった。 久しぶりのダン・ブラウンである。友人がフランス語で『インフェルノ』を読んでいるとか言っていたので、ダン・ブラウン新刊出したのかと思ったら、もう二年以上も前の話。今度はダンテの『神曲』を題材にした話だが、主題は地球の収容能力を超える人口増加に危機感をもった天才的な学者が、13世紀の黒死病のパンデミックみたいな、人間大量死を作り出そうとするのを阻むという話である。
久しぶりのダン・ブラウンである。友人がフランス語で『インフェルノ』を読んでいるとか言っていたので、ダン・ブラウン新刊出したのかと思ったら、もう二年以上も前の話。今度はダンテの『神曲』を題材にした話だが、主題は地球の収容能力を超える人口増加に危機感をもった天才的な学者が、13世紀の黒死病のパンデミックみたいな、人間大量死を作り出そうとするのを阻むという話である。 最近ケーブルテレビでアメリカ映画『デジャヴュ』を見た。デンゼル・ワシントン演じる捜査官の知り合いを含む多数の人が港に停泊中の遊覧船に仕掛けられた爆弾で死亡する。
最近ケーブルテレビでアメリカ映画『デジャヴュ』を見た。デンゼル・ワシントン演じる捜査官の知り合いを含む多数の人が港に停泊中の遊覧船に仕掛けられた爆弾で死亡する。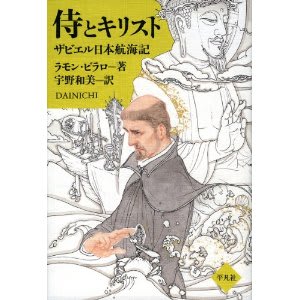 図書館でたまたま見つけた。日本へのキリスト教布教の先陣を飾ったことで、つとに有名な、あのフランシスコ・ザビエルが鹿児島に到着してから、平戸、山口、堺、京都、山口と回って、平戸から中国へ向かって旅立って行くまでを描いた小説。
図書館でたまたま見つけた。日本へのキリスト教布教の先陣を飾ったことで、つとに有名な、あのフランシスコ・ザビエルが鹿児島に到着してから、平戸、山口、堺、京都、山口と回って、平戸から中国へ向かって旅立って行くまでを描いた小説。 邪馬台国の隣にあった那国が漢に使者を送って、漢委奴國王という金印をもらった時代から、邪馬台国の卑弥呼が魏に使者を送って親魏倭王の称号をもらった時代を経て、魏から普に変わった中国に使者を送ろうとする卑弥呼の次の女王の時代の邪馬台国にいたる百有余年の北九州地域の邪馬台国の通訳を務める一族<あずみ>を語り手にした物語。
邪馬台国の隣にあった那国が漢に使者を送って、漢委奴國王という金印をもらった時代から、邪馬台国の卑弥呼が魏に使者を送って親魏倭王の称号をもらった時代を経て、魏から普に変わった中国に使者を送ろうとする卑弥呼の次の女王の時代の邪馬台国にいたる百有余年の北九州地域の邪馬台国の通訳を務める一族<あずみ>を語り手にした物語。 アンリ・ルソーの『夢』という大作(死の直前に描かれた作品)にまつわる真偽を取り上げた作品で、今年のベストなんとかにたいてい入っていたり、この間毎日新聞を読んでいたら、高校生が選んだ文学賞のトップにこの作品が選ばれていた。たしかにすごい筆力でぐいぐい読ませ、作品世界に入り込ませる力をもっている。
アンリ・ルソーの『夢』という大作(死の直前に描かれた作品)にまつわる真偽を取り上げた作品で、今年のベストなんとかにたいてい入っていたり、この間毎日新聞を読んでいたら、高校生が選んだ文学賞のトップにこの作品が選ばれていた。たしかにすごい筆力でぐいぐい読ませ、作品世界に入り込ませる力をもっている。
 連作の最終巻。高校二年生で付き合っていた南枝里子が他の男性とのあいだに子どもができて退学し、恋愛も破綻してしまうという事件があり、なんとかその痛手を隠しつつ、三年生になって、音楽ホールの落成をきっかけに、オーケストラは専攻科だけでやるという方針転換に新たな気持ちで取り組んでいた津島たちの演奏会に突然枝里子がやってきて隠れてバッハのブランデンブルグ協奏曲5番を演奏して、またあっという間に去ってしまう。後から渡された手紙とかつて一緒にやっていた曲の楽譜でやっと踏ん切りをつけた津島は、チェロを捨てる決心をして予備校に通い始める。
連作の最終巻。高校二年生で付き合っていた南枝里子が他の男性とのあいだに子どもができて退学し、恋愛も破綻してしまうという事件があり、なんとかその痛手を隠しつつ、三年生になって、音楽ホールの落成をきっかけに、オーケストラは専攻科だけでやるという方針転換に新たな気持ちで取り組んでいた津島たちの演奏会に突然枝里子がやってきて隠れてバッハのブランデンブルグ協奏曲5番を演奏して、またあっという間に去ってしまう。後から渡された手紙とかつて一緒にやっていた曲の楽譜でやっと踏ん切りをつけた津島は、チェロを捨てる決心をして予備校に通い始める。