ファイル一冊分の準備をしてから(笑)「ドイツ語で日本紹介(ガイド演習)」で「明治日本の産業革命遺産」そして軍艦島についてドイツ語で話しました(2017.8.11)@欧日協会ドイツ語ゼミナール夏季講習←このGWにもやります!!
またまた調子に乗ってファイル1冊分の準備をしてから(笑) 欧日協会夏季講習2017「ドイツ語で日本文化紹介/世界遺産」で 軍艦島について発表してきました~(^O^)/
年に数少ないドイツ語レッスンなので 欧日協会の夏季講習は毎年楽しみにしています 今年は初めて「ドイツ語で日本文化紹介」を夏季講習でやっていただき嬉しい~♡
この講座(4回)は 「世界遺産」「日本の習俗」「日本の文化」「日本の社会」等に分かれており 各自発表するガイド演習というもので レベルも高いです!(現役の通訳案内士も受けているコースです)
私は即座に「世界遺産」のみ申し込み 先日「知れば旅がもっと楽しくなる世界遺産講座」(クラブツーリズム)で聞いた軍艦島のお話をしようと即決!(^^)! ← 他の3つの単元はイタリア語でやってるからパス...だって話す相手のドイツ人がいないんだもの...(;_:)
イタリア語では通訳案内士のレッスンを受けていましたが 日本の世界遺産についてはやっていないのでワクワク♡ 説明はなんとかできても質疑応答はどうしよう... 他にも有名な世界遺産の中から選べたんですが 一番数が多くて難しいのを選んじゃったみたい...まっやりたかったものだからいいか♪
当日は念願の 通訳案内士の試験合格者の皆様と机を並べてレッスンを受け トップバッターで発表(疲れる前に済ませようと思いまして)! 何も見ないで満足ゆく暗唱発表ができました(暗唱までしていたのは私だけでした~)
質疑応答では 軍艦島でない他の構成遺産の「登録理由は?」と聞かれてしまいアワアワ( ;∀;) 書類引っ張り出して答えました すぐに何でも答えられるようになるのは(しかもドイツ語で)大変ですね!! でも「実際に通訳ガイドをしていることを想定した」レッスンなので とても緊張感がありよかったです たっぷり予習ができて 満足 満足~(笑)♡
先生も「こういう言い方はしないよ」と訂正してくださったり 世界遺産を説明する時に使うキーワードをたくさん教えてくださり 初めて習ったのですがベテランで安心して受けられました ^^) _旦~~
プロの方の発表は 地図を配って実際に歩きながらという想定で説明するというスタイル わかりやすい!! 長すぎずポイントを絞って紹介してくれました 私の発表はクイズや 軍艦島の元炭鉱夫のお話も入れました(世界遺産講座で聞いたものですが) 皆さんの盛大な拍手が嬉しかった~(#^^#)
* * *
"Historisce Stätten Japans der industriellen Revolution Japans in der Meiji-Zeit: Eisen und Stahl, Schiffsbau und Kohlebergbau" …und Gunkanjima
「明治日本の産業革命遺産: 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業」…そして軍艦島
*Stätten Japans industrieller Meiji Revolution(Wikipediaより)は Meiji Revolutionは「明治革命」と訳すので「Meiji Restaurazion」が正しいとのこと
なので 上のタイトル(JTPのサイトのドイツ語)にしました
欧日協会ドイツ語ゼミナール夏季集中講座(2017.8.11)
「ドイツ語で日本紹介(ガイド演習)日本の世界遺産」発表原稿(5~7分)
Die neunzehnte Weltkulturerbe in Japan heißt: “Historisce Stätten Japans der industriellen Revolution Japans in der Meiji-Zeit: Eisen und Stahl, Schiffsbau und Kohlebergbau”. Insgesamt 23 Stätten in 8 Präfekturen in Kyushu (Präfektur Kagoshima, Saga, Nagasaki, Fukuoka, Kumamoto) und in der Präfektur Yamaguchi, Iwate, Shizuoka, diese Stätten sind mit dem Konzept “Serialnomination” in der Liste der Weltkulturerbe bei der UNESCO im 2015 aufgenommen*.
日本の19番目の世界遺産は「明治日本の産業革命遺産: 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業」は、九州(鹿児島、佐賀、長崎、福岡、熊本県)と山口県、岩手県、静岡県の8県にある23の資産からなっています。「シリアル・ノミネーション」というコンセプトで2015年にユネスコの世界文化遺産に登録されました。
*登録される=(eingetretenは使わず) in die Liste aufnehmen, registrierenがよいとのこと
 ← 明治日本の産業遺産の地図
← 明治日本の産業遺産の地図
Die Gründe des Eintrags heißen: “Am Ende der Edo-Zeit (1603-1867) strebte Japan nach der Modernisierung. Durch den Import westlicher Technologien konnte Japan mit der schnellen Industrialisierung in diesen Stätten viel Erfolg haben.”
主な登録理由:「江戸時代末期に日本は近代化をすすめた。西洋の技術を輸入して、日本はこれらの場所で短期間で産業化に成功を収めた」です。
Die Hauptstätte:
主な構成遺産:
*ひとつひとつ写真を見せながら説明する
・Miike-Kohlemine(Fukuoka,Kumamoto) 福岡県・熊本県の「三池炭鉱」
 ← 三池炭鉱
← 三池炭鉱
・Burgstadt Hagi(Yamaguchi): die Burgstadt Hagi ist von Chôshû Clan。
山口県の「萩城下町」は、長州藩の城下町です。
・Shōkasonjuku-Akademie: die private Schule, an der Chôshû Clansmann Yoshida Shôin unterrichtete.
松下村塾(しょうかそんじゅく)は、幕末に長州藩士の吉田松陰が講義した私塾です。
 ← 松下村塾
← 松下村塾
・Nirayama-Flammofen(Shizuoka)
静岡県の「韮山(にらやま)反射炉」
 ← 韮山反射炉
← 韮山反射炉
・“Hashino Eisenberg und Ruine der Hochofen” (in der Präfektur Iwate )
岩手県釜石市「橋野鉄鋼山跡・高炉跡」
・Ruinen der Mietsu-Marinenwerft, Präfektur Saga Mit der Brillen kann man virtuellen Blick sehen
三重津海軍所跡(佐賀県)
メガネでバーチャル景色が見られる
・"Nagasaki Werft Mitsubishi”(Nagasaki)heute noch im Betrieb.
長崎の「三菱長崎造船所」(現在稼働中)
・“Früheres Glover-Haus” (Nagasaki): die Residenz von schottischen Kaufmann, Thomas Glover.
長崎の「旧グラバー住宅」: 英国スコットランド出身の貿易商人、トーマス・ブレーク・グラバーの住居
 ← 旧グラバー邸
← 旧グラバー邸
・Misumi West Port, Präfektur Kumamoto
熊本県の三角(みすみ)西港
・Staatliche Yawata Steel Works (Fukuoka) arbeitet heute noch, aber kann man nicht besichtigen.
福岡県の「官営八幡製鉄所」。(現在稼働中、見学不可)
Als Industrialeerbe in Japan sind eingetreten: “Iwami Ginzan(Silbermine) und Kulturlandschaft” (Shimane/2007), “Tomioka-Seidenspinnerei und Seidenfabrik in Tomioka “ (Gumma/2014), anderseits in Deutschland sind eingetreten: “Die Zeche Zollverein /Steinkohlebergwerk in Essen(2001 ), “Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft”(1992), “Völklinger Hütte”(Saarland/1994), usw.
日本の産業遺産には他にも「石見銀山遺跡とその文化的景観」(島根県/2007)「富岡製糸場と絹産業遺産群」(群馬県/2014)がありますが、一方ドイツには「エッセンのツォルフォアアイン炭鉱業遺産群」(2001)、「ランメルスベルク鉱山、歴史都市ゴスラーとオーバーハルツ水利管理システム」(1992)、「フェルクリンゲン製鉄所」(1994)等がありますね。
* * *
Gunkanjima (Kriegsschiff-Insel)
Insel Hashima gehört zur Stadt Nagasaki. Sein Spitzname lautet “Gunkanjima” Kriegsschiff-Insel, weil er am Kriegsschiff der Tosa-Klasse errinert. Von 1887 bis 1974 wurde unterseeischer Kohlenabbau betrieben, seither ist sie unbewohnt.
さていよいよ長崎県の「軍艦島(端島)」についてです。島の外観が「戦艦土佐」に似ていたのでこのあだ名がつけられたとも言われています。1887年から1974年まで海底の石炭採掘が行われ、それ以降は無人です。
 ← 軍艦島
← 軍艦島
Die Blütezeit des Berghaus began um 1890 unter der Leitung des Mitsubishi-Konzern. Damals lebten über 5,000 Arbeiter und Familienangehörige im mehrstöckigen Wohngebäude aus Stahlbeton mit der höchste Dichetn der Welt.
この採掘場の最盛期は1890年に三菱コンツェルンの指導のもとで始まりました。当時は5千人を超える労働者とその家族が世界一の人口密度で、高層の鉄筋コンクリートの住居に住んでいました。
Existierten auch Tempel, Polizeistazion, Badeanstalten, Kindergarten, Schulen, Geschäfte, Krankenhaus, Bordell, lediglich ein Bestattungswesen fehlte, es gab auf der Insel Nakanoshima.
寺、駐在所、銭湯、幼稚園、学校、店、病院、花街等がありました。なかったのは埋葬施設のみで、それは別に中ノ島にありました。
In Laufe der Energiereformen wurde die Werk im 1974 stillgelegt und gesperrt. Aber ab 2009 ist erstmals wieder möglich geworden, mit dem Schiff die Insel zu besuchen.
エネルギー改革の流れの中で1974年に操業停止し閉山しました。しかし2009年からようやく初めて船で訪れることが出来るようになりました。
Die Steine der Uferschutzanlage sind mit der Vergindungsmaterie “Amakawa” verbindet worden, wegen dieser Technik der Verbindung sind diese Teile gegen die ganz wilde Welle durchgehalten, ohne zusammenzubrechen.
また軍艦島では「天川(あまかわ)」という水に強いつなぎで天草石を積み上げた天川工法という方法で護岸工事がなされ、強い波でもその部分は最後まで崩れなかったそうです。
(Ein Quiz)
Wer damals hat am besten verdient von Ärtze, Beamte und Bergmänner ?
- Ärtze. Damals verdienten die Ärtze vielfach als Beamte oder die Bergmänner. Das bedeutet, je schwere unmenschliche Arbeitsbedingngen um so mehr vdrdienten die Ärzte. – So redete ein damaliger Bergmann.
当時この炭鉱で働いていた人に聞いた話ですが、軍艦島で一番稼いでいたのは医者、役人、炭鉱夫のうち誰でしょうか?(クイズ)
- それは医者で、役人や炭鉱夫の何倍も稼いでいました、それだけ過酷で危険な仕事だったということですね。
Wenn man die Dynamit sprengte, lagten die Bergmänner nur in Richtung Dynamit, ohne zu flüchten (keine Zeit). Wenn man in die andere Richtung Dynamit lag, sind immer die Pulver der Dynamit im Nasen eingetreten!
近くでダイナマイトを発破させる時も避難などせず(時間がなくて)、発破の方向を向いて身を伏せるだけだったそうです。反対に背を向けると、鼻から粉塵(ふんじん)が入ってきたのだそうです。
Nach der ganz strengen Arbeit im Kohlenmine, im ganz dunklen Loch nur mit seinem einzigen Licht am Kopf, die Bergmänner lächelten von selbst am Ausgang, weil sie Gott sei Dank mit heiler Haut aus dem Bergwerk zurückkehren konnten. So redete ein damaliger Bergmann.
暗くて深い炭鉱から、ライト1本で1日過酷に働き往復して帰ってきた炭鉱夫は、無事に1日の仕事が終わり帰ってこれたという感謝の気持ちでか、笑顔にあふれたと、かつての炭鉱夫は語ったそうです。
Nach der längeren Sperre und der Evakurierungszeit ist allmählich die Gräser auf der Insel gewachsen, die während der Bergbauzeit fast gar nicht wuchsen.
Auch das Meer, in dem man während der Bergbauzeit von Müll schumuzig war, ist aber jetzt wieder schöne kobaltblau geworden.
Darum war mir zufällig ein Film “HOMO SAPIENS “ (Menschenerbe) von Regisseur Nikolars Geyrhalter in Errinerung. Die Insel Gunkanjima wurde auch in diesem Film gefilmt, in dem er das Thema “die Ruinen” behandelte.
Vielleicht nachdem die Menschen ausgestorben wären, wüchsen wieder die Gräser auf der Erde, meinte ich.
人がいなくなった軍艦島には 人がたくさんいた頃には全く生えていなかった緑の草が生えていたのです。炭鉱当時は廃棄物で汚かった海も、今はコバルトブルーに輝いています。
なので私がこのお話を聞いた時にふと思い出したのが、廃墟ばかりを写したドキュメンタリー映画『人類遺産』(オーストリア・ドイツ・スイス映画/2016 原題『HOMO SAPIENS』... ニコラウス・ゲイハルター監督最新作)を思い出しました。この映画にも軍艦島が登場しています。
もしかしたら私たち人類がやがていなくなったあとの大地には、きっと緑が生えてくるんだろうな...と私は思ってしまいました。
Die Schiffverbindung 船のアクセス:
Vom Hafen Nagasaki laufen die Kreuzfahrtschiffe aus, die die Besichtigungstouren organisieren. Allein kann man nicht landen. Beim schlechten Wetter, z.B. wenn die Windgeschwindigkeit über 5m/s überschreitet, usw, kann man leider nicht landen, nur aus der Nähe die Insel schauen.
長崎港から出航しているクルーズ船による見学ツアーに参加します。一人では上陸できません。悪天候の時、たとえば風速5メートル以上等の時は上陸することができず、近くから眺めるだけです。
(発表は少しはしょりました)
 ← クルーズ船から軍艦島を間近に見る
← クルーズ船から軍艦島を間近に見る
* * *
・ im Original erhalten, originalgetreu rekonstruieren オリジナルに忠実に復元する
・ Wirtschaftszweig (経済)産業部門
・ unter Denkmalschutz stehen 文化財保護(史跡保存)のもとに立つ
・ Berg Fuji ist mehr als ein normaler Berg, Symbol der Seele Japans 富士山は普通の山以上のもので、日本の魂のシンボルだ。
・ Kunstwerke schaffen 芸術作品を創り出す
参考: 「軍艦島」「明治日本の産業革命遺産」Wikipedia、
「軍艦島から新たな革命」(クラブツーリズム世界遺産講座)
夕刊フジの記事『軍艦島から「新たな革命」』(クラブツーリズム「世界遺産講座」の黒田講師の執筆された記事)等
「英語対訳で読む日本の世界遺産」(Jippi Compact)
世界遺産検定テキスト
欧日協会の2018年GW講座でも「日本文化紹介」で世界遺産またやります♪ ← もう申し込みました ^^) _旦~~
このドイツ語夏季講座と並行して 当時はイタリア語スピーチコンテスト(2017年12月)の原稿を書き進め 無事に本選出場となったわけですが よくまぁこんな大変なことをしたもんだなぁ…と自分でも今見てビックリ( ゚Д゚)
* 写真は 夏季講座の説明に使った明治日本の産業遺産の写真 黒田講師が写した軍艦島の写真!!
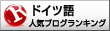 ドイツ語ランキング
ドイツ語ランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
 ← MOE 40th Anniversary 5人展
← MOE 40th Anniversary 5人展 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング











 ← きじとら出版のチラシ
← きじとら出版のチラシ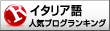

 ← 作成シーンを皆で見る
← 作成シーンを皆で見る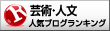

 ← バザーリア
← バザーリア ← 2つの治療文化
← 2つの治療文化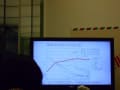 ← 精神病床数の各国比較(厚労省医療計画/H24)
← 精神病床数の各国比較(厚労省医療計画/H24)

 ← 早速買った本にサイン♡
← 早速買った本にサイン♡
 ← 明治日本の産業遺産の地図
← 明治日本の産業遺産の地図 ← 三池炭鉱
← 三池炭鉱 ← 松下村塾
← 松下村塾 ← 韮山反射炉
← 韮山反射炉 ← 旧グラバー邸
← 旧グラバー邸 ← 軍艦島
← 軍艦島 ← クルーズ船から軍艦島を間近に見る
← クルーズ船から軍艦島を間近に見る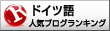

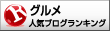

 ← 二松学舎大学のすぐ向かいがイタリア文化会館です♪
← 二松学舎大学のすぐ向かいがイタリア文化会館です♪ ← エル・システマジャパンのパンフレット
← エル・システマジャパンのパンフレット





