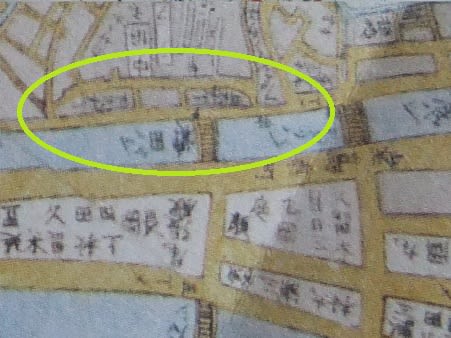三善貞司さんの「大阪伝承地誌集成」に、
旧上福島村あたりに、忠臣蔵で有名な大石内蔵助の仮住いがあったと書かれています。
出典は江戸時代に出版された観光ガイドブック「摂津名所図会大成」。
この本は有名な「摂津名所図会」とはまた違う書籍です。
その本によりますと、内蔵助が住んでいたのは浄祐寺(北区堂島)の西側。
そしてその家は「仮名手本忠臣蔵」に登場する大坂の商人、天野屋利兵衛の別荘でした。
「大坂見聞録 関宿藩士池田正樹の難波探訪」(渡邊忠司)という本にも
大阪の福島あたりに天野屋利兵衛の別荘があり、
そこに内蔵助が身を寄せていたという記述があります。
この本は江戸時代の武士の大坂赴任中の暮らしをつづった
「難波噺」という随筆について書かれたもので、
大坂の市中や郊外に観光に出かけた記録も掲載されています。

「wikipedia:仮名手本忠臣蔵」旧字体:假名手本忠臣藏。
「wikipedia:大石良雄」「良雄」は諱で、通称は「内蔵助」。
「wikipedia:天野屋利兵衛」十段目で天河屋義平として登場。
「大阪伝承地誌集成」には別項目に「天野屋利兵衛宅跡」があり、
浄祐寺の北にある「鵲の森」に
天野屋利兵衛の屋敷があった、と書かれています。
古い地図を何種類か見ましたが、鵲の森なる場所は見当たりません。
個人的な考えですが、浄祐寺の近くに架かっていた梅田橋にちなんだ地名ではないでしょうか。
江戸時代に大ヒットした「曽根崎心中」の中に、
『梅田の橋を鵲の橋と契りていつまでも、われとそなたは女夫星』という詞章があります。
芝居好きの人の間で、梅田橋を「鵲の橋」を呼ぶようになり、
梅田橋の北側にある森を「鵲の森」と呼んでいたのではないか。
内蔵助が天野屋と関わりをもつようになった経緯を詳しく書いた物語もありますが
実際に天野屋利兵衛が赤穂浪士に協力したという事実は無いらしい。
したがって、大石内蔵助が上福島に住んでいたという説はフィクションのようです。
(でも天野屋さんの別荘はあったかもしれないなぁ…)
浄祐寺には赤穂浪士のお墓がありますし、
大阪市北区の円通院には内蔵助のお父さんのお墓があるので、
近くに内蔵助縁の史跡があっても変じゃないような気もします。
矢頭父子の借金は内蔵助が返済したそうですが
その時に内蔵助の使いの人がこの近辺に宿泊したというのが
後日誤って伝えられたというのも考えられる。
もしかしたら、現代には伝わっていないけれど
「假名手本忠臣藏」の大ヒットにあやかって作られた芝居の中に
上福島村に隠棲していたというエピソードがあったのかもしれないなぁ。
※「福島区の風景・街並み」
旧上福島村あたりに、忠臣蔵で有名な大石内蔵助の仮住いがあったと書かれています。
出典は江戸時代に出版された観光ガイドブック「摂津名所図会大成」。
この本は有名な「摂津名所図会」とはまた違う書籍です。
その本によりますと、内蔵助が住んでいたのは浄祐寺(北区堂島)の西側。
そしてその家は「仮名手本忠臣蔵」に登場する大坂の商人、天野屋利兵衛の別荘でした。
「大坂見聞録 関宿藩士池田正樹の難波探訪」(渡邊忠司)という本にも
大阪の福島あたりに天野屋利兵衛の別荘があり、
そこに内蔵助が身を寄せていたという記述があります。
この本は江戸時代の武士の大坂赴任中の暮らしをつづった
「難波噺」という随筆について書かれたもので、
大坂の市中や郊外に観光に出かけた記録も掲載されています。

「wikipedia:仮名手本忠臣蔵」旧字体:假名手本忠臣藏。
「wikipedia:大石良雄」「良雄」は諱で、通称は「内蔵助」。
「wikipedia:天野屋利兵衛」十段目で天河屋義平として登場。
「大阪伝承地誌集成」には別項目に「天野屋利兵衛宅跡」があり、
浄祐寺の北にある「鵲の森」に
天野屋利兵衛の屋敷があった、と書かれています。
古い地図を何種類か見ましたが、鵲の森なる場所は見当たりません。
個人的な考えですが、浄祐寺の近くに架かっていた梅田橋にちなんだ地名ではないでしょうか。
江戸時代に大ヒットした「曽根崎心中」の中に、
『梅田の橋を鵲の橋と契りていつまでも、われとそなたは女夫星』という詞章があります。
芝居好きの人の間で、梅田橋を「鵲の橋」を呼ぶようになり、
梅田橋の北側にある森を「鵲の森」と呼んでいたのではないか。
内蔵助が天野屋と関わりをもつようになった経緯を詳しく書いた物語もありますが
実際に天野屋利兵衛が赤穂浪士に協力したという事実は無いらしい。
したがって、大石内蔵助が上福島に住んでいたという説はフィクションのようです。
(でも天野屋さんの別荘はあったかもしれないなぁ…)
浄祐寺には赤穂浪士のお墓がありますし、
大阪市北区の円通院には内蔵助のお父さんのお墓があるので、
近くに内蔵助縁の史跡があっても変じゃないような気もします。
矢頭父子の借金は内蔵助が返済したそうですが
その時に内蔵助の使いの人がこの近辺に宿泊したというのが
後日誤って伝えられたというのも考えられる。
もしかしたら、現代には伝わっていないけれど
「假名手本忠臣藏」の大ヒットにあやかって作られた芝居の中に
上福島村に隠棲していたというエピソードがあったのかもしれないなぁ。
※「福島区の風景・街並み」