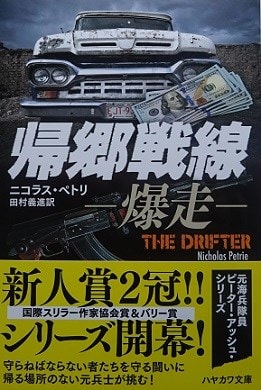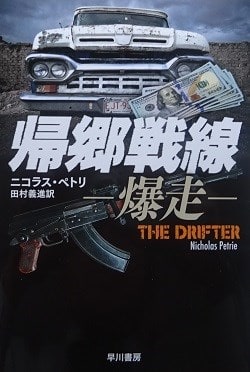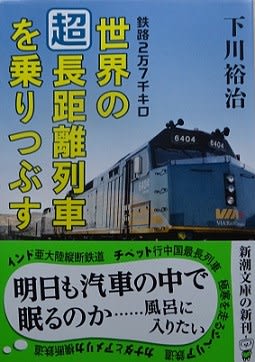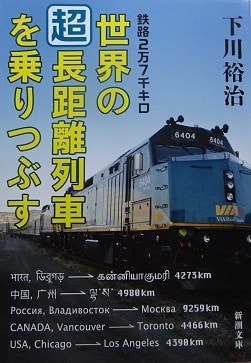小川隆夫氏の本は結構お世話になっている。感覚で書く人と違って、ご自身の体験と多くのデータから書いているのでそこが気持ちが良い。
新しい著書がでたというので図書館に予約して順番がきた。
受け取りにいくと、これがかなりの驚き、ハード・カバーの463ページの大作だった。
2004年1月から6年10月まで全34回にわたって「スイングジャーナル」誌に連載されたものを改定して単行本かしたものでした。スイングジャーナルはこのころ読んでいないので私としては初めて出会う記事です。
内容はジャズの名盤34作品を作品紹介、主要メンバー、全曲紹介、コラム、証言、関連アルバムと紹介もので、その情報量からして大作と書きました。
どのアルバムもよく知っていると言えば言えるけれど、いやここまでは知らないだろうというのがこの本の意味でしょう。
その意味とても価値がああるのですが、重たい。(重量も)失礼だから最初から読み始めて、最初がビリー・ホリディーの『奇妙な果実』。最初のしょうからすべては読めない、メンバー紹介と曲紹介はとばすけれどコラムと証言は面白い。
ラインナップは以下の通り、これ年代順に並べられている。だからホリデーから読み始めたのだけれど、段々重たい、ミンガスあたりからは拾い読みになってしまった。
01 ビリー・ホリデイ『奇妙な果実』
02 アート・ペッパー『サーフ・ライド』
03 チャーリー・パーカー『ナウズ・ザ・タイム』
04 アート・ブレイキー『バードランドの夜 Vol.1 & Vol.2』
05 ヘレン・メリル『ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン』
06 マイルス・デイヴィス『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』
07 アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ『カフェ・ボヘミアのジャズ・メッセンジャーズ Vol.1 & Vol.2』
08 チャールズ・ミンガス『直立猿人』
09 マイルス・デイヴィス マラソン・セッション4部作『クッキン』『リラクシン』『ワーキン』『スティーミン』
10 ソニー・ロリンズ『サキソフォン・コロッサス』
11 セロニアス・モンク『セロニアス・ヒムセルフ』
12 ソニー・クラーク『クール・ストラッティン』
13 キャノンボール・アダレイ『サムシン・エルス』
14 アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ『サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ Vol.1 – Vol.3』
15 バド・パウエル『ジ・アメイジング・バド・パウエル Vol.5/ジ・シーン・チェンジズ』
16 マイルス・デイヴィス『カインド・オブ・ブルー』
17 オーネット・コールマン『ジャズ来るべきもの』
18 デイヴ・ブルーベック『タイム・アウト』
19 マイルス・デイヴィス『スケッチ・オブ・スペイン』
20 マル・ウォルドロン『レフト・アローン』
21 ジョン・コルトレーン『マイ・フェイヴァリット・シングス』
22 ビル・エヴァンス『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』『ワルツ・フォー・デビイ』
23 エリック・ドルフィー『アット・ファイヴ・スポット Vol.1 & Vol.2』
24 ジョン・コルトレーン『バラード』
25 ソニー・ロリンズ『橋』
26 スタン・ゲッツ&ジョアン・ジルベルト『ゲッツ=ジルベルト』
27 ホレス・シルヴァー『ソング・フォー・マイ・ファーザー』
28 リー・モーガン『ザ・サイドワインダー』
29 オスカー・ピーターソン『プリーズ・リクエスト』
30 ジョン・コルトレーン『至上の愛』
31 ハービー・ハンコック『処女航海』
32 チック・コリア『リターン・トゥ・フォーエヴァー』
33 キース・ジャレット『ケルン・コンサート』
34 V.S.O.P.クインテット『ライヴ・イン・ジャパン/熱狂のコロシアム』
名盤だということは誰も疑うことは間違いないだろうけれど、このアルバムをほとんど持っているかというとそうでもない。
愕然とした事実にきがついたのだけれど、それは後回し。38枚のアルバムが乗っているけれど実は持っているのは16枚だった。
ここに掲載されている名盤のリリース年に、私のジャズの聴き初めごろの線を引くと、30番の『至上の愛』ころ、LPを買い始めたのは翌年ぐらいの1966年ごろだと思う。ですからここに乗っているアルバムをリアルで対面したのは最後の4枚程度で、後から買ったのが16枚と言っていい。(V.S.O.Pもコリアも持っていない。
当時買ったのは、ドン・チェリーの「Symphony For Improvider」(1966年)であったりチャールス・ロイドの「FOREST・FLOWER」ショーターの「ADAM'S APPLE」(1967年)コルトレーンの「エクスプレッション」ステーヴ・レーシーの「森と動物園」アイラーの「LOVE CRY」であった。
限られたおこずかいではこのような新しいアルバムを買うのが精いっぱい、以来、新譜が中心のアルバムの買い方だから16枚というわけなのです。
だけれども、愕然とした事実が。それがこれ。
「私、『至上の愛』を持っていない。」
ウーンとうなるばかりだけれど17枚目になるのは間違いのないので、小川さん、ありがとう。