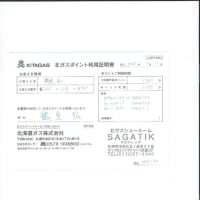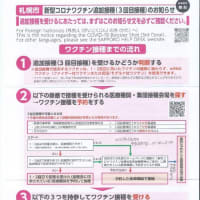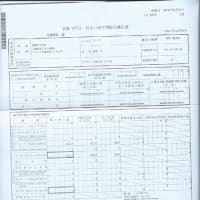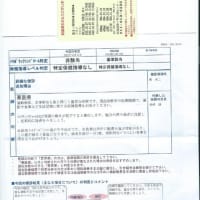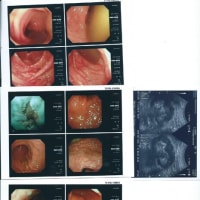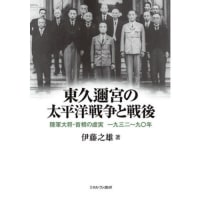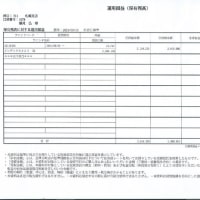今日の続編日記は、映画『幕末太陽傳』(1957年製作 川島雄三監督 フランキー堺 金子信雄 山岡久乃 左幸子 南田洋子 石原裕次郎主演)のラストシーンのことです。添付した写真は、遊郭旅籠『相模屋』から去って一人東海道を下っていく佐平次(フランキー堺)です。
この映画は、幕末の品川宿相模屋が舞台となっていますが、冒頭シーンでは、映画撮影当時(1957年)の姿である後の「さがみホテル」が登場しています。これは、翌年の売春禁止法前の赤線地帯の風景から約一世紀ほど時代を遡って、明治維新6年前の文久2年(1862年)の『相模屋』になっていくとても不思議な演出です。
だから、この映画のラストシーンも川島雄三監督は、当初、佐平次は東海道ではなく、突然撮影用墓場セットがある映画スタジオを走り出して、撮影スタジオの扉を突き抜けて、映画を製作した1957年現代の街並みをどこまでも走り去っていくものであったそうです。そしてさらに、佐平次が走り去っていく街並みは、いつしか冒頭のタイトルバックに登場した「さがみホテル」の風景になり、そこに映画の登場人物たちが現代の格好をしてたたずみ、ただ一人だけ佐平次だけが江戸時代の格好で走り去っていくというとてもユニークな演出だったらしいです。
しかし、この川島雄三監督の奇抜な構想は、現場スタッフやキャストから反対意見が続出して、監督自身が断念したそうです。でも、時代劇でありながら、冒頭は品川駅の列車シーンから始まった異色映画です。ラストシーンも川島雄三監督の構想通りに製作されていても、観客は何ら違和感を抱かなかったと私は今思っています。
これは、川島雄三監督が思い抱いていた映画製作の構想が、あまりに奇抜かつ革新的であり、当時の時代が彼の異才に付いていけず、まったく認められなかった「映画の悲劇」です。
この映画は、幕末の品川宿相模屋が舞台となっていますが、冒頭シーンでは、映画撮影当時(1957年)の姿である後の「さがみホテル」が登場しています。これは、翌年の売春禁止法前の赤線地帯の風景から約一世紀ほど時代を遡って、明治維新6年前の文久2年(1862年)の『相模屋』になっていくとても不思議な演出です。
だから、この映画のラストシーンも川島雄三監督は、当初、佐平次は東海道ではなく、突然撮影用墓場セットがある映画スタジオを走り出して、撮影スタジオの扉を突き抜けて、映画を製作した1957年現代の街並みをどこまでも走り去っていくものであったそうです。そしてさらに、佐平次が走り去っていく街並みは、いつしか冒頭のタイトルバックに登場した「さがみホテル」の風景になり、そこに映画の登場人物たちが現代の格好をしてたたずみ、ただ一人だけ佐平次だけが江戸時代の格好で走り去っていくというとてもユニークな演出だったらしいです。
しかし、この川島雄三監督の奇抜な構想は、現場スタッフやキャストから反対意見が続出して、監督自身が断念したそうです。でも、時代劇でありながら、冒頭は品川駅の列車シーンから始まった異色映画です。ラストシーンも川島雄三監督の構想通りに製作されていても、観客は何ら違和感を抱かなかったと私は今思っています。
これは、川島雄三監督が思い抱いていた映画製作の構想が、あまりに奇抜かつ革新的であり、当時の時代が彼の異才に付いていけず、まったく認められなかった「映画の悲劇」です。