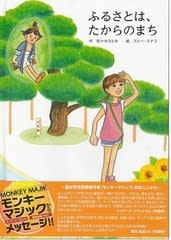
仙台市の隣の富谷は、このたび町から市になりました。合併という形ではなく人口増加によるもの。それを記念して作られた絵本です。
現在も各地で上映されている「ゆずの葉ゆれて」の原作『ぼくとあいつのラストラン』もファンタジーでした。佐々木さんはファンタジー作家。このたびの絵本も、市の紹介が主たる目的なのかもしれませんが、ファンタジー仕立て。そして、市への愛にあふれた絵本になっています。
物語として楽しめ、かつきちんと情報を入れる。力がなくてはできない仕事です。佐々木さんは、コピーライターでもあるので、きちんと伝えるということと、魅力的に伝えるという両方が出来る方なのだなと、改めて思いました。
主人公宮乃と時空をさまよっている十太が、最後に見つけた「富谷の一番のたから」とは? 見事な着地でした。
そして、どの町にも、こういう歴史があり、皆さんが大事にしているものがあり、「たから」があるのです。こういう絵本、各地で作るといいなと思いました。
きのうきょうと、宮城の関連本をご紹介させていただきました。22日、23日は、仙台に行っていたのですが、やはり東北の中心。都会だよ。
*津波の被害を受けた仙台港に近い会館で、結婚式がありました。一見どこにも震災の跡はないように思われます。でも、確かにあの震災はあった。その事実を変えることなどできません。もし、震災前にタイムスリップして、沿岸にいる人達を非難させることができたら……。でもそれはもうできないこと。
そのあたりが、私が映画「君の名は。」を観て、もやもやした最大のところかなと思いました。
ただし、当時仙台の学生で、今も仙台で働いている甥は、「君の名は。」、好きすぎてもう3回観たそうです。20代男性、やっぱり、あの映画好きなのね。
そして、式をあげた新郎のご実家は、津波に流され、現在はまた近くに再建したとのこと。だから、この会場を選んだのかなあとか、やはり現地に行くと違う感慨があります。ホテルで読んだ河北日報に、山元町にできた被災者が入る集合住宅の記事もありました。(仮設ではなく)



 破れ蓮(やれはす、やれはちす) 蓮の実 (秋田)
破れ蓮(やれはす、やれはちす) 蓮の実 (秋田)

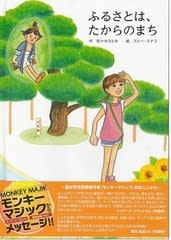
 高学年から
高学年から

 この景色って、芸術的
この景色って、芸術的 たぶん芒(ススキ)
たぶん芒(ススキ) たぶん、荻(オギ)
たぶん、荻(オギ)
 いきなり晩秋っぽい
いきなり晩秋っぽい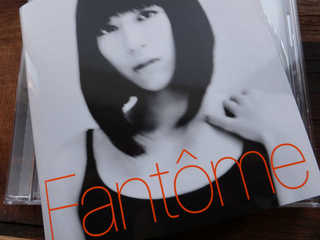
 これは木。
これは木。